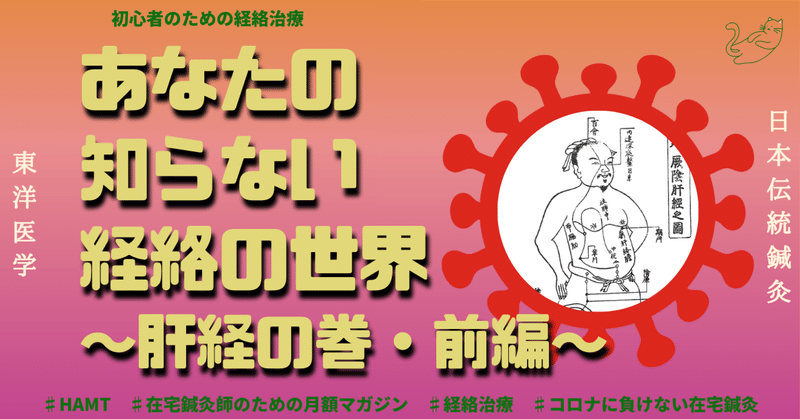
あなたの知らない経絡の世界~肝経の巻・前編
この記事はHAMTに登録すると、今回の記事はもちろん、過去の記事まですべて読むことができます。


記事開いていただきありがとうございます。ゆーのすけです。
最近の私の連載ではこれまで、肺経、大腸経、胃経、脾経、心経、小腸経、膀胱経、腎経、心包経、三焦経、胆経までの流注(経絡の流れ)をみてきました。
今回は、肝経についてまとめていきます。
肝経は、足の親指から始まり、足、脚、体幹、胸部、喉、顔、頭頂へと流れます。そして、主要な内臓(肝、胆、胃、肺)に絡みながら、体内の気のバランスを保ちます。
肝経は、鍼灸における診断や治療において非常に重要です。
今回説明する肝経の流注に沿った不調や症状がある場合、肝経を鍼や灸で刺激することで気の流れが整い、身体が回復していきます。
肝経
正式には、「足の厥陰肝経」と呼ばれます。
肝経の流注
まず、経絡経穴の教科書に書かれている流注をみていきましょう。
■足厥陰肝経
足の厥陰肝経は、足の少陽胆経の脈気を受けて足の第1指外側端【大敦】に起こり、足背内果の前【行間、太衝、中封】、下腿前内側【蠡溝、中都】を上り、脾経と交わり、膝窩内側【膝関、曲泉】、大腿内側【陰包、五里、陰廉】に沿って、陰毛の中に入り、生殖器をめぐって下腹に至り、側腹部【章門、期門】を経て、胃をはさんで肝に属し、胆を絡う。
さらに、横隔膜を貫き季肋に広がり、食道・気管、喉頭、目系 (眼球、視神経)につらなり、額に出て、頭頂部[百会]で督脈と交わる。
目系から分かれた支脈は、頬の裏に下り唇の内側をめぐる。
肝から分かれた支脈は、横隔膜を貫いて肺を通って、中焦に至り、手の太陰肺経とつながる。
十四経発揮 経絡図はこちらです。

今回も原文に忠実に基づいた模式図作ったので、この流注図を見ながら記事読むとわかりやすいかと思います。

ポイント①肝経は、「足の第1指」からはじまる
胆経の流れを詳しくみていきましょう。
足の厥陰肝経は、足の少陽胆経の脈気を受けて足の第1指外側端【大敦】に起こり、足背内果の前【行間、太衝、中封】、下腿前内側【蠡溝、中都】を上り、脾経と交わり、膝窩内側【膝関、曲泉】、大腿内側【陰包、五里、陰廉】に沿って、陰毛の中に入り、生殖器をめぐって下腹に至り、側腹部【章門、期門】を経て、胃をはさんで肝に属し、胆を絡う。
足の厥陰肝経は、足の第1指外側端「大敦」からはじまります。
古典の記載的には「大指叢毛之際」となっています。
大指(=第1指)の叢毛の際。叢毛は「そうもう」と読みます。
ちなみに胆経の終わりも第1指の「三毛」に出ると書かれています。
この「三毛」と「叢毛」は同じもので、毛の生えているところを指しています。(なぜ表記が揺れるのか謎ですが)
そういうわけで、足の第1指外側端といえど、毛の生えているところからはじまると原文に記載されているというのが面白いところです。
なお、肝経のはじまりの経穴である「大敦」は、「霊枢」本輸第二によると
"足大指端及三毛之中” と書かれています。
足の第1指外側端というのは2006年のWHO標準化会議で決まったのであって、古典、原始を重視すると、三毛の中、ようは外側端でなく、毛の生えている中央あたりというのが肝経のはじまりであるでしょう。
また、沢田先生は、「叢毛」は脾経と肝経の交叉するところとし、「大敦」は現代の教科書の取り方(WHO標準化位置とおそらく同じ)を提唱し、それが鍼灸界に一般化したのだと、鍼灸治療基礎学の本に記載がありました。
私は、「大敦」そんな使わないのでどちらの位置が効果的なのかなどよくわかりませんが、知っておくと井穴の反応チェックに応用できそうです。
そのあと、足背を上り、内果の前を通り、下腿前内側を上ります。
そこで脾経と交わって前方に流れがシフトします。
そこから膝窩内側、大腿内側に沿って上行します。
ポイント②肝経は、脾経と脚で3回交わる
肝経は大腿内側を上行し、脾経の経穴である、鼠径部の拍動部の経穴「衝門」や、鼠径部の中央から上に指2本分にある「府舎」も通るとされます。
肝経と脾経は、脚で3回交差しながら走行していることになります。
三陰交穴で1回、膝窩内側であたりで一回、鼠径部の衝門・府舎で一回。
ということは、痛みの場所から脾経と肝経の弁別するのは実は結構難しいのかもしれません。そのようなときこそ脈診が使えますね。
ポイント③肝経は、「陰毛の中」「生殖器」につながる
ここから先は

HAMT〜訪問鍼灸向け教育コンテンツ〜
200以上あるコンテンツが購読すればなんと全て読み放題!購読者限定の無料オンラインセミナーもあります。毎月数本の記事追加されます!各分野の…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
