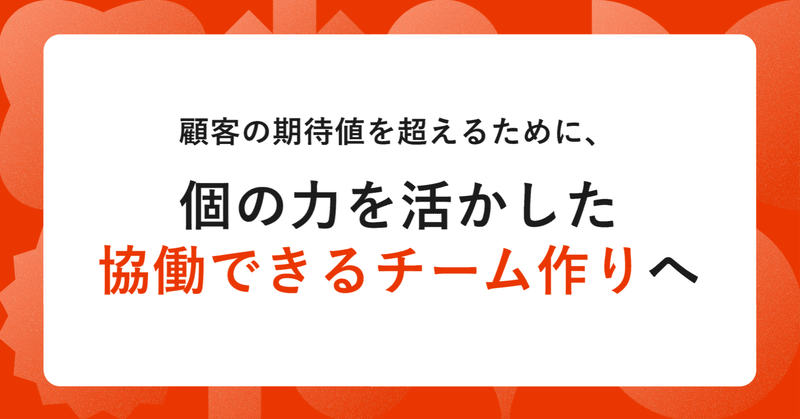
顧客の期待値を超えるために、個の力を活かした協働できるチーム作りへ
こんにちは、セブンデックスの結城です。
今回はメンバーである私が行っている自律的なチームワークを発揮する意識的に行っている事をお話しできればと思います。
(*弊社では案件ごとにマネージャー以上の人間がプロジェクトの統括として入り、クオリティーコントロールなどは行っていますが、今回はメンバー目線での動き、働きかけについて記載させて頂きます。)
私はUXディレクターという職種(戦略立案、UX設計、案件の進行管理、ディレクション、クライアント折衝etc)ですが、直近は以下に集中したPJの携わり方をしています。
①アカウントマネジメント(クライアントとの期待値調整、クロスセル・アップセル)
②プロジェクトの健康管理(チームビルディング、PJ/チームのヘルスチェック、メンバーへのFB)
中長期的なクライアント目線や、チームビルディングに目を配る過程で見えてきた事を今回はお話しできればと思います。
期待値を超えるには、協働するしかない
セブンデックスでは、UXディレクター、UIデザイナーの2名以上でPJ組成がされる事が多いです。支援領域も広範な為、ディレクターがディレクターの仕事に閉じる、デザイナーがデザイナーの仕事に閉じるなどしているとチームとして機能しなくなるケース(依頼スコープをなんとか達成する位)が発生します。
一般的な制作会社だとディレクターが仕切り、ディレクションしデザイナーが働くという形式もあるのですが、ディレクター、デザイナーが双方にビジネスゴールを追求してクライアントワークを行えるようにならないと、クライアントの期待値を超えられない。というのが所感です。
顧客の期待はどこにあるのかを常に念頭に置く
当たり前に期待されるものとして納品物の品質、プロセスの過程で生まれる副産物、納品物が生み出す効果etcなどがオーソドックスかと思います。
一方、支援をしていく中でチームの動き方を決めるには、どんな期待を持って発注を頂いたか?チーム全員で認識しておく必要があります。
スピード感のある支援、忌憚のない議論・提案、予定調和ではない場面場面での最適な支援。様々な期待があって投資の意思決定をして下さってるので、その背景を正しく咀嚼できるか?が重要だと思っています。
もちろんPJのキックオフでは確認はしつつも、シーン毎でアウトプットの目的や期待役割も常に変わります。どなたが、どんな判断で「良し悪し」を図るものなのか?その場がどんなシーンなのか?まで想像する事が大事かと思います。常に期待がどこにあるか、確認し続け、チーム内に共有する事は、チーム内のリソースを無駄使いしない上でも大事な一歩目かと思います。
顧客の期待値はPJの変遷とともに動く
先ほど顧客の期待値は営業時に決まるとお伝えしましたが、顧客の期待値はPJの変遷とともに動いていく前提を置いた方がいいとも思ってます。
フェーズが変わったり、PJを取り巻く環境が変わったりする事で与件そのものが変わったり、支援を続けていく中で期待値そのものが大きくなっていくケースもあります。

顧客の状況が変わるたびに、正しく期待値を推し測り、チーム内に共有し目指すべき水準などを齟齬なく把握し続ける事が地味に重要だと感じてます。
協働する為に必要なこと
私の結論を言うと
ビジネスゴールをチーム全員が理解した上でチームメンバーの状況を深く理解した上で、過不足な部分はどこか?を把握し、「協働の質」を高め、「越境する」事だと思っています。
ビジネスゴールを理解する為の課題設定、課題解決の方法などは既に世に沢山あるかと思いますので、今回は「協働の質」を切り口にお話しできればと思います。
協働の質を高める為にまず必要な事

協働を行う為に前提になるのは、背景理解を前提とした会話量と質だと思います。(上の図のレベル4の段階)可能であれば、Day0(PJの準備期間)の期間でそれぞれの強みや、どんな役割をするべきか?などをチーム内で合意できていると理想です。

もしPJの組成タイミングで、それぞれの力量をアセスメントする事が難しいい場合はPJの1週間程経ったタイミングで、PJメンバーと相互に振り返りを挟みつつ、役割を再設定していく事で最適な配置を決められると思います。
混乱期は社内も、社外も巻き込んで行う

チームを組成してから、それぞれの役割なども見えてくると、社内メンバーとの混乱期が必ず発生します。このタイミングで最も大事な事は忖度をしない事と、プロジェクトの成功を実現する為に自分をどこに配置すべきか?を客観目線を持ちながら、意志を持って発言する事だと思います。チーム内にも自身の責任範囲や役割を明確に主張する事とそれぞれの背景理解をセットで行う事で早期に立ち上がる事ができます。
これらは、社内メンバーだけでなく顧客も巻き込んで行う事がおすすめです。
顧客の期待次第ではありますが、共創しながら成果を生んでいくという特徴がある支援の場合は特におすすめしたいです。
大前提支援する側なので、リードする姿勢は持ちつつも、顧客と壁打ちしながら議論を進めていく方が成果を最大化しやすいというのが実感値としてあります。
PJの初期に適切な衝突が出来ると、自分の勝手な顧客像、勝手な思い込みなどを排除して、相互にプロジェクトの与件の達成に向けて走れるチームが出来上がります。顧客からしても、どんな形でこの支援会社の人と携わればいいのか?の輪郭もできるはずです。
PJの立ち上がり初期にこそ適切にぶつかり合う事が重要だと思っています。
PJは、サッカーやバスケのコートスポーツのように戦う
PJが上手くいかない時のゲーム形式をテニスの団体戦方式と呼んでます。(3シングルス、5ダブルスの 8 試合の勝敗数でゲームで勝ち負けが決まる様式。)それぞれが独立して活動するように活動をしていると、チームの最大値は取れないと確信しています。
個の特徴や状況を見極めつつ、適切に自分と他者を配置し、時には顧客を巻き込みつつ、顧客と一緒にPJのゴール実現に向けてこれからも最適な協働の形を模索していきたいと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
