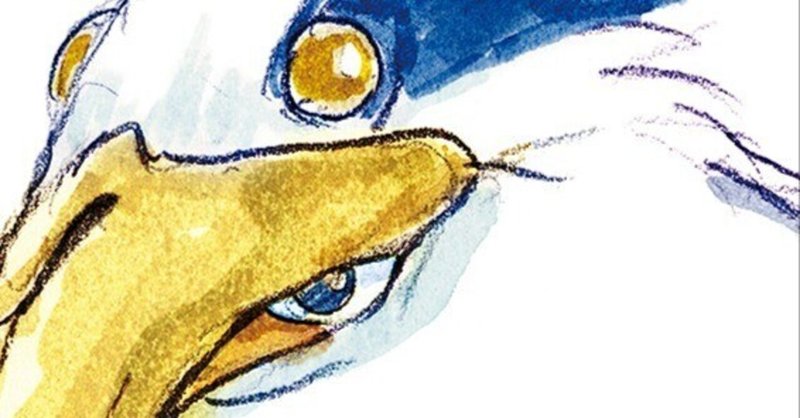
『君たちはどう生きるか』を考察。ジブリブランドとその崩壊を、宮崎駿の視点から眺めたアニメ
※注意 この記事は、映画の内容のネタバレを大いに含みます。映画を視聴された方向けの記事になります。
見てきました。宮崎駿監督の最新作『君たちはどう生きるか』
見終わった感想は…率直に言うと「どういう感想を持てばいいんだろう…?」と頭を抱えてしまったのが感想になります(笑)
それは、自分自身の宮崎駿への思い入れの強さもあり、そこから何らかのメッセージ性を受け取らなければという気持ちもあったのかもしれません。
でも、驚くほど何も浮かばない。それくらい、この映画の内容は宮崎駿の「一人語り」感が強く、私は蚊帳の外でそれを眺めているだけの印象を受けた。
「おそらく、訳が分からなかったことでしょう。私自身、訳が分からないところがありました」。
試写会で、宮崎駿監督自身がこうおっしゃっているくらいなので、かなり心の深いところにあるイメージをそのまま抽出したような内容であることは間違いないのでしょう。
「これは"夢だ"な」
普段から夢占いが好きな自分は、直感的にそう感じました。特に塔の中のファンタジックな冒険に入ってからは、終始夢占いをするような視点で、映像に登場するシンボルの意味を考察しながら視聴していました。
まだ一度しか視聴してないうえに日が浅いので、その考察もまだまだ生煮え感がありますが、書かずにはいられない気持ちもあるのでここに書いていこうと思います。
先に箇条書きしておくと、私の考察では
眞人=若い頃の宮崎駿
アオサギ=鈴木プロデューサー
キリコ=高畑勲
ヒミ=宮崎駿の母親
インコの王様=細田守や新海誠
大叔父=もりやすじ、故人のアニメーター
こんな感じになります。
宮崎駿の人生を振り返る物語
一言で言うならこれが一番近いんじゃないかと思われます。
人間の心理の特性上、何かを純粋に表現しようとすると、無意識にその人の人生観が強く反映されます。監督自身が訳が分からないと表現しているくらいですから、やはり今までの人生が強く反映されている可能性は高いでしょう。それを踏まえたうえで、物語の出来事の流れを考察していきます。
ただ、私は宮崎駿の生い立ちにそこまで詳しくはなく、想像も多分に含まれている事を先にお伝えしておきます(汗)
海辺の草原についた主人公の少年・眞人は黄金に輝く門に閉ざされた墓を見つけます。
墓は「諦めた過去・夢」門は「人生の転機」を象徴します。
宮崎駿監督は遠い昔、過去に誰かが諦めてしまったことを、自分がやってみようと思ったのかもしれません。(でもそれは死ぬほどの覚悟が必要)
そして門は黄金に輝いています。つまりそれは、お金になる事業だったのです。門に近づいた眞人に、ペリカンの集団が近づき無理やり門の中へと押し付けます。このペリカンは、「他者を食い物にする」奴らです。
金になりそう、伸びそうな才能を見つけたら、周りがほおっておかないでしょうからね。もしかしたら、若い頃の宮崎駿監督も周りの期待を背負って絵の道へ進んだのではないでしょうか。
そして墓を暴いてしまった眞人の前に、若い頃のキリコが現れます。
キリコは眞人に、船の扱い方や巨大な魚の捌き方等、生きる知恵を教え込みます。
「人生の船出」というように、船は「人生の選択」を表します。
海は「無意識」を表し、そこから吊り上げる巨大な魚は、幸運をもたらす創作物を表します。
アニメ映画監督の宮崎駿であれば、それは「アニメや映画作品」を象徴することに当てはまります。そしてその漁の師匠的な存在であり、未来では眞人の足を引っ張ったり成果物(タバコ)をいただこうとしたり…
宮崎駿監督でそれが当てはまる人物としたら…もしかして、キリコさんのモデルは高畑勲!?
鈴木プロデューサーが、作中に高畑勲がモデルのキャラがいると仄めかしていましたが、それはキリコさんのことなのかもしれませんね。
大きな魚が港に揚げられると、ワラワラたちが嬉しそうに駆け寄ります。
大きな魚がアニメ作品を象徴しているならば、それを楽しみに集まるワラワラたちは、アニメや映画を楽しみにしている子供たちを表しているのではないでしょうか。
魚を食べて気力を満たしたワラワラたちは、生まれるために夜空へ浮かび上がります。暗い中で輝く夜空は、映画のスクリーンを表しているようにみえます。アニメ映画を見た子供たちは気持ちが満たされ、生まれるため、現実で生きていくための活力を得ることを意味するとも言えます。おそらくは、アニメ映画を製作するうえではそれが一番の目標であり達成感に繋がるのではないでしょうか。
眞人はそれをトイレに行く時に目撃しますが、アニメの制作現場からすれば、映画館は想像したものが排出された後に行く場所。だからトイレなのか(笑)
しかしそこでまたペリカンが現れます。そしてペリカンはワラワラ達を「食い物に」するのです。これは現実でも当てはまりますよね。大人は若い世代を、どうやってお金儲けに繋げるかを考えることが仕事なところもあります。純粋に映画の世界を楽しむ子供たち裏での大人の事情。現実は残酷です。
ヒミが登場しペリカンたちを火の力で追い払いますが、宮崎駿監督もこんな風に、映画製作とそれを取り巻く経済や大人の事情の矛盾と戦いながら創作活動を続けてきたのでしょうね。
火は心のエネルギーを表します。火に包まれ火を操る眞人の母は、心のエネルギー源のような存在であることが想像できます。
どうやら宮崎駿監督の創作の原点は、母親を求める所にあるようです。
宮崎駿監督の母親で検索して画像を見てほしいのですが、映画の中に登場するヒミ(火美?)と似ているところがありますよね、髪形とか。ヒミのモデルは監督自身の母親なのではないかと思われます。
宮崎駿監督の描くヒロイン像はみんな母性が強いとよく言われますが、母親を求める気持ちが根底にあるのでしたら納得ですよね。今作では何故か若返った姿でヒロイン役にもなって眞人に抱き着いたり、「本音を言うとお母さんとラブラブになりたいんです!」というカミングアウトを見ているような複雑な気持ちになりました(笑)
ですが、深層心理では男性は母親を、女性は父親を、好みの異性に投影させるそうなので、夢のような世界でこれは特に不自然ではなく、逆にむしろ自然!健全!の極みなのかもしれませんね。
眞人の冒険は母親を追い求めることから始まります。やはり男の子はお母さんが大好きなんですね!
キミコと別れた眞人はその後、度々インコ達に襲われて食べられそうになります。
大量のインコは「人間関係のトラブル」、食べられることは「エネルギーやパワーを奪われる」ことを象徴します。
映画監督としての知名度が知れ渡ると、その力や地位を奪ってやろうとする人も沢山あらわれます。宮崎駿のようになりたい、そんな風に思う人はいっぱいいたことでしょう。
メディアでも、宮崎駿監督の引退宣言が出たり、ジブリ以外でのアニメ映画のヒット作がでると、メディアはポスト宮崎駿などと煽ったりしていました。実際、次世代の宮崎駿を夢見ていたアニメーターも多かったことでしょう。宮崎駿監督の視点でも、そういう世の中の圧力は当然感じていた、でもそいつらは所詮「烏合の衆」という皮肉も込められているのかもしれませんね。
そんな烏合の衆の中から選ばれしインコ、それは次世代のアニメ映画の世界をしょって立とうと意気込んでいる人物、現実で言えばそれは、「おおかみこどもの雨と雪」でポストジブリと持てはやされた細田守監督であったり、「君の名は」で大ヒットした新海誠監督を象徴しているのかもしれません。
そんなアニメ界に台頭してくる烏合の衆のアニメ作家たちを、宮崎駿監督はどんな風に感じているのでしょうか。それが、大叔父様との対話ややり取りに見てとれます。
眞人は自分のご先祖様である大叔父と、不思議な空間で対峙します。眞人が宮崎駿監督を投影した人物だとしたら、大叔父様はいったい誰になるのでしょう。
私の想像では、それはアニメーションの神様とも称される「森康二さん」が当てはまるのではないかと考えています。それにはいくつか理由があります。
大叔父のいる世界へ入る前に、木で組まれた高い通路を渡るのですが、インコの将軍によって切り落とされ、眞人たちは地面へ落下してしまいます。
このシーン、「天空の城のラピュタ」のセルフオマージュと気づいた方も多いのではないでしょうか。
天空の城ラピュタでは、主人公の少年・パズー達が木で組まれた線路を崩されはるか地下へ落下してしまいます。そこをヒロインであるシータの持つ「飛行石」の力でゆっくりと落下し着地することに成功するのですが、落ちた先の入り組んだ坑道の中で「ポム爺さん」と出会い、飛行石の神秘の片鱗を見せてもらいます。そしてこのポム爺さんこそ、森康二さんをモデルにしたキャラなのです。
「ラピュタ」の中で飛行石は、発動中に持たざる者が触るとバチンッ!っとはじく性質がありましたが、「君生き」でも眞人たちはバチバチと拒絶するように発光する石の空間を通ります。
そんな性質の石を超えた先にいる、森康二さんをモデルにしたキャラ…なんだか共通点がありますよね。
また、森康二さんは若きアニメーターの教育や指導も行っており、宮崎駿も影響を受けた人物の一人となります。そういう意味では、宮崎駿監督は森康二さんの系譜を受け継ぐ人物であり、その点では大叔父と眞人との関係をにおわせます。そして既に故人という点でも…。
宮崎駿監督が、森康二さんからどんなことを学んだかは分からないのですが、きっとそのことが「つみき」に象徴されているのではないでしょうか。
アニメーションは、基本的には子供たちが見るものです。子供たちは、世の中の情報を敏感に受け取ります。何を選んで映像として表現するのか、そしてそれを世に出すのか…。
今ではブランドとして確立したジブリ作品ですが、その裏では相当に慎重な情報の取捨選択が行われていたのかもしれません。そしてそれはとてももろく、ちょっとした衝撃で崩れてしまう。日本のアニメーション文化は、意外とそんな性質を持っているのかもしれません。
さて、そんな場面にずかずかとやってきた烏合の衆のリーダーが、空気も読まず積み木をでたらめに積み替えた挙句、あっさり崩してしまいます。
その結果、大叔父の世界は崩壊、インコ達も野に放たれ、ただのインコに…
宮崎駿監督からすれば近年のアニメ映画界の動きは、過去の大物アニメーターから受け継いできて大切にしてきた技術や思想を、まったく関係ない第三者がめちゃくちゃにしてしまった、という印象を受けるのではないでしょうか。そんな現実の流れを反映したようなシーンにも見えてしまいます。
じゃあ宮崎駿監督はそんな状況を、けしからん、嘆かわしいと思っているかというと、意外とそうでもないのかもしれません。
塔が崩れ、中に閉じ込められていたインコやペリカンは自由になり空へ飛び立ちます。ペリカンが飛ぶことは、頭を悩ませていた心配事が綺麗に解消する暗示です。
また脱出したみんなは鳥の糞だらけになりますが、糞が付くは「うんがつく」となり、幸運が舞い込む象徴となります。
宮崎駿監督は意外と、自分が引退することでたくさんの人が古いしがらみから解放されて、新しい時代が来ることを祝福しているのかもしれませんね。
タイトル「君たちはどう生きるか」
僕はこう生きた。そしてもう引退するけれど、僕がいない時代を君たちはどう生きるか?
そんな宮崎駿監督からの、最後のメッセージのように聞こえてきます。
以上、走り書きなので中途半端な部分もあるかと思われますが、映画もこれから何度か繰り返し視聴して、更に考察を深めていきたいです!
読んでくださった方、ありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
