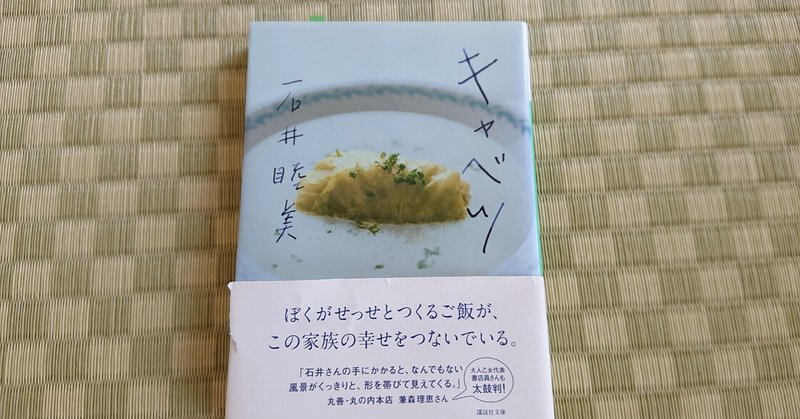
料理男子を連載で書いてみようと思ったワケ②
料理男子について連載しようと決めたとき、「そう言えば…」と本棚に向かいました。
『キャベツ』
独身時代に買った本で、内容はすっかり忘れているけれど、「絶対に処分したくない」と思っていた一冊です。結婚後も、その後の3回の引っ越しの際も、ずっと持ち続けていました。パラパラと本をめくって読み始めると、中学生のときにお父さんを亡くした男の子が、急きょ働きに出るようになったお母さんと妹のために料理をするという、まさに料理男子のお話でした。
「中二でおやじを亡くしてから、母と妹のために、ぼくは毎日せっせとご飯をつくる。冷蔵庫を開けたら戦闘開始! 切ない日も、けんかしたって、この味が家族の幸せを守ってるんだから。」(背表紙より)
あぁ、私もこんな風に、料理男子の話を書きたい、と思いました。
そして、長く長く書き続けるためにはどうしたらいいかな?と感じたので、10数年前に新聞社で働いていたときに当時の上司がくれた本を引っ張り出しました。
『小説家になる! 芥川賞・直木賞だって狙える12講』
上司からの手紙も本の間に挟んだまま残っていて、「小説家を目指しているわけではないのは十分承知です。それでも、フィクションの世界を知ることで、ノンフィクションの世界に何が必要なのかが浮き彫りになってくると思うのです」と書いてありました。
さぁ、書こう! この2冊との再会で気持ちが固まりました。
料理男子の1本目を書き上げて、noteに投稿したちょうどそのとき、学校から下校して、本を読んでいた息子が、私の膝にのっかってきました。もう小学2年生なので、膝の上にのってくることも少なくなってきたのですが、珍しく甘えてきたんです。そして、「目が開きづらい」と言いました。
見ると、両目ともにまぶたが腫れていて、明らかに顔の表情が変わっています。
焦りました。パソコンを閉じて片付けようとしたら、息子が「何、これ?」と私が書いた料理男子の記事に目を留めました。
「料理が大好きな男の子のお話を書いているんだよ、ようたろうのこと!」と言って、すぐにパソコンを片付け、近所の小児科に電話をして相談したり、職場にいる夫に連絡を入れたりしました。
小児科は運よくドクターが電話に出てくれたのですが、「今日はワクチンの大規模接種の手伝いで休診にしているから、診てあげられなくてごめんね。アレルギーがあるなら、病院に連絡したほうがいいよ」とアドバイスをくれました。
息子は食物アレルギーがあるために、かかりつけ医がアレルギーの専門医がいる総合病院なのです。総合病院は電話がつながらず、地方でも医療機関はどこもコロナの対応で忙しいことを思い知りました。
私は息子にあらかじめ処方されていたアレルギー用の飲み薬を飲ませ、様子を見ることにしました。
幸い1時間後には目の腫れがだいぶおさまり、息子も元気が出てきました。すると、「さっきの読みたい。読んで!」と言われました。
「えっ、読むの?」と、私は驚いてしまいました。
私は、料理男子の連載を息子に読ませるつもりは、まったくなかったのです。特に理由はないのですが、息子が興味を持つとは思わなかったからです。
息子に「つまらない」って言われたらどうしよう…。本人を目の前にしているので、急に緊張しました。私はさっきしまったパソコンを取り出してきて、noteを開いて、息子を膝に抱っこして読み始めました。
画面で「料理男子①」を音読しながら、手前に座っている息子の横顔をときどきのぞいてみました。まだ腫れが少し残った目で、ニヤニヤと笑っているのがわかりました。ああ、よかった。ホッとしました。息子が元気になったのと、私が書いた話をおもしろがってくれたことがうれしくて、ものすごい安堵感がありました。
そして。さらに1時間後、ますます元気になった息子は言いました。
「さっきの続きは? 書けた?」
今、コンサルを受けている正岡智子さんがインスタライブで言っていた言葉を思い出しました。「自分の意志の力なんて信用しなくていい。そうせざるを得ない環境に身を置けばいいだけ」。
家の中に、目の前に、「料理男子」の愛読者かつ、督促してくる担当編集者が誕生してしまいました……。まさに、私が連載せざるをえない環境が整ったのです。
参考文献:
石井睦美「キャベツ」講談社文庫
中条省平「小説家になる! 芥川賞・直木賞だって狙える12講」ちくま文庫
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
