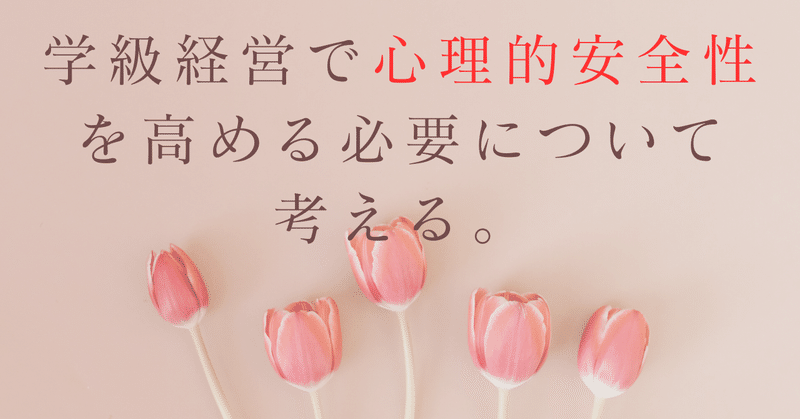
学級経営で心理的安全性を高める必要について考える。
今回は教室内での心理的安全性の高め方について考えていこうかなと思います。と言うのも、私は現在大学院にて学級経営を専門分野として研究しています。その中で、特に『心理的安全性』という部分がこれからの教室には必要不可欠だと感じています。教師の教室内における影響には限界があります。1人の教師が30〜40人いる中ではどれだけ教師が大きなパワーを持っていても、そのパワーには限界があるわけです。子供達のパワーがポジティブに派生することによって、子供達同士の関係の中で子どもが自己肯定感を高めていきます。教師が1人から30人の肯定感を高めることは実際ほぼ不可能だと思いますが、子供達同士の関係性が構築されていれば、相乗効果でその可能性が何倍にも膨れ上がります。個人へのアプローチも当然大切なのですが、集団へのアプローチが結果として個人を高める可能性が多いになるのです。その集団の可能性の高め方が教室内における心理的安全性を高めていくということなのです。「何でも言い合える集団」「何を言っても受容される集団」に属することで、子ども同士は強くつながっていきます。その可能性を広めていく土台として心理的安全性を高めていくことが必要なのです。
①学校における心理的安全性とは?
では、学校における心理的安全性の高め方について考えていきます。心理的安全性とはエドモンドソンによれば

と意味づけされています。これを学校レベルに置き換えると、「教室内の子どもたちが、自分も相手のことも認め合いながら、自分の言いたいことを安心して言い合える集団」と捉えることができます。この状態の根源には心理的な安全性が働いているというわけです。心理的安全性が働いている集団では、教師が考えている以上のポジティブなことが起こり得ます。昨今、グーグルが研究した内容に関しても、チームの生産性を高める一番の要因はそのチーム内における心理的安全性が何より大切であるということがわかっています。学級レベルでその状態を風土として蔓延させることができれば、どれほど子どもたちが集団として伸びていき、そして幸せを感じられるのか。今の私でもその効果は計り知れません。
②心理的安全性が脅かされる
では、逆に考えて心理的安全性が脅かされる状況とはどのような状態を指すのでしょうか。エドモンドソンによれば

だと考えられています。つまり、自分は何も知らない。何もできない。クラスに居場所がない。ネガティブな人間だと感じられている。そのような要因が安全性を低くしているのです。この逆を考ええることで「心理的な安全性が保たれている学級」について考えることができます。「自分には価値があると感じ、そしてどのような言動をとったとしても周りが自分のことを非難せずに認めてくれる」という集団こそが、心理的安全性の高まった集団と呼ぶことができるのではないでしょうか。
③理想的な学級集団とは・・・
上記の内容を踏まえて理想的な学級集団いついて考えてみたいと思います。理想的な集団の要素を考えてみます。エドモンドソンの提唱を参考にすると

だと考えることができます。この要素を含む学級を目指して教師は学級経営を営んでいくことが必要なのです。図で表すのであれば

このような状態というわけですね。つまり、安全性が脅かされている状況から、教師が子どもたちとの関わりの中で上記のような要素を意識しながら学級経営を営んでいくことができれば、子ども同士の関係性が構築され、相乗効果によって「高め合える」集団になっていくというわけです。そこに教師の限界を突破できる鍵が隠されているとも言えるでしょう。
④終わりに
今回は大きな枠で「心理的安全性が高い教室」が求められているという理由を考えてみました。もちろん、これを実行レベルでどのようにしていくのかは別次元で考えていかなくてはいけません。しかし、このような状況を教師自身が理想像として掲げられているかどうかで、学級経営は大きく変化してきます。この概念を念頭に私も学級集団に心理的な安全性を育むにはどうすればよいかを考え、実践していきたいと考えています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
