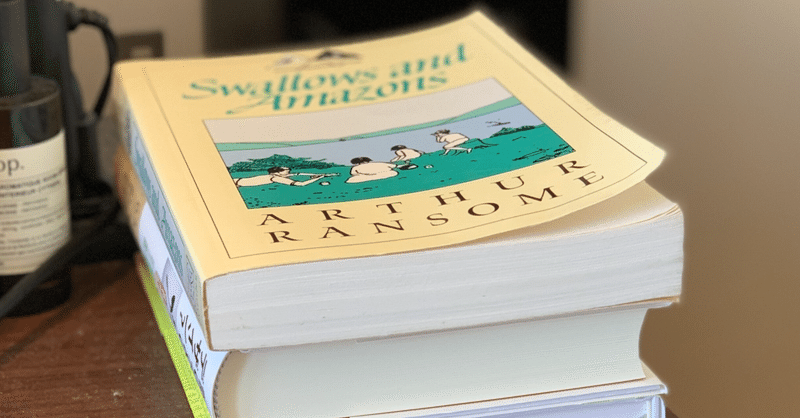
記憶に残る児童書たちを書き連ねておく その1
子供の頃は浴びるように本を読んだ。図書館から5冊本を借りて、その日のうちにすべて読み終えてしまったこともある。現在はさすがにそこまでは読めていないが、時間を見つけては新聞や本、webの記事に目を通すようにしている。読書の習慣は現代では勉強の習慣に置き換わってしまっているが、悪いことではないと自分では考えている。
児童書はいい。たった千円ちょっとで一流の人間が書いた一流の文章を読めるし、将来の糧になる。私は国語の教科書を読むのも楽しいと感じていた。学校の宿題で教科書の音読が課されていたので毎日欠かさず読んでいたがまるで苦にならなかった。教科書に載っている作品たちは篩にかけられた名作揃いである。「ごんぎつね」「大造じいさんとがん」「スーホの白い馬」「ちいちゃんのかげおくり」、いずれも文部科学省のお墨付きである上に物語としても面白く教育的価値も高い。
本稿では私が子供の頃に読んで記憶に残った本を紹介する。自分の気に入った本ばかりを読んでいたので必ずしも教育的価値は高くないが、ひょっとしたら読者の参考になるかもしれないので文章として残しておこう。
名探偵 夢水清志郎事件ノート
推理小説の超入門。読んだのは確か小学校中学年くらいかな…。
大学の元論理学教授と名乗る男「夢水清志郎」が隣人の岩崎姉妹と共に奇怪な事件を解決するというのがあらすじである。岩崎姉妹は彼を教授と呼ぶ。第1作目の「そして五人がいなくなる」では遊園地を舞台としてメディアからスポットライトを浴びせられるような天才少年少女たちの誘拐事件の真相を追う。
作者であるはやみねかおる先生は元教員である。本嫌いの生徒に本を勧めるうちに自ら執筆するようになった。一般的なミステリーでは愛憎渦巻く殺人事件が発生するが、本作はそんな火曜サスペンスみたいな話にはならない。物語の語り部である亜衣の書いた推理小説のオチを教授が当ててしまったり、必ず成績が上がると評判の塾に潜入して真相を追ったりといった具合だ。子供が読むことを作者が想定して書いているためであろう。
この事件はいったいどういう仕組みで発生したのだろう?と思いながら読んでいた記憶がある。この感情は大人になった今だからこそ表現できるが、子供の頃はただひたすら面白くて読み進めていた。記憶力ゼロの教授は自分の生年月日すら思い出せない。ミステリーを読んでいれば一週間食事をとらなくても平気という社会不適合者が鮮やかにそして登場人物全員が幸福になるように謎を解き明かす様は小学生の私には輝いて見えたものだ。読んでいくにつれてミステリーってジャンルは謎があっておもしれぇって思い始めた。そう、謎を面白いと思うことができたというのが収穫である。私の記憶にある限り、教科書に載るような作品にはミステリーというジャンルは存在しない。与えられるままでは得られなかった感情を自ら手に取って選んだ本から摂取できるようになったのである。私の読書体験に大きなインパクトをもたらした作品であると言える。
二分間の冒険
岡田淳先生による和製「剣と魔法の世界」第一歩となりうる作品が本作「二分間の冒険」である。読んだのは小学校中学年くらいだったはず…。
ファンタジーというジャンルは児童書の定番中の定番であり、日本以外の作品の方が知名度は高い。有名どころでいえば「ハリーポッターシリーズ」「ダレンシャンシリーズ」「指輪物語(ロードオブザリングの原作)」など。にもかかわらず本作を挙げる理由は単純だ。一冊で完結しているからである。児童書としてかなり長めなハリーポッターや、辞書のように分厚い指輪物語と違って、本書は約260ページで内容もシンプルだ。
助けたダレカという名前の黒猫に望みを叶えてあげると言われ、とっさにちょっと待ってくれと答えてしまった主人公。ふーん、時間をくれというわけかと返すダレカ。主人公が願いを考えこんでいる最中にダレカは時間を与えるという名目で竜が支配する世界に主人公を送り出す。子供しかいない村に辿り着いた主人公は他の子供たちと徒党を組んで竜退治に挑む。この書き方だと竜に辿り着くまで紆余曲折がありそうだがそうではない。竜vs子供のペアの戦いが数戦にわたって描かれるスピーディな展開だ。
本作の主人公は別に魔法が使えるわけでない普通の小学生だ。唆されて異世界に降り立ち、否応なく戦いに巻き込まれる。ド派手な魔法も出てこなければ、自分一人では想像もできないような突飛なイベントが起こるわけではない。にもかかわらず本作が記憶に深く残ったのは理由がある。当時小学生の私は、竜との戦いで意表を突かれたのである。竜が課すのは二つの試練。一つは謎の試練。一つは剣の試練。謎の試練を突破しなければ固い鱗に覆われた竜の体に剣を突き立てることは叶わないが、竜は何でも知っている。さあ、あなたならどうする?きっとあなたの予想の上をいく展開が待ち構えている。
ファンタジーは代表的な児童書のジャンルなのだが教科書には載っていない。想像力の醸成は国語教育の根幹の一つであり、本作は教育的意義もあるだろう。1冊で完結しているためプレゼントにも向いている。作者である岡田淳先生は他にも「こそあど森の物語」や「選ばなかった物語」なども書かれており、ファンタジーの第一歩としてお勧めできる本である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
