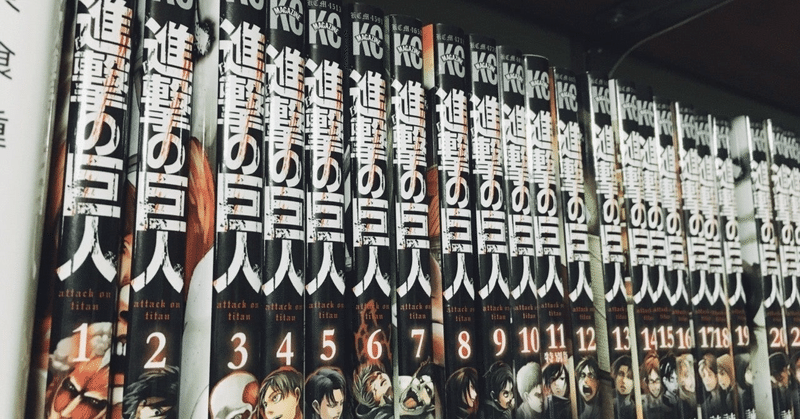
「進撃の巨人」は10年先も語り継がれるであろう傑作だ
マガジンポケットで今現在「進撃の巨人」が全話(チケット対象話を含む)無料公開されていたので読んだ。もともと途中までは読んでいたので、後半部分だけ読んだ形になる。
アニメもファイナルシーズンが現時点で放送しており、最終回前に自分なりの感想を書いておきたいと思い筆を執った。本稿では最終話までのネタバレを含むので未読の方は注意されたい。時系列に沿って段階的にネタバレを行っていく。ただ、私は何度も読み返したわけではないので浅めの感想になっているかもしれない。
完全未読の友人に進撃の巨人をどう紹介する?
「『進撃の巨人』ってどういう話なの?」と聞かれると答えに詰まる。相手が本作をどの程度知っているかによって答えが変わるからだ。が、もしも全く何も知らない人間に説明するのであれば私は次のように答えている。「人間を食らう巨人と主人公たちが戦う話なんだけれども、てっきり主人公が巨人をばっさばっさとなぎ倒していくかと思いきや、そうではなくて、巨人とは何なのか?彼らはどこからきて、なぜ人間だけを襲うのか?といった謎に迫っていく話」と。

これだけでは面白さは伝わらないのだが、ストーリーのネタバレに踏み込まないようにして説明すると大体こんなもんだろう。では、もう少し踏み込んだ説明をするとどうなるか?物語を以下の4ステップに分けて順々に面白さを説明できるだろう。
人類vs巨人
1巻から4巻くらいまでは人類vs巨人の話である。ここからは重大なネタバレを徐々に含んでいくので未読の方は読まない方が良い。

祖先が築いた高さ50 mの壁の中で暮らす主人公が目にしたのは、壁から顔を覗かせる超大型巨人。奴により壁の入り口が破壊され、街に巨人たちが流れこむ。母親を目の前で巨人に食い殺され、主人公エレン=イェーガーは心に刻み込んだ。「駆逐してやる。この世から一匹残らず」と。
そして一巻の末尾でエレンには巨人の力を授かっていると明かされる。本人の自覚もなく、いつの間に彼はそんな力を得たのか?実の父親が残した地下室に謎を解くカギがあるが、そのためには巨人から街を奪還しなければならない。主人公は訓練兵として修練に励み、人類の土地を巨人から奪い返すべく調査兵団に入る道を歩み始める。
あらすじはこんなところだろう。序盤ではエレンの生い立ち、怒りの源泉が描かれ、巨人の恐怖を読者に知らしめてくる。エレンのように強い憎しみを糧にして兵士になっていたとしても、待ち受けるのは非常な現実。こんな巨大な生物に人間が勝とうなんて無理だと思い知らされる。人によってはパニック物ととらえるかもしれないが、そうではない。連載当時は謎が謎を呼ぶ展開が話題を呼び、現在でもその評価は変わっていない。
エレンが巨人に変身して岩でシガンシナ区を奪還したときのカタルシスはすさまじい。人類で初めて月面に降り立ったニール・アームストロングの名言
“That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.”
それは一人の人間にとっては小さな一歩にすぎにないが、人類にとっては巨大な一歩である。
をもじって、”人類にとっての大きな進撃”となるとピクシス司令は述べている。ニール・アームストロングは"giant"(巨人)という単語を使っているからこそ諌山先生はこの発言をもじったのかもしれない。
ここら辺の話も面白いのだが、漫画として面白さが加速するのは次あたりからだろう。
巨人vs巨人

5巻から8巻までは壁外調査で女型の巨人との死闘が描かれるが、この際にはエレンは巨人化の使い方をある程度マスターしている。そう、タイトルにあるように巨人vs巨人の戦いが始まるのだ。もう少し平易な言い方をすれば、「ウルトラマンvsウルトラマン」の格闘技戦が始まる。立体機動装置での戦いにも面白さ・発想の自由さはあったが、格闘技を巨人のスケールでやろうというぶっとんだ発想に「この漫画おもしれぇえええええ」って震えたもんである。
8巻から13巻まではエレンを奪い取ろうとするライナー&ベルトルトと調査兵団との戦いだ。考えてみれば当然なのかもしれないが、私はあまりマンガを考えずに読むので気づけなかった。エレンが巨人に変身できるといことは、他の人間だって巨人に変身で来たってなにもおかしくないじゃないか?アニが女型の巨人というのにはもちろん驚いたが、であるならば鎧の巨人や超大型巨人のように知性を持つ巨人は人間だと考えてしかるべきじゃないか?

ライナーとベルトルトが唐突に自分たちは壁を破壊した巨人だと明かし、エレンに一緒に来てくれと迫る。なぜそんな小さなコマでそんな重要なことを言うんだ!ライナー!と思いつつも、冗談でもなんでもなくて彼らはエレンを奪い取るために巨人へと変身する。辛苦を共にした仲間が、人類を滅ぼそうとする敵だと判明するシーンでは驚きともにエレンへの同情が湧きたつ。あんなに頼りになる仲間としてふるまっていたライナーが、人類の滅亡を望んでいるなんてなぜなのか?と思うこと請け合いである。
ここでライナーの葛藤がわずかではあるが描かれているのものちの伏線である。あの時の俺はバカなガキで、何も知らなかったんだと彼は語る。ガキだからって、人類を滅ぼそうとするか?いったい背景になるがあるんだ?謎は深まるばかりだが、話としては面白い。わからないことが増えていくにもかかわらず、それでも面白いと思わせてくれるのが進撃の巨人という作品のすごいところだ。
当時の私の疑問として、知性を持った巨人と持っていない巨人の差は何だ?と思っていた。その答えは次項で明かされることになる。
人類vs人類

14巻から30巻までは人類同士の争いの方が描かれる割合として大きい。王家の血筋を説明するうえで必要なヒストリアの物語や旧体制の打破、マーレでの潜入作戦が描かれる。獣の巨人と人類の戦いも含まれるのだが、あえて人類vs人類というくくりにした。14巻の段階では薄々と壁外人類の存在を察して、なぜかわからないが壁外人類は壁内人類を滅ぼそうとしていると理解できるためである。
このあたりからテイストが変わったと個人的には感じている。ユミルの発言が象徴的だ。自分をさらったライナーとベルトルトに向けて「お前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するよ」と豪語するエレンに対して、ユミルは冷たく言い放つ。「そんなガキみてぇなこと言ってるようじゃ期待できなぇよ」と。エルディア人という民族が今後生き延びていくためにはライナーとベルトルトに憎悪を抱いているだけでは不足…というよりも、まるでお話にならないとユミルは理解していた。自由を求めて壁の世界を探検するという冒険譚から世界中からパラディ島を守るためにいかなる対策を打つべきかという軍事物へと物語は様変わりをする。巨人の力を駆使する数名の人間にエルディア人は襲われているかのようにエレン達は感じていたが、実際は壁内人類vs壁外人類の死闘が背景にあると理解していく。

民族浄化や不当な差別が背景にある世界でエレンは自らを掛け金として戦いを挑む。調査兵団はエレンの賭けに乗って戦いを挑み結果的に民間人を多数殺傷するのを見て私は思った。自由を求めて戦っていたあの爽快感はいったいどこに行ってしまったんだ。まるで現代社会と何ら変わらない、血で血を洗う悲惨で凄惨な戦いが繰り広げられる。
ガビの視点からは逆にマーレから見た壁内人類の有様が描かれる。ガビだって時間はかかるが気づく。彼らは私たちと変わらない普通の人間だ。悪魔の種族などではないんだと。前述の感想が再び思い浮かぶ。現代社会と全く同じじゃないか?ファンタジーの世界から一気に現実に引き戻され、憎悪の連鎖が続く世界での戦争がテーマなんだとようやく理解できる。ウルトラマンvsウルトラマンが本作のアクションとしての面白さなのは前述の通りだが、壁内人類vs壁外人類の戦いとは、主義主張の違いがあるだけで正義の化身(ウルトマラン)vs正義の化身(ウルトマラン)そのものだと言える。
爽快感はなくなったかもしれない。だが、数々の謎が解き明かされ、エレンの選択から目が離せなくなる。このふざけた世界のどこに自由があるんだよと慟哭したくなり、民間人の殺害を非難するミカサにたじろぎ、サシャの戦死に涙する。ライナーやベルトルトにだって、守るべきものがあるから壁を破壊したんだとようやく理解できるのが本項だ。なんて人間らしい、悩み多きキャラクターたちなんだろう。エレンの視点に立てば憎くてたまらないはずのキャラクターに思わず感情移入してしまう。諌山先生の人間ドラマを描く能力には感嘆するばかりである。
巨人vs人類
31巻から34巻の最終章として描かれるのは「始祖の巨人」と「進撃の巨人」を宿したエレンが発動させた地鳴らしである。これまで壁の中にいた巨人たちに銘じて世界を平坦に変えようとする。

エレンは地鳴らしで人々を虐殺し、世界を平らに変える過程で実感する。「これが自由だ」と。…が、結局はアルミンやミカサに地鳴らしを阻止されてしまい、エレンはこの世を去る。巨人と戦う物語が、いつの間にか巨人として退治される物語に様変わりしてしまう。
本項目の感想は後述する。
アルミンとエレンのどこが違ったのか?
ミカサにとってはエレンの存在が行動原理だった。アルミンは自由への希望が行動原理だった。エレンの行動原理は何だろうか?
エレンの行動力の源泉は母を巨人に殺されたことに対する憎悪だけにとどまらない。アルミンが目を輝かせながら語った外の世界の情景であることは明らかである。その証拠にアルミンが巨人化したエレンの意識を取り戻そうとした4巻のシーンでは母の仇を取ろうとするためではなく、外の世界への渇望を契機として覚醒している。
しかし、エレンは地鳴らしを発動させることを望み、アルミンはそれを止めることを望む。仮にアルミンがエレンの立場だったとしても、地鳴らしは発動させなかったと推定できる。
では、両者の意思決定の違いはどの部分から生じるのか?私は不自由への嫌悪感が二人を決定的に分ける部分だと考えている。

アルミンはリスに餌をあげたり、仲間とご飯を食べる場面でこのために自分は生まれてきたと感じると述べている。充足感を得る場面が日常の中にあると感じているわけだ。
エレンはどうだろうか?俺たちは生まれた時から自由で、そして誰しもが特別なんだと感じる彼にとって、壁や巨人の存在は外の世界への冒険を妨げる鬱陶しい存在でしかなかった。どんなに強大な敵でも関係ない、戦えと作中でモノローグが出ているように、他民族全てという強大な敵を前にしても彼は戦おうとする。エレンにとって壁の外にある余計なものは全て自由を妨げる邪魔者だったのではないだろうか?憎悪で世界を滅ぼそうとしたのではなく、不自由を生み出す源泉を排除しようとしたのだ。作中で子供の命を奪うことに罪悪感がある描写があったが、その人間を憎んでいるわけではないので当然だろう。自由を阻む「壁」だから破壊しようとしたのだ。自民族の命を守るためという大義名分もあるが、仮に地鳴らしが失敗するとわかっていなくても彼は実行しただろうと語るのも、自由を求めての行動だったことを裏付けている。
胸を張って言える感想は何か?
単行本での加筆修正部分を除いて全て読み終えた際に真っ先に思ったことを書いておこう。エレンが地鳴らしを成功できなくて悔しい。漫画の中は自由であっていいのだ。社会から非難されるような内容であっても、描いたっていいんだ。せめて物語の中だけで世界を平坦にしてもいいじゃないか。

自由への渇望を訴えるエレンのことを作品を通して好きになっていった。アルミンやミカサ、ハンジ、ライナーの考えはもっともだが、それでもエレンに自由を与えたくなってしまった。作品を通してエレンに感情移入しすぎてしまったのだ。閉塞的な壁の中の世界で自由を求めて咆哮するエレンが好きであるからこそ、最終回は物悲しい気持ちで満たされてしまった。ベルトルトは無知な状態で壁を壊したが、エレンには自覚的に「壁」を壊してほしかった。
おそらくだが、これまで書いてきた感想はかなり普遍的で平凡なものだと思う。作者である諌山先生からすれば狙い通りの感想になっているのではないだろうか?諌山先生はインタビューでこう述べている。
—「読者に衝撃を与えたい」というのが執筆の動機とのことでしたが、「読者の記憶にメッセージを残したい」という思いもあるのですか?
諫山:「メッセージ」はちょっと恥ずかしいというか、自分に対して「おまえは人にメッセージを与えられるような人間か」とか思ってしまうんですよね。
民族浄化や差別がテーマにあったとしてもメッセージを発信したいわけではないのだから、諌山先生はアルミンの視点の正しさを訴えたいわけではないのだろう。エレンに感情移入する読者がいることを想定しているに違いない。
最終的にはミカサの愛とアルミンの友愛に胸を打たれる最終回になり、エレンの願い通りにならなかった点は悔しい。自由を求めて拳を振り上げているエレンが一番好きだった。が、それでも全編を通して、本作は傑作と胸を張って言える出来になっている。11年かかった長期連載ではあったが、初めから最後まで丁寧に伏線を貼ってそれを回収しており、キャラクターへの好感度がドラマチックに変動するような物語になっているのも面白い。
最後に作者への御礼で本稿を終わりにしたいと思う。
諌山先生、本当にお疲れさまでした。歴史に残る傑作を読めて幸せです。自由を求めるエレンの生き様が、私という読者に活力を与えてくれます。ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
