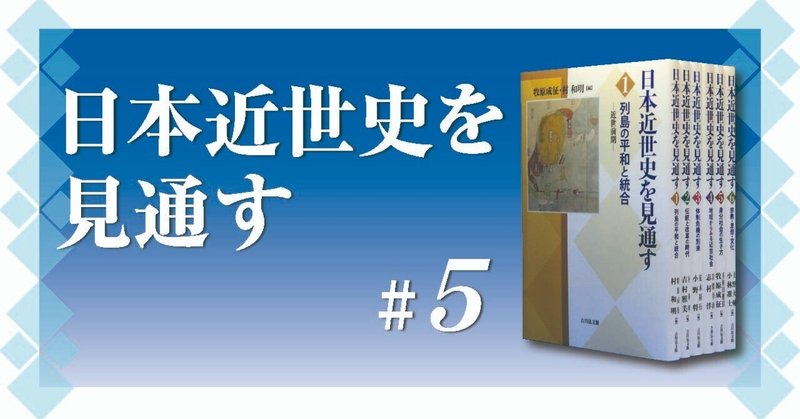
現代人が近世史を学ぶということ 多和田雅保
このほど『日本近世史を見通す5身分社会の生き方』(以下、本巻)の刊行に関わることができた。本巻のねらいについては冒頭「プロローグ」に書いたが、この小文では内容をやや重複させつつ、私が通常の仕事の中で経験したことや考えたことを少しだけ絡ませて述べてみたい。「プロローグ」よりも私見としての性格が強くなるが、わずかでも本巻の普及に役立てばと思う。
私は主に日本近世史を研究しているが、普段は大学の教育学部に勤務して教員養成に従事しており、今年(二〇二三年)で一六年目を迎える。よその教員養成学部でも事情は同じだと思うが、私の勤める学部に日本史の教員は少なく、本年度からは私一人である。
学生の多くは小学校や中学校、そして高校の教員を目指している。自分が日々出会う学生は、小学校教員志望であればあらゆる教科に及び、中学校や高校の教員志望であれば、おおむね社会科や地理歴史科ということになるが、いずれにせよ、日本近世史だけを勉強していればよいというわけにはいかない。
また、二〇二二年度から高等学校の地理歴史科では共通必修科目として、日本と世界の近現代史に重きを置く「歴史総合」が始まった。そのいっぽうで、近世を含む前近代史は選択科目「日本史探究」と「世界史探究」に回されることになった。教育課程において、前近代史と近現代史との間で差が設けられたのである。
近現代の歴史を学ぶことの重要性について異論のある方は少ないと思うが、それでは前近代史や近世史の歴史を学ぶことはさほど重要ではないのだろうか。私は担当する授業において、なるべく機会を設けて近世以外の時代もとりあげているが、やはり自分の専門ということもあって、近世に関する史料や文献を読む時間をそれなりに多く設けている。そのような場合も含めて、常に以下の三つの課題を強く意識しながら、学生と対話を試みてきたつもりである。一つめに、前近代史を学ぶことの意味はどこにあるのか。二つめに、日本史全体のなかで近世という時代がいかなる位置を占めるのか、そして三つめに、近世史を学ぶことが現代を生きる人々にとっていかなる意味を持つのか。学生との対話を積み重ねることで、私自身、研究対象としての近世という時代を俯瞰する眼をわずかばかりでも養うことができたのではないかと思っている。そしてこのことは、本巻の全体構成を考える際にも強い影響を与えている。
本巻はタイトルで「身分社会」と「生き方」という二つのキーワードを掲げているが、普段学生と接していると、日本近世の身分社会がどのような社会であり、近世の人々がどのように生きたのかについて、これまで考える機会を持たなかったという話をよく聞く。多くの学生にとって江戸時代のイメージは、「武士が農民を抑圧していた時代」とか「平和で退屈な時代」、あるいは「町人文化が花咲いた時代」などという、かなり表面的なものにとどまっている。より端的にいえば「あまりピンとこない」時代なのだと思われる。
一方で、近世の身分や生活に関する研究蓄積は地方史なども含めると膨大であり、相当多くの事柄が明らかとなっている。このことと学生の認識との間に大きなズレを感じずにはいられない。学生だけでなく、日常的に歴史研究と関わることのないほとんどの方にとっても事情はおおむね同じだと推測される。戦国時代や幕末ほどではないにしても、江戸時代をとりあげたドラマや小説はそれなりにあって、決して「人気のない時代」ではないと思うのだが。

先に掲げた三つの課題に向き合うためのアプローチはおそらく多様であり、人それぞれであってよいと思う。私の考えは別の機会にやや本格的に論じたことがあり(拙稿「社会集団史を活かす」『部落問題研究』二四五号、二〇二三年)、本巻の「プロローグ」でも言及している。できればそれらをお読みいただきたいが、大雑把にいえば次の二つにまとめることができる。
一つめは、近世を含む前近代が現代とはまったく異なる時代だからこそ、かえって意味があるのだという考え方である。私たち自身の生活が近現代という時期区分の中に位置づけられるとするならば、近現代史のなかで登場する人々は、私たちと同じ括りの中で生きていたということになる。もちろん、近現代とひとくちにいっても段階によって大きく変遷を遂げているし、同じ段階であっても人々の価値観は極めて多様だというべきだろう。しかし、前近代の人間が生活を維持するために集団を形成し、集団に所属することで初めて命をつなぐことができたこと、また、集団を基礎的な単位として身分に所属していたということを重視するのであれば(このこと自体さらなる実証研究を必要とするが)、前近代における人間の存立条件はやはり近現代のそれと決定的に異なっていたとみるべきである。
現代世界における政治や経済のシステムの高度化は、平均寿命の大幅な延びにみられるように、前近代では予測できなかったほど人間の生活や生存を支えてきた側面を持つと思うが、同時に環境破壊や貧富の差の拡大などの問題も生み出しており、絶対視することはできない。人間がいかにして「よりよく生きる」ことができるのかを考えるために、近現代を相対化し、近世を含む前近代にまで視野を広げて人間の生き様を見つめることは大きな意義を持つのではないか。
二つめはこれとはまったく逆に、近世の中に、現代社会の原型ともいうべき事柄を見出すことができるのではないかということである。たとえば都市という存在は、現代社会では極めて高度に展開し、農村社会に生きる人々にも強い影響を与えているが、近世は日本列島全域に大中小の都市がいっせいに建設されたという点で、中世までの社会のあり方と異なっている(この点は中世都市史の研究者との対話をいっそう必要とするが)。本巻には村で生きた人々とともに、都市で生きた人々の生と死について積極的に言及した論考がいくつも含まれている。
ところで日本近世の三都と城下町は、武士による統一政権が列島社会で生きる人々を統合するうえで大きな役割を果たした。多くの人々は、武装を解除されたり武力の私的な行使権を制限されたりする一方で、天下のために有用な職分に従事することが至高の価値とされた。従来の研究では、近世の身分は人間の生活や生存をささえる集団もしくは共同体としての性質と、国家や社会の秩序を維持するために人々に課された役負担としての性質の両面に関わって論じられてきた。近代を迎えて人間は身分編成の枠組みから外れることになったが、「社会的有用性」の有無で人格を価値づけるという思考方法は、現代日本においてもきわめて根強いと私は見ている。有用性を持たないとみなされた人に対するバッシングが起こり、大きな軋轢を引き起こすことがある。その論理を歴史的に解明することは、今を生きる人々にとって重要なのではないだろうか。近世の身分と社会的有用性についても、本巻所収のいくつかの論考から読み取ることができる。
以上の整理に基づくならば、「身分社会」と「生き方」は、先にあげた三つの課題に取り組むために、重要なキーワードといえるだろう。とはいえ最初に書いたように、ここに書いたのはあくまでも個人的な見解に過ぎず、本巻はもっと豊かな論点を多く含んでいる。ぜひお手に取ってご覧いただきたい。
(たわだ まさやす・横浜国立大学教育学部教授)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
