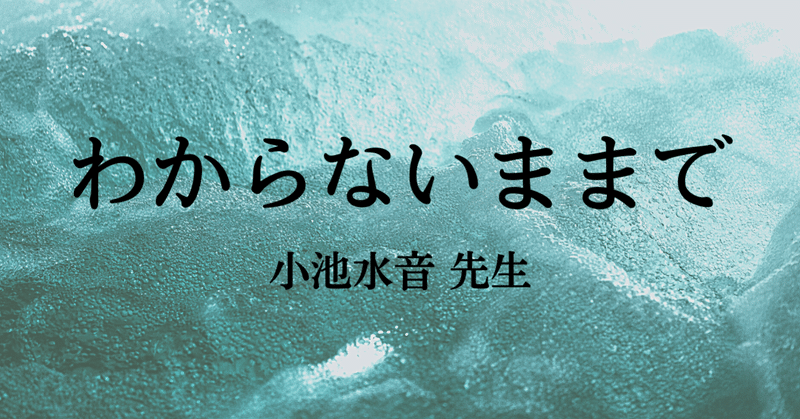
「わからないままで」小池水音先生
※ネタバレを含みます。閲覧にはご注意ください。
※あくまで個人の感想・書評です。
・第52回新潮新人賞受賞作
・約130枚
息子、父、母の交流を描いた家族の物語
離婚した夫婦とその息子の数十年にわたる交流を、多彩なエピソードを交えて描かれた作品。六つの場面から構成されています。
一、息子が幼かった頃の、父親との交流
二、離婚後の父親の生活と、女との交流
三、父親が幼かった頃の、姉との交流
四、母親が死んだ後の、息子と他人との交流
五、半世紀前に亡くなった姉の話と、海外で暮らす息子との交流
六、亡くなる直前の母と他人、そして息子との交流
「いやいや、どれが誰で誰がどれ!?」と思った方、ご安心ください。他の皆さんも、選考委員の方もみんなそうおっしゃってます。
本作には登場人物の固有名詞はほぼありません。ゆえに、登場人物がごっちゃになること必至。しかも、時系列はバラバラです。物事がおこった順に書くと、
三→一→二→六→四→五
となります。(明確に書かれている訳ではないので、間違っていたら教えてください。)
つまり、最初読んでいるときは誰と誰が話している場面なのかがわからない。ただ淡々と、エピソードが積み重ねられていきます。私が読んでいてすべて繋がりだしたのが、四~五のあたりです。それまでは頭にハテナを浮かべながら読んでいました。(読解力が低いだけかもしれませんが。)
ただ頭の中で繋がっていくのは興奮しました。別の場所で流れていた川が集まり一本の川になるような、空いていたパズルのピースが埋まるような、そういう感覚がありました。しかも後半に差し掛かったところだから、ここからクライマックスまでの追い込みとリンクして、後半の方が読んでいて楽しい小説でした。
タイトルの「わからないままで」もいろんな含みが感じられて、考察が捗るなあと感じました。
なんの尖りもひっかかりも湿りもない、無味無臭の文体
文体って筆者が現れるじゃないですか。ねっとりとか、さっぱりとか、あついとか、おもいとか。それが作者の味となり、物語の世界に味をつけていく。文体って、一種の調味料だと思うんですよね。あの先生は和風だし、あの先生はオリーブオイル、みたいな。
特徴がある文体は、味になる分、それが苦手な人には響きにくいという点があります。また、その分野にあった世界観に限定される可能性があることもあるでしょう。ねっとりした文体の作家に青春小説は難しいだろうし、さっぱりした文体の人は読みにくいはず。
でも小池先生の文体は、まさに無味無臭。エアコンで言うと、冷風ではなくドライ。とにかく、湿り気がない。こちらに感想を抱かせない。そこがすごい。なんにでも化けられるし、何より読んでいて引っかからない。前半のわかりづらさを上手く文体で魅せているように思いました。
登場人物の呼ばれ方問題を考える。
本作の選評にも挙がっていた、「登場人物がごっちゃになってわかりにくい」という意見について考えてみます。
確かに、父親、男、夫など、一人の登場人物を指し示す言い方が複数種類あって、場面が切り替わるごとに「この話は息子の話か? 父親の話か? はたまた違う男の話なのか?」と立ち止まってしまうということはありました。
しかし、私はこの手法を肯定的に捉えています。なぜなら、一個人にもいろいろな側面があるということを表現できるからです。本作に登場してくる「父」は、「父」であり、「夫」であり、「男」でもある。「息子」でもあるし、「弟」でもある。人と関われば、その人との関係だけ呼ばれ方がある。本作は家族との交流が描かれ、息子は終盤には夫にもなっており、父にもなっています。その家族としての時間の流れを表現できる手法ですよね。息子もいずれ夫となり、父となり、死んでいく。それが繰り返されていく、輪廻に似た概念が伝わってくるように感じます。
こりゃあ、田中慎也先生もツンデレになるわ。
選評を読む機会があれば、ぜひ田中慎也先生の選評に目を通すことをオススメします。
「好きなタイプの小説ではない」「頭がよさそうで鼻につく」「タイトルが本文の一番最後にいけずうずうしく埋め込んである」など、最初はツンが連発。「わかるけど、まあ落ち着いて」と心の中でなだめていたら一転、後半は怒濤のデレ、デレ、デレ!笑
選評の最後は「だからこそ、この作品を一番に推した。」と締めくくられている。田中先生、小池先生のこと絶賛してるじゃない……。作品への評と作者への評が異なってて、おもしろい選評でした。
作品としてはまだまだ改善点はあるものの、エピソードの秀逸さと文体に関しては絶賛が多かった今回の選評。
小池先生の次回作に期待です。
終わり!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
