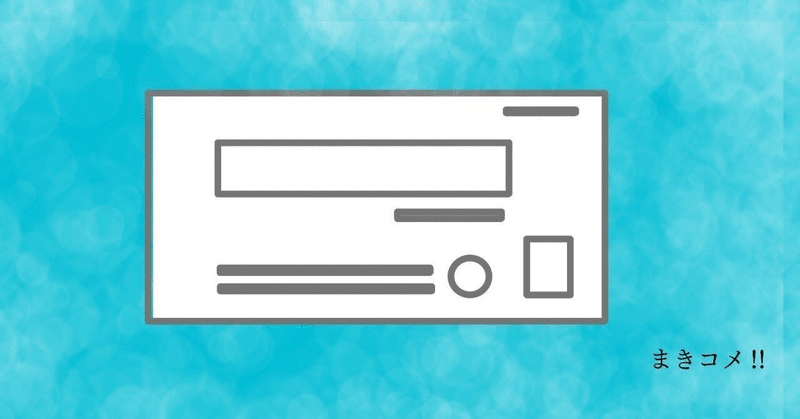
印紙税について~税理士顧問料は領収書に印紙不要~
印紙税についてです。つまり印紙です。まあ、ネタとしてのオリジナリティはほぼありませんが、ちょっと思いついて気ままに書いていて、一応調べたりして、結果かなりの文量になりました。
印紙はけっこう奥が深いのよ
印紙は、商売をやっていればたいてい関わらざるを得なくなると思います。ペーパーレスがいわれて幾星霜、税理士会や会計士会は毎年その廃止を訴えていますが、まあまあの税収規模を誇る(数千億~一兆円くらい)ということなので、残念ながら廃止になることはないのでしょう。
一般に最もなじみ深い印紙は、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号文書)になるでしょうか。いわゆる領収書ですね。普通に物を買って現金で支払った場合、代金が5万円以上であれば、その領収書には売った側が印紙を貼付する必要があります。
ここで、代金の5万円は消費税込なのか抜きなのか(*1)、クレジットカードで払った場合に印紙は関係ないけど、それは各種電子マネーの場合はどうなるのか(*2)等々、日常的によくある場面においてですら論点が生じるので、よーくよーく見ていくと、これはどうなんだというのが出てきます。
*1:消費税額を明らかにしていれば税抜での判断。「消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額」
*2:「コード決済を行った際に作成される領収書等の印紙税における取扱いについて」(令和2年7月2日 経済産業省商務サービスグループキャッシュレス推進室)
税理士が作成する領収書は印紙非課税
さて、タイトルです。タイトルそのままです。税理士の顧問料(ともかく税理士業務の対価)の領収書に印紙を貼る必要はありません。
世の中には税理士専用領収書というのがあります。前橋市だと前橋中小企業会館の3階に、税理士協同組合という組織がありますので、そこで販売しています。「いろんな領収書を集めるのが趣味で」とでも言えば、たぶん税理士でなくとも買えます。複写式、680円です。
その税理士専用領収書には、通常の領収書であれば印紙を貼るべき用紙左上に「印紙税法の規定により非課税」とあらかじめ印字されています。
なぜかというと、「営業に関しないもの」だからです。領収書は営業に関しないものについては金額が幾らだろうと印紙不要です。
国税庁のタックスアンサーNo.7125に「営業に関しない受取書」というものがあります。そこには
個人の場合、「商人」としての行為は営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。
なお、店舗などの設備がない農業、林業または漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。
とちゃんと書いてあります。ここに税理士は例示として出てきませんが、税理士含めいわゆる士業や医師等の作成する領収書は営業に当たらないとされています。(印紙税法通達 別表第一 17号文書 24,25,26)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/07.htm
え?と思うかもしれません。わたしも思います。士業は霞を食べて生きてるのかってなります。でも税理士業務は印紙税法上は営業に関しないものなんです。
商法でどう規定されているかが問題
「営業」の意義については、国税庁はタックスアンサーのほか、質疑応答事例(「営業の意義」)で回答していますが、結局のところ商法に依拠しています。
営業か否かというのは「商人」としての行為か否かということです。「商人」という概念は、ドラクエ3にも出てきますが、現実世界では商法に出てきます。
第4条 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
鉱業と、物品販売業であれば商人で、そうでなければ商行為をすることを業とする者が商人ということなので、では、商行為とは何かというと以下の通りです。商法の規定を全部引っ張ってきますが、適宜読み飛ばしてください。
(絶対的商行為)
第501条 次に掲げる行為は、商行為とする。
一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
三 取引所においてする取引
四 手形その他の商業証券に関する行為
(営業的商行為)
第502条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け
上記の特に第502条各号に定める行為を営業としてするときは、商行為ということになるのですが、ここには税理士の業務は含まれていない、ということのようです。
でも、税理士の主たる業務に税務申告書の作成代理というものがあります。それって第502条5号 作業又は労務の請負 ってことにはならないんでしょうか。税理士は作業の請負を営業している人なんじゃないの。
現に、税務顧問契約書において、申告書を作成することがその業務に含まれるのであれば、その契約書は印紙税法上は、「請負に関する契約書」(第2号文書)に当たるとされています。(印紙税法基本通達 別表第一 第2号文書 17)
士業のほかに領収書の印紙非課税の職業ってほかにもあるよね
ところで、上記の通り、「店舗などの設備がない農業、林業または漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は、一般に営業に当たらない」としていますが、ここに出てこない、また、通達でも出てこない職業であっても、商法上の営業に当たらないのではないかという疑念が出てきます。
例えば、音楽家の演奏代金。演奏をする契約自体は、請負に関する契約となっており、これは法令上明らかです(印紙税法施行令21条4号)。そうすると、演奏契約書を作成したならば、そこには印紙が必要になります。
一方、売上代金の領収書に関しては、不要なんじゃないかと思います。先の商法502条を見る限り、音楽家は商人ではなく、商行為をしているわけではないでしょう(商法の教科書には芸術家は商人ではないとあります)。そうすると、税理士と同様に、売上代金の領収書は営業に関しないものとなります。
あとは、誰かに何かを教える人(塾講師、マナー講師etc…)についても、商法502条の各号にあてはまらなさそうなので、結果として、領収書に印紙不要となりそうです。
「営業」の法令解釈としては商法502条各号に該当するか否か…だと思う
今回、この記事を書くために例によっていろいろググったわけですが、税理の領収書は印紙不要と解説しているのはたくさん出てきますが、ではその理由である「営業」の法令解釈を厳密にどう考えるか、というのまで考えて書いてあるものはちょっとなさそうでした。
ですので、ここからは私見です。
税理士(士業)は営業に関しないから領収書非課税なの?士業は営業してないの?という混乱のもとは、一般的文理解釈上の「営業」と印紙税法上の「営業」が異なっているということではないかと思います。
ぼくのかんがえる法令解釈としては、
①印紙税法17号文書に規定する「営業に関しないものを除く」の「営業」は、商法上の商人と商行為の規定に依る
(すなわち印紙税法上の「営業」=商法上の「商人」)
②そのうえで、士業は商法502条各号に掲げられる各行為に該当しないから商行為はしていない、なので商人ではない。
③士業≠商人 すなわち印紙税法上の「営業」ではない
印紙税法上の「営業」は一般的な意味合いにおいての「営業」と似ているようで異なります。
士業だって一般的な意味合いでの営業、すなわち業として反復継続的行為をしています。当然。
ここで印紙税法上の「営業」は商法上の「商人」と同概念であるというのが私の考えで、さらに士業は商行為をしていないという理由で「商人」ではないとされている、と解釈します。
そのうえで、士業は「商人」ではないから印紙税法上の「営業」に関しない。
と整理するべきところなのではないかと思います。
先の国税庁回答事例も、こういった考えに依っていると思います。
一方、(わりと古色蒼然とした商法の解釈上は)そもそも士業は商法上の営業をしておらず、同条の「営業としてするときは」に該当しないから 商人ではない、としているようです。
(落合誠一・大塚龍児・山下友信『商法Ⅰ‐総則・商行為』 第六版 有斐閣Sシリーズ
近藤光男 『商法総則・商行為法』 第七版)
ただ、わたしは上記の通り、士業は商法502条の各号に掲げられる各行為に該当しないから商人ではないと解釈しています。つまり、士業は営業をしているというのを認めています。営業をしているけれど、商法上の商行為はしていないよねという整理です。これは、事業税において、事業は確かにしているけれども、事業税を課す業種に掲げられていないために対象外となっている、というのとパラレルです。
でも、税理士に限って言えば、税務申告書作成は作業の請負で、これは502条に掲げられている行為になるんじゃないの…という疑問はありますが。
法令解釈を突っ込んでいくとキリがなく、釈然としないところは残るもののともかく、税理士は領収書に印紙を貼る必要はありません。あー印紙は奥が深い。
本日は以上です。ご覧いただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
