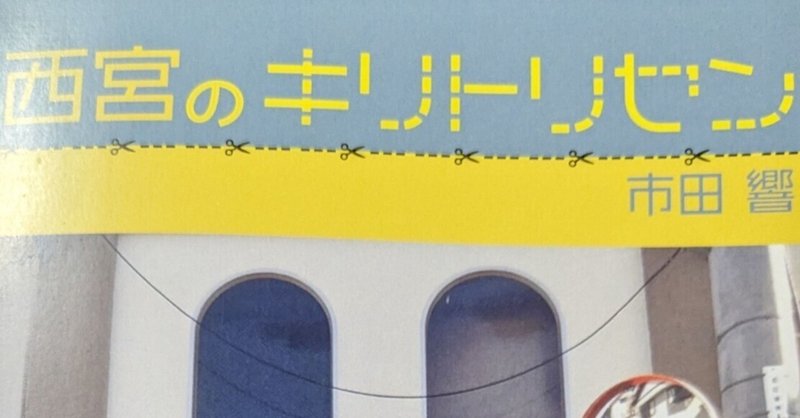
降りてくる西宮
写真というのはたしかにどこか特定の場所を写しているのに、写ったものは常にどこかよそよそしい貌をしている。見慣れた通勤路、見慣れた河川敷、見慣れた信号、見慣れたコンビニ。しかし写真になったそれらは必ずそれらの見慣れた記憶とはどこかずれている。
見慣れた西宮の光景が、初めて見たどこかのように写るかもしれないし、違う眼球から見た映像に見えるかもしれない。まぁあたりまえといえばあたりまえで、レンズという眼球から見てるからなのだが。
人が何かを「見る」とき、動員されるのは眼球だけではないのだと、あらためて思う。場所の記憶が眼球からの情報を歪める。懐かしい記憶は懐かしさを被せるし、嬉しい記憶は嬉しさを、悲しい記憶は悲しさを風景に加えるだろう。
しかし写真はそんな記憶なんていう曖昧なものを剥奪して風景だけに引き戻してしまう。写真がどこかよそよそしい貌をしているのはそのせいだ。
人は何かを見るとき、まぁみごとに都合よく、見たいものだけを見ているものである。
人間の目はほぼ一点にしかピントが合わない。眼球はコンピュータ設計であらゆる収差を除去された最新レンズのようには高性能ではない。その性能の悪さ(?)は、見たいものだけに焦点を合わせるという目的に合致してはいる。
ところが写真のレンズはパンフォーカス的に目の前の風景を網羅する。人がそのとき見なかったものまでドライに写し込む。だからちょっとよそよそしく見える。
よそよそしいというのは、余所余所しい、または他所他所しいと書く。別に悪い意味ではないと思う。
どこに対しての「他所」なのか、というと自分という枠の中にあるものから遠い、ということであり、自分のテリトリーから切り離した外の視点ということだ。
大げさなことを言ってみてもいいだろうか。
神の視点、とか。
大袈裟すぎて恥ずかしいわ。
僕ら写真を撮るもののあいだでは「写真の神が降りてきた」とかいう言い回しをする。あ、写真に限らないか。みんな使ってそうだね。バスケの神が降りてきた、とか。
どのような言い回しであれ、自分の意図とか能力とか、そういう「枠」の外から何かがやってきたとき、人は安易に神のせいにしがち。
神というと大袈裟だけど、ひるがえって「自分」というものの小ささを意識するというのなら、その比較級は間違っていない。
そんな小さな自分が、こじんまりした美意識で、風景を見たり、いろいろ考えたり、目の前のものを美しいと思ったり、コンチクショウと思ったりするのである。
いつもよそよそしく素っ気なく、目の前の風景を切り取るだけのはずの写真が、たまに神を呼んでくるのが面白いよね。ぶっちゃけ自分の小ささ・狭さを知る、というだけの話なんだけど。
たしかに西宮で、見知ったはずの(もしくは知らなくてもありがちな)風景を撮ったはずなのに、見たこともないような場所に写ったりする。
写真という「別の目」で見続ける限り、西宮(じゃなくてもどこでも)は何重層もの風景を積み上げていき、そして前に見た風景を再び同じようには見ることができない。
記憶というのは沈殿してしまうから、同じではない風景を同じと信じてしまいがちだけれど、層に積み上がったその場所の光景を、皮をめくるように新しく見直すことができるのが、写真というものの面白さであり、怖さでもあり、摩訶不思議なところなんだよなぁ。
(市田響写真集『西宮のキリトリセン』笹舟書房2023に寄稿)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
