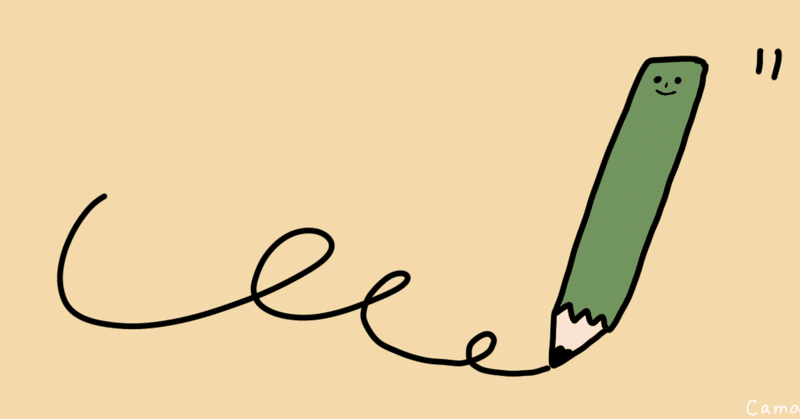
詩とエッセイの境目は?~「詩人会議」4月号の読者会にて
先日、今月号(2024年4月号)の『詩人会議』の読者会(合評会)に出席しました。大塚の詩人会議事務所にお集まりの皆さん(上手宰さん、北島理恵子さんら)と、リモート参加勢(野口やよいさんなど)合計13名が集まり、参加者の作品を中心に、「この表現がいい」「ここはもっとこうした方が」といった意見が忌憚なく出されました。本当に皆さん、詩の読み方が深くて鋭い!毎度のことながら、たいへん勉強になりました。(※読者会は『詩人会議』の定期購読者なら参加できると思いますので、ご興味のある方は事務局まで問い合わせてみてください。)
その中で「詩とエッセイの境目はどこか?」という話題が興味深かったので、記しておきます。
月刊『詩人会議』には、毎号いくつかのエッセイが掲載されています。特に今月号のエッセイは文体が素晴らしく、詩のような美しさだったために、このような話になりました。
以下は今月号に掲載の、野口やよいさん・玄原冬子さんのエッセイの抜粋です。
父が亡くなったあと、堰を切ったように父を巡る詩が頭に浮かんだ。昨年、それらを集めて詩集『星月夜』を上梓した。
(中略)
詩集の中に「ばら」という詩がある。<どんな小石がいつの間に/父子を隔てる山へと聳えたのだろう>
(中略)
それは、強烈な体験だった。命を見送ることは、自分を越えたところの力に委ねること、振り回されること。父はもちろん、見送る側も、人としての体裁を整えられなくなって、平素は行儀よく内に畳んでいるものを外に飛び出させた。激しい嵐のなか、私は気づいたら山を蹴散らして、父の手を握りしめていた。
『詩人会議』2024年4月号 p.26
幼年から小学校を卒業するまでの間、毎年、夏の盛りを小さな海辺の町で暮らした。穏やかな波音に包まれた東伊豆の川奈という、その町。祖父の代からの宮大工を継ぐ、その叔父のもとに妹と二人で預けられて従兄妹や地元の子どもらに交じり、朝から晩まで日がな海辺で過ごす。それが私の「夏」だった。
(中略)
我さきにと浜まで走って、背の高い順に崖のような岩場を弾むように降りる。まだ昼前の、熱く灼けはじめた浜石を跳んで。そうして一旦海に入ると、まるで小魚の群れのように、思い思いに散ったり、ゆるく繋がったりしながら、飽くことなく日の暮れまでを過ごした。
『詩人会議』2024年4月号 p.30
いかがでしょうか? 情景の描写が素晴らしくて、このまま散文詩といってもいいような美しさだと思いませんか?
そこで参加者のお一人・あらきひかるさんが、「以前、中村明美さんに“詩とエッセイの境目はどこだろう”と質問したことがある」と発言されました。それによると、中村さんは、「主張したいことがある時はエッセイ、そうでない時は詩にする」というご見解なのだとか。う~ん、なるほど!
いずれにせよ、今月号の「詩人会議」は、私にとって保存版です。私も野口やよいさんや玄原冬子さんのような美しいエッセイが書きたい!今後のお手本にしようと思っております。(※今月号には私の文章も載っていますが、お二人の文章と比較すると、中学生の文集かとツッコミたくなります笑。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
