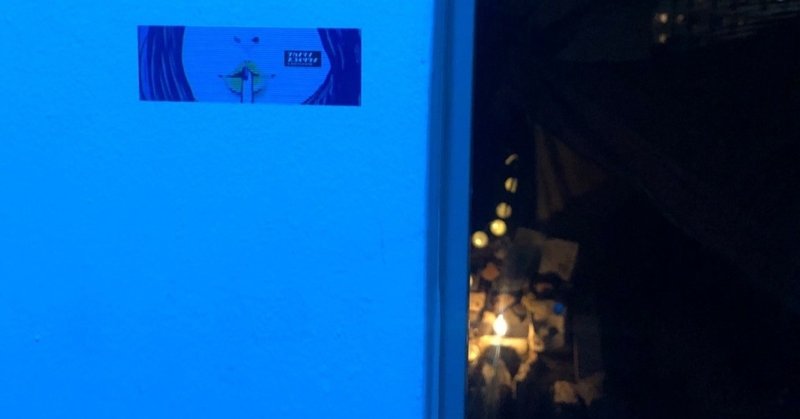
埼玉愛、サウナ愛。「物語」は、いつでも自分の中に
昨日、2年間通った大学院での最期の講義が終わった。
社会デザインとしての物語法
そのシラバス(教授による授業計画)を要約すると、以下であった。
物語は、自分が何者で、何を成すために存在し、どこに向かおうとするかを示唆する枠組みである。(中略)「物語は社会変革装置である」という仮説をもとに、社会デザインの研究と実践の装置となる物語の構造を詳らかにする。
時代は、社会の階層化、排外主義など、社会を分断する主義や価値観が顕著になっている。だからこそ、「他社を遠ざける物語」ではなく、「他者と出会う物語」の重要性の議論を深める講義であった。
大学院では、問題解決のフレームワークを多く習得し、PDCAをいかに効率よくまわすかが議論されるような講義も多く用意されていた。けれど、自分が今後、この大学院での講義を思い出すとしたならば(映画などが多数引用されて楽しく入り込めたというのも大きかった!)、圧倒的にこの講義で共有されたことのような気がする。ビジネス界隈でも、「物語が必要だ」と言われて久しいが、結局は、まずは「自分の物語ありき」なのだよな、と。人に共感してもらうための物語の種は、やっぱり自分の中にしか生まれない。
埼玉愛、サウナ愛
そんなことを考えながら、友人に誘われるまま、「取り壊しが決まっているビルの屋上で移動式テントサウナやっているよ」と神泉(渋谷の奥の方)へ。そこには、外気温と同じ水温、つまり昨夜で言うなら9度(これはシングルと呼ばれ、サウナ界で言っても驚異的な冷たさにあたる)の水風呂も完備し、外気浴、チルスペースも用意されていた。
ツカノマノスゴイサウナ、予約に各種情報は👇に突撃〜🦏🦏
— サイ坊@ツカノマノスゴイサウナ (@SaunaSugoiSai) November 19, 2019
公式: https://t.co/82vKp9qFk6
予約: https://t.co/E9Z1nxpDud
サウナイキタイ: https://t.co/iYSK2MnHRL
ロウリュ、水風呂、外気浴にグランピング、渋谷区神泉の屋上に爆誕したツカノマフードコートとのコラボテントサウナ⛺️サイっこう〜 pic.twitter.com/5nbh2vbpO4
埼玉愛とサウナ愛が極まって始めた活動らしく、埼玉から車で薪を運び、ロウリュウ用に長瀞の水を汲み、奥秩父のドクダミの葉を運び、サウナハットはサイで、外気浴時の椅子は所沢のお婆ちゃんから買い取ったとか……(苦笑)。「まったく採算に合わないんですよ」と運営している若者2人は笑っている。
今、彼らが活動しているビルにはエレベーターがない。屋上(7階部分)までは階段。テントや水や薪を自分たちで運び入れたらしい。急に必要になった備品を近くのスーパーまで猛ダッシュして買い出しし、戻ってきた後「こんな甲斐甲斐しい動き、通常業務(平日はサラリーマンらしい)なら絶対にしない!」と一言。
こういうことは真剣にやった方がおもしろい。
きっと、彼らを衝き動かしているのは、その思いだけなのだと思う。
「好き」は強い
尊い!
最終講義を終えて、いろいろなことが頭の中をグルグルかけめぐったていた時だったけれど、自分のやりたいことをただ無邪気に楽しむ若者の行動力をただただ「尊い!」と思った。案ずるより産むが易し。そう言えば、なぜか気温9度の中、「水風呂から始める」と頭まで浸水した友人も尊かった(苦笑)。あぁ、バカになるって尊い!
そうだ私は、その昔、バカになりたかったではないか!
バカ田大学では、「“バカ”ってなんだろう?」という突き詰めれば突き詰めるほど、どんどん哲学的になっていく問いかけと向き合いました。歳を重ねれば重ねるほど、バカになることが難しくなっていきます。「笑わせる」ことより「笑われる」ことに重きを置いた人生をまっとうされた赤塚不二夫先生の生誕80年企画「バカ田大学」の卒業証書を受け取れた自分を「お前は本当にバカだ」と最大限に褒めてあげたいと思います。これでいいのだ!
FOLLOW YOUR BLISS=至福に従え
講義の最期、教授からのラストメッセージとすべてがシンクロした夜。
【今日の一冊】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
