
アイデアドリブンなものづくり。 『ひともじにっき』をつくって気づいたこと 【前編】
余日[yoka]はアイデアをたらたら出して、 できるものからこつこつ形にして、 「なくてもいい」をつくる集まりです。
「ユーモアのある無駄」と称したアイデアを考え、Twitterで公開。3年間の活動を経て、25個のアイデアが溜まりました。
2023年5月、初のプロダクトである「ひともじにっき」を携えて、余日をリニューアル。アイデアだけにとどまらず、形を与えるところまでに挑戦したのはなぜなのか。
『ひともじにっき』の制作の裏側や、そこから得た気づきを伺いました。
ーーーーーーーーーーーーーー
まひろ : 余日立ち上げメンバー
ありさ : 2年前より余日に参加
聞き手 - きみほ(新入りメンバー)
ーーーーーーーーーーーーーー
▼余日について、詳しくはこちら▼
アイデアは、生活を振り返るところから
ーーアイデアを公開する動きはどういう流れではじまったんですか?
まひろ:どうだったかな…
アイデアを限りなく想像できる形にしてSNSで発信したら、それが起爆剤になって何か生まれるんじゃない?って考えたのがきっかけかな。
ありさ:私が入ったタイミングでは、Miroにいっぱいアイデアの種みたいなものがありましたよね(笑)
Miro:オンラインホワイトボードツール。付箋を貼ったり絵を描いたり、アイデア出しなどでよく使われる
ーーアイデアってテンポよく出てくるものですか?自由すぎると、何から手をつけていいかわからない。みたいな感覚が個人的にあって。
ありさ:うーん。初めて参加したときのアイデア出しは、みんながポンポン出すのが印象的でした。「そういえば昨日さ…」みたいな感じで。
まひろ:あったね。まずは生活の振り返りから入って、1つキーワードが出るとそこからいろいろ派生して出てくる。マインドマップみたいにどんどん広げて、そこから意味ありげなものを選んでいく感じかな。
ユーモアとは「必要に感じてしまう魔法」?
ーー意味ありげなもの。
まひろ:余日は、初期の方では「ユーモアのある無駄」をテーマにアイデアを出していて。
無駄だと思われているものにユーモアを加えたら、誰かにとって必要なものになるかもね、みたいな。
だから、リニューアルして掲げた「誰かの“あって良かった”にしたい」っていう意識はずっと持ってたんだと思う。そうじゃないと成立しない。本当の意味での無駄は本当に無駄になってしまうから。あたりまえだけどね(笑)

ありさ:そこ、毎回壁ですよね。本当にいるのかな?ってちゃんと精査して。
まひろ:アイデアを「たらたら」とは言うものの、割と毎回真剣に考えていたね。それでも恥ずかしくなるようなネタもあったけど(笑)
ありさ:思いついちゃったというか、親父ギャグとして成立してしまったってときは、言わずにはいられないですよね(笑)
まひろ:そうそう。風呂が沸いたらフロアがわくみたいな。マジでくだらないけど、でも誰かに伝えたい。これを本当に誰かが必要としてくれたら面白いし、みたいな。でもそれって、魔法みたいじゃない?(笑)無駄なのに、必要そうって。無駄が必要になるかもしれない魔法。
デザインというかアイデアは、それくらい自由であっていいんじゃないかなと思ってる。どんなにくだらなかったとしても、そこから派生して広がる気づきもきっとあるはずだから。
【#ユーモアのある無駄 No.006|#DJオフロア】
— 余 日 -yoka- (@yoka_yohaku) August 1, 2020
風呂という名のフロアをわかせてくれる、ターンテーブル型の給湯パネル
お風呂って沸かした後入るまでがめんどくさい…
そんな小さな悩みをダジャレが解決(?)してくれました。
DJハイラザルの煽りに合わせて、ノリノリでお風呂にGO!#yoka #余日 pic.twitter.com/Zt3ZJWWVNn
「ひとりよがり」を他者にひらく

ーー今回のプロダクト第一弾「ひともじにっき」の元アイデアが、実は余日としてはじめて公開したアイデアでしたよね。なぜ「ひともじにっき」だったんですか?
まひろ:アイデア段階では「ひともじにっき」も、「日記」というキーワードが何気なく出て、小学校の夏休みとかで書いた1行日記が思い浮かんで。
限りなく単位を減らして、一文字にしたらどうなる…?みたいな、本当に軽いノリで。それ以外にも日記を中心にいろいろなアイデアが出てたような気がするな。そこから、意味とか課題感を肉付けしていくイメージ。
プロダクト第一弾は、正直一番イメージの湧くものを選んだ。あんまり深い意味はないけど、もしかすると一番最初のアイデアが一番力を入れて考えられていたのかもしれない(笑)
【#ユーモアのある無駄 No.001|ひともじ日記】
— 余 日 -yoka- (@yoka_yohaku) June 25, 2020
ひらがな一文字で今日と明日を綴る日記。
1日の感じたこと、明日に向けての願いってうまく言葉に表せなかったり。
いっそのことひらがな一文字で綴ってみたら??#yoka #余日 #ひともじ日記 pic.twitter.com/CxAjDyXOzW
ーー「ものをつくる」にあたって、考えていたことはありますか?
まひろ:これは個人的な思いなんだけど、自分の中の「ひとりよがりな感覚」というのを大切にしていて。
あんまりポジティブに使われない言葉だと思うんだけど、ある種のエッジの効いた個性というか「主観」「譲れないところ」みたいな。「偏愛」とかも近いかも。
最近だとAIの発達もすごいし、このままだとデザイナーの仕事も7割ぐらい、もしかしたら9割はなくなっちゃうかも。そんな中で、AIを使いこなすのはもちろんだけど、楽しい仕事をし続けるにはどうしたらいいんだろうって。
そう考えると、“その人”由来の考え方とか気持ちとか、そういったものしか武器にならないような気がしているんだよね。
でも「ひとりよがり」をそのまま差し出しても、ただの「ひねくれ者」でしかない。
余日に目を移すと、すごい“その人”由来のことをやってきているから、今以上にひとりよがりな部分を人にちゃんと伝えられるように、不快な気持ちにさせずに人とシェアできるようになる必要があるなと。
わかりやすくターゲットが誰か、とかではなかったんだけど、でもやっぱり、どういうシーンで使われるかな、とか、実際はどういったニーズがあるかな、とか。今まであまり考えてこなかった分、「ひとりよがりを他者にひらくぞ!」という意識でその辺りを考えてたな。
ありさ:特に今回の「ひともじにっき」は、メンバー内で話し合いすぎて、余日全体でひとりよがりの固まりになっちゃってて。
他の人にぶつけたときに、ここは伝わらないなとか、こういう使い方がした方が実生活に合うなとか、考え方の変化がありましたよね。
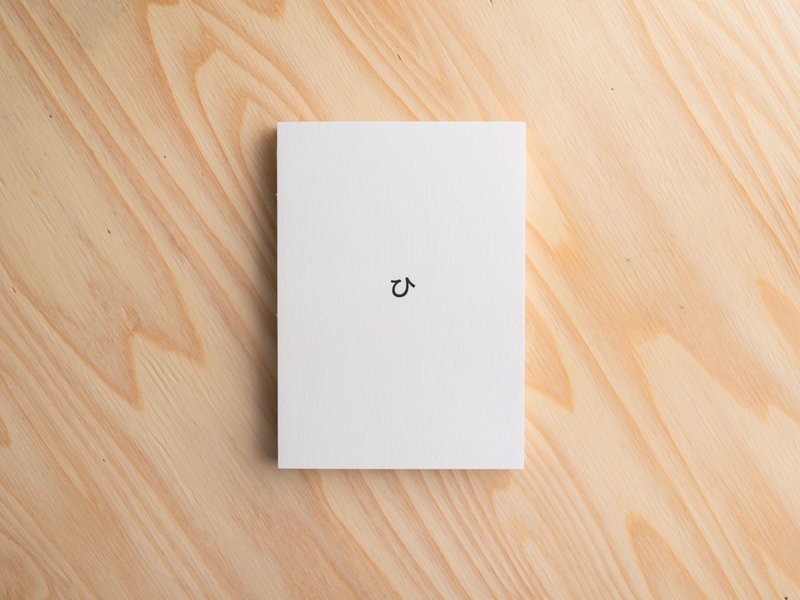
ーー「ひとりよがりのアイデア」が「みんなのモノ」へと変わっていったんですね。
まひろ:アイデアだけだと、良くも悪くも「面白いね」だけで終わってしまう。
モノにするからにはきちんと届け切りたいし、そのためには使い手に「自分だったらどう使うか」とか、僕ら以外の人にも自分ごととして考えてもらわないといけない。これもまたあたりまえなんだけど(笑)
ありさ:余日のアイデアは、手にした瞬間に何かが変わるものじゃないし、ましてや便利になるとか効率化されるわけでもない。それでも、「あってよかった」ものであると信じているし、大きな変化を感じてくれる人もいるかもしれない。
使い手の気持ちや発想に委ねられてる部分も大きいので、プロダクトにしたときに、そこをどう理解してもらうかのハードルは感じていましたね。
ヒアリングは「価値観」を「価値」にする作業

ーー具体的にはどんな部分が変化していきましたか?
まひろ:ヒアリングをした時、「発想はめっちゃ面白いけど、あまりにも僕の目線と一般人の目線に乖離がある」って言われたことがあって。
改めて考え直してみると、発案者がみんなデザイナーだから、一文字にまとめるとか、アイデアを出すみたいなことには確かに慣れていたんだよね。
誰でも自然に使えるだろうと思っていたけれど、ヒアリングする中で「結構難しい」って言われることが本当に多かった。
でも同時に、こうやってすりあわせていくことこそがひとりよがりな「価値観」をみんなの「価値」にする作業なんだなと、腑に落ちた機会でもあったかも。
ーー確かに。私も初めて聞いた時は難しさを感じました。
まひろ:最初は、一文字を書いた上で今日あったことを3行の罫線に記す形式を採用していて。
そもそも一文字の日記って言ってるのに、罫線あるやないかい!っていう気持ちもあって。あんまりしっくりきてなかったの(笑)
それを、色々振り切って見開きで1日分になる今の形に変えて、一文字で表現するためのアイデアスペースを作ったんだよね。左側にメモを取って、キーワードを選んで、右側に一文字を「表現する」ようにしてみた。
そうしたら結果的に、僕らがデザインを考える上でやっているワークが生活の中で追体験できるようなフォーマットになって。
結果的ではあるんだけど、多分元々生活がもっと創造的になるツールをつくりたかったんだなという思いに気付かされた。

ありさ:順番を入れ替えたことと罫線を取り払ったことってかなり大きいですよね。そもそも「罫線を超えてもいい」みたいなルールを破って使う感覚が、メンバー内には暗黙であったというか。自分が使ったら端っこの方になんか適当にメモ書いてるなとか。
まひろ:なんちゅう「ひとりよがり」(笑)
ありさ:でも使う人からしたら、罫線がルールになってしまって、飛び出しにくい。自由でいいんだよとは言いつつも、無意識に書き方の制限をしてしまっていた。
だからこの改善で、自分たち本来の伝えたかったことに近づいた気がします。潜在的な感覚に気づいて、それを顕在化させること。ヒアリングって大切ですね。あたりまえかもしれないですけど(笑)
後半に続く
モノとして存在させるからには、誰かの価値にしたい。
なごやかに、やわらかに、言葉を探しながら話す2人がとても印象的でした。
後編は、近日公開です。
アイデアは形にすることがゴールではない。
むしろ「売る」というスタートラインに立つということ。
「なくてもいいをつくる」こと。
そして、「うる」こと。
余日として、
今回のひともじにっきから得た気づきを踏まえて
話をしてもらいました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
