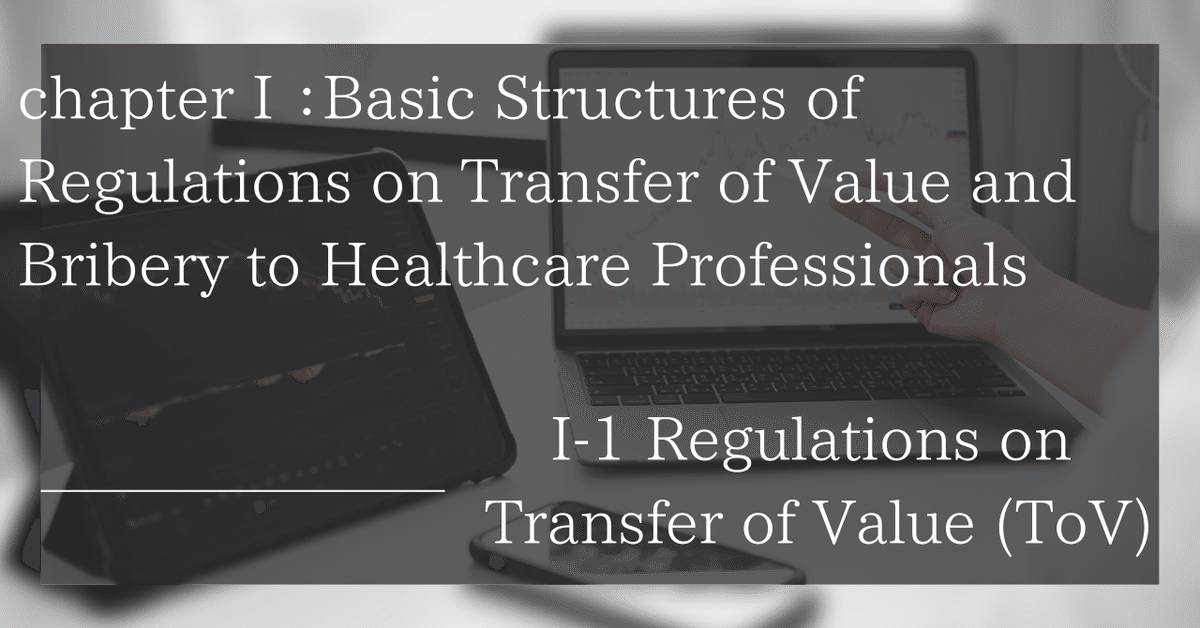
本記事は、医療用医薬品利益供与・贈収賄規制ハンドブック「第一章 医療関係者等への利益供与・贈収賄規制の基本的構造」のうち、1️⃣利益供与規制の内容をまとめたものです。
■英語版は以下をご参照ください。
■関連記事は以下をご参照ください。
(1)法律による規制
1)景品表示法
「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)第4条は,「内閣総理大臣は,不当な顧客の誘引を防止し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは,景品類の価額の最高額若しくは総額,種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し,又は景品類の提供を禁止することができる」としている。
景品表示法は,1962(昭和37)年に独占禁止法の特例法として制定され,従来は公正取引委員会で運用されていたが,2009(平成21)年に,消費者庁が創設されたことに伴い,同庁に移管された。
また,景品表示法が消費者庁に移管されるのに伴い,同法の目的から「公正な競争の確保」との文言がなくなった一方で,「医療用医薬品製造販売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」(公正競争規約)に基づく行為への独占禁止法の適用除外制度(同法第31条5項)に変化はない(ただし,公正競争規約の認定は「公正取引委員会の認定」から「消費者庁長官及び公正取引委員会の共同認定」に変更されている)。
2)医療用医薬品業等告示
「医療用医薬品業,医療機器業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限」(平成9年8月11日公正取引委員会告示第54 号(医療用医薬品業等告示))は,景品表示法第4条の規定に基づき,製薬企業が,医療関係者等に対し,医療用医薬品等の取引を不当に誘引する手段として,正常な商慣習に照らして適当と認められる範囲を超えて景品類を提供する(利益供与を行うこと)ことを禁止している。
ただし,医療用医薬品製造販売業公正取引協議会(公取協)の非会員会社については,公正競争規約の規制対象にはならないため,景品表示法第4条及び医療用医薬品業等告示によって消費者庁による規制を直接受けることになるが,この場合においても,公正競争規約の考え方や内容が医薬品業界における正常な商慣行とみなされ,消費者庁の判断や規制の基準となる。
なお,実務上は公取協へ加盟することが「MR 認定センター」におけるMR(医薬情報担当者)の認定要件となっていることなどもあり,ほぼすべての製薬企業が公取協に加盟しているため,景品表示法及び医療用医薬品業等告示が直接適用される事例はほぼない。
(2)自主基準による規制
1)公正競争規約とは何か?
公正競争規約第3条では,製薬企業が,医療関係者等に対し,医療用医薬品の取引を不当に誘引する手段として,景品類を提供すること(利益供与を行うこと)を禁止している。公正競争規約は医薬品業界の自主基準ではあるが,景品表示法第31 条の規定により,消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けた公正競争規約に基づく行為には独占禁止法の適用除外の効果が認められるため,自主基準とはいえ,法的な裏付けを持ったものである。公正競争規約は1983(昭和58)年に初めて制定され,最新の改定は2016(平成28)年に行われている。
公正競争規約の根拠は,次のとおりである。
❶ 不当な景品類の提供は,医療機関等における医薬品の適正な購入選択を歪め,その結果,医薬品の過剰,不適正使用を招くおそれがある。
❷ 医療保険制度,薬価基準制度の下で,消費者(患者,保険者)の負担する薬剤費及び受けるサービスの内容は定められているので,医療関係者等に対する不当な景品類の提供は,薬剤費に反映されることもなく,医療サービスとして還元されることもない。全く無駄な流通コストになるだけである。
❸ 医療関係者等に対する景品類としての金品提供は,納入価格に反映されることはなく,薬価基準価格の適正な決定を阻害するおそれがある。
❹ 不当な景品類の提供が許容されることは,競争上,外国企業あるいは新規参入企業に不利になり,また,大手企業に有利,中小企業に不利になる。
❺ 医薬品購入の誘引手段として医師等に金品を提供する行為に対しては,社会的非難が強い。
❻ 欧米主要国でも,医薬品の適正使用,医師による適正な処方を歪めることを防止するため,また,医療コスト増大を防止する観点から,製薬企業の医療関係者等に対する金品,サービスの提供の規制は強化される傾向にある。
❼ 今後,医療保険制度の改革が実施されたとしても,景品類の提供行為の弊害は,増大することはあっても減少することはない。

コラム:公正競争規約の成立経緯
日本の製薬業界では,昭和40 年代から50 年代半ばまで,サンプル添付や臨床報告などを利用したキャッシュバックなどすさまじい過当競争が行われていた。1982(昭和57)年10月,当時の厚生省から「医療用医薬品流通の改善に関する基本方針」として,流通改善について具体的取り組みの検討,特に公正競争規約の設定,取引条件の改善についての要請があり,日本製薬工業協会(製薬協)は,同年11 月に医療用医薬品製造業公正競争規約の策定を掲げた。一方,公正取引委員会は,製薬企業と医薬品卸業者のカルテル事件に対し,1983(昭和58)年6 月,製薬協に違反行為の排除勧告審決を下すとともに,日本医薬品卸業連合会に警告を下した。
さらに,1983(昭和58)年6月,厚生省,公正取引委員会は連名で「医療用医薬品の流通改善について」を発表し,製薬産業界に対する具体的な方針を示した。これを受けて「公正競争規約」案を作成し,公正取引委員会の認定を受け,1984(昭和59)年7月に「公正競争規約」が施行され,同時に医療用医薬品製造業公正取引協議会(現在の公取協)が設立された。
このような歴史的な経緯もあり,公取協の権限・運用は完全に製薬協から切り離された。その一方で,景品表示法・公正競争規約の所管が公正取引委員会であったこともあり,日本の利益供与規制は,形式的には「競争法」の一部として位置付けられることになった(この点が日本特有であることは、以下の記事*を参照)。
しかしながら,本来利益供与規制は「処方の選択は患者利益を中心になされており,製薬企業からの不当な利益供与によって医療関係者等の意思決定が歪められていない」という,社会からの信頼(Trust)を維持・向上させるための高潔さ(Integrity)の一部として建てつけられるのが「原点」であり,当該「原点」を十分に理解して公正競争規約を「解釈」することが有益である。この視点を常に有しておくことで「なぜこの行為は禁止されるのか」という根本的な意義・趣旨から規制を理解することができ,「明文で禁止されていないことはやっても良い」という極端な意思決定を遠ざけることができる。このことは,究極的には患者貢献を核とした社会価値の提供と,それによる持続的な企業価値の向上という,各製薬企業,ひいては製薬産業全体の存立意義を高めることにもつながるものである。
2)公正競争規約の構成
公正競争規約は,公正競争規約本体が12ヵ条,公正競争規約施行規則*1 が6ヵ条,運用基準が4つあり,運用基準はさらに10項目に細分されている。公正競争規約施行規則は公正競争規約の実施に関する事項を,運用基準はさらに具体的な実施に関る事項を定めたものである。
公正競争規約本体については消費者庁長官及び公正取引委員会の「認定」,公正競争規約施行規則については同長官及び同委員会の「承認」,運用基準等については同長官及び同委員会への「届出」を行うことによって,これらが景品表示法第31条の要件に適合しているとの消費者庁長官及び公正取引委員会の確認を得ている。
なお,実務上は運用基準の「解説」(公取協会員企業用の内部資料)も重要となるが,「解説」自体には消費者庁長官及び公正取引委員会への届出義務はない(ただし,通常の場合「解説」が改訂される際は,公取協から事前に会員企業へ通知がなされる)。

3)公正競争規約における景品類の定義
公正競争規約第3条「医療用医薬品製造販売業者は,医療機関等に対し,医療用医薬品の取引を不当に誘引する手段として,景品類を提供してはならない」における「景品類」とは,「顧客を誘引するための手段として,方法のいかんを問わず,医療用医薬品製造販売業者が自己の供給する医療用医薬品の取引に付随して相手方に提供する物品,金銭その他の経済上の利益」(公正競争規約第2条第5 項)のことであり,「経済上の利益」として,次が挙げられている。
❶物品及び土地,建物その他の工作物
❷金銭,金券,預金証書,当せん金附証票及び公社債,株券,商品券,その他の有価証券
❸きょう応(映画,演劇,スポーツ,旅行,その他の催物等への招待又は優待を含む)
❹便益,労務その他の役務
http://www.iyakuhin-koutorikyo.org/index.php?action_download=true&kiji_type=1&file_type=2&file_id=2355
なお,「正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして医療用医薬品に附属すると認められる経済上の利益」は,「景品類」には含まれないものとされている(公正競争規約第2条第5項)。
公正競争規約では,製薬企業が提供することができる景品類または経済上の利益の具体例として,次を挙げている。
❶自社医薬品の使用上必要・有益な物品・サービス又はその効用,便益を高めるような
物品若しくはサービスの提供
❷医療用医薬品に関する医学・薬学的情報,自社医薬品に関する資料,説明用資材等
❸試用医薬品
❹製造販売後の調査・試験等,治験その他医学,薬学的調査・研究の報酬及び費用の支払い
❺自社医薬品の説明のための講演会等における華美,過大にわたらない物品,サービス,出席費用
❻施設全体の記念行事に際して提供する華美,過大にわたらない金品
❼少額で正常な商慣習に照らして適当と認められる範囲を超えない物品
http://www.iyakuhin-koutorikyo.org/index.php?action_download=true&kiji_type=1&file_type=2&file_id=2355

4)公正競争規約の運用及び執行
公取協とは,公正競争規約を運用する業界の自主団体であり,次のような活動を行っている。
❶公正競争規約の内容の周知徹底
❷公正競争規約の相談や指導など
❸公正競争規約違反の疑いがあった場合の事実調査と違反に対する措置
❹景品表示法及び公正取引に関する法令の普及と違反防止
公取協の会員会社は,2021(令和3)年1 月1 日現在で224 社となっている。会員会社による総会の下に理事会が置かれ,原則として日本製薬団体連合会(日薬連)会長が公取協の会長となり,製薬協,日本ジェネリック製薬協会(GE薬協),日本医薬品直販メーカー協議会(直販協),日本家庭薬協会(日家協),日本漢方生薬製剤協会(日漢協)の5団体の代表がそれぞれ副会長に選任されている。なお,理事会は29 名によって構成されている。本部には,26 社の常任運営委員会社を含む56 社で構成される運営委員会があり,その下に実務委員会が置かれ,さらに運用基準グループ等が設置されて公正競争規約に関しての研究等を行っている。
また,公取協は本部の他に,全国に8支部を置いており,各支部では,公正競争規約の遵守徹底や違反防止などの活動を行い,会員会社に対して,公正競争規約に関する相談(事前相談制度)や,違反の疑いのある事案の調査等を行っている。
公取協は,事前相談委員会において公正競争規約上不可と判断した案件と同様の企画を,他の会員会社が気付かずに実施することを防止する等のために,相談会社の秘密保持の希望に反しない限りにおいて,会員会社の参考となる事前相談の回答内容を「通知」するとともに,「公取協ニュース」や「相談事例集」などで解説,あるいは支部研修会で報告することがある

(3)違反に対する制裁
公取協本部または支部の調査委員会は,会員会社の違反行為の有無を調査し,違反行為が認められた場合には,当該行為の排除や再発防止の措置を講じる(支部解決が原則だが,支部調査委員会では解決不能な事案や,支部で処理することが不適当な事案は,本部調査委員会が担当する)。
また,調査後は次の「措置基準」に基づいた処分が採られる。
❶違反なし:違反なし,違反に当たらないもの等
❷注意:違反が単発・軽微,将来違反の発生のおそれがあるとき等
❸指導:組織的・意図的な違反行為であって,調査中に当該行為を中止し,再発のおそれがないとき等
❹ 警告:違反行為が組織的・意図的かつ反復・継続,違反の内容・程度が重大であるとき等
❺厳重警告:警告を受け,これに従っていないとき等
❻違約金(100万円以下):厳重警告を受けた会社が,警告に従っていないと認められたとき
❼除名処分:違約金の措置をしたにも拘わらず,これに従わないとき,又は,同様な違反行為を再び行ったとき。
❽ 措置請求:消費者庁長官に対して景品表示法違反として必要な措置を講じるように求める。
調査によって違約金あるいは除名処分となった場合,当該会員会社へ措置案が送付される。なお,措置案に異議がある場合は,10 日以内に公取協に対して文書により異議申し立てをすることができる(措置案に対して異議がない場合は,当該措置による処分が決定することとなる)。
公取協は,異議申し立てにおける追加主張及び立証の機会を当該会員会社に与えて再度審理を行い,それに基づいて措置が決定される。
なお,異議申し立ての手続きは,公正競争規約上,違約金,除名処分の措置を採る場合についてのみ定められているが,実際の運用においては,「警告」以上の措置の場合にも異議申し立ての手続きが認められている。

(4)実際の違反事例:MSD株式会社
現在までのところ,違約金や除名処分,措置請求については実例は確認されていない。しかし,警告以上の措置を受けた場合は公表の対象となり,当該違反行為が認定されることによるレピュテーションリスクは深刻である。
事例:MSD株式会社
2011(平成23)年に公取協は,〇〇株式会社に対し,2009(平成21)~2010(平成22)年にかけて,医薬品取引を誘引する手段として医師に金銭提供した同社の行為を公正競争規約違反とし,次の4件について「厳重警告」した。
❶ 2010(平成22)年11 月,同社の降圧薬に切り替えた場合の治療効果症例をインターネットによって160例収集するプログラムを実施し,医師には1症例当たり1万円の商品券を提供することにしていた。
公取協の指摘によって当該プログラムは2010(平成22)年12月に中止になり,商品券は医師に渡らなかったが「処方すれば商品券の提供があるプログラム」を実施したことが,不当な金銭提供とされた。
公取協は「インターネットを用いて簡単な症例調査を行い,医師に対して謝礼を支払う行為は,一般的に処方することにより金銭の提供が生じることから,原則として規約上金銭の支払いが認められる調査委託ではない」と認定した。
❷ 2009(平成21)年10 月から1年にわたり,同社の糖尿病治療薬の使用実績が多いオーストラリアのBaker IDIへ若手糖尿病専門医をのべ48人派遣し,謝金,旅費など1人当たり約65万円を同社が負担した。会合では参加者の発言時間は最短で約5分30秒,最長で約14 分であった。帰国後の学術誌などへの執筆や講演も依頼がなく,議事録も作成されていなかった。
公取協は「本件謝金の支払い及び旅費等の負担は,規約で認められている海外で開催される自社製品関係の調査研究に関する会合に派遣する際の報酬及び費用には該当せず,不当な金銭提供及び旅行招待である」と認定した。
❸ 2010(平成22)年9月から11月まで,同社が今後扱うHPVワクチンの普及,診療実態,公費助成方法のアドバイスを得るための会合に,のべ88人の医師を招き,1人当たり7万円又は3万円の謝金を支払った。しかし,1人当たりの発言時間は10分前後であった。
公取協は「発言時間は短く,有意義なコンサルティングとはいえない。事前に資料が配布されていない。十分な知識があったとはいえない者も含まれていたことなどから『仕事の依頼』に対する報酬とは認められず,不当な金銭提供である」と認定した。
❹ 2009(平成21)年1月から2010(平成22)年9 月まで,同社の高脂血症治療薬に関するアドバイスを得ることなどを目的とした会合に,のべ3,268 人の医師を招き,勤務医向け会合の参加医師には1人当たり7万円,開業医向け会合の参加医師には1人当たり3 万円の謝金を支払った。しかし,座長,演者以外の1人当たりの発言時間は7分程度であった。
公取協は「発言時間は短い。事前に資料が配布されていない。2010(平成22)年8月25日以前の会合では議事録が作成されていないことから『仕事の依頼』に対する報酬とは認められず,不当な金銭提供である」と認定した。
公取協は事例❶~❹に関して,特に事例❸と事例❹が,以前同社が受けた「警告」と「同様の事案」であることをふまえ,同社に対し社内コンプライアンス体制を抜本的に改善することを求めた。なお,当該措置を受け,同社は公取協の理事を辞任した。
■(参考資料)公取協TOP 医薬品業等告示および公正競争規約、同施行規則、同運用基準
http://www.iyakuhin-koutorikyo.org/index.php?action_download=true&kiji_type=1&file_type=2&file_id=2355
■英語版は以下をご参照ください。
■関連記事は以下をご参照ください。
■全文及び添付資料は以下より入手可能です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
