
独学研究のススメ(CiNiiとJ-STAGE)
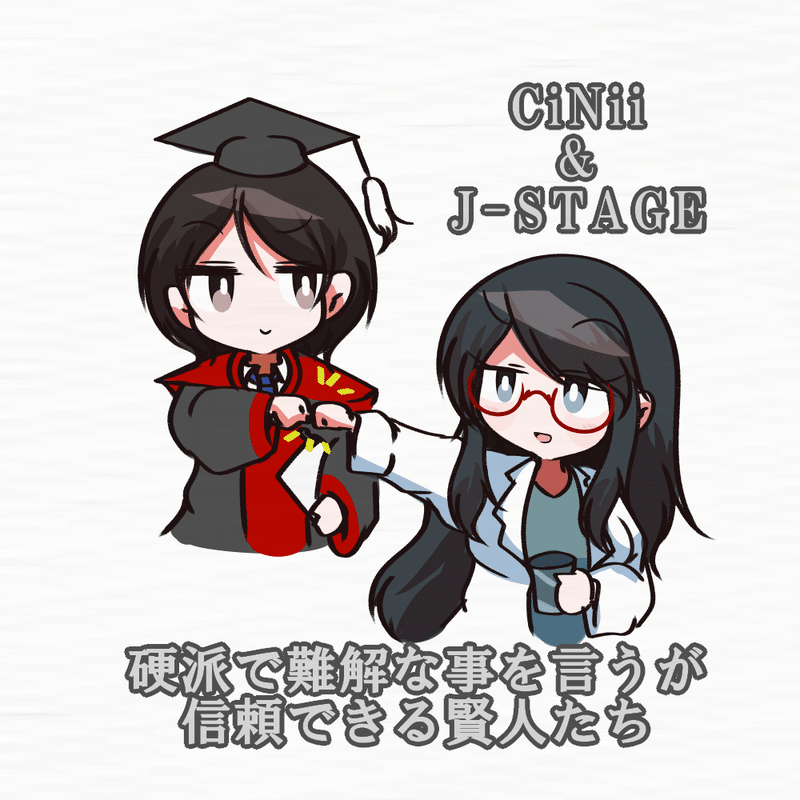
CiNiiとJ-STAGEは、がちがちの論文サイトです。両者共に「硬派で話が難しいが、ある程度の知識や教養があるとこれほど情報を持っている人はいない堅実な学者」というイメージがあります。
堅苦しさという点においては初心者向けではないのですが、確かな情報と論文の掲載量には信頼をおけます。
学術的な視点で悩んだ際やある程度独学研究が進んだ際に見るのをおすすめすべき、中・上級者向けのサイトです(もっとも、転がっている論文を拾い読みするだけでも面白いです。もちろん初心者が使っても構いません)。
CiNiiは、国立情報学研究所が、J-STAGEは文部科学省管轄の独立行政法人科学技術振興機構が展開する情報サイトです。
英語で名付けられているためになんだか難解なイメージを覚えますが、一口で言えば「学術論文や学術誌掲載記事の検索サイト」です。
兎に角質のいい論文や典拠を探したい場合は、ここがトップです。
論文や記事をまとめて紹介してくれる上に、その掲載元まで飛べるようにしてくれる。中にはPDFファイルになってダウンロードができ、自宅でも持ち歩いてでも読める資料もあります。
一部では「レポートや論文のコピペ元」とかなんとか悪く言われているようですが、裏を返せばコピペされるだけの有能な資料や論文が揃っているというわけです。
論文だけに難解で、前提知識が求められるのが欠点で、初心者にはあまりおすすめできませんが、独学研究がある程度進んだ状態においては知っていて損のないサイトだと思います。
学術論文は基本的に信憑性が高く、価値もあるため、独学研究における確認や論拠の紹介などでは絶対欠かせない存在です。
文学哲学をはじめ、諸々の学問の先駆者の論文や学説が集っているのは、とにかく大きいメリットと言えましょう。
内容こそ難解、ニッチな側面もありますが参考文献や注釈が詳しく記されており、この論文をベースにして、参考文献や注釈を読み漁り、知識の蜘蛛の巣を作っていく――というのは、よくよくあることです。
「この部分がよくわからない……」と長らく疑問に思っていたことが、論文や学術記事を通して、先例を発見し「なるほどこういうことなのか」と解決したり、大きな典拠に至ることはよくあることです。
私個人としても文学やら歌舞伎の方面で、何度論文の世話になったかわかりません。
学術機関が作っているだけあってか、サイトの作りは非常に平易で、検索窓がデンと置かれています。ここに調べたいワードや作者を入れて調べなさい――といわんばかりの潔さです。
ただ、J-STAGEは登録論文の大半が認証制限が欠けられており、購入しないと読めない場合があります。
J-STAGEの方が最近出された論文や発表を中心に掲載しており、著作権やらなんやらの縛りがあるわけですね。
それを読む上にはMy J-STAGE登録の上に支払いもせねばならないという制約があります。個々が少し面倒臭い。
しかし、「今現在進んでいる・取り組まれている学説」という物を知る上では、J-STAGEの方に軍配が上がります。腐っても文科省がやっているだけのことはあります。
一方、CiNiiの方は、無料閲覧が多くできますが、情報が古くなっている可能性があり、論文や何やらを参考にする際は、「昔の論文」という視点を考慮しておかないと思わぬ誤りにぶつかる可能性もあります(文系ではそこまでの瑕瑾は無いと思うのですが、理系や医学では掲載されている論文が古臭い学説になってしまっている例は結構あります)。
もっとも、古い論文でも参考になるところは多々ありますので、「古いから時代遅れ」みたいな見方を持つのはやめましょう。
中には「その時代、未だ関係者や当事者が生きていたお陰で採録が出来た」という論文や資料もあります(聞書きや調査報告書)。
こういうものは、今現在では絶対に入手できない代物なので、「古臭そう」と思わず、ドンドン見ておくべきです。
こういう事を云うと嫌味になりそうですが、悪意を持って書かれたモノ以外は、基本的に資料や論文に罪はありません。
学説や発見が二転三転するのは当然ですし、「イマココ」で書かれたものが数年後あっているという保証もありません。
「この論文は間違った事を書いている!」と怒るのは簡単ですが、情報の取捨選択をするのは我々です。
論文を信頼するのも、切り捨てるのも皆己のさじ加減です。勝手に盲信をしておいて欺かれても「この論文や資料が駄目だから」と怒ってはいけません。
情報は毎日のように更新されていきます。そうした発展を知りながら、論文や資料に向き合うことが大切です。論文や資料の比較は、定期的にやっておくべきです。
「論文=絶対的正義」と考えて立ち向かうと痛い目に遭うので、論文にも冷静な目を持って「これは今でも通じる」「これはもう時代遅れだ」といった判断を身に着けていくことが大切です。
もっともこれは一朝一夕に身につく事ではないので、多くの論文や資料を読み、「これは大多数が記している事」「これはどうも眉唾」といった判断材料を有していくことが大切です。そのことに関してはまたおいおい説明しましょう。
最後に、CiNiiの昨日の一つ「CiNii Books」を紹介します。これは意外に便利な検索機能です。「ブックス」の名の通り、大学や研究機関が有する蔵書を調べる事が出来ます。
単なる検索機能と思いきや、全国の機関が有する蔵書・巻数・閲覧状況などをまとめて見せてくれるので、隠れた優れものです。
雑誌類の中には、国会図書館にも所蔵されていないものが引っかかったりします。
無論、検索機能だけなのでそれ以上の閲覧は出来ないのですが、「ここにこういう資料がある、この資料を持っている」と把握するだけでも研究はグッと進歩する事が出来ます。
この機能を使いこなすにはある程度の領域に達することが必要なのですが、その領域の段階は人によってさまざまであり――「この資料を読みたい」という段階が何処で来るかわからない故、最初の方に紹介しておきます。
「そういえばCiNiiにこんな機能があったな」と思い出してもらえるだけでも、研究調査が楽になるのは言うまでもないでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
