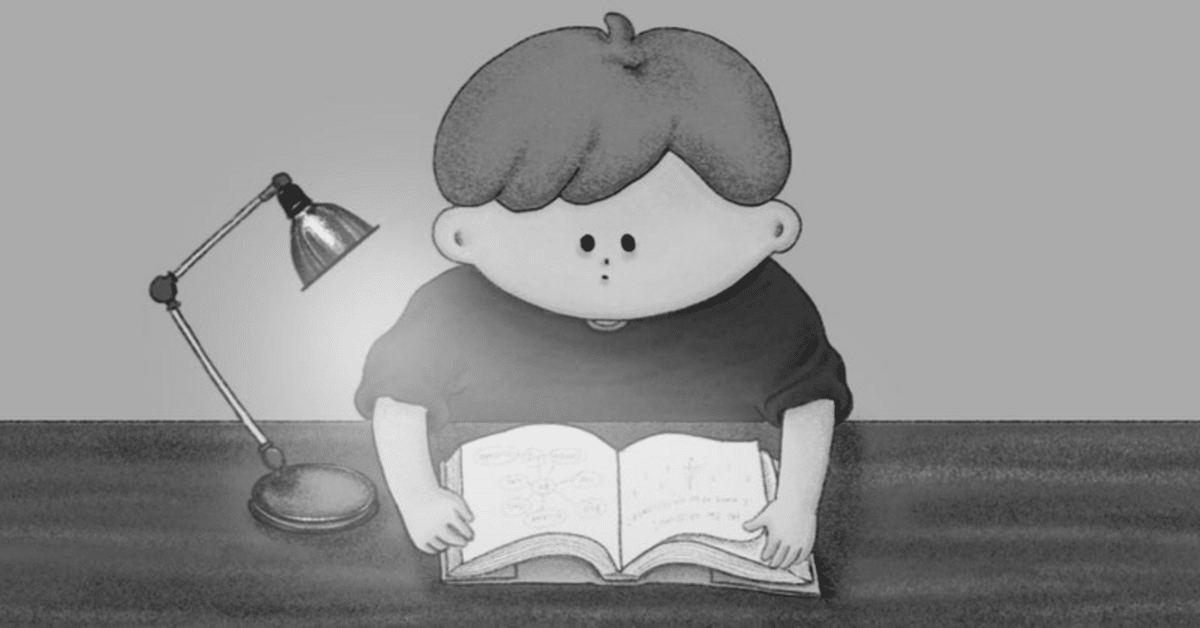
予備試験短答式試験の勉強法
1 目標点数
まず、予備試験の短答式試験には、法律科目として、以下の科目があります。
憲法
行政法
民法
商法
民事訴訟法
刑法
刑事訴訟法
これらの法律科目は、全て30点満点で、法律科目の合計で210点満点となります。
目標は、別の記事でも紹介したとおり、法律科目で210点満点中160点、つまり76%強を得点することになります。
一般教養科目をアテにしないことが合格への一番の近道であると思います。法律科目で160点取れれば、年度によってそれだけで合格点に達することもありますし、また一般教養科目で0点ということもさすがに考えにくいため、法律科目で160点を取れていれば、まず落ちることはないでしょう。
そこで、法律科目で160点を取るために、どのような勉強をすればよいのかについて考えていきましょう。
2 勉強法
(1) いわゆる「武蔵理論」
受験生界隈で知られている短答式試験の勉強法として、「武蔵理論」と呼ばれているものがあります。この「武蔵」とは、自動車教習所演習ソフト「ムサシ」が、過去問の選択肢を解きまくるというものであることになぞらえたものです。
受験生界隈では、この「武蔵理論」がオワコンなのではないか、ということがささやかれています(YouTubeでもこれについて考察を加えている方がいらっしゃいました)が、実際のところどうなのでしょうか。
私個人の意見としては、少なくとも今のところ、「武蔵理論」は、必ずしもそれだけで満点を取ることができるものではないものの、予備試験短答式試験で160点を取るという観点でいえば、「武蔵理論」で十分可能だと考えています。
「武蔵理論」の弱点は、それだけでは未知の選択肢に対応ができないという点にあります。
おそらく、「武蔵理論」がオワコンであるといわれる大抵の場合は、選択肢に未知の問題が出題された結果、オワコンであると言い始めた人がその問題を解けなかったことがきっかけであると考えられます。
特に、民法の場合には、「武蔵理論」は非常に有効であるといえます。民法の問題は、ほとんどの受験生が消去法を用いて選択肢を絞っていくと思います。それは、大体の問題において、5つの選択肢のうち2つないし3つが過去問において出題されたものであることが多いからです。
したがって、たいていの場合5つの選択肢のうちの2つないし3つの選択肢の正誤が「武蔵理論」による勉強の成果によって、即座に判断することが可能です。そうすると、あとは2つないし3つの選択肢の消去によって答えが決まればよし、選択肢が残ったとしても、何とか1つに正解を絞る作業に時間をかけることが可能になります。
このように、民法においては、「武蔵理論」による短答過去問の周回は、本番における選択肢を「削る」ための最大の手段となるわけです。
これに対し、憲法や行政法では、「武蔵理論」が有効ではない場合があります。
しかし、これは、「武蔵理論」がオワコンだからではなく、憲法や行政法の短答式試験の性質上、当たり前のことなのです。それは、民法とは異なり、全ての選択肢について完全に正答しなければ得点が入らないためです。
とはいえ、私の経験上、憲法や行政法は、多くの問題において3つのうち2つ、5つのうち4つは既出の文章である場合が多く、場合によってはすべての文章が既出の文章であることもあります。したがって、この場合でも1つの文章の正誤を判断することに時間を割くことが可能になります。
したがって、憲法や行政法においても、「武蔵理論」による勉強だけでも20点を下回らない程度の結果を求めることは十分に可能です。実際、私は予備試験の憲法、行政法においては、「武蔵理論」だけでそれぞれ26点、21点を取ることができました。
また、刑法や刑事訴訟法は、「武蔵理論」が有効な分野と有効でない分野があります。
いわゆる学説対立問題と呼ばれている問題においては、当然選択肢の暗記である「武蔵理論」はあまり意味を持ちません。ただし、学説対立問題については、論文知識が問われているか、現場思考が問われているかのどちらかなので、そもそも短答式のために特別の暗記すら要求されていないことが多いです。
これに対し、学説対立問題以外の問題については、基本的には「武蔵理論」による勉強だけで安定して点数を取ることが可能になります。刑法でも、憲法や行政法と同様に、全ての選択肢について正解することが必要になる問題もありますが、刑法の場合には既出の文章が出る場合だけでなく、憲法と異なり論文知識で解くことが可能な文章もかなり多いです。そのため、学説対立問題以外の問題についても、刑法や刑事訴訟法ではしっかり正答率を稼ぐことができるはずです。
実際、私は刑法・刑事訴訟法も「武蔵理論」だけで望みましたが、ともに24点ずつ取ることができました。
「武蔵理論」だけでは若干厳しいのは、商法でしょうか。
商法では、会社法だけでなく、商行総則・商行為法、手形・小切手法からの出題もあります。特に手形・小切手法については、論文の勉強をしないという人も多いかと思うので、全く基本知識のない手形・小切手法については「武蔵理論」だけではどうにもならないと思います。
手形・小切手法からの出題はほとんどない(1問くらい)ことからすれば、手形・小切手法を捨てるのも一つの手かと思いますが、怖いのであれば、薄い基本書を一冊購入して、「武蔵理論」を実践するしかないのだと思います。
(2) 結論
結局のところ、私は、「武蔵理論」が短答式試験合格のために最も簡単かつ有効な勉強法であると考えています。
その理由は、まずやることがシンプルであることにあります。
つまり、勉強を始めるために、特に考える必要もなく、とりあえず短答の過去問集を買って、開いて、解く、それだけで済むのです。
次に、「武蔵理論」以外の方法では、ゴールがない、ということも私は「武蔵理論」が優れているといえる大きな理由だと思います。
ゴールがないということは、ずっと短答のための勉強が終わらないことを意味しますが、これでは論文の対策に時間が取れないという悲劇的な状況に陥ってしまいます。
そして、最大の理由が、選択肢を切る・考えるべき文章を少なくしていく、という効果が絶大であるということにあると考えています。
そして、憲法・民法・民事訴訟法・刑事訴訟法については、時間があれば条文を素読することで、さらに穴を塞ぐことができます。刑法や行政法では全くもって素読する必要はありません。
正直、これ以上のことは短答式試験のためにやる必要はないと思っています。なぜなら、予備試験の短答式試験はあくまで突破が目的であって、短答式試験から論文式試験までの期間が2ヶ月しかないことを考えると、短答式試験の前であってもあくまで論文式試験の対策がメインでなければならず、これ以上の勉強はもはや短答式試験のためだけの勉強になってしまうからです。
3 さいごに
以上から、皆さんが予備試験の短答式試験の合格のためにすべき勉強は、いわゆる「武蔵理論」、つまり短答式試験の過去問全7科目が載った本を買ってそれを周回し続けること、ただそれだけです(ちゃんと全ての選択肢について解説を読んで正誤判断ができるようにしてくださいね。)。
解説に色々書き込んだり、択一六法を用意したり、色々なことをおっしゃっている合格者の方がいらっしゃいますが、最大公約数的に言えば、そのような方々も基本的には過去問を周回するのがメインで、そのまとめの方法として書き込みや択一六法を使用したりしているにすぎません。
つまり、予備試験合格のためには、過去問を周回し、それを覚えればいい、ということに尽きます。まとめ方については、自分なりに見つける、というのが最もよいのだと思います。
最初は分からない問題が多いと思いますが、だんだんとスラスラ解けるようになってくるはずですので、何とか力を振り絞って頑張っていきましょう!
では、最後までお読みいただき、ありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
