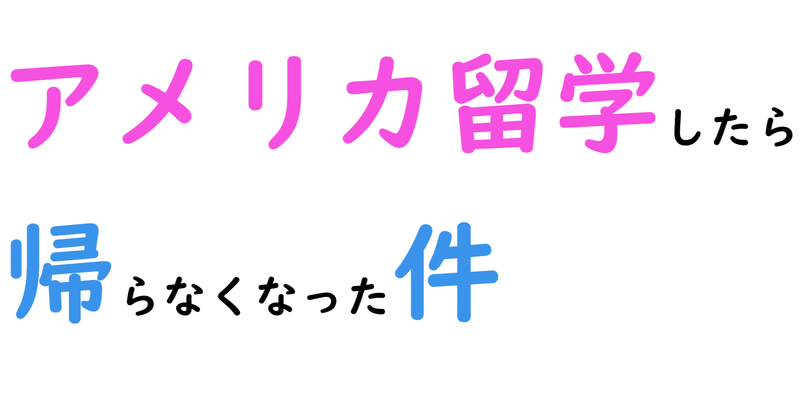
研究室立ち上げの仲間を集めよう!
こんにちは。イリノイ大学の山田かおり (@KaoriYamada01)です。日本で博士号を取ってアメリカで自分の研究室を持つに至った経緯を少しずつ話していこうと思います。今日は2018年年末からの話。
立ち上げメンバー
大型研究資金を得てさぁラボを立ち上げようとした時に誰をまず仲間にしようかと。ポスドク募集、テクニシャン募集を同時にかけますが、私の腹づもりでは1人目のメンバーはテクニシャンがいいと思っていました。ラボマネージャー兼テクニシャンでラボのメンテナンスを一手に引き受けてくれて基本的なルーティンの実験はそこそこの精度でこなせる人材。遠くからリクルートして来てくれるとは思えませんので、大学のサイトで募集をかけ、近隣のラボから流出したような有能な人材を狙います。2019年初頭から現テクさんが参加してくれました。テクさんはとにかくラボの維持には重要なポジションですから、重宝しています。
最強のNo. 2
ポスドク募集はかなりの時間をかけました。アメリカに来たい人は多いので、私のプロジェクトに興味がなくても分野が経験が合ってなくても応募してくる人は多かったです。若手PIが立ち上げるラボでは採用できるポスドクは一人だけ。このポスドクに誰を選ぶかでラボの命運が決まります。
妥協せず気長に探す間に、lab aidsとして学部生が参加してくれました。学部生にとっては研究室で実践を学ぶチャンス、ラボにとっては比較的簡単な実験を分担してくれる人手。経験ゼロから教え込む手間はかかりますが、教育や指導を軽視しては大学の研究室は成り立ちません。大学内のマッチングシステムからまず一人。クチコミで、よくよく知っている研究者夫婦の、息子さんの、友達という伝手で二人目、その子の友達でもう一人。この頃コロナの影響で1か月研究室が閉まり、大学の授業はすべてリモートとなったことで、一人目は研究室をやめ、薬剤師への道を歩み始めました。残った二人は研究室再開後に戻ってきてくれて、初めての実験技術もどんどん吸収して言ってくれています。子供ほど年の離れた子達です。やる気もあって大事に育てるのも楽しいです。
そうこうしているうちに、厳選に厳選を重ねたポスドク候補がようやく決まりました。前の研究室のボスが手放したがらないのを、いったんプロジェクトに区切りがついたらというふうに交渉し(そのほうがポスドク自身の実績にもいいですし)、待つこと数か月、さらに州をまたいでの移動なので自主隔離2週間、待ちに待ったポスドクさんが参加してくれたのが2020年9月のことでした。
働き者、かつ実験手技が実に細かい、丁寧、片付けがきれいすぎて私が散らかすのが申し訳なくなるレベル、ウェスタンブロットのバンドがきれいすぎて、私がもうウェスタンはやらないと引退の決心をするレベル。待った甲斐があったというものです。
仲間がいるよ!
現メンバー、ポスドクさん、テクさん、学部生2人、だんだん人が増えてくるにつれ、最初は未熟なPIもどきだった私が、だんだんPIらしい行動をするようになってきて、だんだんラボがラボらしくなってきました。思えばラボを立ち上げたころ、近隣のラボを見て、どうやって人を集めるの?どうやって人と関係を築くの?と聞きまわっていた私がうらやましいと思っていたような人間関係が、私のラボでも築けていたことに気づきました。こんなラボにしたい、あんなラボはちょっと、と周りのラボを見てイメージしていたこと、ロールモデルが周囲にいたこと、そんないい環境を知っていてここでラボを立ち上げると決めたことがうまくまわったようです。人がいてこそのラボ、今のメンバーを大事にしてプロジェクトを進めていこうと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
