
楽譜のお勉強【51】ヴェルナー・ハイダー『プラカート』
前回の「楽譜のお勉強」は50回目の記念回としてモーツァルトのオペラを読み、少し長い記事を書きました。今回から通常回に戻るのですが、実は今回もちょっとした記念回です。この投稿で私がnoteを始めて連続投稿100週連続を達成いたしました!コツコツと文章を書き続けることも向いているかもしれないなどと感じています。今回は、私がドイツに渡った頃に知り、集中して勉強した作曲家ヴェルナー・ハイダー(Werner Heider, b.1930)の『プラカート』(»Plakat« für Orchester, 1974)を読むことにしました。
「プラカート」とはドイツ語でプラカード、もしくはポスターを意味する言葉です。作曲者は楽譜の冒頭に曲に関する短い文章を掲げています。
この曲はプラカードである。
音楽的ポスターであり、
告知であり、広告であり、
公的な宣言である。
このポスターはオーケストラの
プロモーションである。
音楽の内容とこの文言を照らし合わせると、なるほどこの作品が書かれた1970年代のオーケストラの仕事の、特に現代音楽演奏での仕事で要求されるいろいろな技術的な側面を表していて、プロモーション的な音楽として使えないこともないと思います。楽器の特殊な奏法が多様されていますし、さまざまに工夫されてヴィジュアル的に面白みのある楽譜を再現する作品になっています。
この曲の魅力の大きな一端を担っているのが楽譜の見た目です。この記事のシリーズで何度か図形楽譜作品をご紹介しました。『プラカート』は図形楽譜ではない部分がほとんどですが、ぐねぐね曲がる曲線を自由な解釈で即興演奏する箇所などもあり、図形楽譜の影響があります。また、曲全体は概ね音群作法で作曲されているので、群による音響の推移を示すために特殊なスコア配置を採用しています。楽器の舞台上での配置は特別な指示はありませんが、通常スコアを書くときと違った順番で各楽器が書かれていることがあるのです。ただし、通常のスコアと同様の順番で書かれているページも多数あり、その割合はおよそ半々です。
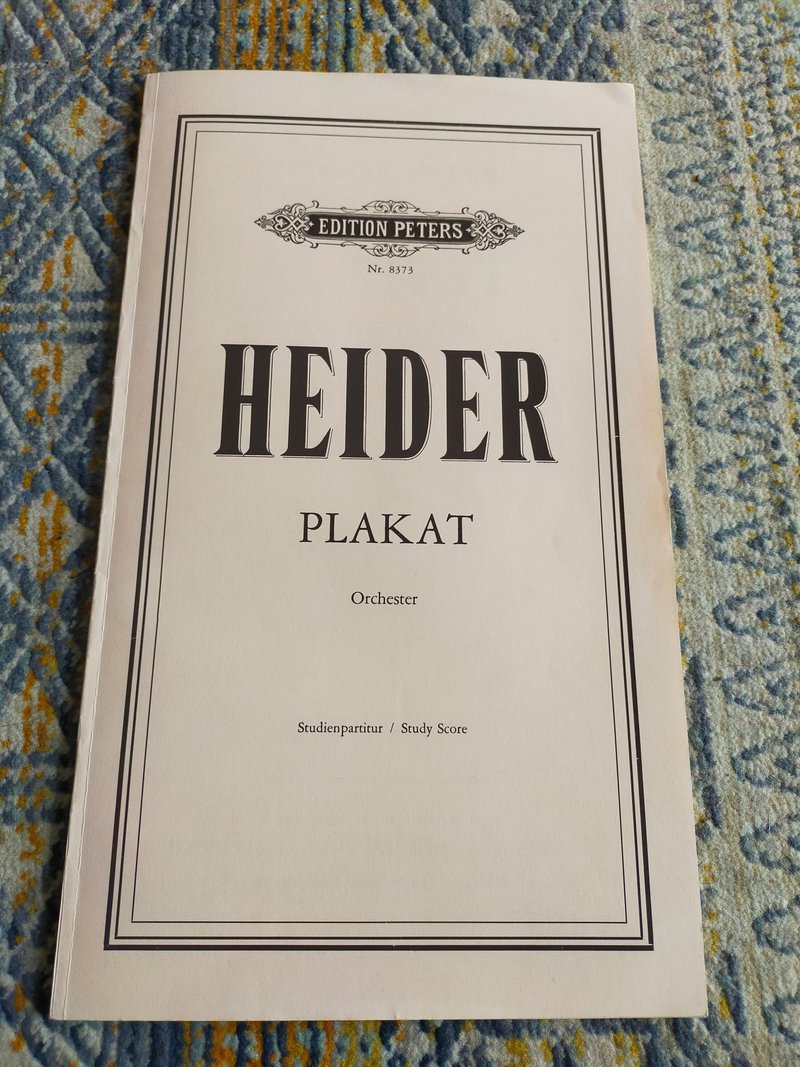
編成は通常の三管編成のオーケストラに、ピアノとオルガンが入ります。弦楽器は第1ヴァイオリン12人、第2ヴァイオリン12人、ヴィオラ8人、チェロ8人、コントラバス6人です。第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンが同数、ヴィオラとチェロも同数というところに特徴があります。3人の打楽器奏者は各奏者14種類ずつの楽器を演奏(重複楽器もあります)する必要があり、物々しい大編成になっています。打楽器セクションが肥大化したことも現代のオーケストラ音楽の特徴の一つに挙げられますから、「プラカード」としての見せ方を意識していると考えられます。
『プラカート』の楽譜を読みづらいものにしている要因の一つに先述のような曲の途中でのスコア配置の変更があります。他にも多くの記譜スタイル変更が曲中にあって、特にテンポやリズムの記譜を厳格なものと曖昧なもので書き分ける際にいくつかの書法が混在していることは、目の流れが止まる要因になっています。記譜の哲学が一定でないように見えます。しかし場面ごとの音楽内容には沿っているので、考えてみると納得する面もあって、なかなか複雑な音楽です。
冒頭はテンポの指示のない、秒数指定で持続をクラスター的な和音を楽器ごとに重ねていきます。ウッドブロック、テンプルブロック、ティンパニ、段ボール箱、ガラス瓶などの打楽器で短い音が奏されますが、これも短い音価が書かれているだけで、休符などは用いずにプロポーションによる記譜で書かれています。ページをめくり、2ページ目になるとすぐにテンポ指定(BPM=60)と拍子の指定(3/4)があります。しかし3小節後には秒数指定記譜に戻り、次の小節でテンポと拍、また無拍子、という風にサンドイッチ状に拍子と無拍子が交代します。無拍子の小節は基本的に音が伸びています(ゆっくりなヴィブラート状のグリッサンドを含む)。考えてみると、BPM=60と1秒を基準に持続時間を測る無拍子は同じ単位時間を持っているとも言えます。なので試しに無拍子の小節を音価で書いてみます。音価で書いてもその小節は音が伸びていることは目視でき、グリッサンドのじわじわ揺れる線が音符から伸びているので、印象はあまり変わりません。ですが、「あまり変わらない」のと、「同じである」のは同義ではありません。私の心理的には「異質なものが通常の音楽の間に挟まっている感じがする」感覚は演奏に影響しそうだと思えるので、なんとなく納得しました。
4ページ目からはBPM=112のテンポ感の良い音楽になりますが、リズムを厳密に指定されている管楽器・打楽器群に対し、弦楽器はプロポーショナルに音符が置かれていて、拍子の中で自由なリズムでピツィカートを演奏する音楽になります。大勢の弦楽器奏者が各々のタイミングでピツィカート奏をするサウンドは、音質の揮発性と相まって効果が高く、現代の音楽でしばしば用いられる手法です。続くセクションでは管楽器も自由に揺れるリズムになりますが、こちらは短い音ではなく、レガートで波状にうねる音型を奏します。そして波状の音型は細かく分断されて、リズムを厳密に記譜されたものへと展開します。この時に呼応するように打楽器群もポリリズムによる層を演奏します。このように各楽器群に特徴的な音楽が割り当てられ、群ごとの役割を持って層を成していく書法がしばらく続きます。
大きな変化が現れるのは15ページで、これまで楽器は同属楽器や同種楽器グループごとに群を生成するように進行していたのが、別のフォーマットに書き改められます。ピッコロ、フルート、小クラリネット、ヴァイオリン、ヴィオラ、トランペットを含む高音楽器群が上部に記譜されるグループH(グループは2群に小分割されます)、フルート、オーボエ、ヴァイオリン、ヴィオラ、トランペット、ホルン、打楽器、ピアノ、オルガンを含む中音域グループM(3群に小分割)、そしてイングリッシュ・ホルン、クラリネット、バス・クラリネット、ファゴット、コントラファゴット、トロンボーン、チューバ、ヴィオラ、チェロ、コントラバスを含む低音域グループT(2群に小分割)に分かれます。各小分割グループはそれぞれ管楽器と弦楽器を含み、したがってスコアは上からピッコロ、第1ヴァイオリン1、小クラリネット、第1ヴァイオリン2、フルート1、第1ヴァイオリン3、オーボエ1…という具合に見たことのない煩雑な配置になります。これは、完全に音群の配置を図示するためだけの目的で、「プラカード」を実現するために他なりません。

このような音響推移を見せるためのデザイン的楽譜が曲の半分くらいあるのです。響きを想像するのにはとても整合性があって良いかと思いますが、指揮者が具体的な指示を出す必要がある楽器がある場合は、特殊な準備をしておかないと使いづらい楽譜だと言えます。ハイダーの大きなアンサンブル作品やオーケストラ作品にはこのような記譜がしばしば見られ、今日それほど彼の作品が演奏されない要因の一つかもしれないと推察しています。ただ、ここから続く音群の推移をデザインした楽譜はとても迫力があって、魅力的です。音響自体のコントロールもこのフォーマットで書く場合、入念なスケッチの準備も不要と思われるので、作曲技法としては理に適っています。
22ページからさらに新たな記譜が見られます。無拍子の秒数指定による記譜の拡張版という感じで、大枠の和音ごとに秒数指定があり、更にその範囲を秒単位で割った線を引いて伸びている音の中の小さな動きを秒単位で分かるように示しています。個人的にはこれはやりすぎな気がします。秒単位で線を引くならいよいよ先述のBPM=60との差がありません。なおかつハイダーはテンポを指定してある箇所の中での自由なリズムを既に先行セクションで書いています。いろいろな記譜の哲学が混ざっていたずらに多くの記譜法を読み解く練習をさせられる曲、と言う人も出てきそうです。
もう一点、『プラカート』の楽譜では読みづらいと感じることがありました。それは音部記号(ト音記号、ヘ音記号、等)を省略していることが多い点です。それぞれの楽器の音部記号が固定で更に楽譜のフォーマットも変わらないならば、音部記号を省略してもギリギリ読める気もします。しかし、この曲では音部記号が変わる楽器も出てきます。更に楽器の並び順がページによって大胆に変わってしまうスコア・フォーマットを採用しているため、音部記号の省略はリスクが高いと言わざるを得ません。フォーマットが変わるタイミングではもちろん書き直しているのですが、それでも曲の途中からリハーサルを始める場合などには不親切な楽譜になってしまっています。
作品としては各楽器群の個性的な音楽内容がよく吟味されていて、個性を感じる層を成していることや、楽器群ではなく高音から低音への配置意識から音群のダイナミックの展開を目で確認することで響きのコントロールを自在に行なっている点などが魅力的な作品だと思います。ただ、以前からハイダーの作品を勉強するときに、『プラカート』ほどでないにしても記譜の方法の混在が招く混乱がもどかしく、彼の書法を学ぶ意欲が減ったことも事実です。今回は久しぶりにハイダーの作品に向かい合ってみようと思い、まだ読んでいなかった『プラカート』を聴きました。楽譜に関しては幾らか思うところのある作曲家なのですが、作品は面白いものが多いです。ハイダーは多作な作曲家で、管弦楽曲や協奏曲だけでも相当な数の作品を残しています。小編成のものは、記譜上の混乱が起きにくいものが多いので、演奏もしやすいと思います。日本ではほとんど全く演奏されていない作曲家なので、ご紹介の意味も込めて、私がおすすめしたい曲をいくつか最後にご紹介いたします。

(ピアノとオーケストラのための『Bezirk』、1969)
(声とアンサンブルのための『Commission』、1972)
(トロンボーンと管弦楽のための『-einander』、1971)
*「楽譜のお勉強」シリーズ記事では、著作権保護期間中の作品の楽譜の画像を載せていません。ご了承ください。
作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
