
中小企業診断士2次試験のストレート合格に重要なのは「2次試験の〇〇」を理解すること
こんにちは。
中小企業診断士のやす(@yasulog2)といいます。
本noteをご覧いただき、誠にありがとうございます。

下記に当てはまる人は、本noteがお役に立つことができます。
✔この記事をぜひ読んでほしい人
・2次試験に短期間で合格したい人
・受験予備校の解答解説がしっくりこない人
・2次試験に3年、4年たっても合格できない人
・2次試験に向けて何を勉強したらいいのか分からない人
このnoteは、中小企業診断士2次試験の受験生が最短合格するために必要な「2次試験の力」を徹底的に身につけることを目的に書いています。
言い換えれば、2次試験合格のための「土台作り」です。
※2次試験合格のためのノウハウやテクニックが詰まったものではありませんので、その点はご留意いただけますと幸いです。
✔本noteの信頼性
・筆者自身が診断士資格にDVD通信講座で10ヶ月ストレート合格
・企業内診断士として10年間、診断士活動を休まず実施
・2次試験受験生向け勉強会の講師役として約4年間担当
・2次試験本試験事例Ⅰの解答解説を約4年間執筆
・2次試験受験生200名超の論文添削
・診断士関連の共著を2冊出版
✔この記事を読むことで得られること
・2次試験の本質が分かる
・2次試験と実際のコンサル現場との関連が分かる
・2次試験合格に必要なテクニックを活かす基礎知識が身につく

まずは自己紹介を簡単にさせてください。
大学院修了後、大手情報通信会社に入社。パワハラで4年間のメンタルダウンを経験した後、36歳で異業界へ初転職。現在、経営企画職のマネージャー+3社の社外監査役として働いているサラリーマンです。
▼プロフィール
▼運営しているTwitter

Twitter @yasulog2
中小企業診断士の資格を目指したのは社会人5年目。
10ヶ月830時間のDVD通信講座の勉強で1次・2次試験にストレート合格を果たすことができました。
✔やすの診断士受験歴
・2010年12月:大阪府にて受験予備校のDVD通信講座で勉強開始
・2011年7月:愛媛県へ異動。6月後半~7月後半は、引っ越しでバタバタ
・2011年8月:1次試験合格(429点)(勉強時間638時間)
・2011年10月:2次筆記試験合格(勉強時間192時間)
・2011年12月:2次口頭試験合格
・2012年2月~3月:愛知県で15日間の実務補習
・2012年4月中小企業診断士登録
▼やすの受験体験記
また、本業をしつつ、中小企業診断士の資格を活用したいわゆる「企業内診断士」として10年間、副業を続けてきた結果、年7桁の副収入を得ることができるようになりました。
2021年4月に開業届も提出。
本業+副業のパラレルキャリアを目指しています。

「中小企業診断士の資格ってどうなの?」
こう聞かれたとき、僕の答えはコレです。
診断士資格は会社員人生を変えるパワーを持った資格。
2012年に企業内診断士として活動をスタートして、11年目。
ただの会社員だった僕が、診断士資格のおかげで大きく人生を変えることができました。
▼僕の中小企業診断士としての主な活動実績
・36歳で初転職・共著2冊の出版
・1.5年間のデュアル勤務
・1次試験受験テキスト執筆
・1次試験・2次試験本試験の解答解説執筆
・2次試験受験生の論文添削(40~60枚/年)
・2次試験受験生向け勉強会講師(約4年間)
・経済産業省補助金申請サポート(5~10件/年)
先行き不透明な時代。
将来に備えた準備は誰もが必要な時代です。
特に会社員は、一つの会社にしがみつき定年まで頑張りぬくモデルはすでに崩壊しています。
自分自身の人生やキャリアは、会社に委ねるのではなく自らの手で切り拓いていくことが必要です。
診断士の資格は、自分自身の手で人生やキャリアを変えていくための最高の武器になります。

診断士試験に合格するには、1次試験、2次試験(筆記・口述)の3つの試験を突破し、さらに実務補習を受講する必要があります。
この中で最大の関門は、間違いなく2次試験(筆記)です。
(そのため、本記事では、「2次試験(筆記)」のことを「2次試験」と定義しています)
「診断士試験=2次試験」といっても過言ではありません。
1次試験は1年~2年で合格できたのに、2次試験に中々合格できず、2次試験だけで3年以上かかっている受験生を何人も見てきました。
複数年受験生からは次のような言葉もよく聞きます。
・合格できる気がしない、、
・来年も受験したいなんて家族に言えない、、
・ここまでやってきたから、あきらめたくない、、
一方、初学者の方は、はじめて2次試験の問題や解答を見たとき、1次試験とのあまりの違いに愕然とするケースも少なくありません。
・こんな試験どうやって合格するの?
・2次試験の勉強ってどうやって進めていくの?
いかに2次試験を突破できるか。
これが診断士試験合格の最大の鍵となります。

2次試験がむずかしい理由はいろいろありますが、一言でいうなら「受験対策が立てにくい」ということに尽きます。
主な理由は2つあります。
✔受験対策が立てにくい理由
①模範解答が公表されない
②受験予備校の模範解答がバラバラ

2次試験が、高校・大学入試やほかの資格試験と最も異なる点は、試験実施団体から「模範解答が公表されない」ことです。
模範解答が公表されないので、
・試験対策ができない
・本試験の分析ができない
・合格/不合格の基準が分からない
・いまの勉強が良いのか分からない
・自分の解答の良い/悪いが分からない
と、困ることがたくさん出てきます。
正解がないから、何を目指して、何を拠りどころに勉強すればよいのか分からない。
模試や本試験を受験して「手応えあり!」と思ったのに、思ったほど点数は伸びておらず合格ラインをクリアできていない。
勉強の対策が立てにくく、勉強しても合格に近づいている実感が湧かない試験。それが2次試験です。

模範解答は公表されませんが、各受験予備校は、それぞれ2次試験の解答を公表しています。
受験予備校の解答を見れば、模範解答が公表されない悩みは解決されるのか?
ところが、そんなに甘くありません。
なぜなら、各受験予備校の解答には統一性がなく、解答表現、解答構成、キーワードの書き方、すべてバラバラだからです。
そのため、どの解答が本試験に合格できる解答なのか分からず、どの解答や解答プロセスを信じればいいのか分からなくなってしまいがちです。

2次試験について、中小企業庁や受験予備校から提示されている客観的なデータがあります。
✔2次試験関連のデータ
①2次試験のここ10年間(H22年度~令和元年度)の合格率は19%前後
②診断士資格に3年以内で合格している人は全体の69%
このデータを見れば、1年はムリでも、2年、長くても3年勉強すれば合格できるのでは?と思うかもしれません。
でも、このデータには大きな落とし穴があるので、気をつけてください。

2次試験のここ10年間(H22年度~令和元年度)の合格率はだいたい19%前後で推移しています。

ほかの難関国家・民間試験では、合格率が10%を切る試験もあるので、2次試験の合格率は一見高いようにも見えます。
しかし、「合格率19%前後」には隠れた前提があるので要注意です。
それは
2次試験受験生の母数は「1次試験の合格者」
ということ。
そもそも、1次試験に合格すること自体が相当むずかしく、2次試験に挑む受験生はハイレベルな人ばかりです。
1次試験の合格率を20%とした場合、1次試験の合格率20%と2次試験の合格率20%の意味合いはまるで違うということです。
しかも、1次試験、2次試験にストレート合格できる確率はわずか4%(20%×20%)。
ほかの難関資格と比較しても、非常に難易度の高い難関試験であることが分かります。
2次試験は表面上の合格率以上に厳しい競争環境なのです。

某受験予備校の診断士合格までの勉強期間のデータを見ると、3年以内に合格した人の割合は69%となっています。
また、パンフレットや合格体験記を読むと、ストレート合格、2回目の受験で合格できた受験生の体験談もたくさん載っています。
しかし、裏を返せば
残りの3割の方は、診断士試験合格に4年以上かかっている。
ということです。
僕は2次試験受験生向け勉強会の講師役として、約4年間、たくさんの2次試験受験生と関わってきましたが、3年どころか、5~6年目を迎えている受験生も数多く見てきました。
では、彼らが全然勉強していないのかといえばそんなことはありません。
毎回勉強会にしっかり出席して、受験予備校の模試も解いて、忙しい中で勉強を続けている受験生ばかり。
それなのに、全然合格できない、、
受験予備校のパンフレットや受験体験記では、ついつい良き面に目が向きがちですが、こういった現実があることもきちんと知っておくべきです。

ここまで、2次試験の厳しい面ばかり見てきました。
ちょっとどんよりした気持ちになってしまったかもしれません(汗)
でも、ストレート合格または1次試験が終わってから2か月の勉強で短期合格できる受験生がいるのも事実です。
僕自身も、1次試験が終わってから勉強を始めて2か月の勉強、具体的には192時間の勉強時間でストレート合格することができました。
それでは、なぜ短期合格できる受験生がいる一方で、5年、6年経っても合格できない受験生がいるのでしょうか?
受験予備校のテキストや市販の参考書、SNS、2次試験合格のために必要な情報、テクニックは巷にあふれているので、取得できる情報量・質の違いはそこまで大きくありません。
知っている情報は同じなのに、なぜ、こんなにも結果に大きな差が出るのか?
それは
受験生が「知っている情報」を「正しく使いこなすこと」ができるかどうか。
この一点に尽きます。
言い換えれば
・短期合格できる受験生は、知っている情報を使いこなすことが「できる」。
・なかなか合格できない受験生は、知っている情報を使いこなすことが「できない」。
ということです。
日常生活に置き換えればグッと分かりやすくなります。
・たくさん英単語を知っていても外国人とスラスラ話せるわけではない。
・ゴルフのスイングを頭で分かっていても、良いスコアが出せるわけではない。
つまり、「知る」ことと「できる」ことの間には、ものすごく大きな壁があるのです。
2次試験に合格するためには、この「知る」から「できる」の壁を超える必要があります。
「知る」から「できる」の壁を超えるために重要なことが「2次試験の本質を理解する」こと。
つまり、
2次試験に関する基礎知識を身につけて、2次試験そのものを深く知る。
ということです。
「え、そんなこと?」って驚く受験生がいるかもしれません。
しかし、勉強、趣味、スポーツなど、どんな分野でも基礎となる土台作りが一番大切です。
土台となる基礎がグラついていては、いくら土台の上に素晴らしいものを積み上げても活かしきることはできません。
2次試験でいえば、2次試験の基礎(土台)を身につけないまま、どれだけ与件文・設問文の読み方、解答の書き方、重要キーワードなどの応用知識を学んだとしても、その知識を活かしきることはできません。
何年も2次試験に苦戦している受験生は、2次試験のテクニックに関する知識はあるのに、その知識を実際の解答作成のプロセスで使いこなせていないように感じます。
短期合格できる受験生は、2次試験の基礎知識を土台にした上で、解答テクニックを使いこなすことができる人。
一見、遠回りに見えますが、徹底的に基礎を磨き上げることが、間違いなく2次試験合格の近道です。

繰り返しになりますが、この記事は、中小企業診断士2次試験の受験生が最短合格するために必要な「2次試験の基礎力」を徹底的に身につけることを目的に書いています。
また、一つ一つの論点や疑問点につき、現場のコンサルティング場面で起きていることと照らし合わせながら解説しているので、イメージを持っていただけやすいと思います。
✔この記事を読むことで得られること
・2次試験の小手先のテクニックではなく、2次試験の本質が分かる
・2次試験合格に必要なテクニックを活かせる基礎知識が身につく
・2次試験と実際のコンサル現場との関連性が分かる
2次試験合格のための解答テクニックはすでにさまざまな情報があふれ返っていますが、肝心の2次試験そのものについてしっかり学ぶための教材は少ない気がしています。
本noteでは、僕自身が受験時代に学んだことはもちろん、「2次試験受験生向け勉強会の講師役を約4年間担当」「2次試験本試験事例Ⅰの解答解説を4年間執筆」「2次試験受験生200名超の論文添削」といった実績やノウハウを踏まえ、重要な基礎知識にフォーカスして執筆しているものです。
そのため、初学者/複数年受験者問わず、お役に立てるものがあると思います。
✔初学者の方
2次試験の基礎を最初に徹底的に学ぶことで、ムダなく効率よく採点距離で勉強できるようになります。
✔複数年受験の方
2次試験の基礎知識を再確認いただくことで、これまで学んできた解答テクニックを活かし切ることができるようになります。
それでは、気になる本noteの価格についてお話します。
1,480円(返金不可)
2次試験の勉強が長引けば長引くほど、貴重な「お金」や「時間」を失うことになります。
さらに、目に見えない勉強疲れ、「もう1年勉強させてほしい」と家族に言えない精神的なストレスなど、どんどん心身への負担は大きくなっていきます。
本来、資格試験の合格は「ゴール」ではなく「スタート」。
そのため、1日も早くスタートラインに立った方が絶対良いです。
こんな風に考えていただければ、本noteは価格以上の価値があるものと考えています。
2次試験は大変な試験ですが、本質を理解し勉強方法さえ間違えなければ、短期合格が目指せる試験です。
ぜひ、一緒にがんばっていきましょう!
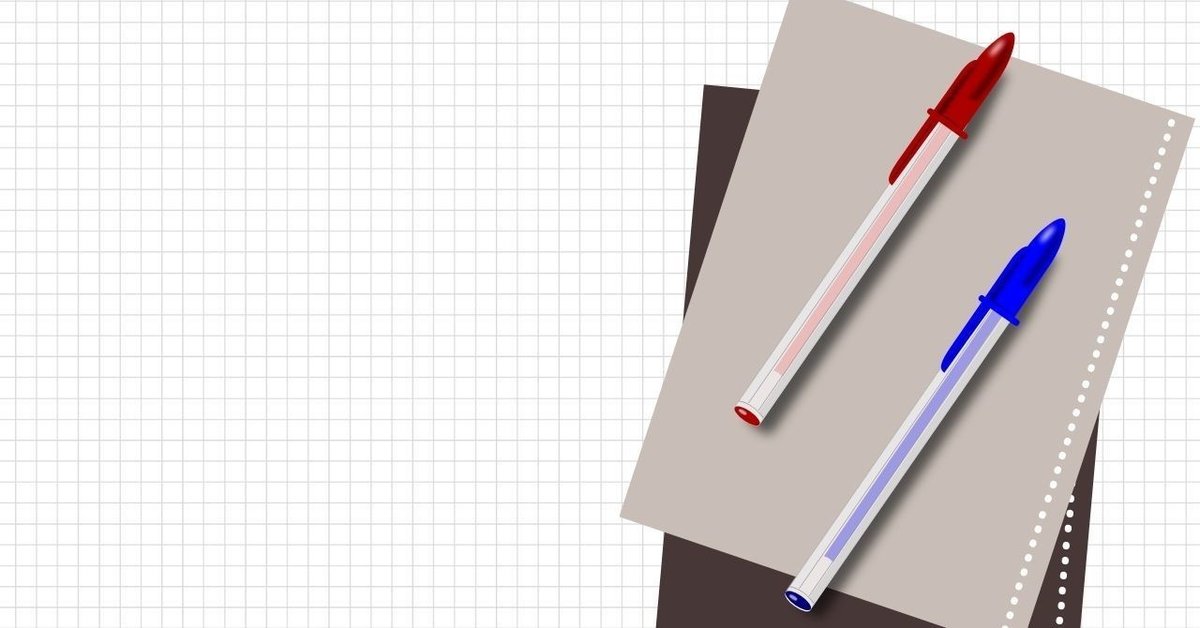
1. 1次試験と2次試験は別試験

2次試験の本質を学ぶ前に、まずは1次試験と2次試験の違いを押さえておきましょう。
ここから先は
¥ 1,480
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
