
【受験体験記】地方通信受験生が中小企業診断士資格に10ヶ月ストレート合格するまで
こんにちは。
中小企業診断士のやす(@yasulog2)といいます。
本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます。
✔この記事をぜひ読んでほしい人
・これから勉強を始める受験生
・まわりに受験仲間がいない孤独な受験生
・通信講座でひとりがんばっている受験生
・都会ではなく地方でがんばっている受験生
この記事は、僕が地方通信講座受験で中小企業診断士試験に1次試験、2次試験に10ヶ月でストレート合格した際の受験体験記を書いています。
✔この記事を読むことで得られること
・1人の診断士受験生のリアルな体験談が読める
・ストレート合格するために工夫したことが分かる
・1人・地方・通信講座受験でも合格できる!ということが分かる

まずは僕の自己紹介を簡単にさせてください。
新卒は大手情報通信会社に入社。パワハラで4年間のメンタルダウンを経験した後、36歳で異業界に初転職。現在、経営企画職のマネージャー+3社の社外監査役として働いているサラリーマンです。
▼詳細なプロフィール
▼運営しているX(Twitter)

Twitter @yasulog2
中小企業診断士の資格を目指したのは社会人5年目。
10ヶ月830時間のDVD通信講座の勉強で1次・2次試験にストレート合格を果たすことができました。
✔やすの診断士受験歴
・2010年12月:大阪府にて受験予備校のDVD通信講座で勉強開始
・2011年7月:愛媛県へ異動。6月後半~7月後半は、引っ越しでバタバタ
・2011年8月:1次試験合格(429点)(勉強時間638時間)
・2011年10月:2次筆記試験合格(勉強時間192時間)
・2011年12月:2次口頭試験合格
・2012年2月~3月:愛知県で15日間の実務補習
・2012年4月中小企業診断士登録
✔やすが診断士の勉強をはじめたときの環境
・勤務地:大阪府
・仕事:情報通信会社勤務
・職種:事業企画職
・職場まで:自転車通勤で10分
・勉強開始時の年齢:30歳
・家族:妻(新婚2か月)
・月の平均残業:30~40時間
また、本業をしつつ、中小企業診断士の資格を活用したいわゆる「企業内診断士」として10年間、副業を続けてきた結果、年7桁の副収入を得ることができるようになりました。
2021/4に開業届も提出。
いま本業+副業のパラレルキャリアを目指しています。

僕はDVD通信講座で勉強を始めたので、受験仲間・先輩診断士、勉強コミュニティとの関わりはゼロ。
自分で選んだ勉強スタイルですが、受験のことを誰にも相談できず、悩みを吐き出すこともできず、なかなかつらいものでした。
おまけに1次試験直前の7/1に大阪から愛媛へと転勤があり、6月末~7月末までは社内引継ぎや転勤先での仕事や環境・人間関係に慣れること、家の環境を整えることでとにかくバタバタ。
1次試験の直前にも関わらず、7月は勉強量が一気に落ちました。
大きな不安と焦りに襲われましたが、6月まで勉強を続けてきた自分を信じてなんとか持ちこたえることができ、8月の1次試験を無事合格することができました。
30才の7月。転勤で初めての土地へ。新しい仕事や人間関係。住居探しでバタバタ。8月に控えた中小企業診断士資格1次試験。勉強量がガクンと落ちた。今年は無理かな。でも勉強続けてきた7ヶ月間を捨てたくなかった。できる範囲で追込み。結果、無事合格。諦めなければ奇跡は起きる。自分を信じよう。
— やす (@yasulog2) January 20, 2022
8月に入ってからも仕事は覚えることばかりでバタバタの毎日。さらには2次試験の勉強が思ったように進まず、心身ともに苦しい時期が続きました。
「こんなとき誰かに相談できれば、、」
受験仲間がいる受験生のことをうらやましく思う時間が増えました。
それでも、あきらめずに自分なりに工夫しながらコツコツ勉強を続けた結果、なんとか2次試験にも合格。
10ヶ月に及ぶ、診断士受験生活を終えることができたのです。
以下、僕の診断士受験記を書いていきます。
それでは、どうぞ。
1.診断士受験まで
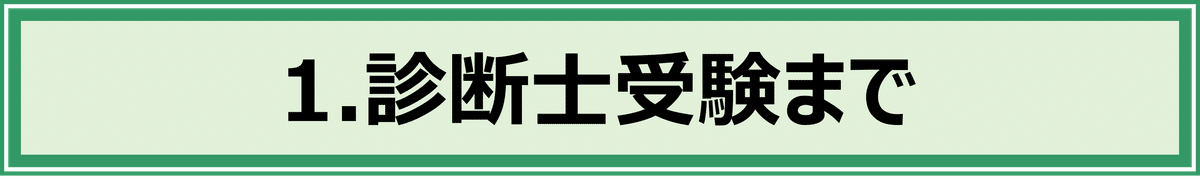
1.1 家族の協力を得る
僕が受験を決めたのは、2010/12。
実は、2か月前の10月に入籍したばかりで、新婚1年目のホヤホヤでした。
中小企業診断士の平均勉強時間は「1,000時間」。
しかも1,000時間勉強したから合格できる保証はどこにもない、、
・新婚早々なんて言われるかな、、
・いやな顔されるかな、、
不安なことばかり考えて、ドキドキしながら妻に切り出しました。
そうしたら、
「いいんじゃない。やりたいなら、やったら」
思いもよらなかった一言があっさり返ってきたのです(汗)
このとき背中を押してもらった妻には感謝してもし切れません。
こうして僕の診断士受験生活が始まりました。
1,000時間。中小企業診断士の資格の平均勉強時間。勉強始めたのは新婚1年目。妻は「やりたいならやったら」と後押ししてくれた。10ヶ月後に無事合格。あれから10年。コツコツ診断士の複業を続けてきたおかげでプロフまで到達。いまも妻は複業を後押ししてくれている。昔も今も妻には感謝しかない。
— やす (@yasulog2) February 2, 2022
1.2 受験予備校のDVD通信受講講座でスタート
診断士の勉強では、受験予備校/独学、通学/通信、といろいろな勉強方法がありますが、僕は「受験予備校のDVD通信講座」で勉強することを選びました。
理由は、平日は残業になることが多く、夜の授業が始まるまでに教室へ行くことがむずかしかったからです。
あとは、決められた時間に勉強するよりも、自分で決めた時間に勉強した方が気持ちの面で乗っていけたので、時間と場所に制約をとられない通信講座の方が自分に合っていると思いました。
一方、ノウハウや勉強スケジュールの詰まった受験予備校の講座を選んだ方が効率的に勉強できると思い、受験予備校で勉強することを選びました。
2. 1次試験

2.1 勉強概要
1次試験の勉強時間は「638時間」。
▼勉強時間の内訳
・企業経営理論:116時間
・財務・会計:135時間
・運営管理:128時間
・経営情報システム:39時間
・経営法務:67時間
・経済学・経済政策:89時間
・中小企業経営・政策:64時間

2次試験関連科目は多めに勉強。
1次試験科目は、得意/苦手科目に応じてメリハリをつけて勉強するようにしました。
▼毎日の勉強時間
・平日:2~3時間
・土曜日:5~6時間
・日曜日:オフ
勉強開始から1次試験前日まで一貫してこのサイクルを回していきました。
▼得意/苦手科目
・得意:経営情報システム
・苦手:経営法務、経済学・経済政策
経営情報システムは、受験時は情報通信会社で働いていたので、日ごろから情報システムに関わっており、各種情報処理技術者試験やITベンダー試験にも合格していたことから、得意科目でした。
一方、経営法務と経済学・経済政策は、日常で法律や経済学に接する機会がまったくなかったので、イメージがつかず苦手科目でした。
▼勉強スケジュールの概要
・12月:勉強スタート
・12月~2月:2次関連科目(企業経営理論、財務・会計、運用管理)からスタート
・3月~5月:これまでの3科目+経営法務、経済学・経済政策、中小企業経営・政策
・6月~:これまでの6科目+経営情報システム
最終目標は、1次試験合格ではなく、あくまでも2次試験合格。
そのため、まずは2次試験関連科目の強化を心がけました。
ただし、1次試験科目をおろそかにしては合格できないと考え、4月から得意科目の経営情報システムを除いた1次試験科目3科目の勉強を始めました。
経営情報システムは、6月から過去問を中心に勉強を始めました。
✔中小企業診断士1次試験の最短攻略法はこちら
2.2 勉強習慣
毎日少しでも勉強を継続できるように、以下の工夫をしました。
①自分の気持ちが乗れる基本的な勉強習慣を作る
②自分が集中できる勉強場所を探す
③例外ルールを作る
①自分の気持ちが乗れる基本的な勉強習慣を作る
毎日の勉強リズムが決まっていないと、どの科目をいつどこで勉強するのかを決めるだけでストレスがたまってしまい、モチベーションがダウンしてしまうことがイヤでした。
そこで、はみがきやお風呂のように何も考えずとも、自然と勉強に向かえるリズムを作ることを心がけ、気持ちに左右されないように気をつけました。
僕の具体的な勉強習慣は以下の通りです。
・出社前:近所のマクドナルドで苦手科目(経営法務、経済学・経済政策)
・帰宅途中:近所のマクドナルド/会社近くの図書館で手を動かす科目(財務・会計)
・帰宅後:そこまで苦手意識のない科目(企業経営理論、運営管理、経営情報システム、中小企業経営・政策)
出社前は、睡眠も取った後で脳もさえていて気持ちがスッキリしているので、あえて苦手科目に取り組むようにしました。
出社時間も決まっていて健全な強制力があったので、メリハリをつけれてよかったです。
帰宅途中は、仕事上がりで疲れもたまっているので、手を動かして眠くならない財務・会計を勉強するようにしました。
帰宅後は、お風呂を上がって寝るまでの時間。
苦手意識のない科目を勉強するようにして、眠たい中でも集中力を保つようにしました。
もちろん、勉強を始めたときからこの習慣ができていたわけではなく、いろいろ試した後にこの勉強習慣にたどり着きました。
勉強時間・場所、科目の組み合わせ、インプット/アウトプット含め、いろいろ試して自分にしっくりくる習慣を作ることが大切だと思います。
②自分が集中できる勉強場所を探す
自分が勉強に集中できる場所を見つけることも、気持ちを乗せていくためには大切です。
僕の場合、
・図書館の1階は集中できないけど2階の窓際は集中できる
・土日の自宅は集中できないけど平日夜の自宅は集中できる
・駅前のマクドナルドは集中できないけど近所のマクドナルドは集中できる
といった感じです。
勉強効率を上げるためにも、自分が集中できる勉強場所を探しましょう。
③例外ルールを作る
・今日は1時間勉強すると決めたのに15分しか勉強できなかった、、
・財務・会計10問解きたかったのに、5問しか解けなかった、、
・仕事が忙しすぎて夜勉強できなかった、、
計画通りに勉強が進まなかったとき、ついつい自分のことを責めてしまい、自分で勝手にモチベーションを下げてしまうことがありました。
これは良くないと思い、
・1時間勉強できなかったけど、きちんと15分勉強できた。
・財務・会計を5問も解いた。
・今日は仕事をがんばった。
と思い、「できなかった部分」ではなく「できた部分」に目を向ける、0点か100点で考えるのではなく40点でも60点でもOKとするよう意識を変えました。
このおかげで、自分を責めずに自分を褒めることで、自己肯定感や達成感を感じることができるようになりました。
2.3 勉強方法
1次試験は出題範囲が広く、勉強時間も限られているため、少しでも勉強効率を高めていくことが大切だと考えました。
そこで、7科目一律で勉強するのではなく、以下の工夫をして濃淡つけた勉強を心がけました。
①科目ごとに勉強方法を変える
②インプットは、受験予備校のテキストのみ
③アウトプットは、基礎問題集、過去問、受験予備校の模試
④各科目で意識したこと
①科目ごとに勉強方法を変える
王道は、受験予備校の講義を受けてテキストでインプットして、基礎問題集から過去問の順でアウトプットだと思います。
しかし、得意/苦手科目とも同じように勉強していては非効率と考え、勉強方法を変えることにしました。
具体的には以下の通りです。
・得意科目→過去問から
・過去に少し触れたことがある科目→基礎問題集から
・まったく触れたことのない科目→王道のインプットから
得意科目の経営情報システムは、いまの状態でどの程度、本試験の点数が取れるか確認しようと考え、まずは過去問3年分を解くようにしました。
僕の場合、過去3年間のいずれの問題でも合格基準の60点を超えることができたので、経営情報システムは後回しにして、インプットも過去問で解けなかった論点だけ確認する方針にしました。
過去に少し触れたことのある科目(財務・会計)は、基礎問題集を使って自分がどのくらい解けるのか、覚えているのかを試すようにしました。
すると、まったく覚えていなかったことが判明(汗)
これはまずい!と、一からインプットしていくことにしました。
このとき、解けたか解けなかったかではなく、自分の現状を正確に把握することを心がけました。
そのほかの初見の学習科目は、インプット~基礎問題集の繰り返しで一歩ずつ勉強していくようにしました。
②インプットは、受験予備校のテキストのみ
インプットは、受験予備校のテキスト1冊だけで、市販の参考書などは見ないようにしました。
インプット教材を増やすと、あっちもこっちも手付かずになったり、集中力がなくなると考えたからです。
また、基礎問題集や模試、過去問でアウトプットしていく中で、テキストに載っていない用語や論点が出てきた場合は、テキストの関連性のある分野の余白に書き込んでいくようにしました。
1冊のインプット教材をとことん強化していくことで、これさえあればインプットは大丈夫、という教材を作るようにしました。
③アウトプットは、基礎問題集、過去問、受験予備校の模試
アウトプットは、各科目ともにTAC出版のスピード問題集を購入し、基礎力向上に努めるとともに、過去問は5年分、模試は3回以上解くようにしました。
これ以外のアウトプット教材は一切利用しませんでした。
僕の場合、1回復習しただけで覚えることはできなかったので、いろいろなアウトプット教材に手を出すことはかえって非効率だと考えたからです。
また、アウトプット教材が増えれば増えるほど、あれもやってない、これもやってない、と、不安だけが膨らみ、復習も十分にできなくなるので逆効果だと思いました。
それよりも、同じ教材をひたすら解きまくることで、しっかり知識を定着させることにフォーカスしました。
④各科目で意識したこと
財務・会計は、1日1問は必ず解くようにして、計算力が落ちないように気をつけました。
経済学・経済政策は、グラフの結果だけ覚えるのではなく、グラフが導かれるプロセスを理解することに努め、応用問題が出題された場合にも対応できるように意識しました。
中小企業経営・施策は、あえて中小企業白書を購入しました。
もちろん、受験予備校のテキストにも数値やグラフは記載されているのですが、これだけでは本試験の出題範囲をカバーすることはできず、あまり勉強しても意味がないように感じました。
そのため、思い切って中小企業白書を購入し、数値やグラフを見て概要を把握するようにしました。
これによって、かなり本試験での対応力がついたと思います。
2.4 マインド
1次試験は、長期間に渡る勉強が必要です。
仕事、家事、育児、趣味と忙しい日常生活の中、毎日勉強を続けていくことは本当に大変。
そのため、途中で挫折しないよう、以下でモチベーションを保つようにしていました。
①毎日、診断士を目指した目的、実現したいことを紙に書く
②毎日の勉強で達成感を味わう
③日曜日は完全オフでリフレッシュ
④科目合格制度には頼らず1年合格を目指す
①毎日、診断士を目指した目的、実現したいことを紙に書く
仕事が忙しくなったとき、心身がつらくなり勉強を投げ出しくなるときがありました。
でも、まわりに受験仲間も相談できる相手もいなかったので、なんとか自分1人でモチベーションを保ち続ける必要がありました。
そこで、僕が工夫したことは、毎朝「診断士を目指した目的」と「診断士に合格してから実現したいこと」を書いてから勉強をスタートすることです。
これによって、診断士を目指した初心に戻ることができ、診断士資格に合格できれば「きっと自分の人生を変えることができる」と自分を奮い立たせることができました。
この2つがあいまいだと、ちょっとでも苦しいことがあると挫折の原因になるような気がしました。
なぜなら、診断士試験に合格しなくても究極的には自分の人生で困るわけではないからです。
途中で勉強に挫折しないためにも、
・診断士を目指した目的
・診断士に合格してから実現したいこと
この2つは、自分の腹に落ちるまできちんと自分と向き合い考え抜くことが大切だと思います。
②毎日の勉強で達成感を味わう
毎日手帳に1日の勉強科目と科目ごとの勉強時間を書いていき、1週間、1ヶ月の終わりには科目ごとの勉強時間を合計していきました。
勉強時間を見える化することで、
・昨日より勉強できた!
・今週は先週より勉強できなかったら翌週またがんばろう!
・昨日は2時間勉強したから、今日も最低2時間は勉強する!
とモチベーションを維持するようにしました。
ロールプレイングゲームで、レベルが1上がるとモチベーションが上がるような感覚ですね(笑)
日々、達成感や充実感を味わうための工夫を取り入れることで、毎日の勉強に取り組むモチベーションを維持し続けることができると思います。
③日曜日は完全オフでリフレッシュ
診断士資格に合格するには膨大な勉強量が必要です。
そのため、
・土日も休んでいるヒマはない!
・休んでいたら合格なんてできない!
と四六時中、頭から勉強のことが離れなくなってしまうこともあります。
しかし、1次試験は短期間ではなく長期間にわたる勉強が必要なので、最初から全力で走っていては息切れしてしまいます。
言うなれば、短距離走ではなくマラソンのイメージ。
マラソンを走り切るには、途中のペース配分を考えることも大切だし、途中の給水ポイントでしっかり休止を取ってエネルギーを蓄えることも大切です。
そこで、日曜日はあえて完全オフにして、家族との時間をとり、リフレッシュするようにしました。
単純に考えれば、日曜日を完全オフにすることで勉強時間は減るのですが、平日は絶対にサボることができない、家族との時間も大切にしている、と勉強効率をあげたり家族への罪悪感をなくしたりすることができたので、かえって良かったです。
土日のどちらか少しでもいいので、オフの時間を作ってメリハリをつけることは、心身のリフレッシュや気持ちを新たにする上でも大切だと思います。
④科目合格制度には頼らず1年合格を目指す
1次試験は科目合格制度があるので、1年ではなく複数年計画で受験を検討する方法もあると思います。
しかし、僕は「最初から1年で絶対に突破する!」と決めていました。
なぜなら、複数年計画にした瞬間に自分に甘えた気持ちが生まれてしまい、かえって勉強に身が入らなくなるようなが気がしたからです。
また、この苦しい受験勉強を2年も3年も続けたいとも思わなかったのもありました(汗)
3. 2次試験

3.1 勉強概要
2次試験の勉強時間は「192時間」。
▼勉強時間の内訳

内訳は、事例Ⅰは42時間、事例Ⅱは44時間、事例Ⅲは33時間、事例Ⅳは73時間。事例Ⅳに大きく時間をかけてきました。
基本的な勉強スタンスや試験への向き合い方は1次試験のときと同じ。
勉強習慣も、平日は2~3時間、土曜日は5~6時間、日曜日はオフで変わらず。自分にとって一番しっくりきた勉強習慣をそのまま維持することにしました。
▼勉強スケジュールの概要
・8月1次試験本試験の翌日:勉強なし(リフレッシュ)
・8月1次試験本試験の2日後:勉強スタート
・8月:受験予備校の教材を中心とした勉強
・9月~:「ふぞろいな合格答案」を中心とした勉強へ切り替え
僕は、1次試験本試験までは2次試験の勉強を一切していなかったので、1次試験本試験が終わってからが2次試験のスタートでした。
8月は、受験予備校の教材中心で勉強を進めるも、まったく理解が進まず自信だけがなくなっていきましたが、9月から「ふぞろいな合格答案」に勉強の軸を切り替えたことで光が見え始め、そのまま最後まで駆け抜けた感じです。
✔中小企業診断士2次試験の最短攻略法はこちら
3.2 2次試験で悩んだこと
「何をどうやって勉強したらいいのか分からない」
2次試験の勉強を始めてぶち当たった壁がこれでした(汗)
2次試験は模範解答が公表されません。
そのため、何が正解で何をどこまで勉強すればいいのかまったく分からなかったのです。
それならば受験予備校の解答解説で、と、過去問を片手に受験予備校の解答解説を見ながら、過去問を振り返ったのですが、今度は別の問題が、、
✔受験予備校の解答解説で悩んだこと
・解答の表現がとても思いつかない
・解説を読んでも、なぜこの解答に行きつくのか分からない
・受験予備校ごとに解答解説がバラバラで、何が正解なのか分からない
何回解説を読んでも通信講座の解説DVDを見ても、私には本試験の80分で書き切れるイメージがまったく浮かんできませんでした。
それでも、受験予備校の教材を信じて日々がんばっていましたが、不安は募るばかり、、
8月の終わりには自信がなくなり、焦りと不安だけに悩まされていました。
3.3 書店で出会った1冊の参考書
「このままでは絶対に合格できない」
強烈な危機感と焦りを感じながら、何かいい参考書はないかと会社帰りに書店にフラッと立ち寄って中小企業診断士コーナーに向かって手に取った1冊。
「ふぞろいな合格答案」。
タイトルのおもしろさに惹かれて中身をパラパラと。この本との出会いによって私の2次試験の勉強方法は一気に変わり、明るい光が見えたような感じがしました。
✔「ふぞろいな合格答案」の主なメリット
・本試験受験生の解答をたくさん見ることができる
・本試験に合格できる/できない解答が分かる
・本試験合格に必要なキーワードが分かる
・自分に合った解答の書き方が分かる
過去数年分の「ふぞろいな合格答案」を買いそろえて、受験予備校の教材中心の勉強スタイルから「ふぞろいな合格答案」中心の勉強スタイルへと一新することにしました。
3.4 最終的な2次試験の勉強スタイル
「ふぞろいな合格答案」を買いそろえたのが9月の上旬。
これ以降の僕の勉強スタイルは以下の通りです。
✔9月以降の2次試験の勉強スタイル
①過去問は5年分を5回転
②事例Ⅰ~Ⅲは「ふぞろいな合格答案」
③事例Ⅳは「模試」「個別計算問題集」「ふぞろいな合格答案」
①過去問は5年分を5回転
僕は、2011年(平成23年)受験だったので、平成18年~平成22年の5年分を何度も何度も解きまくっていました。
②事例Ⅰ~Ⅲは「ふぞろいな合格答案」
事例Ⅰ~Ⅲは、本試験問題と「ふぞろいな合格答案」をひたすらにらめっこ。
本試験の問題を使って、「ふぞろいな合格答案」の合格者の解答の中で、自分に合ったものを探し、解答の書き方やキーワード、表現などを勉強していきました。
「ふぞろいな合格答案」で実際に合格している解答を見ることで、合格するためにはこのレベルの答案が書ければいいんだ、と合格の目安を知ることができたのがよかったです。
③事例Ⅳは「模試」「個別計算問題集」「ふぞろいな合格答案」
事例Ⅳは、事例Ⅰ~Ⅲとは逆に模試の復習はそれぞれ3回転ほどしっかり回しました。
なぜなら、模範解答が公表されずとも、事例Ⅳは計算で解答が導き出せること、数字は客観的な指標のため正解が一つにしかならない、ことから、受験予備校の作成する解答と本試験問題の解答の解答基準のズレが少ないと考えたからです。
一方、計算問題ではなく文章問題については、事例Ⅰ~Ⅲと同じく「ふぞろいな合格答案」の解答解説を読んで理解を深めていきました。
また、計算力を鍛えたいと思い、過去問と模試のほか「TACの個別計算問題集」を1冊購入して解いていました。
そして、計算問題は手を動かさないとすぐに忘れてしまうので、事例Ⅳだけは、毎日小問1問だけでも解いて計算力を鈍らせないように気をつけていました。
4.まとめ
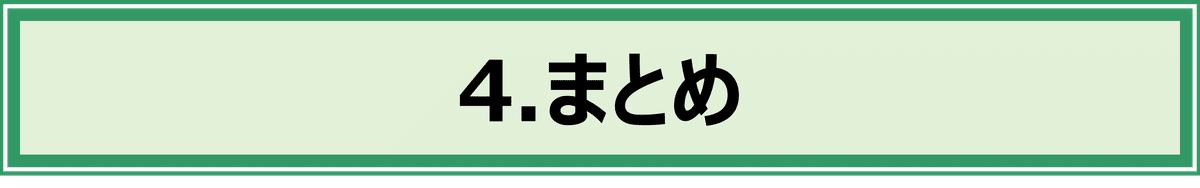
中小企業診断士の勉強はほんとに大変。
僕自身、同じ受験生時代を過ごしていたので、その大変さは痛いほどよく分かります。
しかし、大変な受験生活を乗り越え、診断士の合格を手にしたときの感動は今でも忘れられません。
そして、中小企業診断士として活動している今、会社員生活だけでは味わえない新しい経験やご縁があり、診断士資格を取ってよかったと心から実感しています。
830時間。中小企業診断士資格の勉強に費やした時間。平日は3時間勉強。テレビや飲み会もガマン。正直、つらいときもあった。でも資格に合格してから10年。会社では手に入らない経験やご縁、心の充実感に恵まれて副収入も年7桁に到達した。困難の先に光がある。今日も明るい未来に向かって頑張ろう。
— やす (@yasulog2) March 25, 2022
「中小企業診断士の資格は、人生を大きく変えるパワーを持つ」夢のある資格です。
この記事をお読みいただいているあなたの合格を心より祈願しています。
そして、中小企業診断士仲間としていっしょに活動できる日がくることを心より願っております。
ここまで貴重な時間を使って最後までお読みいただき、心から感謝申し上げます。
本noteに少しでも共感いただけた方に、ぜひ以下のお願いをさせてくださいませ。
①本noteのスキをクリック
②ぜひX(Twitter)とnoteをフォロー
③本noteをリポスト、または引用リポスト
この記事が、あなたの受験勉強に少しでもお役に立てたなら幸いです。
ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
