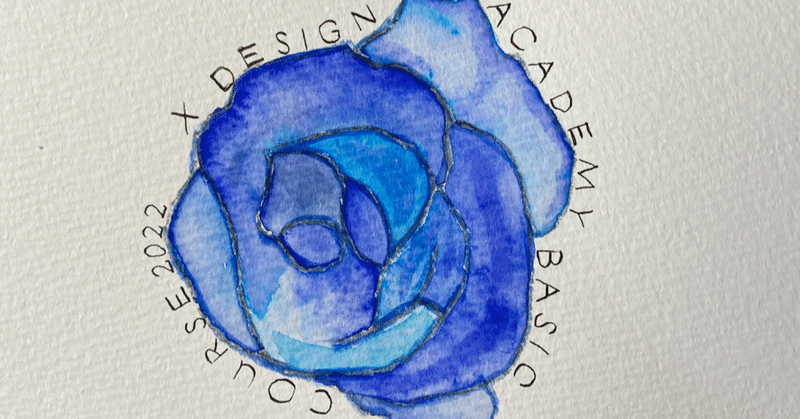
Xデザイン学校#6のリフレクション
はじめに
2022年10月15日。6回目はアイディア創出と受容性評価。広義の大部分を使って、バリューシナリオを検討した。もうリサーチフェーズには戻れない、だからこそリサーチフェーズが重要だったのだ、ということを痛感した回だった。
事実だっけ?仮説だっけ?
グループワークの際、私がユーザインタビューから得られた事実だと思っていたことが、実際は事実ではなく、上位下位分析で見出した本質的欲求価値、つまり仮説だった、ということが起きた。
本質的欲求価値はインタビューで得られた事実の分析結果ではあるので、もしかしたら事実か仮説か誤認したまま作業を進めていても大きな問題にはならなかったかもしれない。
ただ自分が知らず知らずのうちに事実と仮説の区別がつかなくなっていたことはとてもショック、この辺りから確証バイアスの罠にハマって行くのかもしれないと思い、背筋がゾワッとした。
新規プロダクト開発においては、仮説検証を高速に回すことが鍵というが、今回の経験を経て、仮説検証を高速に回していると、何が事実で何が仮説なのかは、だんだん区別がつかなくなっていきそうだと思った。
そこはきちんと事実と仮説の区別をつけ続ける必要があるのか、それとも事実か仮説かわからなくなってしまうのは仕方のないことと割り切って、「事実か仮説かわからなくなったもの」と事実とを突き合わせられる状態にしておく(例:頻繁にユーザリサーチができる状態にする)ことが大事なのだろうか。なんとなく後者の方が現実的かと思っているが、どうだろう。
複数ペルソナを設定することは迷いの表れなのか?
私たちのグループは、ペルソナをメインペルソナとサブペルソナの2種類設定している。当初はサブペルソナがサービスのメインターゲットだったこともあり、2種類のペルソナを設定していることに違和感がなかったが、バリューシナリオを検討する中で、ペルソナが2種類設定されているせいで、サービスが提供する価値や収益モデルがボヤけてしまっている可能性があるように思う瞬間があった。
その後の実装フェーズを考えても、このままだとメインペルソナに向けた一番価値ある機能を実装するのか、それともメインペルソナとサブペルソナに共通する機能を実装するのか、といった話に発展してややこしそうなので、今の段階ではサブペルソナは捨てて、メインペルソナに注力すべきかもしれないと思った。
実装フェーズの知識・経験が、ない!(1ヶ月ぶり2度目)
今日は構造化シナリオ手法の中のバリューシナリオを使ったワークを行なった。前回の上位下位関係分析に続き、これも全く知らない手法だった。構造化シナリオ手法は体系だって整理されているようで、次回の講義のメインテーマにもなっているものなので、サイトや先生が紹介されていた書籍を読んで、予習した上で次回の講座に臨みたい。
スペシャリストを極めた先に
講義の最後、Xデザイン学校の先輩の松薗 美帆さんが「私の履歴書と新しいUXリサーチャー像」というタイトルで講演をしてくださった。私はXデザインフォーラムで一度拝聴していたが、改めて聞くことで理解が進んだ。特にジェネラリスト/スペシャリストに関する松薗さんの考え方の変化が興味深かった。松薗さんはUXリサーチャーの先に組織への働きかけがあると気づいたという旨をお話をされていて、これは私が今業務で当たっているスクラムマスターが、レベルが上がるごとに働きかけのスコープを、開発者→スクラムチームおよびステークホルダ→組織へと広げると言われることと一致して、すごく共感した。(参考:https://scrummasterway.com/scrummasterway-ja.html)
スペシャリストを極めるというと、スコープがどんどん狭まっていくようなイメージを持っていたが、スペシャリストを極めた先でスコープが広がるというイメージがすごく好きだ。
松薗さんの中に息づく人類学の知を感じた気がした
最近、ティム・インゴルドの「人類学とは何か」を読み終わったところだったが、松薗さんのお話を聞いていて、松薗さんの中に、人類学的なモノの見方、考え方が息づいているように感じる瞬間があって、興味深かった。以前Xデザイン学校で聞いた「人は一番得意なことにすがって判断をする」の話を思い出した。私は今人類学に興味があるが、書籍一冊読んだ程度では単なる知識に過ぎず、自分の中で息づくようなスキルにはできていないので、デザインと併せて、人類学も学んでいきたいと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
