
「やさしい日本語」と翻訳とのちがい
愛知県「やさしい日本語」の手引き
「やさしい日本語」には、基本のルールがありますが
元の文章をそのまま書き換えるのではありません。
愛知県が2013年に作成した「やさしい日本語」の手引きに
「やさしい日本語」を作るときの流れとポイントがあるので
見てみましょう。(p5)

「やさしい日本語」を作るときの流れとポイント
「やさしい日本語」を作るときの流れは以下です。
1.数ある情報の中から必要なものを取捨選択する
2.できるだけ余分な情報をカットする
3.伝えたいことを前に持ってくる
4.必要に応じて補足情報を加える
これらを行ってから、
5.一文中で、一つの情報提供に留める
6.一文を短くする
7.主語と述語を明確にする
8.難しい言葉を易しい言葉に置き換える
9.「分かち書き」にする
10.漢字には、すべてルビをふる
11.必要に応じて、写真やイラストをつける
やりがちなのは、とにかく元情報を頭から順に
やさしい言葉に言いかえするというパターンですが
この作業をするのは8番目なんです。
まずは、情報の取捨選択から
まず初めにすることは情報の取捨選択。
元の文がわかりにくいと、いくら「やさしい日本語」に言いかえても
わかりにくいままとなります。それがよくわかるのが下記です。
新たに日本に入国し、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方は、市区町村に新たに住所を定めた日から14日以内に、在留カード(空港等で在留カードが交付されなかった方については、パスポート)などをお持ちいただいて、お住まいの市区町村に転入の届出を行う必要があります。
(法務省HP 外国人住民に係る住基台帳制度 転入・転出より)
これは日本に入国した外国人が、在留カードをもらい、
市町村に転入届を出すという手続きについてですが
一読してわかりました? 何度も読みなおしませんでした?
手順を無視して、言葉だけを頭からやさしくしたとしても
やっぱりわかりにくくなると思います。
では、下記はどうでしょう。
【出入国在留管理庁】やさしい日本語版の
『生活・仕事ガイドブック ~日本で生活する外国人のみなさんへ』から
転入届を出す手順です。
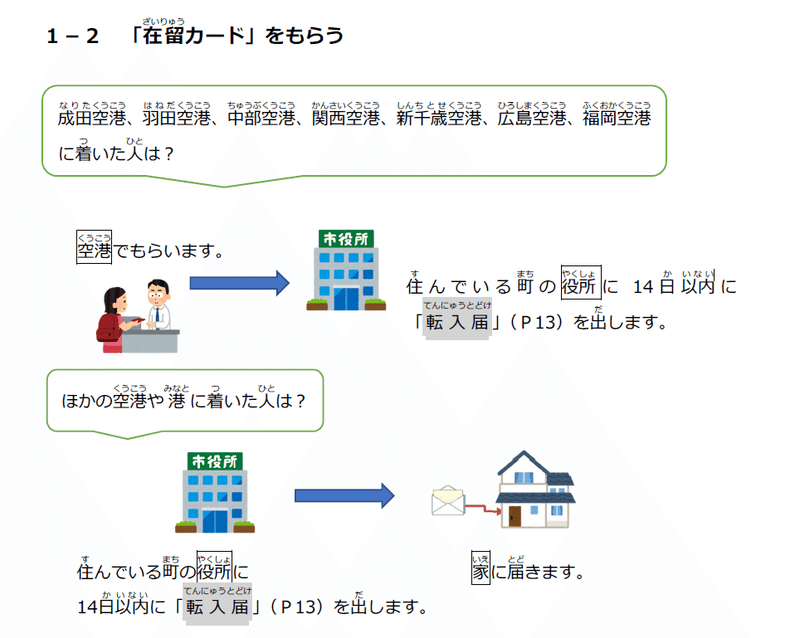
伝えたいことを前に持ってくる
そして、情報の順番も大切です。
行政の文は一つの形式があるようで。
たとえば「断水のお知らせ」で、HPにこんなお知らせがありました。
市民の皆様には日頃より・・・と、まずはご挨拶
今回の断水では多大なご迷惑をお掛けしたことを・・・とお詫びが続き
現状、原因など・・・の説明があり
今、精一杯復旧に努力している、という話のあと、やっと
市役所による水の配給の時間と場所
いやいや、読み手が知りたいのは「いつ、どこで給水が行われるか」です。外国人が辞書を引き引き読むことを考えたら
知りたい情報にたどり着くまでに疲れ果ててしまういます。
ご紹介した「やさしい日本語」を作るときの流れでは、
手順の3番目に「伝えたいことを前に持ってくる」ですので
給水の場所と時間はトップに持ってくることになりますね。
そもそも日本人だって、提供されたお知らせ文を
100%しっかり読むことは稀です。
斜めに読んだり、関心興味のある所だけ選んで読むとか
見出しだけ読んで後からじっくり読むとかしますよね。
「やさしい日本語」への書きかえを通して
気がつくこともたくさんあります。
外国人住民向けだけでなく、誰にでもわかりやすい情報が出せるよう
見直す行政も増えています。
さらに広がることを期待しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
