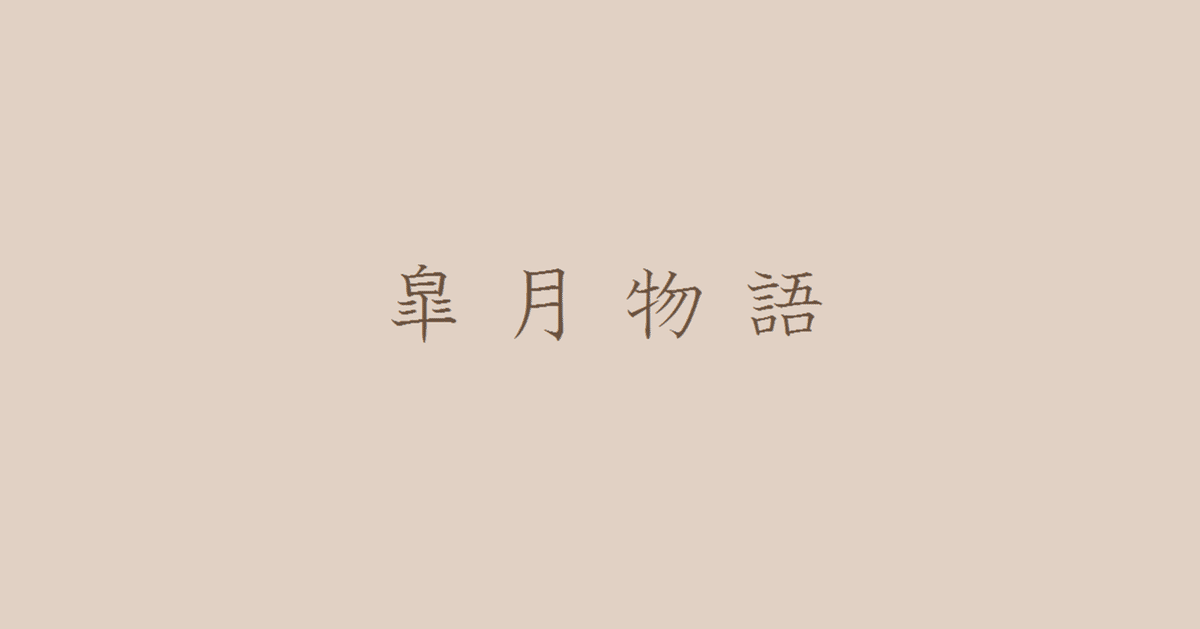
美しい芸妓 (皐月物語 6)
検番の勝手口に鍵がかかっていたので、玄関に回って皐月の家と同じ紅殻格子の引き戸を開ける。皐月が求めていた冷気がここにはあった。
「お母さんいる?」
お母さんとは検番を細々と守り続けてきた老芸妓の京子のことだ。
「あら、皐月じゃないか。久しぶりだねえ。ずいぶん黒くなっちゃって。それよりあんた、また背が伸びたんじゃない?」
矢継ぎ早に話しかけてくる京子に皐月はほっとする。
「検番は涼しいね。何か飲み物ってある?」
「なんだい、涼を取りに来たのかい。最近顔を出さないからお子様向けの飲み物なんて置いてないよ。緑茶かコーヒーならあるけどさ」
「俺コーヒーがいい。ブラック」
「あんたコーヒーなんて飲むようになったのかい。へぇ~」
「この前、真理に教えてもらったんだ。あいつ、大人ぶっちゃってて面白いよ」
「ちょっと待ってて。今持ってくるから」
応接間の黒光りする古びたソファーに腰掛け、スマホを取り出し、鉄道系のインスタグラムをチェックする。もう乗れなくなった踊り子185系の写真を見て、一度乗っておきたかったなと皐月は悔やむ。
京子がアイスコーヒーを持ってきた。フリージアの彫刻がなされたガラスの足つきの美しいタンブラーだ。皐月が検番でお世話になっていた時はこんないいタンブラーで飲み物を飲んだことがなかった。
「はい、冷コー」
「玲子さんがどうかしたの?」
玲子は京子の娘で、今は芸妓をしていない。子供の頃、皐月や真理はよく玲子に面倒を見てもらっていた。
「玲子じゃなくて冷たいコーヒー。略して冷コー」
「ダセ~っ!」
喫茶パピヨンで飲んだコーヒーはホットだったが、これはペットボトルのアイスコーヒーだった。思ったよりも飲みやすかったが、飲んでも飲んでも喉の渇きが収まらない。
「やっぱりお茶ちょうだい」
「あんた、自分で淹れといで」
「何かお菓子とかある?」
「煎餅とか御欠ならあるよ」
「なんだ、婆菓子しかないんだ」
「ここにはババアしかいないからね」
勝手の知った台所に行き、お茶とお菓子を取りに行く。どこに何があるかはわかっている。
「ねえ、お母さん。今日うちに来る頼子さんのこと聞きたいんだけど……」
「なんだい、百合から聞いていなかったのかい?」
「何となく聞きづらくて……。頼子さんってママの同級生なんだよね。そんな齢の人が今から芸妓なんてできるの?」
「さすがに一から芸を覚えていくっていうわけじゃないんだけどね。彼女は温泉旅館で仲居を長くやってきたから接客ができるのよ。あまり機会はないかもしれないけれど、忙しい時に手伝ってもらおうと思ってるの」
「そうなんだ」
今まで母は住み込みの弟子に住む場所を無償で提供していた。だから頼子にも同じことをするだろう、と皐月は考えている。
だが母は頼子に皐月の食事の世話をしてもらうつもりでいるようなので、きっと食費も援助するのだろう。もしかしたら自分の面倒と引き換えに、それ以上の経済的な支援をするつもりなのかもしれない。そしてそれが小百合と頼子の友情の証なのだ、と皐月は自分なりに理解している。
「高校生の女の子も一緒に家に来るんだけど、その子って芸妓になるの?」
「ああ、祐希ちゃんのことね。特にそういった話は聞いていないよ。まあこんな田舎だし、高校卒業してすぐに飛び込んでくるような世界でもないからね。今は芸妓だけで生活できるような時代でもないし。うちの子たちは兼業の子がほとんどだしね。ここじゃ芸妓一本でやっているほうが珍しいよ」
皐月の母の小百合が芸妓だけでやっていけているのは株式投資で利益を上げているからだ。真理の母の凛子は恋人からの援助があるからだと皐月は真理から聞かされた。真理はそのことを嫌って勉強にのめり込んでいる。お金に絡む話がリアルに迫ってきて、皐月は嫌な気分になってきた。
「後で百合が頼子を連れてここに来るけど、あんたそれまで検番にいるかい?」
「ううん、ちょっと休んだらすぐに帰る。ところで今日は芸妓さん、誰も来ていないの?」
「明日美が稽古場にいるよ」
「ちょっと顔出してくる」
明日美はここの一番人気の芸妓だ。この仕事だけで生活をしている、ここでは稀有な存在だ。若くて美人だからよくお座敷に呼ばれる。英語ができるので、名古屋まで出張して外国人相手の宴席に呼ばれることもある。最近は病気がちだと聞いていた。
二階の稽古場に上がっていくと明日美がビデオで撮影しながら何かの振り付けの練習をしていた。邪魔にならないように部屋の隅に座って明日美の背後から舞を眺めていた。明日美の美しさを目の当たりにすると、皐月の記憶の中でさっきまで一緒にいた入屋千智のことが霞んできた。
明日美は皐月の知る限り最も美しい女性だ。もしかしたら実際に会えばテレビなどで見る芸能人の方が綺麗なのかもしれない。だが芸能人には直接会ったことがないので、その人の持つ実際の美しさは皐月にはわからない。そばにいて同じ世界に身を置いて、初めてその人の持つ魅力がわかる。
練習がひと段落した時を見計らって、皐月は明日美に近づいて挨拶しようとした。
「あれ? 皐月?」
「皐月だよ」
「何、久しぶりじゃん!」
明日美が抱きついてきた。皐月はこれが好きで明日美に会いに来た。いつもと同じ明日美の香りがして、軽く意識が飛ぶ。
「背、伸びたな~。もうすぐ抜かれそうだ」
「育ち盛りだからね」
「ちょっと真っ黒じゃん。日焼けし過ぎだよ。焦げてんじゃないの?」
明日美がケラケラと笑う。
「せっかく色白なんだから、ちゃんとケアしないとシミになっちゃうぞ」
「そんなの気にしてないよ」
「ダメだ。勿体無いじゃん。もう、バカだな~」
「何だよ、バカって。うっせぇなぁ」
「お前はバカでかわいいな~。チューしてやるよ」
皐月はこうして明日美にかわいがられるのが大好きだ。明日美は人がいるところで決してこんなことはしてこないので、これは皐月は明日美との秘密だと思っている。
「今日ね、うちに新しいお弟子さんが来るんだ」
「さっきお母さんから聞いた。寿美姐さん以来だね、住み込みの人って。家が賑やかになるね」
「まあそうなんだけどさぁ……」
「何? 百合姐さんと二人の方が良かった?」
「そうじゃないけどさ……。なんかお守をつけられるような気がしてちょっと複雑な気分。俺ってそんなに信用ないのかな?」
「皐月はまだ小学生だから仕方がないでしょ。アメリカじゃ13歳未満の子供に一人で留守番させるとネグレクトにされちゃうからね」
「ここは日本だし。ところでネグレクトって何?」
「育児放棄。虐待の一種だね」
明日美は皐月が相手でも時々難しい話をする。子供扱いをするかと思えば、大人同然の扱いもする。皐月にとって明日美との会話は刺激的だ。
宴席でお客と会話ができるように明日美は毎日新聞は欠かさず読んでいるという。新聞以外にも良く本を読むと母から話を聞いている。
「虐待なんて全然。俺は思いっきり可愛がられてるよ!」
「わかってるって。でも、百合姐さんは皐月を家に一人にさせていることを気にしてるから」
「俺なら平気なのにな。家の事なら何でもできるし、料理だってできる。いつも仕事先からビデオ通話がかかってくるから、ウザいくらいだ」
「そういうこと言うな。百合姐さんも寂しいんだから。姐さんって人気あるのに仕事セーブしてるの知ってた?」
「何、それ?」
「かわいい皐月ちゃんと一緒にいたいって、時々お座敷を断っているんだよ。特に私との仕事とか」
「えっ? 俺のせいで仕事できないの?」
頼子が家に来てくれたら仕事を増やせるという話を聞いていた。その話を聞いた時、皐月には意味がよくわからなかったので聞き流していた。
「ん~、ちょっと違うかな。仕事を選んでるだけ。私と一緒に出張しちゃうと、その日は向こうで泊りになっちゃうから嫌なんだって。家に帰りたいって」
明日美の話を聞いた皐月はいろいろ考えたいことがあったが、情報量が多くてぼ~っと虚空を見つめることしかできなかった。
「もっとも仕事を選んでいると言うよりも、単に私と一緒にお座敷に上がりたくないだけなのかもしれないけどね。私は百合姐さんに嫌われてるから。愛する皐月ちゃんを取られちゃうんじゃないかってね警戒されているのかもね」
「そんなことないよ。ママは明日美のことすごく褒めてるから」
「本当? そんな風に言ってもらえてたら嬉しいな。私、百合姐さんのこと尊敬してるから」
「そうなの? ママのこと、尊敬してるんだ」
「百合姐さんはね、お客の扱いがとても上手なの。私はそういうの苦手だから、百合姐さんってすごいな~っていつも思う」
この話を皐月は母から聞いたことがある。明日美は美人だから客受けがいいけれど、くだけた話題になると上手く客の相手ができないので、いつも自分がフォローしなきゃいけないから大変だと。明日美はその時の百合の感情を読み取って、自分が嫌われているのだと誤解をしているのかもしれない。
「明日美に俺のことを取られたくないとか、そんな話は聞いたことがないな……。ママは俺にガールフレンドができたら喜ぶんじゃないかな」
「同じ年頃の女の子が相手なら喜ぶかもしれないけど、相手が私みたいな芸妓じゃ百合姐さんだって怒るよ」
「俺は明日美が恋人だったら最高なんだけどな~」
「嬉しいことを言ってくれるね。ありがとう」
明日美は笑いながら皐月を抱き寄せて、頬に軽くキスをした。ゆさゆさ揺すられているうちに皐月は気持ちよくなってきた。
「そういや高校生の娘が来るんだってね。皐月、浮気なんかしたら許さないからな」
最後まで読んでくれてありがとう。この記事を気に入ってもらえたら嬉しい。
