
櫟本分署跡に中山みきを訪ねる
月日 すべての悲しみをいやせ

東京にある上の弟の家に、きょうだい3人が揃って集まる機会があった。私にとって姪や甥にあたる弟の家の子どもさんたちとは、懇意にさせて頂いている。本当だったら転げ回って一緒に遊ばせてもらうところなのだけど、こういうご時世である。自分が持ち込んでしまうかもしれない新型コロナウイルスで、弟の家の人たちがバタバタと倒れてゆく悪夢のような光景がどうしても頭をかすめてしまう。せっかく久しぶりに会えたのに、不必要なぐらいギクシャクした再会になってしまった。
私たちきょうだいは全国バラバラな場所で暮らしているもので、3人が全員顔を合わせることのできる機会は滅多にない。話は自然と、奈良の家で過ごしていた小さい頃の思い出話に傾いた。正月やお盆はいつも親戚と一緒に天理教の本部へ「おぢばがえり」に行って、神殿の回廊のツルツルに磨きあげた床板を滑り台代わりにして遊んだものだったな、といった方面の思い出に話が及んだ時、下の弟から
おれら、何も知らんと「あしきをはろうてタスけたまえ」とか言うてたけど、天理教ちゅーのはあれ、どういう宗教やねん?
という疑問が発せられた。
大阪のおばぁはんちに、「おやさま」てマンガがあったやろ。今の天理教本部がある場所に住んではった、中山みきちゅー農家のおばさんが、江戸時代に始めた宗教やがな。
女の人が作らはったんか?
じぶん、そおゆうとこから知らんかったんかいな!
私の育ったのが天理教の家だったことは、以前にも別のところで書いたことがあったけれど、正確には「母方の祖母の家」が天理教の家だったのであって、奈良の実家では取り立てて「神さん」を祀ったりはしていなかった。ただ、一番先に生まれた私は、弟の出産で母親が入院している間などにその祖母の家に預けられていた期間が非常に長かったため、弟よりも余計に天理教の影響を受けていたということは、あったのかもしれない。それにしても、同じ屋根の下で暮らしていていろんな宗教行事にも一緒に参加してきたはずの弟が、そうした基本的なことについて何一つ知らされる機会を持たないままああいうのに「つきあって」いたのかということは、衝撃的なことだった。
かく言う私自身、上の記事を書くために自分で調べてみるまでは、知らずにいたこともいろいろあった。自分たちの家の歴史に関わる話でもあり、それならせっかくだからみんなが知っておいた方がいいだろうということで、天理教の話が始まった。二人の弟を相手にそういう話をするのは、初めてのことだった。
中山みきが天理教を始めはったんは、時代が幕末に入るちょっと前。西暦で言うたら1838年のことで、天理高校の生徒さんは「人は参拝」の語呂合わせで暗記させられるらしい。年号で言うたら、天保9年になる。
「天保の改革」の天保か。
せや。その頃は、今の日本もせやけど、世の中がめちゃめちゃに乱れとった。それまでの封建社会の歴史が溜め込んできた矛盾が、爆発する限界に差しかかっとったちゅーことがまずあるわけやけど、それに加えていろんな天変地異も起こった。「天保の大飢饉」ちゅーのがあって、大勢の人が亡くなった。
おお、聞いたことあるぞ。
家族の誰かが飢え死にしたら、残った家族が泣きながら死体の肉をむさぼり食ったとか、そんな話があちこちにあったらしいわ。「天保の改革」ちゅーたかて、問題はその人らの命やのーて、幕府の財政なわけやから、そうやって苦しんでる庶民からどないしてもっと年貢を巻き上げるかちゅー話にしか、なるわけあらへん。幕府に対する怒りはあちこちで高まって、天理教が始まる前の年には大阪で大塩平八郎の乱ちゅーのが起こった。
それも聞いたことある。大阪で起こったんか。
天満の街に並んどった悪い役人の屋敷に、片っ端から大砲ぶち込んだ。
ごっついな。その大塩平八郎ちゅーのんは、どおゆう人やったんや。農民か。
それが、その幕府の奉行所の与力をやってた人やった。
ほお、それはエラい人やな。
弟の口から感心したような声が出た。この弟は弟で、組織の中で生きている人間がその不正と対決することの大変さと崇高さを身にしみて理解できるような年の重ね方をしてきたのだな、といったような、兄的感慨が込みあげてくるのを感じた。
中国の思想家に王陽明ちゅー人がおってな。大塩平八郎はその人が始めた陽明学ちゅー学問を身につけとったんや。「知行合一」ちゅーて、学問ちゅーのんはアタマで分かっとっただけではアカン。正しいて信じたことは行動に移さひんだら意味があれひんちゅー思想やな。
それも何か、習ろたよーな気ぃするわ。
郷ひろみという人がこの王陽明を讃えて歌わはったんが、「王陽明サンバ」という歌や。
ほんまか!
…「ほんまか」ちゅわんといてくれよ。
大塩平八郎の乱は、「救民」の旗印のもとに武士階級の人間をリーダーとして戦いぬかれた、日本の歴史で唯一の戦争だったと言うことができる。当時の大坂では豪商と結託した不正役人による汚職が横行し、庶民の生活は食い物にされるばかりだった。さらに巷に餓死者が溢れているのをよそにして、江戸では将軍家の代替わり儀式の準備が進められており、大坂からはその式典のために夥しい米が、庶民の口に入ることもなく、運び出されて行った。義を見てせざるは勇なきなり。もはや幕府に自浄能力はないと見切った徳川家譜代家臣の子孫である大塩平八郎は、自分と門弟たちの命をかけて「幕府をいさめる行動」に立ちあがったのだった。この反乱は農民主体の「世直し一揆」として全国に拡大し、日本の歴史は幕末の動乱期へと、本格的に突入してゆくことになる。
天満の役人町に火ぃつけて、次は船場の商人町や。大坂はあっちゅー間に火の海になった。
あかんがな。
火ぃつけたんは悪い商人の家だけやったけど、風の強い日ぃやったらしくてな。「大塩焼け」ちゅーて、その日の間に大坂の5分の1くらい丸焼けになったらしい。けど巻き添えで家焼かれても、町の人らの中に大塩平八郎を恨む人は誰一人いてへんかったちゅー話やな。
そうかー。
こんな歌も残ったあるがな。
だーれかさんが
だーれかさんが
だーれかさんが火ぃつけた
心斎橋 心斎橋
心斎橋にー火ぃつけた…
あれって、そおゆう歌やったんか⁉︎
…おまえ、いちいち信じるなよ。話し甲斐があっておもろいけど。
その夜、奈良盆地から見上げた生駒山の向こう側の空は、「大塩焼け」の炎で真っ赤に染まっていたのだという。そんな風に奈良から見て生駒山の向こうの夜空が真っ赤に染まった出来事は、歴史上三回しか伝えられていない。一回目は大坂夏の陣の時。二回目が大塩平八郎の乱の時。三回目は大阪大空襲の時。いずれも日本の歴史が大きく変わる、節目節目に起こった出来事だった。それがどんなにか「不気味な予感」をはらんだ光景だったろうということは、毎日生駒山を眺めて暮らしていた身としてはすごくリアルに想像できる。奈良盆地の東麓で農家の主婦をやっていた中山みきという人の心に「何かが起こった」のは、その「真っ赤な空」を見たときのことではなかったか。そんなイメージがいつの頃からか私の心には、焼きついて離れなくなっている。もとよりそれは、同じように奈良で育った一人の人間としての、個人的な空想にすぎないわけではあるのだけれど。
そおゆう時代の空気の中で、天理教ちゅー宗教は始まったわけや。一言で言うたら、人間は殺し合いをするために生まれてきたんやない。天皇も武士も百姓もない。みんなが平等に助け合って生きていかなアカンちゅー教えやな。
立派やないか。
天理教用語で、支配階級のことを「高山」と言い、支配される民衆のことを「谷底」と言う。この「谷底」をせり上げて、世の中全体を平らに。当時の奈良の方言で言うたら、「ろっくの地」になるように、ならす。そこから「陽気ぐらし」の世界が始まるちゅーのが、中山みきちゅー人の説かはった教えの骨子や。
なるほどなるほど。
「人間は平等である」ということは、いまだに全然そうなっていない実情はあれ、少なくとも現代では国定教科書にも記載されている「かくあるべき社会通念」として、「当たり前の常識」になっている。だが身分差別制度の上に成立していた当時の武家社会にあっては、そうした思想は支配体制の根幹を揺るがす最大の危険思想に他ならなかった。時代を考え合わせるなら、中山みきという人は何と大胆な人だったのだろうと、率直に言って思う。
さらに重要なのは、この時代にあって中山みきという人は女性としての立場から「男女の平等」を説いた人だったということだ。このことは決して「身分差別からの解放」という問題一般の中に、解消されていい話ではない。19世紀、すなわち中山みきと同時代に、アメリカやイギリスで女性解放運動の先駆者として活動していた人たちの伝記をまとめた本を私は読んだことがあるのだが、そこに名前が載っていた人々のあまりに多くが「最後は精神病院で死んだ」と書かれていて、心底ゾッとしたことを覚えている。「死んだ」のではなく「殺された」のである。男性を中心とした社会のあり方に異を唱えたがゆえに、「精神異常者」の烙印を押されて、社会から抹殺されたのである。「法の下の平等」を説いている国家においてさえ、そうしたことは無数に繰り返されてきたし、今でもそれは続いている。
そうした同じ時代にあって、確かに同じように「狐憑きのばあさん」と嘲笑されたり、何度となく警察に引っ張られたり、最後はその警察の拷問によって受けたダメージが元となって亡くなったりしたわけではあるけれど、中山みきという人は「人から尊敬される人」としてその一生を終えたわけだし、今でも尊敬を受け続けている。無名のまま抹殺されていった多くの先駆者の人々のことをおとしめる意味をもって言うのでは決してないけれど、それはやはりそれだけの「力」を持った人だったからなのだろうなと、思わないではいられない。
それで、その中山みきちゅー人は、どおゆう人やったんや
41歳になるまでは、ほんまにフツーの農家のおばさんやってはったらしいで。それがその天保9年の旧暦の10月23日に、「神がかり」にならはったちゅーねん。
「神がかり」てか。
中山みきの長男で秀司さんちゅー人がいてはってんけどな。その人の足が急に痛み出してえらいことになったんやと。ほんで、今の西名阪の福住インターの手前の長滝村ちゅーところに有名な山伏さんがいてはって、その人に頼んで祈祷をしてもらおーちゅーことになった。
ほおほお。
ところが、その山伏の人が祈祷をする時にいっつも依代を勤めてはった女の人が、その日は用事があって来られへんかった。
ヨリシロって何や。
何か、その山伏の人が護摩を焚いたら、その女の人に神様が乗り移ってどこが悪いのか教えてくれるちゅーのが、その祈祷のやり方やったらしーねん。コックリさんの10円玉の役を生きた人間がやる、みたいな感じやったんとちゃう?知らんけど。
まあ、大体わかったからええ。ほんで?
ほんで、しゃーないからお母さん、中山みきがその依代の役やってくれませんか、ちゅー話になったんやて。「そんなん私よーしません」て中山みきは言わはってんけど、「お母さんは信心深い方やから大丈夫ですよ」言われて、こわごわ両手に御幣持って、座ってはったらしいねん。ほしたらいきなり、山伏が呼んだんとは「違う神さん」が、降りてきたらしーねん。
それは、どおゆう神さんやったんや。
さあ、それはええ質問やぜ。
中山みきの説いた「神」がどういう存在だったのかということは、天理教という宗教の根本に関わる問題なわけだが、その教えは彼女の死後、さまざまな形でねじ曲げられて伝わっており、本当のところがどうだったかについては、いまだに詳しく分かっていないことも多い。上記の「神がかり」のエピソードについても、「まことしやかに語られてきた作り話」にすぎない可能性が極めて高い。どうしてそういう作り話が横行することになったのかというと、彼女の死後に天理教の「教団」を作った人間たちが、「明治」の天皇制政府のもとで活動の認可を得るために、「人間はみな平等なものだ」という中山みきの教えの根本的な部分を、ねじ曲げて伝えたからである。このために第二次世界大戦以前の教義においては、中山みきが天皇の祖先神であるイザナミノミコトの生まれ変わりであるといった教説が様々なモッタイをつけて語られていたし、現在の天理教本部もそれを「間違いだった」と公式に認めるところにまでは、行っていない。だから公式に刊行されている天理教の教典が伝えている「教祖像」と、実際の中山みきという人がどういうことを考えてどう生きた人だったかということは、区別して考える必要がある。そういったことを「前置き」として話した上で、「伝えられている通りの話」を私は弟に語った。
元の神、実の神である。
中山みきの身体に入り込んだ「神さん」は、居並ぶ親戚一同を前にそう名乗ったと伝えられている。「元の神」とはこの世界を創造した最初の神、「実の神」とは現在でもこの世界を実効支配している、同時代的な存在としての神、といった意味合いが込められた「神名」なのであろう。「支配」という言葉を使うのがこの場合適当なのかどうかは、よくわからないところなのだけれど。
この屋敷にいんねんあり。このたび、世界いちれつをたすけるために天降った。みきの身体を神のやしろに貰い受けたい。
「神さん」にそう言われ、みきの夫の善兵衛をはじめその場に居合わせた人々は、面食らった。一家の生活を支える主婦であるみきの「身体を貰い受ける」とは、どういうことになるのだろう。少なくとも善兵衛たちにとってそれは、みきという人が「自分のものでなくなる」ことを意味していた。それは、困る。なので「当方はまだ子どもも小そうございますゆえ、どうか別のところへお下がりを…」と恐る恐る、みきの口を借りて語っている「神さん」に頼もうとした。するとたちまち
もし承知せんのなら、この家、粉ぉも残らんようにする!
という恐ろしい言葉が、ものすごい迫力で、発せられた。一同は慌てて平伏したが、しかしやはり、困るものは困る。そうした「神と人との押し問答」が三日三晩にわたって続けられ、そのかん一睡もせず、一滴の水も飲まず、御幣を握りしめて「神の言葉」を語り続けるみきの両手からは、血が滴っていた。これ以上続けたらみきの命に関わると考えた善兵衛が、観念して、「わかりました。仰せの通りに致します」と答えたところ、みきはたちまち放心状態になり、その場にくずおれた。 10月26日の早朝のことだった。
働き者の主婦だった中山みきはその日から家事一切を放棄して蔵の中に引きこもり、「神さんとの会話」にふけるようになった。家族はもちろん困るし、心配もするわけだが、何しろ「神さん」と「約束」してしまったわけである。みきの行動を止めることは、もう誰にもできなかった。みきは家にあるものを何から何まで、道行く貧しい人に施してしまったので、一家の生活はたちまちどん底に落ち切った。やがて連れ合いの善兵衛さんが亡くなると、みきはとうとう家の母屋まで売り払ってしまい、一家は土蔵で生活することになった。
ほんで「あそこのばあさんはキツネ憑きや」言われて、ずっとさげすまれてはってんけどな。しばらくすると「あそこのばあさんには病気を治す力がある」ちゅーことが評判になって、奈良盆地だけやのーて京都や大阪からも、病気の人が庄屋敷村に集まってくるようになった。ほんで命助けてもろた人らがお礼参りに来たら、中山みきから「今度はあんたが助ける側に回るんや」言われて、そうやってどんどん信者の人が増えていった。
それって、ほんまにそおゆう力を持ってはったってことか?
超能力者やったとかそういうわけでは、なかった思うねんで。せやけど病気になって生きる希望を無くしてはった人らの一人一人が、「もっぺん生きたい」って心から思えるような、そういう気持ちにさせてくれる力を持った人やった、ちゅーことになるのんと違うかなあ。コロナの今かて、そうやがな。病気になった人は、病気自体の苦しみもそうやけど、人から嫌われて「あっち行け」言われて、そういうのが一番人間から「生きる力」を奪うわけやんか。昔はもっとそういう差別が、きつかった思うで。そういう中で「自分が生きてることをこんなにもよろこんでくれはる人がいてはった」ちゅーことが、一番最初の頃に信者にならはった人らが中山みきちゅー人に対して感じてたことやなかったかって、おれは思てるねん。
みきが晩年になってから信者になった人に、ヤクザの親分をやっていた平野楢蔵という人がいた。この人もまた、彼女の教えた「おつとめ」の力で、「ない命」を救われた人だった。
人からさげすまれる中で、突っ張って生きやんなんかったから、あんたもしんどかったやろ。せやけどな。人を傷つけて生きてたら、我が身も傷つくばかりやで。人を助けたら、我が身も助かるんやで。
中山みきのそうした教えに感激した楢蔵は、その場で子分たちと水盃を交わし、ヤクザの組を解散して「お助け人」としての第二の人生を歩むことを決意した。しかし「今日から人助けを始めるぞ」と思って地元の大和郡山の街をウロウロしてみても、「ヤクザの楢蔵」しか知らない周りの人々は気味悪がって、当初は誰も声をかけてくれなかったという。
「明治」の19年、1886年に関西一円でコレラが流行した際には、楢蔵は警察が設置した「立入禁止」の看板を乗り越えて、毎日のように患者の発生した村に通いつめた。動けなくなった患者の人たちの身体を拭いて回り、物を食べる力も無くなった人には金平糖を噛み砕いて口移しで飲み込ませ、そして中山みきから教わった「みかぐらうた」と「手踊り」で、一心不乱に祈り続けた。
その「おつとめ」で助かった人もいたのかもしれないけれど、助からなかった人もやはりいたはずだろうと思う。病気は飽くまでも病気なのだ。けれども助かった人たちは間違いなく「うれしかった」はずである。自分が助かったことはもちろん、平野楢蔵のその気持ちを何より「うれしい」と感じたに違いないと思う。そして楢蔵もまた、相手が助かったことはもとより、「自分にも人を助けることができた」ということが、「うれしかった」はずである。その人たちはそこから、「新たな家族」になった。
そういうのが、天理教の一番最初の時代における、信者さんたちにとっての「信仰」のあり方に他ならなかった。
付け加えて書いておくなら、この平野楢蔵は中山みきの死後、古くからの信者の人たちに「天皇陛下のことを神さんと認めないとは何ごとか」「お道がつぶれてもええんか」と日本刀を突きつけて脅して回り、教団に国策迎合の「応法の理」路線を歩ませてゆくための行動隊長的な役割を果たした人である。やがて日清·日露戦争が始まって帝国主義の時代が本格化してゆくと、日本人が銃をとって外国の人々を殺しに行くことを止めようとしたどころか、「よろこんで」いた人である。ホメられた話ではないどころか、最悪だとしか言いようがない。中山みきが死んでそんな楢蔵のことを「叱って」くれることのできる人がどこにもいなくなってしまったことは、この人自身にとっての最大の「不幸」だったと言えるだろう。とはいえそうした人物の中にも、天理教で言うところの「助け一条の真心」が出発点においては確かに存在していたわけであり、どうしてその真心をもって朝鮮や中国の人々とも向き合うことができなかったのだろうかと私はいつも思う。
この平野楢蔵ちゅー人が、郡山大教会を作ってそこの初代の会長になった。本部と別の場所にできた最初の教会や。その弟子に、岡山の方から出て来て初代の会長に助けられた人がいてはって、その人がまた、滋賀県の山奥に住んでたおれらのひいおばあさんのことを助けてくれはった。これがうっとこのお母はんの家が、天理教の家になるまでの歴史のあらましちゅーことになるわけや。
なるほどなー。しかしお前、よおそんな話、スラスラ出てくるもんやな。
まあ、最近、勉強し直したよってな。
ほんでお前自身はそんな風に勉強し直して、中山みきちゅー人のことをどない思たんじゃ。
ん?そらやっぱり、エラい人やってんなって、思ったよ。
おお、そうかそうか。
一番最後になって弟はえらくうれしそうな顔をしたのだけれど、その顔の意味するところが私には分かるような感じがした。私というのはそんな風に素直に他人のことをホメたり認めたりすることが昔から全然できなくて、いつも相手のアラ探しをすることばかり考えているようなそういう人間だったからである。「だった」と過去形で書いたが、私自身がこのnoteという場所で短い期間に書き綴ってきたいくつかの文章を読み返してみただけでも、自分のそうした態度はいまだに全然変わっていないように感じられる。そうした鼻持ちならない私の性格の最大の犠牲者となってきたのは、今までにつきあってきた女の人を別にするならば、常に最も身近なところにいた二人の弟たちに他ならなかったはずだった。
おれもマルくなったということなのだろうか、みたいなことをその弟の顔を見ながら思いつつ、一方では単に弱気な性格になっただけなのかもしれないな、みたいなことを、同時に思った。
弟の家を後にしてからも、私は「立入禁止」の看板を踏み越えてコレラが発生した村へ通い続けたという、130年前の平野楢蔵の気持ちについて、考え続けていた。新型コロナウイルスが猛威を振るっている現在、今の天理教本部がそうした形で感染者の人たちへの「お助け」の取り組みに乗り出すようなことはまず絶対にありえない話だし、そうした行動に出ることが「正しいこと」であるとは、私もまた思わない。相手のことを本当に大切に思うなら、「三密」を避けて一定の距離を保って、みたいな今の常識から考えれば、平野楢蔵のやったこと自体、彼自身がコレラ菌をいろんなところにバラまいて回るようなとんでもない行為だったという話にしか、なりようがないだろう。それは決して「美談」などではなかったのだし、「美談」にされるべきではない話なのだとも思う。
けれどもそうした「助け」を「必要」としている人々の数は、今まさに世界中で増え続けているわけだし、それは患者の人たちにとって「他の形」では絶対に求めることができないようなタイプの「助け」だったのではないかとも、一方では思う。私自身、今この瞬間にウイルスの感染が発覚してどこかに閉じ込められてしまうようなことになったとしたら、求めずにいられないのはそうした「外の世界からの助け」であることだろう。そしてそうしたことは誰の人生の上にも、本当にいつ起こってもおかしくない状況を迎えている。
新型ウイルスという未知の脅威に対する恐怖と不安が拡大する中、差別や迫害に一回でもさらされた感染者の人の心には、その体験が「一生消えない傷」となって、間違いなく残り続ける。そういう目に遭わされた人は例え病気が治ったとしても、生きることをよろこぶことそれ自体が、できなくなってしまう。そのことが人間の心にもたらす危機は、病気それ自体よりも遥かに深刻なものであると思う。
「立入禁止」の看板を踏み越えたという平野楢蔵の行動が、医学的に見てどんなにデタラメなことであるかは明らかであるにも関わらず、どうしても「感動的」に思えてしまうその理由は、それが人間の作り出すそうした心の壁、差別の壁を打ち破るために、壁のこちら側の人間、と言うより壁を作り出す側に身を置いている人間がとることのできる、唯一の具体的な行動に他ならないことを、我々自身が「わかって」いるからなのではないだろうか。そんな感じがする。そういうやり方でしか示すことのできない真心というものが、世の中にはあるものなのだ。
「やり方」「示す」という言葉が自分の中から無意識に出てきてしまったわけではあるけれど、しかしながら真心というのは「あるかないか」の問題なのであって、「表現の仕方」の問題ではない。もともと持ってもいない真心を「表現の仕方」で「ある」ように見せかけるなどということは、発想が既に詐欺師のそれになっている。「立入禁止」の看板の向こうの患者の人たちとどうしても「共に生きたい」という真心、「一緒に助かるのでなければ自分もまた助からない」という真心を、平野楢蔵という人は、強烈に持っていた。だから、行かずにいられなかった。それを持っていたということがまず、立派なことだ。天皇賛美の戦争協力者になった人間であれ、そのことはやはり認め、見習ってゆかねばならない。見習ってゆきたい。
で、それを見習った上で、果たして自分自身はどう生きて行けばいいのだろうか。
どうやら自分の直面しているのが「宗教的な問題」であることを、私は認めないわけに行かないようだった。
心の中では王陽明サンバが鳴り響いていた。

まだ10代の頃のことだったと思うが、ボアダムスの山塚アイという人が、「自分は大本教の家に生まれて、小さい頃から教会であげる祝詞や神楽の音に包まれて育ってきたから、それが音楽的なバックボーンになっている」みたいなことを語ってはったのを新聞で読み、とても親近感を覚えたと同時に、「大本教の人はそういうことを胸張って言えるのが、うらやましいな」と感じたことを覚えている。私も胸を張ればいいのだが、天理教という宗教がやってきたことの歴史を考えると、あまり胸を張る気になれない。
大本教は中山みきが亡くなった5年後にあたる1892年に、京都の綾部で「神がかり」になった出口ナオという人が始めた宗教だ。中山みきは「これが真実みなまことやで」「そこでじっくり見ているのやで」といった「やでやで口調」で人々の心の成人を促してはった人だけど、出口ナオは「この世は暗がりであるぞよ」「ビックリ箱が開くぞよ」といった「ぞよぞよ口調」でブイブイ言わしてはった人で、AKIRAに出てくる「ミヤコ様」に代表されるようなマンガやアニメの中の「新興宗教の教祖様」のステレオタイプなイメージは、大体この出口ナオという人をモデルにしている場合が多い。中山みきがモデルとなっていると思われるキャラクターは、「うしおととら」の日崎御角さんぐらいなものではないだろうか。何しろ見た目のインパクトという点で、天理教は大本教から圧倒的に水をあけられている。
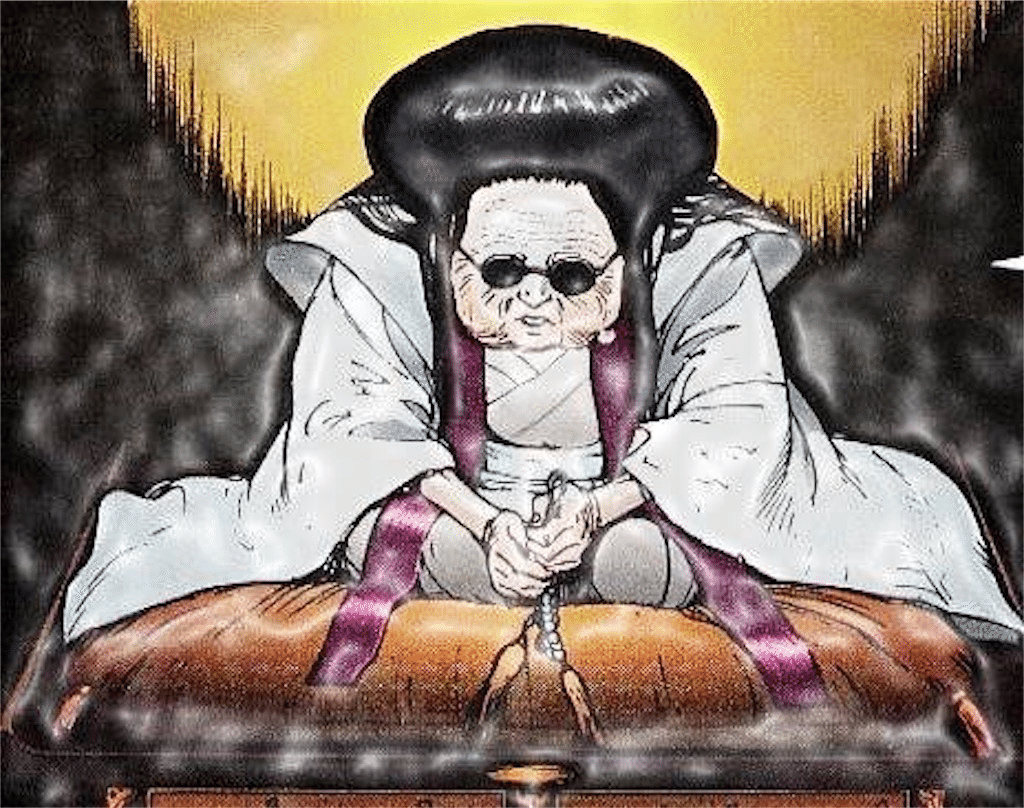

大本教は時の天皇制政府の意向を「忖度」することなど毛ほども考えず、記紀神話と全く相容れない独自の世界観にもとづく教理を堂々と展開し、さらには私利私欲のために戦争を起こして若者を死に追いやっている為政者たちのことを舌鋒鋭く批判し続けた。このために官憲の憎むところとなり、「大正」から「昭和」にかけては「第一次大本事件」「第二次大本事件」の名で知られる大弾圧が強行された。京都府亀岡市の明智光秀の城址に建設されていた広大な神殿はダイナマイトで跡形もなく破壊され、教団は非合法化されて信者の人々は散り散りになったが、それぞれの場所でなおもその信仰を守り続けた。この顛末は高橋和巳の「邪宗門」という小説のモデルになっている。
実に、かっこいい。
これに対し、「明治」政府による弾圧を「応法の理」にもとづく国策迎合でやり過ごし、「教派神道」として首尾よく国家から活動を公認された天理教は、それから何をやっていたか。記紀神話と矛盾する「泥海古記」を自ら焼き捨て、皇居の草刈りの勤労奉仕などを頼まれもしないのに自ら買って出て点数を上げ、天理中学では天皇の世界支配を究極の理想とする「八紘一宇」の思想を公立の学校以上に熱を入れて教え込み、ひたすら権力者の顔色をうかがって、そのご機嫌を取り結ぶことに汲々としていた。
実に、かっこわるい。
正直言って思春期の頃の私は、大本教に対してコンプレックスを感じていたし、自分がその中で育ってきた天理教よりも、どちらかといえば大本教にシンパシーを感じていたぐらいだった。
とはいえ、ネットの時代になって誰でも簡単に閲覧できるようになったその「原典」の内容を眺めてみると、大本教というのも天皇制のことを笑えないぐらい、相当にエグい宗教である。「明治」の25年に出口ナオが初めて「神の言葉」を文字にして書き記したとされる「大本神諭」の第一号は、こんな感じだ。
三ぜん世界一同に開く梅の花、艮の金神の世に成りたぞよ。梅で開いて松で治める、神国の世になりたぞよ。日本は神道、神が構わな行けぬ国であるぞよ。外国は獣類の世、強いもの勝ちの、悪魔ばかりの国であるぞよ。日本も獣の世になりて居るぞよ。外国人にばかされて、尻の毛まで抜かれて居りても、未だ眼が覚めん暗がりの世になりて居るぞよ。是では、国は立ちては行かんから、神が表に現はれて、三千世界の立替立直しを致すぞよ。用意を成されよ。この世は全然、新つの世に替へて了ふぞよ。三千世界の大洗濯、大掃除を致して、天下太平に世を治めて、万古末代続く神国の世に致すぞよ。神の申した事は、一分一厘違はんぞよ。毛筋の横巾ほども間違いは無いぞよ。これが違ふたら、神は此の世に居らんぞよ。
…現在の大本の人たちは、この「神諭」に示されたあからさまな排外主義と選民思想にどのように「決着」をつけた上で、信仰生活を送っておられるのだろうか。私は「信仰」を持っている人間ではないけれど、天理教の家に生まれた人間として、天理教という宗教がおこなってきた戦争協力と植民地支配への加担の歴史に対しては、その責任を一生背負い続けて行かねばならないと考えているし、同じ間違いを二度と繰り返させてはならないと考えている。大本の中からも同じような問題意識を持った有志の方が現れて下さることを、私は強く期待してやまない。
でもって私は別に大本教の話がしたかったわけでもなかったのである。
生まれた時から身の回りにあった宗教的な環境が「音楽的なバックボーン」を形作ってきたという話で言えば、私の場合もそれは同じだった。ということなのだ。

天理教信者の信仰生活の中心に位置しているのは、「おつとめ」と呼ばれる「歌と踊りで構成された神への礼拝」である。とりあえず私自身は、「おつとめ」というものを子どもの頃からそう理解していた。
「おつとめ」はまず、
あしきをはろうてたすけたまえ
てんりおうのみこと
という「歌」を21回繰り返して歌うことから始まる。天理教といえば「あしきをはろうてたすけたまえ」である。落語の「地獄八景亡者戯」や、江州音頭の「デロレン祭文」などにもそのフレーズがそのまま取り入れられているぐらいだから、信者でなくてもこの文句だけは知っているという人は、多いのではないかと思われる。
ちよとはなし
かみのいうこときいてくれ
あしきのことはいわんでな
このよのぢいとてんとをかたどりて
ふうふをこしらえきたるでな
これはこのよのはじめだし
なむてんりおうのみこと
という「歌」が、それに続く。「神の言うこと聞いてくれ」という出だしからして、「神さん」というのはえらく腰の低い「人」なのだなという印象を、子ども心に感じていたことが思い出される。それにつけても「一番」の「あしきをはろうてたすけたまえ」が「人間の立場から神にお願いする歌」であるのに対し、この「二番」は「神の立場から相手に語りかける歌」の形をとっている。このことを私は、小さい頃から奇妙に感じてきた。さらに「三番」
あしきをはろうて
たすけせきこむ
いちれつすましてかんろだい
というのが、三回ずつ三回、合計九回繰り返して歌われる。ここまでが「すわりづとめ」と呼ばれていて、座ったままつとめる。なお、それぞれの歌には「手踊り」と呼ばれる「振り付け」がついている。
「おつとめ」はそこから「立ちづとめ」に移り、振り付けも「立って踊る」ダイナミックなものに変わるのだが、子どもには難しいからということで、私の家では子どもはそこから「見ているだけ」の時間になっていた。年のために立つのが大儀になった祖父の膝に座って、私はいつもオトナの人たちが踊るその踊りを、眺めていた。
自分の親や親戚が一堂に集まって「同じ歌」を合唱し「同じ踊り」を踊っているのを見た経験のある人って、果たして世の中にどれぐらいいるのだろうか。私はそれを、毎月見ていた。昔はそういうのを「当たり前」だと思っていたわけだけど、今にして思えば相当に「特異な経験」だったのではないかと思う。そして自分にとって一番身近なオトナの人たちが真面目な顔で歌っていた歌の文句や踊りの振り付けのひとつひとつは、自分自身がオトナになった今でも心の中に強烈な印象となって、刻みつけられているのを感じる。
いちれつに はやくたすけをいそぐから
せかいのこころも いさめかけ
という一節が「みかぐらうた」にはあるのだが、この「助けを急ぐ」というフレーズには両手を前後に振って全力疾走するような振り付けがついている。歌がその部分にさしかかるたびに、子どもだった私の目には、親や親戚の姿がピンチになった仲間のもとに駆けつけようとしているスーパーヒーローのように映っていたものだった。
いつもわらわれ そしられて
めづらしたすけを するほどに
という一節ではまるで「自分の一族の苦難の歴史」が語られているようで、いつも楽しそうに暮らしている親や親戚も実はそんな思いをしながら苦労して生きてきた人たちだったのだな、とか、この先自分に待ち受けているのもそういう人生なのだろうな、とかいったことを、コドモなりに極めてげんしゅくな気持ちで考えさせられたことを覚えている。
やまとばかりや ないほどに
くにぐにまでも たすけゆく
という一節では、奈良県という小さな枠に収まってしまうことなく、もっと「でっかいこと」のやれるオトナになって行かなアカンちゅーことを言うてはんねやろうなー、みたいなことを考えて、一人で納得したりしていたものだ。大和以外の地域の天理教信者の子どもたちの耳にこのフレーズがどんな風に響いていたのか、またはいるのか、私は全然知らないのだけど。
何しろ、私が生まれた世界で一番最初に自分の周りに響いていたのは、そういう「歌」だったのである。
ところが。
という話が、ここから始まる。

そんな風に私たちが子どもの頃から慣れ親しんできた「おつとめ」とは別に、天理教の教会本部では「かぐらづとめ」と呼ばれる「特別なおつとめ」が行なわれているらしいということを、私は親や親戚に教えられるのではなく、中学の時に図書館から借りてきた宗教学の本を通じて初めて知らされたのである。その本に書かれていたのは、大体以下のような内容だった。
天理教本部の神殿の中心に据えられた「かんろだい」とその周囲の正方形の一角は、教祖中山みきが前生において最初の人間を産み下ろした人類発祥の「ぢば(地場)」として、何人も足を踏み入れることを許されない聖域となっている。教祖の月命日にあたる毎月26日には、教祖の直系の子孫である真柱(しんばしら)と特別に選ばれた関係者10人がこの「かんろだい」を取り囲み、神楽面をつけて生命の誕生を象徴する舞を踊る。「かぐらづとめ」と呼ばれるこの儀式は、戦争中も官憲の目をかいくぐって継続されてきた天理教の最高の秘儀であり、人間が神に変わるための儀式である。
…「何これ?」と私は思った。そこに書かれていたことは、自分の知っていた「天理教」とは全く別の宗教の話であるようにさえ思われた。「かんろだい」なら、見たことがある。ただし、「その下の地面」は見たことがない。本部の建物は、「見えないような構造」で造られているからである。そこが一番「聖なる場所」だったということなのか。だから我々シモジモの人間には、見せないような造りになっていたのか。「人間は平等だ」というのが天理教だと思っていたのに、実はその天理教から自分たちは「下等な人間」扱いされていたのだということに気づかされた感じがして、何だかとてもくやしくなった。
でもってその「見えない床下」みたいになったところでは、信者にも見せないような形で百何十年もずっと、「秘密の儀式」が行なわれていたというのだろうか。天理教って実はそんなに、オドロオドロしくてマガマガしい宗教だったのだろうか。「特別に選ばれた10人」って、どういう人たちなのだろう。その人たちは我々シモジモの人間の知らないような、どんなことを知っているのだろう。それにつけても「人間が神に変わる儀式」って、何なのだ。
天理高校出身の母親に聞いてみると、「別に秘密の儀式ちゅーわけでは、ないよ。毎月26日には全国からいろんな人が見に来てはるわ。せやけど、見えへんで。人いっぱいやし」という答えが返ってきた。
「じゃあ」と私は思った。そのマガマガしくてオドロオドロしいのを、一番前で見てみたい。
学校の休みと重なる26日までは数ヶ月を待たなければならなかったが、地元の強み。私は朝5時に本部の神殿の扉が開くのと同時に中に飛び込んで、竹で囲いがしてある真ん中の「穴」のギリギリのところまで行って場所をとり、「かぐらづとめ」が始まるまで5時間待った。母親の言った通り、時間が近づくと全国からやって来た信者の人が次々と集まりだして、3157畳もあるという本部の神殿はじきに満杯になってしまった。天理教って、スゴい宗教だったのだなと改めて思った。
「かぐらづとめ」というのは、始まってみると何ということはない。私たちがいつもやっていた「すわりづとめ」を「立ってやる」というだけの内容のものであるらしかった。踊っている人たちは確かに「面」をかぶっているのが分かったが、ほとんど見えなかった。真柱らしい人がかぶっている獅子舞みたいな大きな頭がゆらゆらしているのが辛うじて見える程度で、その下の部分は角度の関係から、全然わからない。あと、振り付けの細かい部分が「すわりづとめ」とは若干異なっていることも確認できたが、正確なところはやっぱりわからない。それにつけても、本部で演奏される「みかぐらうた」は、荘重なムードを作り出すためなのか何なのか、伸びきったテープのようにゆっくりと演奏されていて、全然心が勇んでくる感じがしなかった。
私と同じように早朝からやってきて隣に座っていた、中国地方の教会のハッピを着たおばさんは、一生に何度も見られない「かぐらづとめ」を少しでもちゃんと見たいという気持ちからか、正座の姿勢から何度も背伸びをしては「床下の穴」を覗き込んでいて、そのたびに横にいた人に袖を引っ張られていた。信者としては当然の気持ちだと思うし、私ももう少しガッツがあればどさくさに紛れて「背伸び」をしてみたい誘惑に駆られ続けていたのだが、「公開」の形をとっていてもいかんせんそれはやはり、「秘密の儀式」なのだった。「見せてもらえないのに」そこに座っている我々は、自分たちが「神に選ばれた特別な人間」ではないことを確認させられるために、そこに正座させられているようなものだった。
もはや見るべきものは見つ。そんな気持ちがしていた。天理教のことをそれ以上真面目に考える気持ちが無くなってしまったのは、その時以来のことだったように、今にしてみると思う。「秘密の儀式」なんかやっているような人たちは、それ以外の人間のことなんて「どうだっていい」と思っているに違いないのである。だったらこっちだって、真面目に相手をしてやらねばならない理由はどこにもない。
ずっと、そう思っていたのだった。

「かぐらづとめ」=「かんろだいづとめ」は、人間が助け合って生きるための真理を歌と手振りで誰もが体得できるよう、教祖中山みきが教えてくださったものである。それが本部の密室で一部の人間しか知ることのできない「秘儀」とされてきたことは、教祖の教えに反している。信仰のあるところにはどこにでも「かんろだい」が建てられるべきだし、すべての「おつとめ」はそれを囲んで輪になってつとめるのが、天理教の本来の姿である。
そんな主張のもとに、中山みきが教えた当時のままの形の「かぐらづとめ」を再現して、継承する取り組みを行なっている人たちがいることを、最近知った。天理教本部から自転車で15分ほど北に行ったところにある、「櫟本分署跡保存会」の方々である。
「大阪府奈良警察署櫟本分署」は、中山みきが89歳の時、「天皇も百姓も同じ魂」であるという主張を曲げなかったがために12日間にわたる拘留を受け、そのまま二度と起き上がれなくなるまでに体を痛めつけられた「教祖最後のご苦労」の場として知られるところで、1986年の教祖百年祭を前後して、廃屋同然になっていたところを保存会の人々が整備し、人間中山みきの在世時の姿をしのぶ記念館のような場所として、現在では運営されている。同時にこの保存会では、かつて天理教本部の修養課で「教祖伝」の講師をつとめ、2014年に亡くなった八島英雄という人を中心に、ゆがんだ形で教えられてきた中山みきの教えを「復元」するための取り組みが、進められてきた。
本部が秘密にしている「かぐらづとめ」を誰に対しても開かれたものにすることを主張しているわけだから、見る人によってはこの人たちのやっていることは「異端」なわけである。ネットを眺めてみると、ずいぶんいろいろな悪口を言われていることも目に入ってくる。だが、保存会の趣旨から考えても、そこで活動している人たちが、中山みきという人が「人間は平等である」という信念にもとづいて天皇制と対決した事実を大切にしようとしている人たちであることは、間違いないだろうと私は思った。それならば、行って話を聞いてみたい。そう考えて、先日帰省した際に、立ち寄ってみた。
中山みきが「神がかり」になったという話は、ウソである。
保存会の人は「天理教の人」であるにも関わらず、気持ちいいぐらいにそう言い切った。中山みきに「中山みきでない言葉」を喋らせた「超自然的存在」としての「神」など、どこにもいない。中山みきは「神」という「自分でないもの」に「命令」されて、「お道の教え」を語ったわけではない。中山みきは「自分の意志」で「世界を助けたい」と思い、その通りに生きた、一人の人間であり、女性だったのだ。
私が何よりも衝撃を受けたのは、その事実そのものよりも、保存会の人が「そう言い切ったこと」だった。だったら天理教というのは、宗教ではない。「中山みきという人の思想」として、伝えられるべき教えだったということになる。
それなら中山みきの説いた「神」とは、何だったのか。記紀神話に出てくる天皇家の祖先神のことでもなければ、キリスト教で説かれてきたような超越的存在のことでもない。キリスト教国の科学者もイスラム教国の科学者も等しくその「道」に従うことを自明のことと考えて探求を続けているところの、「天然自然の理」それ自体を中山みきは「神」と呼んだのである。その「天然自然の理」に照らして、人間社会に差別があることは間違っており、誰もが平等に助け合って生きなければ世界は幸福にならないという結論が明らかだったから、中山みきはそう説いた。「神が教えた」というのは、比喩である。
「神」という日本語は、中山みきが「助け一条」の生き方に身を据えた江戸時代に至るまでは実にさまざまな意味内容を包含する言葉だったが、「明治」になってから時の権力者によって「天皇」のことを指す言葉として、そして意味内容としては西洋の唯一神「God」のことを指す言葉として、定義が書き換えられた。と言うよりも、それ以外の意味内容において「神」という言葉を使おうとする人間は、暴力によって弾圧される時代が始まった。だから中山みきはその後半生においては「神」という言葉を使うのをやめており、「をや」や「月日」といった言葉に改めている。「一緒にされてはたまらない」と思わはったからなのだろうし、「神」という言葉にこだわりがあったわけでも、なかったのである。
「天然自然の理」に沿った生き方を身につけることで、人間は誰でも「人を助ける力を持った存在」に、生まれ変わることができる。言い換えるなら「神」になることができる。子どものうちは誰でも「人から助けてもらう」ことでしか生きて行けないが、「親」になった人間は誰でもその子どもの成長を助け、共に喜ぶことのできる「力」を、「自然に」身につけることができる。その「助けられる立場から助ける立場への転換」を、天理教用語では「心の成人」と呼んでいる。また仏教界においては、同じように求道者が「助けられる立場から助ける立場」へと「生まれ変わる」ことを象徴する儀式として、伝説上のインドの帝王「転輪王」の故事にちなみ、「輪王灌頂」と呼ばれるものが、昔から行なわれてきた。誰もがその「転輪王」になって生きよう、というのが中山みきのそもそもの教えだったし、「おつとめ」が「人間が神になるための儀式」であるという私が中学の時に読んだ本の記述も、その意味ではあながち間違いではなかったわけだ。もっともそれが「教団本部が特別に認めた人間」だけに「許された」儀式であるとすれば、それが意味するところは全く違ってきてしまうわけなのだが。
「吾々は人間が神にかわらうとする時代にあうたのだ」という水平社宣言の一節が、子どもの頃に祖父の膝の上で見た「おつとめ」の情景と重なってくるのを私は感じた。全国水平社が結成されたのは中山みきが亡くなってから35年後のことだったわけだが、差別からの解放ということを一人一人の生涯をかけて追求してきた故郷の先人たちの営みの中で、その思想には「つながっていたところ」もあったのかもしれないということを少し思った。
したがって、「天理王命」という「神名」を中山みきが説いたという話からして、ウソだったのである。事実彼女が生涯に文字として書き残した言葉の中で、「天理王命」という言葉は一度も使われていない。
「あしきをはろうてたすけたまえ てんりおうのみこと」に至っては、もっとウソだったのである。中山みきが説いた教えは「人間が神になって互いに助け合うこと」だったのであって、「神という絶対的存在にお願いして助けてもらうこと」ではなかった。それを教団が彼女の死後、「ご利益」を売りにして信者を集めるために大正5年になってから初めて唱え始めたのが「あしきをはろうてたすけたまえ」だったのだとのことで、中山みきの在世中には、このような「おつとめ」は一度も行われていなかったという。「おつとめ」の「一番」と「二番」では「主語」が変わっているという、子どもの頃の私が感じた違和感は、やはり「根拠のあること」だったわけだ。
中山みきの「本当の教え」がそこに記されていたのかもしれないと、私がロマンチックな憧れを感じていた「泥海古記」も、話を聞いてみたら「ニセモノ」だった。彼女が生前に「天然自然の理」を説明するための「たとえ話」として語ったことを、教祖を神格化したい人たちが様々な牽強付会を重ねて「神話」にまとめあげた作文にすぎなかったというのが、その実体だったらしかった。別にそう聞かされても、大したショックは私にはなかった。私だって別に、人間の先祖はドジョウだったといったような話を、本気で信じて聞いていたわけではない。進化論を踏まえるなら「逆の意味で」それは正しい話だったということになるのかもしれないが、そこには何も「神秘」はない。そして中山みきという人は、「神秘」を説くことにはおそらく何の関心も持っていない人だったのである。
ただ、「神」とは「天然自然の理」のことであるとした上で、その「天然自然の理」をどう受け取るかによっても、人間の生き方は変わってくる。弱肉強食の競争原理が「天然自然の理」だと思っている人間は、人種主義や優生思想にもとづくさまざまな差別を「科学」の名のもとに正当化し、その中で「勝ち残る」生き方を説くことを「正義」だと考えている。だが、中山みきが説いたのはそうした教えではない。ダーウィンの進化論が「倒し合い進化論」であるとすれば、中山みきが説いたのは「助け合い進化論」だった。「かぐらづとめ」の手ぶりの一つ一つには、そのことが誰にも理解できるように表現されている。保存会の人たちがそう説明してくれたことは、付記しておいたほうがいいように思う。
そして、そうしたいろいろな話を聞かせていただいた上で、今まで「天理教本部の秘密の儀式」としか聞かされてこなかった「かぐらづとめ」を、私は体験させてもらうことができた。「あしきをはろうて」は教祖の教えではなかったからということで、ここでは行なわれておらず、「おつとめ」は「ちょとはなし」から始まった。
高さ八尺二寸の「かんろだい」を囲んだ踊りの輪が広がったり縮まったりするさまは、そのまま脈動する生命を表現しているように感じられた。「立ちづとめ」で前に進んだり後ろに進んだりする足の運びのひとつひとつにも「意味」があったということは、実際にそこに立ってみて初めて理解できたことだった。
「いちれつすましてかんろだい」というフレーズの「すまして」というところでは、世界を平等にならすという意味を込めて両手を水平に広げる所作が入るのだが、「かんろだい」を囲んで8人でそれをやると、広げた手がつながって「輪」ができる。できた瞬間に、ビックリした。その振り付けを通して中山みきが伝えようとしたことは、確かに「輪になって」踊るのでなければ、何も分からない。
最後の「かんろだい」というフレーズの部分では、輪になって踊っている8人と、その外側で「男五分の理」「女五分の理」を表現して踊っている2名とが、それぞれ一斉に違った手ぶりをする。「ぬくみ」「すいき」「つなぎ」「つっぱり」「引き出し」「飲み食い出入り」「息吹き分け」「切る」という、人間が生きていくのに欠かせない様々な「天然自然の理」が、それぞれ補い合い助け合って調和を作り出すことで初めて生命は生命として成立できる、ということがここでは表現されている。そして一人一人の人間も、「補い合い助け合って」暮らすことを通して初めて幸せに生きることができる。そのことを「補い合い助け合って」暮らしている人間の一人一人が自覚し確認し合うための方法として、中山みきが作り出したのが「おつとめ」だったわけである。
中山みきと一度も会ったことがなかった私の曾祖母も、そこから生まれた祖母も母親も親戚の人々も、そして私自身もまた、「おつとめ」の「本当の意味」というものを何一つ知らされることがないまま、ただそれを「神さんに感謝をささげるための儀式」であると漠然と理解して、親から子へ、子から孫へと教え継ぎ、教えられてきたのだということになる。そしてその「神さん」というのがどういう存在であるのかということも、天理教の中ではその人ごとに受け取り方が全然違っている。私の母親は「神さん」とは「形も何もないもんや」というキリスト教的なイメージを私に教えてくれたものだったが、古い信者の人には「天理王命」とは「尻尾に九本の剣が生えた大龍」であるというイメージを頑なに守り続けている人もいる。そしてその一人一人が、「神さん」とは何ものなのかということも分からないまま、極めて「真面目に」その信仰生活を送ってきた。
私はそのことを「無意味なこと」だったとは思わないし、その人たちが生きてきたのが「無駄な人生」だったとはなおさら思わない。「神さん」が何ものであるかということは「おやさま」にしか分からないことだとしたうえで、誰かが誰かのことを助けたりまた助けられたりといった具体的な人間同士のつながりの中で「天理教の世界」は形作られてきたのであり、私もまたその中で生まれたのである。
けれどもその天理教を始めた中山みきという人がどういう気持ちでその教えを説いたのかという事実に初めて触れたことは、少なくとも私の人生にとって「意味のあること」だったし、それを文章にして残しておくことは世界中に広がった信者さんたちの一人一人にとっても、「意味のあること」になるに違いない。そんな気持ちで今回の記事は、書かせて頂いた。
中山みきは「世界を助ける」という「自分の意志」にもとづいて行動し、生き抜いた人だった。その生き方はやはり、今のような時代にあってこそ、見習ってゆきたいものだと、私は素直にそう思っている。

サポートしてくださいやなんて、そら自分からは言いにくいです。
