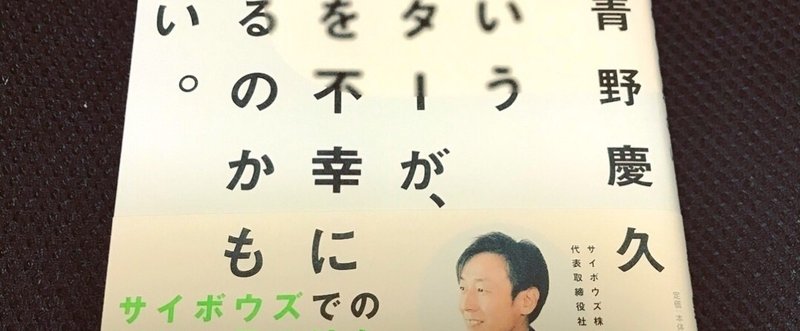
カイシャとは何か:現代の企業用具説
企業のあり方や働き方、さらには選択的夫婦別姓制の導入など、その発言が注目される経営者の一人であるサイボウズ社長の青野慶久さんが、『会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない』(PHP研究所)を上梓された。卒読しただけの状態ではあるが、ひじょうに興味深い一冊。詳細はぜひとも手にとってお読みいただきたい。
冒頭のカイシャ論(法人論)からして、まことに「然こそ!」と膝を打ちたくなる。私事にわたって恐縮ながら、私も1年生向けの基礎科目としての〈経営学〉という講義を担当することがある。そのとき、避けて通れないのが「会社とは」という点である。これは「企業とは」という議論とは、少し異なる。なぜなら「会社」というのは、基本的に法律上の概念であるから。
細かいところは措いて、ひとまず企業という存在を様態から規定するなら、企業とは何らかの価値を創造するためにさまざまな資源や活動を結びつけている〈関係態〉であるといえる。これを権利や義務、自由や責任を担いうる存在にするための法的手続が〈法人〉で、企業の場合には〈会社〉というかたちをとる、そう説明している。
青野さんは〈会社〉という存在が持つ「得体の知れなさ」に目を向けて、それをどう乗り越えるかを、この本で論じている。そのなかで企業理念が「自分は何のために働くのか」という問いに対するよりどころとして位置づけられているのは、まことにすんなりと理解できる(56ページ)。
61ページ以降では、「いいカイシャとは」という議論が成果活用の観点から展開される。ここは本書の中でも白眉。一言でいうなら売上を次期以降のために、また企業が掲げる理念の成就のために、どのように分配・投資していくのかという点の重要性が強調されている。
私が本記事のサブタイトルに「現代の企業用具説」とつけたのは、まさにこの点に拠る。企業用具説とは、ドイツの経営学者・R.-B. シュミットが提唱した考え方で、「企業は、ステイクホルダーの期待や欲望を充たすための用具・手段である」という企業観。もちろん、1960年代から1970年代にかけて提唱された学説であり、学生運動の激しさに対応するかたちで打ち出されたという側面もある。ただ、そういった時代背景はあるにせよ、企業という存在を考えるとき、この視点は脱け落ちてしまいがちである。シュミットが企業は維持されるべきという前提であるのに対して、青野さんは「協力したいと思える理念やビジョンがなくなったときには、そのカイシャは解散すべき」という主張。この点は対極のようにもみえるが、シュミットの企業用具説も裏を返せば「ステイクホルダーが、その企業に対して何も期待しなくなったとき、その企業は崩壊する」とも読める。ちなみに、シュミットは企業政策(企業の全般的な基本方針や目標方向づけ)を成果使用体系、つまり獲得した成果を次期以降に向けて、誰にどれくらい分配し、何にどれくらい投資するのかを示す方針として、企業理念をそのための基礎ないし根拠として位置づけている(R.-B. シュミット、吉田和夫監修・海道ノブチカ訳『企業経済学』第3巻「成果使用編」千倉書房)。
このあたり、さらに考えてみたい。
第2章は、そのためにどう考え、どう動くべきかに関する提唱。興味深い点は多々あるが、そのなかでも「やりたい」「やれる」「やるべき」の3つの重なりを重視するという点は、特におもしろい。言い換えれば「欲望 / 意欲」「能力 / 可能性」「意義 / 責務意識」となろう。たしかに、この3つの点が重なり合うとき、爆発的なエネルギーが発揮される。その他にも、コンフリクトの創造的解決(永続的弁証法といってもいいかも)という観点から〈交渉〉を捉え返す点や、その際のコンセプトの重要性、情報発信と共感の獲得、掛け算による新しい価値の創造など、まことにおもしろい論点が数多く提示されている。
第3章以降も、会社論・企業論として興味深い議論が続いている。また機会があれば、この本を手がかりに考察して、書いてみようと思う。
そういえば、本書にも出てくるが、青野さんは以前に伊那食品工業の塚越寛会長と『「いい会社」ってどんな会社ですか?』(日経BP社)という本で、突っ込んだ対談をしておられる。この本もすごくおもしろいので、一読をお勧めする。見解を共有できているところと、それぞれの「いい会社」観の相違がくっきりと浮き彫りになっているところがあって、スリリング。マザーハウスカレッジでも、マザーハウス副社長の山崎大祐さんとの議論のなかで、同様に一致するところと相違するところが糾い合うように展開されておもしろかった。
「企業とは何か」「会社とは何か」といった、ややもすると青臭いと言われかねなかった議論が、こうやって優れた経営者たちから打ち出されているのは、ひじょうに喜ぶべきことだと思う。経営学に携わる以上、その提唱をしっかりと受けとめて思索を深め、何らかの見解を示すべきであろう。
今日、この本と併せて、遠藤功『生きている会社、死んでいる会社』(東洋経済新報社)も購った。論点は少し異なるが、企業論としてやはり興味深い。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
