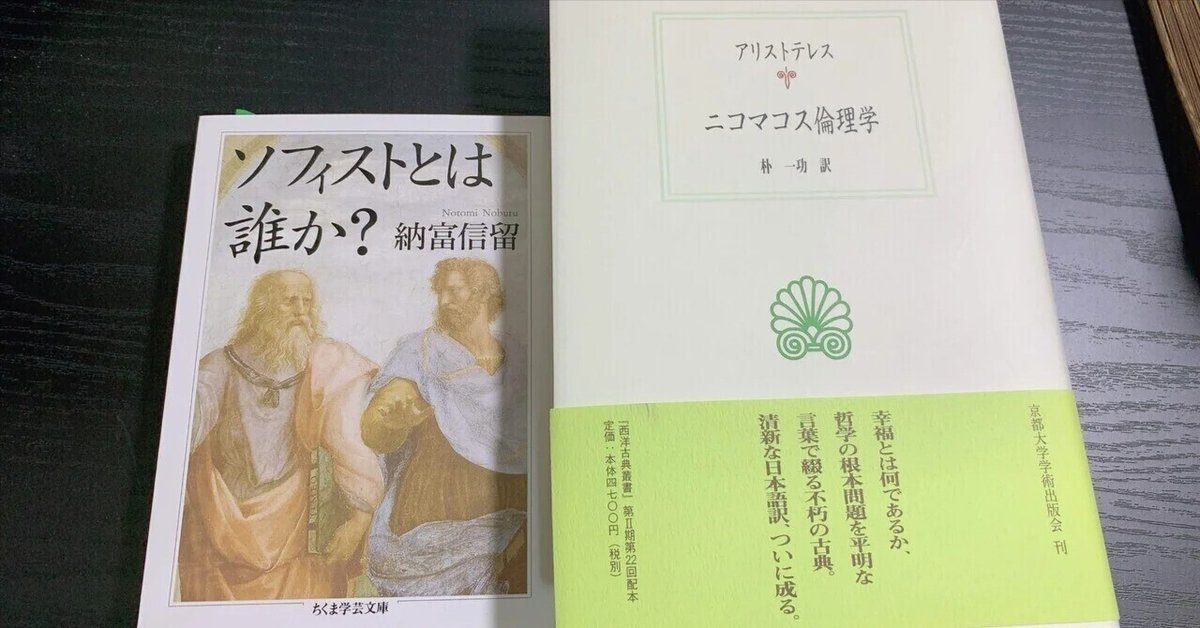
関係性のなかで定まっていく〈正義〉あるいは〈不正〉:道徳哲学の淵源として。アリストテレス『ニコマコス倫理学』をよむ(5)。
アリストテレスの『二コマコス倫理学』(朴一功訳、京都大学出版会)と納富信留『ソフィストとは誰か?』(ちくま学芸文庫)を交互に読んでいくという試みの第6回。
今回は、アリストテレス『ニコマコス倫理学』の第5巻。毎回注記してますが、巻といっても、現代的な感覚でいえば“章”に近いです。今回は、正義と不正と題された巻。前の巻では〈中庸〉が採りあげられたが、それを他者との関係性に拡張した議論とみることができそうだ。
読書会での設定文献は↑の翻訳だが、最近になって以下の文庫版の存在も知った。ここでは西洋古典叢書版を用いるが、たまに光文社古典新訳文庫版を参照することもあるかもしれない。
摘 読。
どうも読む限り、第5章までの議論と、第6章からの議論の二部構成とみたほうがよいようにも感じる。もちろん、どちらも深く関連はしている。ただ、第5章までがどちらかというと相対関係を想定した正義の議論であるのに対して、第6章からは社会や共同体、ポリスといったより広い対象が想定されている。さらに、自発的であるか非自発的であるかといったことが論じられている。この点に留意して、第5巻を読んでみよう。
正義とは
まず、ここで採りあげられている〈正義〉とは、前者が「人が“正しいこと”をおこないうる”状態”」つまり、人がそれによって正しい行為をし、かつ「正しいこと」を望むところの状態と規定される。ここで状態と呼ばれているのは、いわゆる静止的なものではなく、むしろ行為に向かう基点であり、判断基準、そういったものの融合としての姿勢に近いとみていいだろう。〈不正〉の場合は、同じように不正なことを望むところの状態として規定される。
ただ、正義にせよ不正にせよ、どちらも多義的であり、しかもその異義の境界は明瞭ではないというところに、一つの課題がある。そこで、アリストテレスは「不正な人」というのが、どういう意味合いでいわれるのかという点から考察を始める。これに関しては、(1)法を破る者、(2)より多く取る人=公正ではない人という2つの点で整理する。ここから、「正しい人」は(1)法を守る人、(2)公正な人とひとまず規定できる。そして、さらにこれを「人」ではなく、「こと」にも展開する。この「人」と「こと」を分けるという視点は、きわめて重要だろう。
さて、ここで「法を守る/破る」という点に関して、法というものの位置づけをアリストテレスは確認している(訳書200頁, 1129b_17)。それによれば、「法はすべての人々にとって共通の利益をめざすか、あるいは最も優れた人々にとっての利益をめざすか、あるいは支配的地域にあるような人々、さらには何か他にもそれに類する条件を備えた人々の利益をめざす」と指摘し、「社会共同体にとっての幸福ないしは幸福の諸部分をつくり出したり、それらを保護する性質」のものを「正しいこと」とする。その際にも、無条件な「完全な徳」なのではなく、あくまでも「他者との関係における」完全な徳であるという。
かくして、正義とは「完全な徳」を自分自身に関してだけでなく、他者に対しても使用することができるときに成り立つ。アリストテレスは、それが困難なことであることも指摘する。
そのうえで、具体的に正義がどのようなかたちで現れるのかの議論に移る。ここで、アリストテレスは全体的な不正だけでなく、部分的な不正というものがあるという。むしろ、全体的な不正に対応する「無条件に善き人」をつくるひとりひとりの人間としての教育に関しては、別の問題として切り離される。これは、どのような種類の「市民」であるのかということもまた別問題である。ここで議論されるのは、部分的な正義にかかわることがらである。
この部分的正義は、配分にかかわる正義(配分的正義)と是正にかかわる正義(是正的正義/矯正的正義)に分けられる。さらに、是正にかかわる正義は自発的なものと非自発的なものに分けることができる。
交換をめぐる正義
配分的正義とは、交換をめぐる等しさにかかわっている。これは価値にもかかわる。この点に関して、比例関係にもとづいて、それぞれが等しく善きものを手に入れることができる状態をさしている。一方、是正的正義とは、自発的な交渉にせよ、非自発的な交渉にせよ、そこで生じた利得と損失を是正することである。それを担うのが、裁判官なのである。
ここで、アリストテレスは応報という概念を登場させる。ピュタゴラス派は無条件の応報を正しいものとしたが、アリストテレスはそうはみていない。その際に浮上してくるのが「比例関係にもとづく」応報である。実際、交換においては、それぞれ異なる者がやり取りされる。アリストテレスが医者と農夫の関係を挙げているのがそれである。あるいは、家職人、靴職人、家、靴の関係性からも考察している。交換においては等価性が重視されることはもちろんだが、一方の者の作品が他方の者の作品よりも価値がある(認められる)ということはありうる。そこで、その比例関係を測ることが重要になるわけで、貨幣はそのために出現してきた。
この比例関係を測る基準として、アリストテレスは〈必要〉を挙げる。ちなみに、貨幣とは人々の取り決めによって、必要の代替物になったものであり、それは自然にではなく、法によっている。さて、例えば農夫と靴職人との関係で考えた場合、農夫の靴職人に対する関係が、靴職人の作品の農夫の作品に対する関係とちょうど同じものになるとき、そこには応報関係が成立する。ただ、その際に交換を済ませた時点で、それぞれのものを比例関係の図式に導いてはならず、あくまでもそれぞれが自分のものを持っているときでなければならない。そういう状態において、双方はたがいに等しいものとなり、共同関係を結ぶことにになる。それは、求められている等しさが、その時に初めて双方のあいだに実現されるからである。かくして、交換に際しては〈必要〉が前提となり、交換を可能にする尺度として貨幣が欠かせないということになる。そして、それが正しいか不正かをわけるのが、比例関係なのである。
社会的な正しさ
アリストテレスが探究しているのは、無条件的な正しさばかりではなく、社会的な正しさである。社会的な正しさとは、互いに自足することを目的にしながら、自由かつ、平等な者 ——その等しさが、比例関係にもとづくものであれ、算術的なものであれ―— として生活を共にする人たちにおいて認められるものである。この点を欠いていると、人間相互の関係における「社会的な正しさ」というものはなく、単に類似性にもとづくある種の正しさが認められるに過ぎなくなる。法というのも、この関係を自分たちで律するためのものである。だからこそ、アリストテレスは人間が支配するのではなく、道理(ロゴス)にもとづいて支配をおこなうべきだとする。それゆえ、支配者というのは「正しいこと」の守護者であり、また「等しいもの」の守護者でもある。
ここにおいて、アリストテレスが支配者のありように対して、きわめて冷静な視点を持っていることには十分に留意すべきであろう。ここでの「正しいこと」というのも、支配者が独善的に決めていいものではなく、あくまでも正義は「他者の善」であり、そう考えると、支配者が自分自身に「一般的に善いもの」をより多く自分に割り当てるということはせず、他人のために働くものだからである。ここは、きわめて重要な指摘だろう。
これに続く論述で、主人の正しさや父親の正しさは、これと似ているけれども同じではないとする。これは自分が所有しているもの=奴隷や、独立するまでの子どもは、自分自身の部分のようなものであるから、それを害するような選択をする人はいないというのが、その理由である。ただ、夫と妻との関係においては、「家政における正しさ」という別の基準が存在する。
何をもって、不正行為とされるのか
さて、この社会的な正しさには、自然的なものと法的なもの*がある。前者が普遍性を持つのに対して、後者は人為的に設定されるものである。ここでアリストテレスは前者を重視する。ただ、いずれにしても「不正なこと」がひとたびなされたなら、それは「不正行為」となる。ここで留意しなければならないのは、この「不正行為」が自発的に、つまり選択にもとづいておこなわれた場合、その人は「不正な人」とされるが、そうではない場合、つまり非自発的に行われた場合は、まだ「不正行為」とまで呼んでいいかどうか判断が難しい事象も存在する。
* この自然的なものと法的なものという区分は、いわゆる自然法と実定法という考え方につながるものとみてよさそうである。個人的には、以下の文献から山縣は影響を受けている。
これに関して、アリストテレスは共同関係における3つの種類の加害に言及している。一つ目は、人が思っていた相手に、思っていたことを、思っていた手段で、思っていた結果になるようにおこなうことができなかったとき、そうした場合に、もっぱら無知によってなされたものを「過失」と呼ぶ。二つ目にあげられるのは、不条理な仕方で加害が生じる場合である。この加害は「不運な事態」と称される。そして、三つめが「不正行為」である。これは、行為者が行為の是非を知っていながら、あらかじめ熟慮せずになされた加害をさす。ただ、ここでは意図的な選択によるものは含まれておらず、人間に必然的に生じる激情やその他の情念によっておこなわれる限りの加害が、ここでの対象である。
それに対して、行為が選択にもとづく場合、その行為者は不正な人であり、邪悪な人である。このような場合の不正は断罪される。
では、非自発的な場合の加害、不正行為はどうなるのか。これは無知や不運な事態の場合は赦されうるが、情念にもとづく場合は、やはり赦されないとアリストテレスは言う。
品位。法律からこぼれ落ちる事態を酌み上げること。
そもそも、人間は自発的に不正を自身に受けたいとは考えない。ただ、配分する人が自分の行為を知りながら、かつ自発的に相手に自分よりも多くのものを割り当てているとき、そのような人は自分で自分に不正な行為をしていることになる。これこそ、「適度を守る人たち」がしていることであって、「品位ある人」と呼ばれる。ただ、その際にも留意しておかなければならないのは、より少なく取ったからといって、むしろ評判や、無条件に美しいものといった、別の種類の善きものをより多く取るかもしれない点である。
この品位というのは、正義と無条件に同じものであるとは見えないが、異なっているわけでもない。ここで、アリストテレスは「品位がある」ということと「適正なこと」を対応させているが、この「適正なこと」というのは「合法的な正しさ」を是正するものであると指摘する。つまり、法というのは普遍性を持つものとして制定されているが、あるものごとに関しては、普遍的な仕方では事態を正しく語ることができない場合がある。つまり、法によってだけでは「正しさ」を示しえないとき、この「適正なこと」が前面に押し出される。つまり、法律の一般性に起因する誤りよりも善いというのが、「適正なこと」の本性である。
こうみると、「品位ある人」というのは、さまざまな状況において「適正なこと」を選択し、かつ行いうる人なのである。これは、「正しさに固執する人」ではなく、たとえほうが自分の助けになる場合であっても、自分のものをより少なく取るところの「控えめな人」である。こうした性格の「状態」を「品位」と呼ぶわけである。
不正を自らしないこと、不正を身に受けないようにすること。そして、重要な付加。
かくして、アリストテレスは、自発的に不正なことを選択して行為することを厳しく難じる。基本的に、人間は自分自身に不正な行為をすることは考えられないが、その場合もその人にはある種の不名誉が帰せられるがゆえに、その人に何らかの不利益が降りかかるとする。
アリストテレスは自分の身に他者から不正がなされて、何らかの損失を身に受けた場合は、それをし返すことを不正とは見なしていない。当然、自分が自発的に不正を他者になそうとした場合は、自発的に不正な行為を身に受けるということも想定されるわけである。
そもそも、不正な行為を身に受けることも、それ自体としては低劣だとアリストテレスは言う。もちろん、自発的に他者に対して不正をもたらそうとするのに比べれば、その程度は低いわけだが。
さて、「主人的なもの」や「家政的なもの」の場合、つまり自分に属する諸部分のあいだにおいても正しさというのはある。アリストテレスは、これを社会的な正しさと類似性を持っているが、別のものとして捉えている。なぜなら、これらの場合、異なる人間がいるが、いわゆる独立した市民としては位置づけられていないからである。ここは、これ以上に言及されていないが、経営学的には興味深いところである。
私 見。
ひじょうに興味深い巻であるが、内容がかなり広範である。ただ、いわゆる道徳哲学とのつながりを考えると、きわめて現代的にも重要な巻といっていいだろう。私も、企業行動論の講義のなかで、交換を論じる際にアリストテレスに言及するのは、このあたりだ。
この巻を読んでいると、倫理というのが、もちろん善悪を対象とはするのだけれども、それが人間生活のきわめて広い部分にかかわってくるということをあらためて思い知らされる。しかも、アリストテレスは第4巻での〈中庸〉をめぐる議論と同様に、ここでも関係性のなかで〈正義〉〈不正〉が定まるのだということを、さまざまな側面から論じようとしている。
もちろん、それは相対主義的な姿勢を採るということではない。むしろ、アリストテレスのなかに、どのような状態が〈正義〉であるのかという考えはそれなりに明確なものとしてあるのだろう。しかし、それを絶対視せず、さまざまな状況や関係性のなかで、何が正しいのか、正しくないのか、その境界が動くことを捉えようとするのが、アリストテレスの思索の根幹にあるといえるように思う。
そして、この品位の問題。これ、まさにドラッカーがいったintegrity(高潔性/統合性)とも重なり合う。アントレプレナーシップの問題を考えるうえでも、欠かせない論点となるだろう。
ここの巻は、ほんとうにいろんな思索を触発してくれる。原理主義的な自由放埓主義でもなく、原理主義的な全体的計画主義/社会主義でもない可能性を示してくれている。そして、その根底には、他者などとの関係性における道徳的自律性としての“徳”をいかにして、個々人が内在的なものとして(動的に)保つのかという問いがある。その意味で、ここでの議論はおそらくWell-beingを論じていくうえで不可欠なものとなってくるに違いない。
ただ、それゆえに別の視点も浮かび上がってきそうである。
例えば、「主人的なもの」や「家政的なもの」には、社会的な正しさがそのまま当てはまるわけではないというあたりは、アリストテレスの社会観も含めて、いわゆる組織体(Betrieb)の内部と外部との関係性を考えさせる。アリストテレスの社会の捉え方が現代と懸け離れているからといって、それを批判しても全く意味がない。ただ、当時との社会のありようの相違を踏まえたうえで、現代の課題を考える手がかりとしなければならないことはいうまでもない。
さらに、品位をめぐる議論も、それ自体としてきわめて穏当であり、難じるところは取り立ててないのだが、社会構造的に「損失」を受け続けている人がいるとき、それを告発するためにどうすればいいのかという点については、微温的であるとみる人もいるかもしれない。aestheticな論点というのは、まさにこの点に対する告発という面を含んでいるといえよう。これはポパーがプラトンに対して論難した唯美主義を逆手に取る議論であるともいえるし、最近翻訳が出たランシエールの『文学の政治』の議論とも繋がってくるかもしれない。このあたりは、もう少し時間をおいて考えてみたい。
ほんとにいろいろと思索が散乱して、大変である(笑)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
