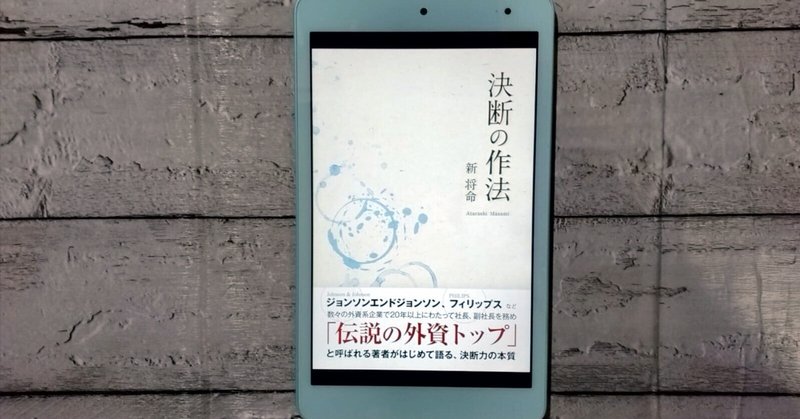
【読書感想文】経営者でない自分でも成果を上げるためのヒントを数多く得ることができた『決断の作法』
成果を出すためには、成果につながるアクションの実践が必要です。私自身、自分が期待するような成果を出せない時が少なくありません。これまで私は、思ったような成果をなかなか出せない原因として、「成果のために何をすべきか?が分かっていなかった」と考えていたのですが、つい最近それが誤解ではないか?と感じるようになりました。
本書「決断の作法」を読んだことが、それに気づいたきっかけです。本書の筆者である新将命さんは、J&Jやフィリップスをはじめとする世界的に名高い企業6社に身を置いてうち3社で経営者を務めた、プ新さんは、企業について「人間と違いとても死亡率が高く、誕生後、5年以内に約8割の会社がこの世から姿を消してしまう存在」とお話します。本書を読んでまず私が実感したのは、企業を存続させていくことの大変さでした。
企業が永く存続させるためのカギとして、新さんは「強い組織構築」と「方向性の明確化」の2つを挙げています。しかし、実際に会社が倒産してしまう場合の多くは、組織の構築と方向性の明確化が「上手く実行できなかった」からではありません。「実行に移せない」というのが新さんによる企業が生き残れない要因なのだそうです。
経営者は企業を舵取りするので、トップの下す決断は会社の決断でもあります。一方で、企業組織は一人ひとり異なる人間が集う集団でもあるため、組織には大小様々な意見や思惑が存在します。故に経営者は、これら多くの意見を意思決定の参考にするにしても、組織の方向性を決める時は必ず最後は経営者自身の責任で決断することが求められるのだと新さんは言います。先ほど「上手く実行に移せない」というのは、この決断すべき時に経営者が最後の一歩を踏み出せず、決断できない状態です。決断できないことが会社が生き残れないことにつながるため、会社を成長させる上で「決断力」は不可欠なのだそうです。そして新さんは、経営者にとって不足しているのもまた「決断力」なのだと、ある意味厳しいお話をされます。
私は経営者ではありません。しかし、新さんのお話しする「決断力」の話を聞き、この「決断力」こそが、先ほど自分が期待するような成果を出せなかった原因の一つであるのではないだろうか?と思いました。「決断力」は自分自身の課題でもあると感じています。
「成果のために何をすべきか?」はとりあえず分かっていたのかもしれません。しかし、「すべきことをやる」という決断をなかなかすることができず、結果行動量が落ちてしまったのではないか?の反省もあるように思います。
本書は自分にとって厳しい1冊となりました。しかし同時に本書は経営者でない自分でも成果を上げるためのヒントを多く得ることの出来た1冊でもあります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
