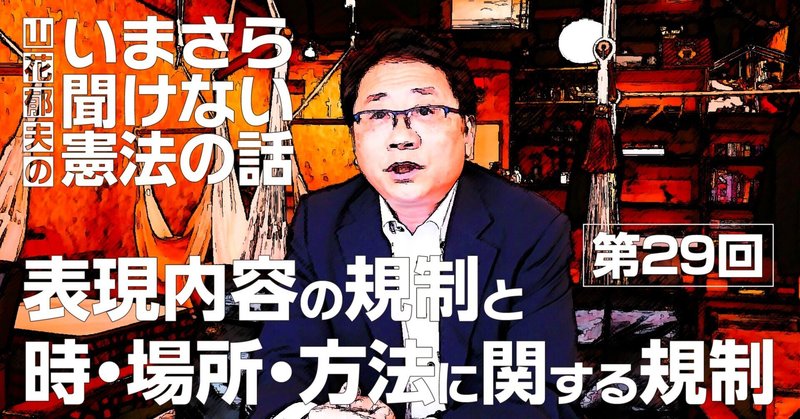
【第29回】表現内容の規制と時・場所・方法に関する規制 #山花郁夫のいまさら聞けない憲法の話
表現内容そのものについての規制でない場合
わいせつの表現について、内容ではなく、売り方の規制であればあり得るという話をしてきましたが、これは、表現の自由一般に言いうる考え方です。
表現内容の規制と、内容に中立的な規制に分けて考えて、内容の規制については厳格に違憲性の審査を行うけれども、内容中立的な規制、つまり、時、場所、方法などについての規制の場合には、そこまで厳格に考えなくてもよい、とする考え方です。
たとえば、政府を批判する内容の発言を禁止することは表現の自由に反することは誰しもが理解できると思いますが、真夜中に拡声器でマンションに向かって大音量で演説することまで禁止してはいけないとは考えないと思います。これは特に政府批判という内容について規制したものではなく、音楽であれ、なんであれ、大きな音を立てて迷惑をかけてはいけないという内容に中立的な規制です。ほかに、美観や風致の破壊を防止する目的で屋外広告を禁止することなども、表現の内容にかかわらず、つまり政府に賛成する意見であれ、反対する意見であれ、あるいは商業的なものであれ、規制されるという意味で、内容に中立的な規制です。
これもとらわれの聴衆?
屋外広告と言えば、衆議院の憲法審査会で海外調査に行った時のことです。リトアニアで、ビルなどに大きな看板での広告は禁止されているが、それは、通行人が見たくなくても見ざるを得ない状態に置かれるからだ、という説明を伺いました。とらわれの聴衆に似た考え方が東欧にもあるんだなぁ、と思ったことを思い出します。
より制限できでない他の選びうる手段(LRA)
一般的には、時・場所・方法に関する規制は、内容の規制に比べれば、直接に表現の自由を弾圧しているわけではありません。しかし、人権一般に言えることですが、その制限は必要最小限度のものでなければならないはずです。特に優越的地位にある表現の自由については、より制限的でない他の選びうる手段がある場合には、憲法違反とする考え方が学説上主張されています。これは、アメリカの連邦裁判所で発達してきた理論で、Less Restrictive Alternativeの略でLRAの法理とか、LRAの基準と呼ばれています。
「学説上」という限定を付けたのは、残念ながら日本の最高裁判所ではこの基準に従って違憲判決が出た例はまだありません。ただ、集会の自由との関係で、敵対的聴衆の法理であるとか、敵意ある聴衆の法理と呼ばれる考え方に基づいて、公共施設の不許可処分を違法とした判例があります。これは、より制限的でない他の選びうる手段があることの一つのカテゴリーとも考えられます。
具体例については、次回検討してみたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
