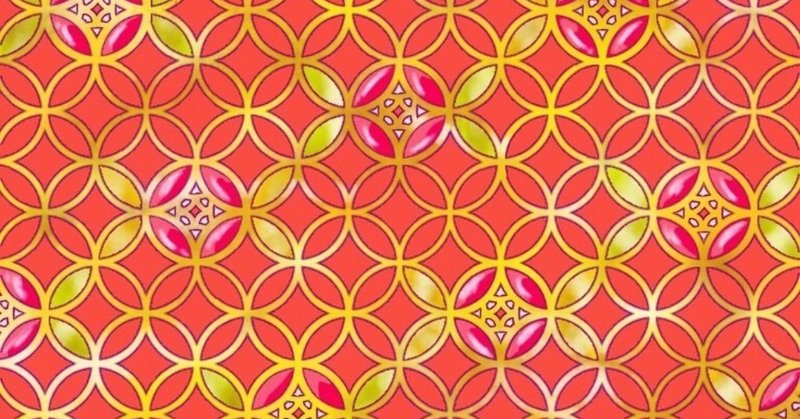
雛さまの船に乗る
昼時の八階ラウンジは食堂になる。
十二時、さりげなく、ひたすらさりげなく斥候が静かに席をたつ。わたしも焦る心を悟られないようにエレベーター前を通過し、非常階段で三階から八階へ。これは自分に課した運動ノルマだ。
いつものメンバー&なぜか係長の五人で窓際の席を確保した。とはいうものの、隣のビルの窓はブラインドが降りているし、亀のように首を伸ばさないと空は見えないしで眺めは悪い。けれど今日はいい天気だなとか、曇ってるんだとか、雨が降ってるねとか、外の様子を感じるだけでもほっとできる。午後のためにささやかなリフレッシュ。
弊社ビルが出来た当時はきっと世の中を睥睨できる眺めだっただろう。過ぎていった時間は名古屋駅前という利便だけを残してくれた。耐震工事も済んで安全もバッチリ、建て替え話は皆無である。
弁当持参はわたしだけ。用心しないと卵焼きがさらわれる。それを見越して余分に作ったりしない。きりがない、ということを学ぶことができた。
弁当を開く前にスマホを確認する。着信いろいろあり。
「おベント、開けてあげようか」
親切そうな声に無言で首を振り、返信に精を出す。
さてさて、かあさんのメールは何かな。
「お雛さまの御殿が崩壊した。犯行はお隣のミケによるものである。御殿を仕上げて台所でコーヒーを飲んでいた隙を狙った模様(怒り顔の絵文字)」
着信は本日二月二十二日午前十一時四三分。画像が三つ添付されている。
一つめは緋毛氈が敷かれた三段の雛壇の、一番上に組み上げられた誇らしげな御殿の画像。
二つめの画像は見事にバラバラに崩壊して雛壇に散らばる御殿の残骸と、二段目に座って左前脚をなめている実家の隣の猫のミケ。よく見たら、御殿の屋根は割れて柱も折れている。御殿の階段も原型を留めていない。雛壇は緋毛氈が片肌脱ぎの状態だ。
ミケよ、いったいおまえは何をした。昭和二〇年代の年代物だぞ。
そして三つめ、かあさんが「見本」と呼ぶ古い白黒の完成した雛壇の写真の画像。
続く二通目のメール。
「昭和は遠く、やはり平成は終わるのだ!」
わたしは二分ほど考えて、「お疲れさまでした」と返信した。
ほっとしてテーブルを見ると、お弁当箱はとっくに開けられて卵焼きが消えていた。
御殿つきの雛人形は、六六年前母が誕生したときに曽祖母が買ったもの。写真でしか知らないひいばあちゃん。
かあさんが言うには、「中学生のときに御殿の組み方を教わって、高校生になったらお雛様は登場しなくなってたよ」なのである。
そういうところって、かあさんとばあちゃんはよく似ている。年中行事にあまり興味がないのだ。アニバーサリーも同じで、結婚記念日はとうさんが指摘するまでかあさんは忘れていたりする。
そういうところって、きっとわたしも似てんだろうな。
そういうことに抜かりなし手抜きなしで丁寧なおにいちゃんを見習おうにも、わたしは三日坊主にさえなれないのだ。
おにいちゃんの節句飾りは、じいちゃんが買った「藤堂高虎の兜」だ。
「じいちゃんの在所は伊勢だから藤堂高虎なのだ」とにいちゃんは言う。
藤堂高虎の兜を買った理由を、誰もじいちゃんから聞いてないと思う……たぶん。
どうして藤堂高虎だったんだろう? という疑問が湧いてきたのは、じいちゃんが亡くなってからだ。
にいちゃんの高虎様の兜は、床の間に収まるようにトンボの羽が短めなのだった。
姪っ子のお雛様は殿様と姫様のカップルで、丸っこくてひたすらかわいい。孫の雛かざりに関して、我が家のジジババに出番はない。
御殿つき雛飾りはばあちゃんが気まぐれに何年かに一度は、「フル装備」だったり、お人形だけだったり、殿様と姫様だけだったりだけれど、ちゃんと二月の風にあてて、三月三日の夜には片付けていたらしい。
そうか! かあさんはお雛さまを平成最後の二月の風にあててあげよう、殊勝にもそう思ったんだ。それならゾロ目で二月二十二日が最適だと、何の根拠もなく思ったに違いない。そして二月二十二日はニャンニャンニャンの猫の日なのだから、ミケを責めることはできない。
雛飾りはばあちゃんの家にあった。わたしにもばあちゃんちでお雛さまを見た記憶がぼんやりあるような気がする。
「お雛さまを飾ったから見においでん」
そんなふうにばあちゃんから連絡があったんだろう。ばあちゃんちでわたしとお雛さまが一緒に写っている最後に撮った写真は小学五年生のときのものだ、とかあさんは言う。
「あんたったら、大きくなったらお雛さんを見に行かなくなっちゃったもんねぇ」
じいちゃんが亡くなり、十年たってばあちゃんが亡くなった。
「お雛さまはお姉ちゃんが面倒みてね」
固辞する母VS強引に譲る叔母という場面に、兄もわたしも従姉弟たちも立ち会ったが、従姉弟たちも「お雛さまはうちに貰おうよ」とはひと言も言わなかった。
わたしも「お雛さまを貰おうよ」と言わなかった。もしわたしに娘がいたら、姪っ子のお雛様のような雛飾りを選ぶだろう。
「雛御殿はほんとに豪華で綺麗だったんだから」と母は言う。古い白黒の見本写真からも「豪華で綺麗」を感じられるが、わたしの記憶には古さだけが残ってしまった。
ちゃんと見たかったな、ちゃんと見ておけばよかったな、と今更なことを思う。母に「お雛さまを飾ろう」と提案したことはなかったのに。
なんだか、すごく、もったいないことをした。
御殿を修復するのかな。費用はどうするんだろう。近いうちに実家へ顔を出して訊いてみよう。修復費用が高かったら、少しならわたしも出せると思う。
五日後、かあさんから御殿なし雛さまフルメンバーの雛飾りの画像つきメールが届いた。
「お寺さんが御殿の供養を引き受けてくれたから、お願いしちゃった」
供養の費用は諭吉さま一名。妥当なのかどうかはわからない。
お雛さまはかあさんのものだから、とうさんは我関せずを貫いたことだろう。
わたしは五分ほど考えて、「お疲れさまでした」と返信した。
年度末の気忙しさに加えて、平成最後という騒めきのなかで三月が進んでいく。
桜が咲いたらかあさんとお花見に行こうかな。
などと考えながら帰宅すると、玄関の上がり端に古ぼけたダンボール箱が置いてあった。箱と蓋をひと目見れば、曽祖母が母に贈ったときのダンボール箱だとわかる。ボロいとしか言いようがないダンボールだ。
いわゆるダンボール色は褪せて白っぽくうっすら灰色をしている。雨漏りなのか、もしかしたらネズミのおしっこの跡なのか茶色の染みが点々と広がり、蓋も箱も爪が当たると簡単に破れてしまうほど劣化している。なので角や端は出来損ないのフリルのようにヒラヒラしている。そして蓋も箱も劣化した紙が張り付き、ダンボールの畝があばら骨のようだ。
箱の上には、「雛さんたちはちゃんと二月の風に当てたからね。あとはよろしく。母」と書かれた桜の花びらが舞う一筆箋に、わたしの大事な大事な一目惚れしたバカラの梟が文鎮がわりに載っていた。
ひゃっ、と声にならない悲鳴をあげて、まずは梟を定位置に置いた。
桜の一筆箋を手に取ると、その下にには猫の引っかき傷としか思えない跡があった。
かあさんは昭和二〇年代後半のダンボール箱をそのまま使っていたのだ。小さめの柳行李とか、桐箱とか新しいダンボール箱に入れ替えたりせずに、そのままボロのまま使っていた。
箱を開けると、一体一体薄紙で頭部をくるみ、胴も薄紙で丁寧にくるんだ人形たちが、ちゃんと座っていたり、斜めになったりして収まっている。
薄紙にくるんだ弓、矢、刀、太鼓、笛、扇、銚子などの持ち物が、人形たちの隙間に埋まっている。桜と橘、ぼんぼりも薄紙にくるまっていた。底の緋色はきっとあの毛氈だ。
斜めになっている人形を手に取ると、五人囃子の一体で額にネズミの噛み跡を見つけてしまった。
きみが齧られたのはいつのことなのかな?
わたしは蓋をして、仕舞い場所を考えた。
これだけ箱が古いと、ダンボールといえどおいそれと新しくできない。行李にしろ桐箱にしろ買って雛たちを収めたとして、古い箱を捨てられるだろうか。母と同じようにお寺さんに箱の供養をお願いしたくなってしまう。
母が間髪を入れずに御殿をお寺さんへ持っていった気持ちがわかる。
間を置けば修理修繕が頭をよぎる。けれど費用を考えると二の足を踏む。壊れたままにしておけば罪悪感の虜になる。
もしかしたらかあさん、ミケよよくやった、と肩の荷を一つ下ろした気持ちになったのかもしれない。ほとんどお雛様を飾らなかったことへの罪悪感をミケが壊してくれた。
それならばと、「あとはよろしく」と雛たちをわたしの所へ連れてきた。1DKのわたしの住まいの、いったいどこに飾れと言うんだろう。
来年は二月の風を忘れてはならない……のだろうか。金屏風は買うか作るか作ってもらうかしなければいけないだろう。人形だけなら四段が必要な飾り段はどうしよう。
「あー、もう……」
お腹すいた。確かプリンがあったはず。まずは手っ取り早く空きっ腹を慰めよう。
冷蔵庫を開けるとケーキの箱が入っていた。箱の上には「おつかれさま」と書かれた桜の一筆箋がセロテープでとめてある。
箱の中には小さめのイチゴのケーキ、ワンホール。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
