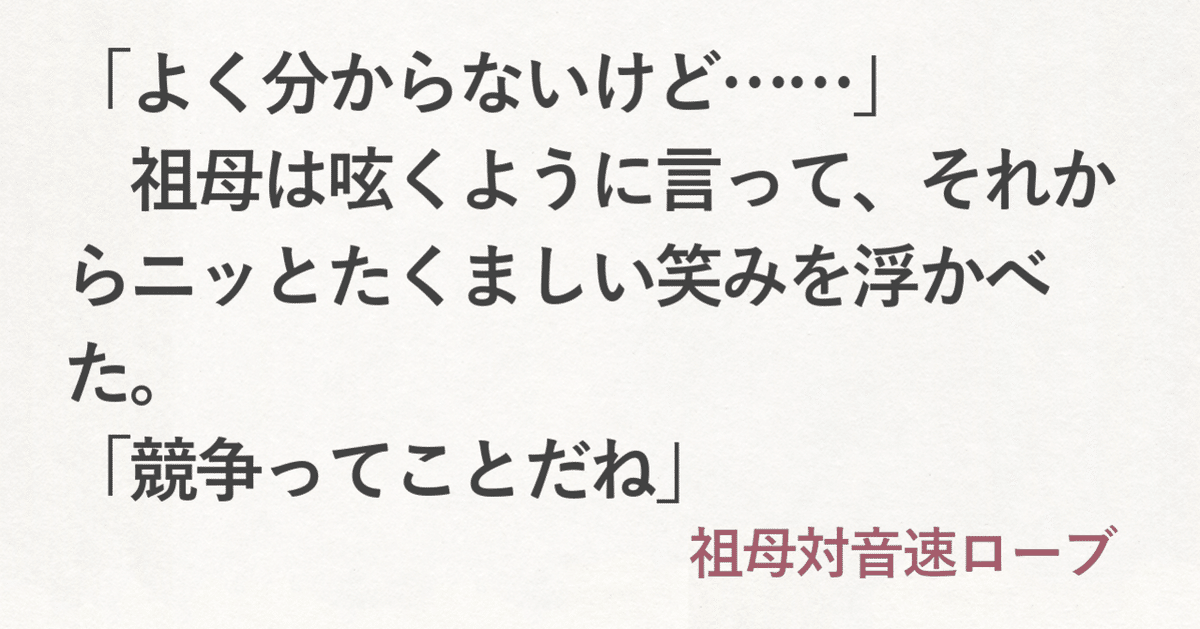
祖母対音速ローブ
私が中学生だった頃、「音速ローブ」という怪談が周囲で流行ったことがあった。
早朝ジョギングをしていると、フード付きのローブを身にまとい、肩に青白いタオルを掛けた人影が、いつの間にか後ろを走っている。フードの下の顔は陰影に覆われて見えず、呼吸や衣擦れ、地面を踏む音も聞こえず、いかにも奇妙な様相だという。
人影はぴたりと貼りつくようについてくる。ペースを速めても振り切ることはできず、緩めても追い越されはしない。そうしてしばらくついてきた後、突然人影は甲高い金切り声を上げ、タオルを投げつけてきたと思うと、一気に速度を上げて追い抜き始める。
ひとたび追い抜かれると、投げられたタオルが首に巻きつき、人影との距離が離れるほどギュウギュウと絞まる。ついていけず離れ過ぎれば末路は一つ。生き延びるためには、人影が足を止めるまで後を追い続けるほかはない。しかし走れば走るほど人影は速度を増す。必死に食らいついたとしても、やがては人間の限界を超えて追い切れなくなってしまう。
「『音速ローブ』に出会ったらもう終わり。足が止まれば息の根も止まる」
声を低めた友人の語り口を聞き、当時の私はぶるぶると肩を震わせた。寒がりだったからだ。「怖っ」と顔をしかめながら私は使い捨てカイロを両手で揉んだ。
あの頃私たちは、そういう類の怪談や都市伝説に興味津々だった。怪談の載ったウェブサイトを毎日のように巡り、怖い噂話が集まるSNSコミュニティに入り浸った。そうして仕入れたとっておきの話を、互いに共有し合うのが何よりの楽しみだった。語りに熱が入り過ぎて「話より顔が怖い」と言われたことも何度もあった。
音速ローブの話を聞いた数日後、私は普段なら寝こけている早朝にベッドから出た。正確には、目覚ましのアラームをのろのろした手つきで止め、「ぐもう」とか「うごう」とか意味のない呻き声を天井に向かって繰り返した後、掛け布団と毛布をぐるぐる巻きにして壁際に押しやり、故障寸前のリクライニングシートのようにぎこちない動作で身を起こして、ようやくベッドから出た。
目的は音速ローブだった。怪談通りの出来事が起こるかどうか試そうと、私は厚手のジャージを着てこっそり家を抜け出した。噂を信じていたというよりは、話のタネになるかもという程度の思いつきだったけれど、頭の片隅で「もしかしたら」とも思っていた。私は自転車を引いていき、いざとなったらそれで逃げようと考えていた。
私はひんやりとした朝の空気に身を震わせながら歩いた。街路は薄っすらと明るく、人の気配はなく静かだった。何となく心細くなって自転車のベルをチリンと鳴らしてみると、応えるようにどこかでスズメがチュリンと鳴いた。
「どうしたの? こんな早くに」
不意に背後から声をかけられて、私はギャアッと悲鳴を上げた。
慌てて振り返ってみると、困ったような微笑を浮かべた祖母が立っていた。淡い色の運動着を着た姿を見て、私は祖母が早朝のジョギングを日課としていることを思い出した。
「ごめんね、驚かせちゃったね」
「ううん、こっちこそ……」
言葉を続けようとして、私は再びギャアッと叫んだ。
祖母の更に後方から、フード付きのローブを身にまとい、肩に青白いタオルを掛けた人影がゆっくりと近づいてきていた。
「ばあちゃん、う、後ろに」
「ああ、あの人。さっきから後をついてきてね。妙な人だねえ。足音がちっともしないし」
祖母の言う通り、人影は何の音も発していなかった。フードの下は陰のようになって中身が見えず、肩の上で揺れる青白いタオルだけが、不気味なほどはっきりと目に焼き付くようだった。
話に聞いた通りの特徴。あれは音速ローブだ、と私は確信した。
人影が近づくにつれ、全身が無意識のうちにぶるぶると震え出した。今度こそ恐怖による震えだった。その時ちょうど鋭い寒風が吹き、寒さによる震えも上乗せされ、私はかつてない振幅と振動数を発揮した。
設定を間違ったマッサージチェアのようになっている間に、人影との距離は段々と縮まっていった。人影は緩やかな足取りで祖母の横側まで来て、そこでぴたりと動きを止めた。
「ええと。何かご用ですか?」
穏やかな調子で言って、祖母は人影に一歩近づいた。私は反射的に「ばあちゃん、駄目!」と静止しようとしたけれど、舌がもつれて「バルトロメ!」と言ってしまった。
人影は祖母の質問にも私の言い間違いにも反応を示さなかった。身じろぎせず立っていたと思うと、すっと肩のタオルに手を伸ばした。その動作を見て、私の頭から血の気が引いた。
タオルを高々と振り上げ、人影はギャアッと甲高い金切り声を発した。鋭く禍々しいその声に私は震え上がった。ただ、思い返してみると、私の悲鳴も似たようなものだった気もする。
私は祖母の体を引き戻そうと腕を伸ばしたけれど、間に合わなかった。人影の投げた青白いタオルは、祖母の首元へ吸いつくように巻きついた。
ぽかんと立ち尽くす祖母と青ざめた私をよそに、人影は再び動き出した。それまでの緩慢な動作とは打って変わって、矢のように鋭く素早い走りだった。
「ばあちゃん、走って!」
私は人影の背中を指さし、声の限りに言った。
「あいつを追いかけて、離されないで!」
喚く私を祖母は訝しげに見つめた。その間にもゆらゆらと、祖母の首元でタオルがうごめいていた。私は気が焦って惑乱し、腕をぶんぶん振り回して「ゴー! ゴー!」と甲高い声で繰り返した。
「よく分からないけど……」
祖母は呟くように言って、それからニッとたくましい笑みを浮かべた。
「競争ってことだね」
瞬間、祖母の体が弾けるように動いた。
力強く足を動かし腕を振り、祖母は猛然とアスファルトの街路を駆けていた。均整と迫力を備えたフォームで速度を生み出し、先を行く人影との距離をすぐさま縮めていった。後に残ったのは虚しく腕を空転させる私だけだった。
祖母が本気で走る姿を、私はその時初めて目にした。昔陸上競技をやっていたとは聞いていたし、ある程度のトレーニングを続けていることも知っていたけれど、想像を遙かに超えて祖母は速かった。回し疲れた腕をだらりと下ろしながら、私は離れていく背中に驚嘆の眼差しを向けた。
私は引いてきた自転車に飛び乗った。前方の祖母は人影に追いつき、肩を並べて激しく競り合っていた。私の脚力ではついていけそうもないハイペースだった。でも自転車ならいける、と私はペダルを漕ぎ始めた。日頃ほとんど乗っていなかったため操縦がおぼつかず、車体は道路の脇に積まれたゴミ袋の山へ向かって勢いよく発進した。
冷や汗を流しながら方向を修正し、私は人影と競り合いを続ける祖母を追った。一旦走り出せば操縦も安定して、それなりの速度で順調に進んでいった。冷たい空気が体にまとわりついて寒く、私は何度もベクショイとくしゃみをしながら、懸命にペダルを踏む足を動かした。
「嘘でしょ……」
息を荒げながら私は呻いた。
私はぷにぷにの筋肉を駆使してペダルを漕いだ。道が下り坂に差しかかったのも相まって、自転車はかなりの速度に達していた。それにも関わらず、祖母との距離は一向に縮まらなかった。
「嘘でしょ!」
嘘ではなかった。祖母はローブ姿の人影と並び、物凄い速さで疾走していた。勢いが落ちる様子もなく、両者は抜きつ抜かれつのデッドヒートをいつまでも続けていた。
勢いを落としたのは私だけだった。足がペダルを回しているのか、ペダルが足を回しているのか、もはや判然としない状態で進み続けたけれど、下り坂が終わる頃には体力が底を尽き、私は弱々しい手つきでブレーキを握った。
ひとたび自転車を止めると、二つの背中は急速に遠ざかっていった。真っ直ぐ伸びた道の先へ、あるいは地平の彼方までも、際限なく走り続けていくかのようだった。
私はサドルにまたがったまま呆然とした気分で立ち尽くした。
聞いた話の通り、音速ローブという恐ろしい怪異は存在した。けれど私はそれよりも、祖母が見せたとんでもない脚力に衝撃を受け、怪談がどうのという思考は頭から吹き飛んでいた。
やがて祖母も人影も見えなくなった。奇妙な夢の中にいる心地でぼうっと街路の先を眺めていると、遙か向こうの方から、空気が破裂するような音が聞こえた気がした。
家族が起き出した頃になって祖母は家に帰ってきた。
ボロボロになった靴について、他の家族には「気分が乗って走り過ぎた」と説明していたけれど、私にだけは「勝ったよ」と嬉しげに教えてくれた。手には音速ローブから投げつけられた青白いタオルを握っていた。
祖母の話によると、しばらく走り続けて曲がり角にたどり着いた時、突然人影が立ち止まったらしい。人影は祖母に向かって満足げに頷きかけ、日の光に溶けるように消えていった。後には青白いタオルだけが残ったという。
「いい勝負だった。またやりたいね」
弾んだ声で言う祖母を前にして、私は安堵と呆れの混じった泣き笑いを浮かべるほかなかった。
それから数日経った後、私は学校で妙な噂を耳にした。
早朝ジョギングをしていると、淡い色の運動着を身にまとった老婆に競争を持ちかけられる。うかつに勝負を受けてしまうと、とてつもない速度を発揮する老婆の脚力に大差をつけられ、快足自慢もしょんぼり気落ちしてしまうという。
怪談ではない気がするけれど、この話は「音速ローブ」にちなんで「音速老婆」と呼ばれていた。「ダジャレじゃん」と友人は呆れていた。
家に帰ってから祖母に「音速老婆」のことを話すと、祖母は「なるほどねえ」と神妙な顔つきをした。
「その手があったね」
祖母はニッとたくましい笑みを浮かべた。
それからしばらくの間、私の家の近所を中心に「音速老婆」の目撃談が相次いだ。
サポートありがたいです。嬉しくて破顔します。
