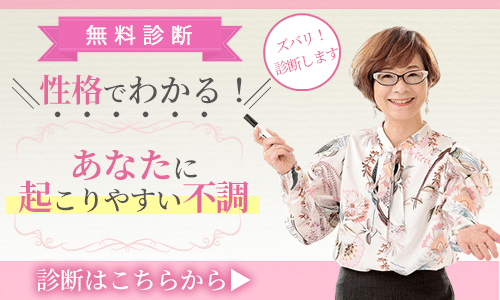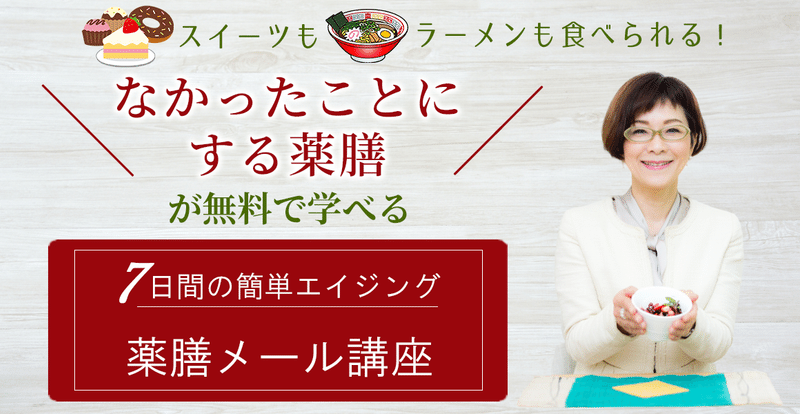法律を守って講座を開催するのは、受講してくださる方を大切にするということ
8月1日に薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等)が改正され、課徴金制度が追加されました。
ワクチン接種が進んできたとは言え、またしても感染拡大が起きている状況下、「免疫力アップ」や「殺菌力」などを謳ったウイルス予防商品や食品に関する注意喚起と優良誤認表示を理由とした行政処分も行われて来ました。
今回、8月1日からは、該当する商品売り上げの4.5%を課徴金として納入することが追加になりました。それが世間で今、言われている「薬機法改定」です。
「私は商品は売ってないから大丈夫!」と思ったら間違いです。
薬膳講座やアロマ講座の募集のために、SNSやホームぺージなどで発信していることは、全て広告になるからです。
薬機法には、第66条に誇大広告の禁止という条項が含まれています。
1.何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2.医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
「何人も」とあるように、商品を製造したり販売していなくても、掲載している広告が消費者に効能、性能を間違って認識させてはいけないというものです。
広告は出していないと思うかもしれませんが、SNSやブログを使って宣伝して募集していれば、それが立派な広告です。
時々、「バレなければ大丈夫」と思って続けている人もいます。
けど、なぜここまで法律を厳しく改定して行くのかを考えたら見えて来るものがあります。
ここでは、講師として活動する上で法律はなぜあるのか?を考えてみます。
消費者が安全で安心して商品を選べることを目的としている
薬機法の目的は以下の通りです。
・保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止
・指定薬物の規制
・医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進
私達講師に直接関係するのは、人の健康に係る物事に対して、危害の発生や拡大が起こらないようにすること。
つまり、「〇〇のためにはこれを飲んでおけば予防できる」というものを信じて飲み続けたために、医療機関にかかることなく取り返しのつかない病気になってしまうのを防止するということ。
人の健康と命にかかわることなので慎重になるのは当然ですよね。
効果効能が言える食品は「機能性表示食品」
薬機法に抵触することなく効果・効能を言える食品は消費者庁管轄の「機能性表示食品」というもの。
消費者が正しい選択ができるよう安全性や科学的なエビデンスをそろえることなどで、一定の効果効能をうたうことを認める制度です。
申請して認められれば「機能性表示食品」として言える効果・効能もあるのです。
ここでは、薬機法のことを掘り下げるのではなく、薬機法の改定はあくまでも自分の活動を見直すきっかけにして欲しくて取り上げました。
薬機法に関わるのは薬膳や漢方だけでなく、私が以前携っていたアロマテラピーにも関係します。
アロマテラピーの勉強をしていた時、関連法規という単元で薬機法についても含まれていました。その他の関連する法律についても一番気をつけなければならない部分は学びました。表現の仕方なども。
自分の事業に関わる法律を知っておいた方が良い
これから、講師として活動したい人、すでに始めたけれど法律のことは考えたことがなかったと言う人、この機会に法律についても考えてみてください。
薬機法だけでなく、『健康増進法』『景品表示法」など関連する法規があります。
そして、食品を扱うのであれば『食品衛生法』『食品表示法』、お弁当やお惣菜等として販売するなら、営業許可が必要です。
営業許可を取り、食品衛生責任者資格(主催は公益社団法人日本食品衛生協会)を持っていないとなりません。栄養士や調理師はわざわざ取らなくても大丈夫。
自宅のキッチンで作ったものを、販売したりお弁当として出すのは法律違反になる場合が多いです。
なぜ、こんなに法律、法律というのかと私のことを嫌な人と思うかもしれません。でも、主婦から起業した人には特に「知らなかった。」で済まないことがあるという認識を持って欲しいのです。
受講してくださる方を大切に思っているか
最初に戻りますが、なぜ法律はあるのか考えたら、根本はこれではないでしょうか?
『受講してくださる方を大切に思っているか?』
薬機法に違反する内容と言えば、誤解を与えて隠れている病気を見つけられず重症化したり手遅れになってしまうなどになっていないか?ということ。
医師ではない人間が、病気の診断をしては医師法違反です。
診断は国家資格を持った医師だけができること。
〇〇は癌に効くとか××を食べると妊娠できるという、まるで治療をすることができるような表現は薬機法違反になりますし。
それを信じた人が、医療機関にかかることなく手遅れになってしまうリスクを回避するためにあります。
ランチ付きセミナー・講座で自宅で作ったお弁当やお惣菜を出すのもどうでしょう?
特にこの暑い時期に食中毒を考えたらできることでしょうか?
家族がなんともないから大丈夫というのと、お金をいただいて仕事として提供するのとは全く違います。
受講してくださる方を大切に思っていたら、法律の網の目をくぐることを考えるより、一度ご自身の関わる法律を挙げて、それぞれについて調べてみてください。
講座やセミナーの主催者が「大丈夫!それを気にする人は来ないから。」と言うから断れないと言っているのを聞いたことがあります。
女子の世界にあるあるで、受講される方の中には、「本当は気になるけど言い出せない。」と言う人もいるかもしれません。
それに、趣味でやっているのではなく事業者なら、法律を守って事業を継続することは不可欠でしょう。
自分の考え、信念でどうするのかは判断してください。
法律は、自分では「そんなのどうでもいい」とか「自分にとっては不都合」だとしても知らなかったでは済まされないものです。
車の免許を持っていなくても運転技能があれば、免許証は不要でしょうか?
人の命と直接かかわることだからこそ、誰でも勝手に運転の練習をするのではなく国から決められた教習所で規定時間の教習を受け、交通法規を学び、試験に合格して初めて運転ができるのと同じです。
守らなければならない法律はチェックして、受講してくださる方を一番に考えたら「大丈夫これくらい!」「みんながやっているから。」はできなくなるはずです。
まとめ
薬機法の改定を契機に、個人で講師をしている人も一度自分の事業に関わる法律を調べてみると良いです。
開業届を出さずにお金をいただいて講座やセミナーをしているから関係ないと思っているとしたら、講座を受講される方にリスクを負わせることになります。
法は守らなければならないもので、知らなかったでは済まされません。
健康や命に係わることなら、抜け道を探すより受講される方を最優先に、やるべきことを考えましょう。
性格からわかる、起こりやすい不調とおすすめ食材を無料でお知らせします。
下のバナーからお答えください。
なかったことにする薬膳が学べる7日間の無料メール講座を配信中です。下のバナーをクリックしてお申込みください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?