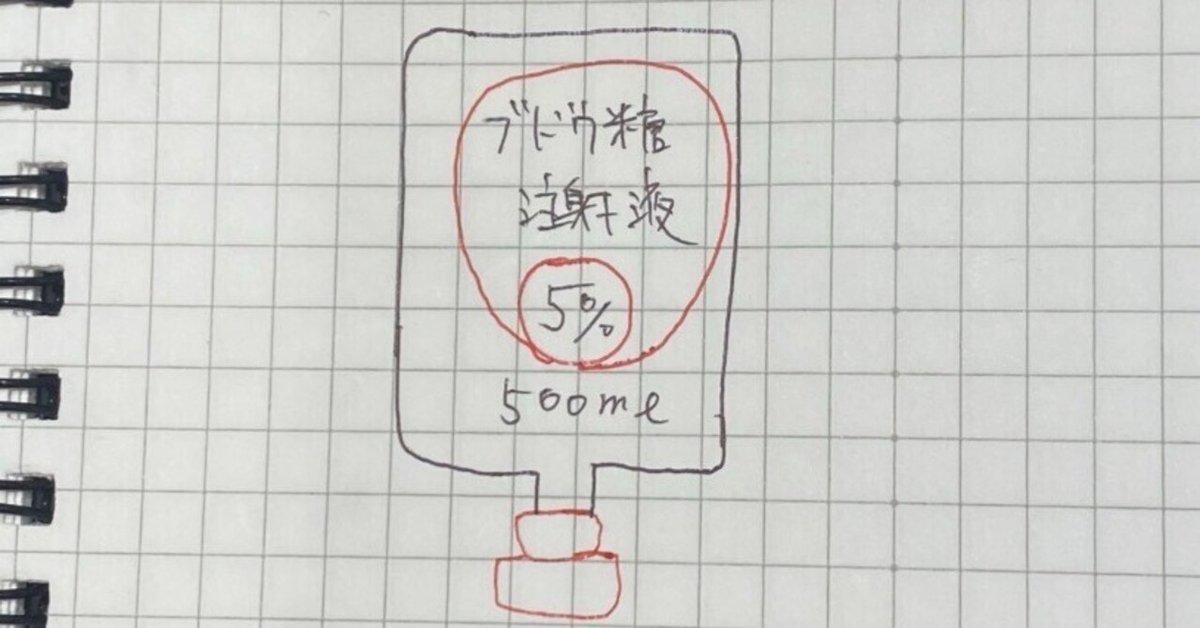
ブドウ糖液は何故自由水になるのか?
日局で採用されている生理食塩液と5%ブドウ糖液
これら2つの輸液はどちらも血漿浸透圧 約285mOsm/Lと同等の浸透圧である
それなのに5%ブドウ糖液が細胞内液を補う自由水として使われるのは何故か?
例えば、
維持輸液として使われてる1-4号液は、生食と5%ブドウ糖液を一定の
割合で混合した製剤です。
この製剤は生食に対してブドウ糖液の割合が高くなるにつれて4号液に近づき、
細胞内液への補充がしやすい輸液となっていきます。
この理由についてもやはり、ブドウ糖液が自由水として浸透圧の低い性質を持つ
ためであると説明されます。
浸透圧は生食と同じなのに、ブドウ糖液は何故自由水となりうるのでしょうか?
インスリンぱわー
実は、ブドウ糖は血中に入るとインスリンによって細胞内に取り込まれてほぼ
真水になるのです。
なので、点滴した直後はある程度の浸透圧を保つようですが、そのあと直ぐに
自由水になって浸透圧はほぼ0になります。
インスリンの即効性と代謝速度すごいですね。
ちなみに、元から浸透圧0の蒸留水を直接点滴してはいけません。
これは血中の赤血球が存在するためです。
点滴投与すると、直後の血管内で赤血球の細胞膜内外での張度に急激な変化が
起こり、赤血球内に自由水が入り込んで膨張して溶血を起こします。
なので、糖尿病性ケトアシドーシスで遭遇する高血糖+高Na血症が原因の
細胞内脱水を生じる例では、
蒸留水と生食を1:1で混和したハーフ生食なるものが溶血を起こさないように
投与されます。
そう考えると、5%ブドウ糖液は等張液なので溶血を起こさず、細胞内液補充のため自由水として使うにはとても有用な輸液であることがわかりますね。
ちなみに私は5%ブドウ糖といえば250mlを真っ先に思い浮かべます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
