
【押尾信インタビュー】「さっと掬った出汁のほうがうまいんですよ」
インタビュー企画「街場のクリエイターたち。」のお時間です。第3回のクリエイターさんは、押尾信さんです!
クリエイター:"小説家" 押尾信

文学フリマやnoteにて、小説執筆を中心に活動。プロの小説家を目指して、精力的に新人賞の公募に挑戦されている方です。
生活感のある静かな筆致で、人生の意味について考えさせてくれる押尾信さん。執筆のスタンス、小説をかきはじめたきっかけ、noteの更新などについて深掘りしてみました!
(インタビューは2月の下旬、都内某所のレストランで行われました)

イントロダクション
押尾:僕、初めてですよ。インタビューとか受けるの。
やひろ:基本的にはじめての人に対してやる、っていうコンセプトでやってるんで、大丈夫ですよ。
押尾:なんですかそれ。宝探しみたいな感じですか?
やひろ:いや、宝探しというわけではないです。こうやって人と会うのが結構好きで、誰彼かまわず会って話するんですけど、なんかオーディエンスひとりだけで聞くのもったいないなと思って。その瞬間、自分しか聞いてないから。録音とかして、公開してもいいんですけど、まあ文字の方があとで編集したりできるんで。人って、同じことを3回ぐらい言ってたりするんですよね(笑)。
押尾:今日は、よろしくお願いします。
やひろ:こちらこそ、よろしくお願いします。
基本的にマイペースな村上春樹
押尾:最近、小説読んでくれた人が感想を言いたい、みたいなことを言ってくれた人がいて、二人でお茶することになったんですよね。それで、小説の感想の話とかしだしたんですけど、5分ぐらいで感想タイムが終わってしまって(笑)。
累計で二時間ぐらい話してたんですけど、小説の感想とは関係ない話ばっかりしてました。雑談として、離婚調停の話とか子どもの話とかしてくれたんですけど、話してるうちに、そっちの方がなんか面白くなっちゃって。
やひろ:確かに、そっちの話のが面白いかもしれないですね。っていうか、その話って、押尾さんの作品に出てきそうな感じで。
押尾:だから、その人も、ネタに使ってくれる前提で、むちゃくちゃ情報提供してくれたんですよね。なんか、ドロっとしたところとかも。
やひろ:それ、めっちゃいいじゃないですか。そういう人間関係も大事ですよね。そもそも、僕って押尾さんとは何で知り合ったんでしたっけ? 文フリ(*文学フリマ。小説やエッセイなどの同人即売会)の前の日にTwitterでフォローしたとか、そんな感じでしたっけ?
押尾:多分やひろさんがなんかのタイミングで僕のnoteにスキをしてくれたんじゃなかったですかね。僕はスキの数がすごい少ないので、一個一個がすごく貴重で。
見知らぬ人にスキされたんで、「誰、誰?」みたいになって、調べたら、いろんなことをされている人だったんで興味もって、それでフォローした、とかじゃないですかね。だいたい、知らない人でスキしてくれる人っていうと、たいがい商売っ気のある人が多くて……。
やひろ:でも僕、文フリの当日、押尾さんのブースを意識してましたよ。意識してて、時間あったら行こうみたいな感じで、隙を伺ってました。そうこうしてたら、僕のブースまで来てくれたんで、その時にちょっと会話して。で、後で買いに行きますよって言って、遊びに行った感じです。
押尾:すごいふわっとした出会いでしたね……。
やひろ:ちゃんと押尾さんのnote読んでますからね(笑)。レッチリ(*レッド・ホット・チリ・ペッパーズ。海外のロックバンド)の紹介とかも読んでます。これわかる人にはわかるけど、聞いたことない人に一切伝わらんやろうな〜とか思いながら見てます(笑)。
押尾:そうなんですよ。楽曲レビューにしても、歌詞とかいうよりは楽器のマニアックな部分とかをピックアップしたりしてるんで。あれは、「伝えたい」というよりも、何も書いてないという状況にモヤモヤして、「何でもいいから書こう」っていう苦し紛れで書いてる記事です。
やひろ:レッチリの解説で、「わかるわかる」って思うところもあるんですよ。僕もそういうとこあるんで。でもちょっと、刺さる層が狭すぎる感はありますよね。
でも、実はあれを読んでる時に、この人、村上春樹が好きなのかなっていう感じがしまして(笑)。何でかって言うと、村上春樹って読者が知っていようが、知っていまいが、小説の本文で突然音楽の説明とか始まったりするじゃないですか。
押尾:始まる始まる(笑)。レコードの話とかね……。
やひろ:あれにちょっと近いものを感じて。なんか、突然説明が始まる、みたいな。
押尾:なるほど。僕もなんですけど、多分、根本の性格がマイペースなんですよね。相手のリアクションとか、ニーズとかを放棄して、突然ただただ自分の言いたいこと言い続けるという。
やひろ:そういう角度で村上春樹批評するの、なんか新鮮ですね(笑)。確かに言われてみればそうかも。うんちくがはじまった瞬間、読者おいてけぼりですもんね。
押尾:誰も聞いてないのに、急にワーグナーのレコードの話とか何楽章の何分のところがどうのとか。
やひろ:多分、あれを読んで「じゃあ、ワーグナー聞いてみるか」って思う人って、そんなにいないと思うですよね。みんな読み飛ばしてるんじゃないかな。
押尾:ワーグナー出てきたと思ったら、次の展開でまた別の作曲家とかが出てきますからね。全部チェックしきれへんやろって言う。なんとなくおしゃれな雰囲気が出るツールにすぎないというか。
やひろ:僕、村上春樹好きだったんですけど、最近は全然ですからね……。何か考えてるように見せて実は何も考えてないんじゃないか、っていうのに気づいてしまったというか……。
押尾:人が悩んでる時って、一歩が前に踏み出せなくて、グルグル思考が巡ってるような状態だと思うんですけど、ただ悩んでるだけで、別に前に進んでるわけじゃないっていう。
村上春樹の小説も、そんな感じだと思うんですよね。自分が悩んでいるときに読んだら、ある意味慰めになる気がするんですけど、10代の時みたいな、とりとめのない悩み方って今はそんなにしないので。
やひろ:僕が一番、村上春樹読んでたのは大学1年ぐらいの時ですね。それまで小説は好きで書いてたんですけど、あんまり読むほうには関心がなくて、もっぱら書くことに専念していたんですね。
それで、大学入ってから村上春樹を読み始めたんですけど、苦痛なく読めるからこれすごいな、と思って。今になって振り返ってみると、村上春樹の小説って読み飛ばしても成立する小説なんですよね。
理解できなくてもとりあえず読めてしまうというところが、当時の僕には刺さったっていうか。実は低カロリーで読めるんですけど、こんなに長い小説を読んだと言う達成感とか満足感とかがあって。
押尾:ちょっと頭良くなった、みたいな。
やひろ:そう、そんな感じ。そういう需要を満たしてるんじゃないかなと。
押尾:めっちゃおしゃれなところ行って帰ってきた人みたいになってますね(笑)。おしゃれな私かっこいい、みたいな。
やひろ:インスタ映えですよ、村上春樹は。今日のキーワードきましたね、これ(笑)。押尾さんの文章を読んで、この人絶対村上春樹好きやろなとか思ってたんですけど、Twitterのプロフィールの好きなもの列挙してあるところに村上春樹って書いてなかったんで、そこが疑問だったんですよ。もしかしたら、「かつて好きだったパターン」なんじゃないかな、と。
押尾:ご明察。まさにその通りですね。
やひろ:いや僕もそうなんですよね。さっき抽象的に言った、「何か通じるものが」っていうのは、そういうところでもあるんですよ。
押尾:村上春樹の登場人物でめっちゃそれ言いますよね。何かしら通じ合うものがあるとかなんとか。ヒロインがよく言うやつです。
やひろ:村上春樹の世界観が始まってた? 既に。
押尾:影響の残像が(笑)。昔は好きだったんですけど、今はもう全然ですね。「騎士団長殺し」とか、「1Q84」とか、買ったんですけど、展開の遅さとか、ストーリーのパターンとか、ぱっと読んだ感触でしかないですけど、今までと一緒じゃねっていう。もう読んでて、もどかしくて。
やひろ:騎士団長殺し、確かにやばかったですね。
押尾:読みました?
やひろ:読みましたよ。
押尾:最後まで読めましたか?
やひろ:読みましたよ、僕。
押尾:がんばりましたね。どう思いました?
やひろ:これ、かなり読み飛ばしても、いけるなと思いましたね(笑)。そう思って、さささーって読んだら、いけたんですよね。
押尾:そんなに噛み締めて読んだわけではない、と?
やひろ:全然噛み締めてないですね(笑)。
押尾:僕は、噛み締めないと無理なんですよ、文章って。

noteってどうやって書いてますか?
やひろ:今、押尾さん、年齢いくつなんですか?
押尾:28です。今年で29ですね。
やひろ:僕今32で、今年の夏で33なんですけど。4つ離れてるのかな。
押尾:4つ離れてるから、仕事内容とかも全然違いますよね。やひろさんの仕事って、何かディレクターの感じなんですけど。
やひろ:ディレクターじゃないですよ。もっと泥臭いですよ。僕、仕事のことを抽象的には書くけど、具体的なことは何も書かないんですよね。
押尾:そうそう、そうなんですよね。絶対教えてくれないんですよ。でもそれが逆に読みたくなるところだったりもして。
やひろ:仕事の話自体はめっちゃ書くのに、内容の話は全然しないっていう。
押尾:それを貫き通してますよね。どういう記事が書きたいんですか?
やひろ:結構、押尾さん的な感じで、日記的な感じがほんとはいいんですけどね。ただ、僕、プライベートの事はあまり書かないんで。
押尾:朝何食べたとか、散歩したとか、全然ないですもんね。やひろさんのブログを読むのが僕の朝のルーティンになってますよ。朝起きて歯を磨きながらやひろさんのブログを読んでます。眠気まなこで。
やひろ:まぁ、毎日更新されますからね。
押尾:朝になったら絶対更新されてますから(笑)。
やひろ:全部10分ぐらいで書いてるんですけどね。今、僕、ブログって完全音声入力なんですよ。ただ、音声入力だと漢字の誤変換とか結構あって。手直しにむしろ時間かかってる感じしますね。6、7分で本文入力して、6分ぐらいで直してる感じです。
押尾:まぁ、それでも、10分ちょいでできちゃうんですね。
やひろ:できるんですけど、手の負担が劇的に減ったんですよね。押尾さん、腱鞘炎になったってどっかに書いてなかったですか? 僕、基本的に仕事でもずっとキーボード叩いてるんで、仕事でもずっと書いてるのに趣味でも使ってたらほんとに指がもたないと思って。
音声入力に切り替えたら、スピードはそんな劇的には速くないんですけど、指の負担が減ったんで音声入力は手放せないですね。もう仕事も音声入力でやりたいぐらいですよ。
押尾:ブースみたいなとこ入って、真顔でやったりしてね(笑)。それやったら、人として何かを失いそうですよね(笑)。まだ手でやってる方が「やってる感」出ますけど、音声入力やともう何やってるかわからなくなりそうですけど。
やひろ:音声入力、慣れるまで2週間ぐらいかかりましたね。慣れたらもうスイスイなんですけど。何か、使ってる脳の領域が違う気がするんですよね。
押尾:キーボードで手を使うことによって、発想が生まれやすいみたいなものってあるじゃないですか。
やひろ:声は声で別の発想を引き起こすような感じもしますけどね。今こうして話してる会話も、文字数にしたら結構すごいと思うんですよね。インタビューとか、文字起こしすると結構凄いですよ。この内容で1万文字? みたいな。
押尾:この会話の薄さでこの量、みたいな。
やひろ:1万文字をひねり出すのがいかに難しいか、ということをわかっている我々としてはね(笑)。
押尾:文章だったら、持ち時間って無限じゃないですか。普通の会話って将棋の待ち時間にみたいに自分の持ち時間存在してて、その自分の持ち時間の数秒のうちにある程度、面白みのあること言わないといけない、みたいな。
やひろ:そう思うと格ゲーみたいですね、会話って。音声入力のいいところってもうひとつあって、基本的にノンストップなんですよねね。ひたすら前に進んでいくっていうか、前のところに戻ったりは基本的にしないんで。そこが何か、緊張感あって早く書ける感じがしますね。
押尾:文章書くときとかって「結論をここにもってこよう」みたいなのをイメージして書くんですか?
やひろ:全然ないですよ。
押尾:なんとなくやっていくうちに結論が見えてきたみたいな感じですか。
やひろ:実は、「たくさん書くコツ」がそれなんですよ。何か書いて、最初考えた結論と全然違う結論になったな、っていうときに、じゃあもともと考えていたやつ明日また書こうって、量産できるんで(笑)。
押尾:ずるい!(笑)
やひろ:で、次の日の記事で、今日話せなかったことをまた話そう、って言って連鎖的に繋がっていくっていう、ね。そういう感じでやってるんで、基本的にネタ切れとかは起きないですよね。常に、今日うまいこと言えなかったから明日に回そう、ってなるだけなんで。
押尾:なんか、いろいろ書いていくうちにいろんな可能性を思いついちゃったりするんでしょうね。でもブログの記事って基本的にひとつの結論しか到達できないから、それが次に繋がっていく、と。あらためて、ずるいですね、それ。
やひろ:僕、創作全般がそんな感じですよ。小説に関してもそういうところあるんで。今回できなかったことを次やろう、みたいな。それが結局、次回作の意欲に繋がるわけじゃないですか。
押尾:でも、なんかやひろさんの要領が良すぎる感はありますね。音声入力しながら、結論とかは考えてなくて、しゃべってるうちに別のテーマ思いつく、って。それでいてその日はその日でちゃんと完結できて、明日のネタにも困らないと言う。もっと苦しんで書いてくださいよ(笑)。
やひろ:苦しみは確かにちょっと足りないかもしれないですけどね。
押尾:ブログとか小説とか見てますけど、苦しんでそうなところまだ見たことないんですよ。就活の時点で、潰されない会社を選んだとかなんとか、成熟した考え方してて。
やひろ:よく読んでますね。
押尾:その考え方で就活できるのすごいなと思って。そんな視点で就活したことないですよ。全部落ちましたからね。要領いいって、普段から言われるでしょ。
やひろ:もうどっちがどっちにインタビューしてるか分かんないですけど(笑)。

いつから小説書いてるんですか?
やひろ:押尾さん、小説はいつから書いてるんですか。
押尾:18歳の頃からですかね。
やひろ:そんなはっきり言えるんですか。神宮球場で野球見てる時とかだったりします?。
押尾:それ村上春樹じゃないですか(笑)。小説書き始めの話ですよね……。僕、毎週、この話してる気がする。飲み会とかあると、話せって言われたりするんですよね。人生であと57回ぐらい語りそうな気がする。
やひろ:もう鉄板ネタじゃないですか。
押尾:小説を書き始めたのが大学の時なんですよね。入ったサークルが軽音系のサークルで、バンド組んでライブをしよう、みたいな感じでした。でも、その軽音サークルが、すごい体育会系のサークルで、ステージとかを自分たちで組み立てるんですよ。
頭の上に機材とかステージのパーツを持ち上げて、ひたすら倉庫とステージを行き来するんですけど、すれ違うときに全力で挨拶とかしなきゃいけないんですよね(笑)。昭和かよ、みたいな。
やひろ:軽音部感が全くないんですが……。
押尾:それがめっちゃストレスで。ギターはまあまあ弾ける方だったんで、そこに対してのストレスは割と少なかったんですけど、こんなとこでギター弾いてもどうにかなるもんでもないし、ギターも嫌いになっちゃったんですよね。で、じゃあ何すんだみたいなことになって、お金もなかったし、小説書こう、って思って。
やひろ:その瞬間にひらめいちゃった。
押尾:音楽やってると、とにかくお金がかかるんですよね。エフェクター買ったりとか、弦を張り替えたりとか、支出にキリがないんですよね。小説はもう完璧にタダだし、究極のエコだな、って思って。サークルでのストレスと、集団生活でのストレスが頂点に達した中で、小説やったらひとりで全部できるから、なんて素晴らしいんだろうと思って。
やひろ:一人で創作する自由を得た、と(笑)。でもそこからやりだしてよく続きましたね。やっぱ根本的に向いてたんですかね。
押尾:割とちっちゃい時に作文とか得意なタイプだったんですよね。すごい気合い入れて書いてるタイプだったというか。
やひろ:あー、いるいる、そういう子。
押尾:めちゃめちゃ得意だったというよりは、苦じゃなかった、という感じなんですけど。そんな今につながるほど当時からすごかったわけでは無いですけどね。
やひろ:よく言われるのが、小説を書きたいっていう人は世の中に腐るほどいるらしいんですよ。でも実際に書く人ってほんの一握りで、かつそれを最後まで書き上げるやつってほんとにいないらしいんですよね。その比率ってえげつないぐらい低いらしくて。
さらにそれを新人賞に出すやつなんてほぼゼロで、何回も新人賞出すやつなんてほんとに皆無に等しいらしいんですよ。でもそこまでは、僕たちやってるわけじゃないですか。
押尾:まぁ、全部一次選考で落ちてますけどね。まぁ、でも、それだけやってきた、ということでもあるんですけど……。
やひろ:正直言って、押尾さんの作品、一次落ちするようなクオリティじゃないですよ。
押尾:まじすか。
やひろ:だと思います、僕は。ほんとお世辞抜きで、最初読んだときにすごい成熟している書き手さんだなと思いました。初めて小説読んだとき、この人、年上なのかなと思ったんですよ。
押尾:ええ?
やひろ:だって、シングルマザーの話とか書いてるし。作品からにじみ出る生活感がすごいなと思って。生活感に、20代には出せない感じを感じ取りました。でも、noteを見てみたら、ちょっと、若い人なんかな、って言う感じがして(笑)。
押尾:ちょっとなんかチャラいっていうか、軽い感じしますよね、noteだと。
やひろ:noteはなんとなく若者っぽいですよ。小説は結構チャラさが少なくて、と生活感があって、すごいなぁと思って。実は僕、逆なんですよね。小説の方が若いって言われて、エッセイの方が大人だと言われる。
押尾:めっちゃそれ思いますね。なんでそうなるんですかね?
やひろ:いやそこがすごい不思議だなと思って。そういう意味でも、僕らすごい対照的なんですよ。そこが興味を持った要因ではあります。
押尾:noteは抜け殻の状態で書いてるんですよね。手を抜いてるっていうよりは、小説に考えてることとか、人生経験とか、全部投入して、その残ったものだけでnote書いてるって感じなんで。今、やひろさんと喋ってるのはその中間ぐらいですね。小説は、めちゃめちゃ集中するぞって言う気持ちでやってるんで、文章が硬くなるところはありますね。
やひろ:あーそれなんかわかる。
押尾:脱力してないっていうか、小説に対しては、常に緊張感を保ちたいっていう。
やひろ:緊張感もそうだし、格調を低くしたくない、っていう印象を受けますけど。
押尾:主人公の苦しみは、ほんとに心の底からそれを感じて書いてますね。「主人公が苦しんでる方が物語としてうまく回るから、苦しませる」ってことは僕はしないです。都合よく展開をさせないっていうのは決めてますね。
都合よく展開させようと思ったら無限にできるんですけど、それを自分で読み返したときにいいと思えるかって言うと、やっぱりつまんない、面白くないと思うんで。そう思わないようにしようと頑張ってますね。100%そうだと思ってなくても、その気持ちはわかるよ、っていうの以外は書かないことにしてるんで。
やひろ:矜持がすごいですね、なんか。
押尾:小説って、全部自分で体験したことだけじゃないじゃないですか。体験した事は無いけど、なんとなく知ってる感覚っていうか、ある程度はなんとなくでもいいんだけど、がっつり想像もできる範囲でのものしか書いちゃっいけないというふうに制限してますね。
やひろ:シングルマザーの小説、よく書けましたね。
押尾:シングルマザーは、目黒での体験がベースになってます。目黒で仕事してたことがあったんですけど、仕事で、公園にいる時間がすごく長かったんですよね。で、公園には主婦とかがいっぱいいたんですよ。それを観察してました。
やひろ:それで書けるんですか? 家の中の様子とかって、わかんないじゃないですか。
押尾:家の中は、公園の隣に唐突にめっちゃ高級なマンションがあって、遠目から見えた風景とかを参考にしました。なんとなく見えるじゃないですか、内装の様子とか、マンションなのに二階があるメゾネットだな、とか。この便利なロケーションで、しかもメゾネットで、向かいに公園があるってかっこよすぎじゃないですか? それでインスピレーションを得て、物語が浮かんできた、っていうのはありますね。
やひろ:まぁ、でもその状態で想像できないようではきっと小説家にはなれないよね。それぐらいの素材で書けるのが必要条件というか。それでも、作品としては結構生々しいなっていう感じはしましたけどね。
押尾:夫との関係の問題とかね(笑)。あの話が一体どこから来たのか自分でもよくわからないんですけど。
やひろ:まぁ夫との関係もそうなんですけど、子どものちょっと手のかかる感じというか、どうしようもない感じってあるじゃないですか。あれにすごい共感しましたけどね。ドラマとかの子どもってすごく聞き分け良いじゃないですか。絶対子どもってあんな感じじゃないよな、って常々思いますもん。もっと言語化不可能なことやるじゃないですか、子供って(笑)。そういう感じが、なんか押尾さんの小説では表現されてる気がしたんですよね。
押尾:でも取材も何もしてないですけどね。公園で遊ぶ親と子どもの情景を死ぬほど見ただけなんで。割と記憶力はある方なのかもしれないですけどね。その見た情景とかをそのまま使うとかじゃなくて、小説を書こうと思った時に、何かぱっと思い浮かぶんですよね。どこかにそういうのが切り替えるスイッチがあるのかもしれないです。小さい頃の記憶とかもめちゃめちゃ覚えてるし。
やひろ:そっか、子供はみんな子供だった時があるから、実は書けるんだ。
押尾:それもありますね。子供の時、自分だけやたらテンション高くて、親がちょっとそのテンションうざがってるときってありません(笑)? そういうのを思い出したりしますよ。公園で遊んでる親子を見て、そのやりとりとか見てると自分の子供時代もこんなやったなぁ、と思ったりしますね。何かひとつ、きっかけがあれば、そこから広がっていくんですよね。
やひろ:これまでこの企画でインタビューさせてもらったんですけど、絵の場合は僕は描かないんでただすごいですねとしか言えないんですけど、小説に関しては僕は書き手でもあるわけだから、「自分との差」を見るんですよね。どこが違うかに注目するというか。
その視点で見た時に、「生活の生々しさの描写」が僕よりも圧倒的に上だなと思って、どうやってこれ書いたんだろう、みたいに思ったんです。さっきおいしいもの食べないとダメなんですよって言ってたじゃないですか。僕って食にはかなり無頓着なんですよ。
おいしいものも美味しく食べるけど、そこそこのものでも美味しく食べれるタイプなんですね。だからかはわかんないですけど、自分の小説って、あんまり食事のシーンがないんですよ。
押尾:それはそこを重視して生活してないからなんですかね。
やひろ:そこが悩みといえば、悩みなんですよね。
押尾:まぁでもだからといって無理矢理おいしいもん食べたとしてもそれは小説に生きるかって言うと、また別の話ですよね。
やひろ:後は、自分はタバコを吸わないんですけど、登場人物には吸わしたりするんですよね。お酒についての知識がないでもどうしようもないって言う感じ。
押尾:よく映画監督とかでもおいしいご飯食べろっていますよね。それによって撮影できる幅が広がるから、と。まぁでも、自分の得意なジャンルって絶対あるはずなんで、まずそこを伸ばすのが一番いいんじゃないですかね。僕も別に努力して生活感とか記憶力とか鍛えたわけでもないんで。まず得意分野があって、それをうまく支えるために勉強するみたいな感じだったらいいと思うんですけど。

たい焼き屋さんってできますか?
押尾:やひろさんの小説って、なんか結構エンタメ的な作り方ですよね。やひろさん的には、エンタメ的なところに着地したいんですか。
やひろ:ゴリゴリのエンタメではないけど、純文学では無いかもしれないですね。暗いエンタメみたいな(笑)。でもなんか最近、「進撃の巨人」みたいに、絶望的なエンタメって増えてますよね。救いがない話が最近多いなと思って……。
押尾:残酷な話っていうかね。
やひろ:押尾さんの作風は純文学になるんですよね? エンタメではないような気はしますけど。
押尾:わかんないですね……。純文学とエンタメの中間のジャンルとかもありますからね。
やひろ:スカッとしたらエンタメみたいな。ジメジメしてたら純文学……みたいな感じですかね。
押尾:まぁ、モヤモヤさせるのが別に目的ではないんですけどね(笑)。でも、例えば村上春樹が純文学なのかっていったら、もはやよくわかんないじゃないですか。でもエンタメかって言われても、ちょっと迷う。
もはや、あんまりジャンルに意味は無いかもしれないですね。たとえば、作家そのものはジャンルのひとつになることってありますよね。川上未映子が好きだって宣言したときに、「それなら、こういう作家もありじゃない?」みたいな感じでおすすめされた時は、川上未映子がひとつのジャンルとして機能してるってことじゃないですか。
とりあえず個性があれば、どういうジャンルに分類されるかは、なんでもいいような気がしますけどね。
やひろ:もうひとつ、押尾さんに聞きたいことがあって。僕が小説を書きはじめたのって中学ぐらいの時なんですけど、高校生になったときに、自分の生きている世界がとても狭いことに気がついて、このまま職業作家になったとしても絶対先細りするというか、「読者を超える」ことができないんじゃないかって悩んでたんですよね。
押尾:「読者の期待を超える」ってことですか?
やひろ:いや、期待というんじゃなくて。要するに、社会経験のないままに作家になってしまったら、読者の方が人生経験が深くなってしまうと思ったんですよね。
で、いざ大学卒業して、就職するぞってなったときに、本読むのが普通の人より好きだったんで、本屋に勤めながら小説家を目指す、っていうプランを目論んでたんですよ。まぁ、でも、現実的には本屋もそんなに景気の良い商売ではないし、「小説家を目指す人が本屋に就職する」って、結構ありがちなパターンだと思ったんですよね。
そんな、人と同じことをしてたらすごいものなんて書けないんじゃないかと思って、それまで全然興味のなかった会社に就職することにしたんですよ。その結果が今なんですけど。
押尾さんが小説を書くにあたって、こういう経験をしたほうがいいんじゃないかとか、そういうのって考えたりすることあります? つまり、自分の身の回り、半径5メートルの話でいいのか、それとももっと広い範囲を扱う方がいいのか、っていうことです。
押尾さんの書いた話を読む限り、結構目に見える範囲というか、自分の視界に入る人たちをメインに話を作ることが多いなと感じていて。そのスタイルでずっとやってくつもりなんですか?
押尾:それは、どんどん広げたいし、変えていきたいなと思ってますよ。半径5メートルじゃなくて100メートルぐらい広げたいなとかは思いますよ(笑)。
とりあえず、半径5メートルの話を書くのが得意っていうのは、割とわかってきたんで。このコースからのシュートは俺が決めれるぞっていうのは掴めたんで、あと20メートルぐらい離れても、なんとなくいけそうな気はしてますけど。
やひろ:得意技がわかったというか。
押尾:じゃあ逆サイドの20メートルがどうなんかって言うと、そこはまだ自分トライしたことないんで、挑戦してみたいなとは思いますけどね。
やひろ:僕は「何でもできる人」になりたいんですよ。得意技とかじゃなくて、「全てできる」になりたいんですよね。
押尾:すごいなそれ。
やひろ:純文学も書ければエンタメも書けるし、ノンフィクションも書ける、みたいなのが僕の理想なんですよ。
押尾:すごすぎでしょ、それ(笑)。
やひろ:だから得意技みたいなのって、逆にあんまり考えてないんですよね。結果的に苦手なこととか得意なことはあるんですけど。基本的に何でも出来るようになりたいというのがあって、そこが多分根本的に違うんですよ。
押尾:僕は、たい焼き屋さんをやってたとしたら、たい焼きはそこそこうまく作れるようにはなってて、お客さんもそこそこ来てくれて、そこそこの成功を納めてるんで、「タコ焼きもやってみようかな」みたいなこと考えてるレベルですよね。やひろさんの場合は、たこ焼き屋の次に「ポルシェ作りたい」みたいな、そういうレベルじゃないですか。それでいて、かつ「バイオ燃料の開発もしたい」みたいな。
やひろ:できるかどうかは置いといて、「不得意な分野がある」というのが許せないんですよね。
押尾:僕はそういう欲求はゼロですね。小説さえよければ、例えば「会話する能力」がもっとなくなってもいいとさえ思う。それぐらい、小説に特化した人になりたい。
やひろ:これ、少年漫画やったら僕のほうが圧倒的に雑魚ですからね(笑)。いろんなことやりたいって言って結局何もならないって言う。押尾さんの方が序盤は苦戦するけど最終的には強いみたいな、主人公タイプですよね。
押尾:芸術家タイプじゃないんですよね、きっと。芸術家っていっこのことに一生飽きない人たちだと思うんですよ。安藤忠雄っていう建築家が一時期すごい好きだったんですけど、あの人いっつも同じパターンなんですよ。またこれですかっていう。
コンクリート大好きおじさんで、幾何学が好きで、装飾とかが全然ないんですよね。それで、作品がどんどんよくなってるかっていうとそうでもなかったりして。ステーキずっと焼いて喜んでるおじさんみたいな。やひろさんって、例えば同じ商店街でたい焼き屋さんを50年やるみたいなことってできます?
やひろ:まあ、でも、小説という枠の中では、20年ぐらいやってますよ。音楽にしてもそうです。
押尾:その2つがずっと続いてるってすごいですね。もともといろんなことに興味があったけど、ナイアガラの滝みたいに、一個に収斂していったんですかね。僕の場合、もともとちょろちょろやったのが、プシューって広がっていく感じですかね(笑)。
ひとつのことを極め続けた人が最後に勝つみたいなのがテンプレ的にはあると思うんですけど、今日的な価値観で言うと、割といろんなことやる方が強いのかもしれないですね。いろんなことやってて一気にクオリティーが全部上がっていくっていうの、あると思いますよ。
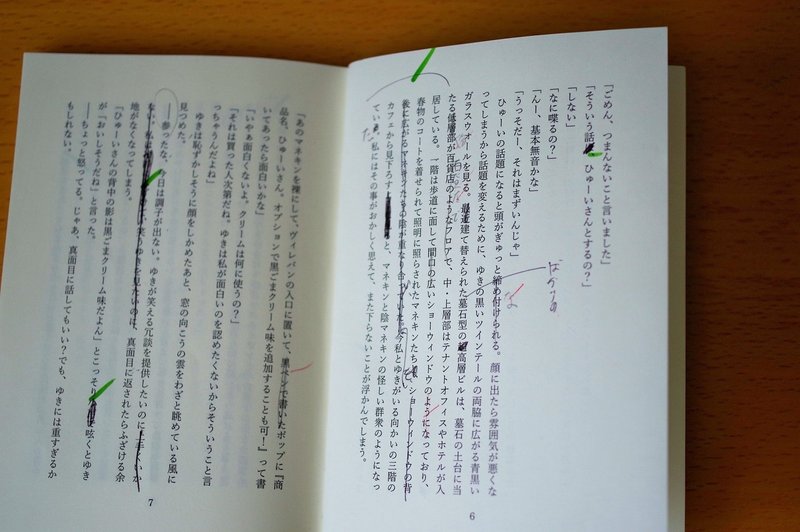
小説書いてる俺ら、すごい
やひろ:やっぱ、こうやって話していくとお互い通じるところもあれば違うところもありますよね。当たり前ですけど。
押尾:自分が芸術家とはあんまり思ってないけど、芸術家ってほぼほぼ変態ですからね。自分の身を削ってひたすらやっていくのもいいんですけど、自分の身を削らないでやってくっていうのも、結構やりたいんですけどね。たとえば宮崎駿って、一作作るたびに、ちょっと病気になるぐらい「やり切った感」あるじゃないですか。僕はああはなりたくないなと思ってて。自分の身を削っていく以外にもやりようはあるだろう、と思うんですよね。
やひろ:でも結果的には、押尾さんもそういうタイプなんじゃないですか?
押尾:結局疲れますよね。なるまいなるまいとしながらも、燃え尽きタイプではありますね。書き上げたあと、2ヶ月ぐらい何も書きたくなったりして。
やひろ:やっぱ燃え尽き系だと思ってましたよ(笑)。その燃え尽きに関して、同じ作家志望同士の間で話をしたいんですけど、小説書くってこんなに報われないことってあるんですかっていう感、あるじゃないですか。半年とか1年かけて書いた作品が一次落ちして、特に何のリアクションもない、みたいな。
押尾:ふざけんなって思いますよね(笑)
やひろ:しかも結果出るまでに半年位かかるじゃないですか。半年間待ってなんもないって言うね。
押尾:きついよね。きついけど、それぐらい狭き門を叩いている、っていうところはありますよね。
やひろ:倍率とか、冷静に考えると500倍とか、1000倍とかですからね。
押尾:有名な賞だったら、下手すると3000とかいきますからね。就職活動でももうちょっと反応ありますよね。
やひろ:僕は、二次選考に通ったことがあるんですよ。で、5ちゃんねるの情報によれば、最終選考に残る前に編集部から電話がかかってくるらしいんですよね。で、そこから僕、2週間ぐらい編集部からの電話を待ち続けたんですよ(笑)。
押尾:それって、バレンタインの当日がずっと続くみたいなことでしょ?
やひろ:一回経験したらもう二度やりたくないですよ(笑)。結局落ちてましたからね。何次通っても、落ちたら一緒なんやなってつくづく思いましたよ。
押尾:24歳ぐらいのとき、絶対いけると思って出した時があるんですよね。その時、仕事も建設現場の補佐みたいなことしてて、そんな状況でも小説書いてる俺すごい、みたいな感じで、結果を待ってたんですけど。
最終選考が決まる前に、最終選考の人が全員雑誌に載るみたいなのがあって。当然その前に電話がかかってくるはずなんですよね。で、絶対かかってくるって信じきってたんですよね(笑)。もうその時期は馬鹿みたいに電話ばっかり見てました。それで音沙汰が何もなかったんで、ショックで肩が落ちそうになりましたよ。
やひろ:でもまぁそこはみんな通る道なんじゃないですか。若い頃って、自分が最強なんじゃないかと思う時もあれば、たいしたことないんじゃないか、と思うような時もあるじゃないですか。
小説家に抱いていた幻想
やひろ:10代の頃に抱いていた小説家と、現実的な小説家の像ってやっぱり違うわけじゃないですか。僕は、大学2年ぐらいの時に、好きだった小説家のインタビューを見て、小説だけでは食えてないみたいなのを見て、かなりびびりましたよ。また、小説一本で食えてる人なんて、100人ぐらいしかいない、っていうのも知って。
押尾:そういうの見ると、ひるみますよね……。
やひろ:その後僕が感じたのは、普通に働きだした後に、こんな労働でこんなにお金もらえるんやと言う衝撃ですね(笑)。自分がやりたいこと、得意なことをやっても全然お金にならないのに、普通に働いたらたったこんだけのことでこんなに金もらえるんや、みたいな。
押尾:お金って何なんだろうって、逆になりますよね。自分の頑張りと全然比例していないという。
やひろ:結局、人様の役にたつかどうかなんですよね。役に立つ行為は金になるし、役に立たない行為は金にならない。小説って究極的に実用性ないですからね。
押尾:役に立たないからこそ美しい的なのもありますよね。
やひろ:役に立つものに囲まれてるから美しいかというとそうでもないですかね。まぁ、そういう意味でも同じ金銭感覚のもの同士と言う感じでもありますよね。新人賞に出して落ちるって言う行為は何一つ生み出してないですから。
押尾:誰も知らないですからね。審査員の人が読んだだけですからね。
やひろ:現代においてここまで報われない行為ってそうそうないと思うんですよ。noteとかは数字が出るんである程度モチベーション出ますけどね。逆に、こんだけけちょんけちょんにされて、やり続ける自分すごいってなりません?
押尾:なりますよ。こんな非効率なことやってる人ってそうそういないですもん。SNSでフォロワー増やすような即物的な賞賛を差し置いて、作品に精力注ぐ俺かっこいい、ってなりますよね(笑)。

さっと掬った鰹節の出汁のほうがうまい
やひろ:押尾さんと僕のスタンスで、似てるようで違うところも結構ありますよね。押尾さんの作風って結構世の中に迎合してないところありますよね。
押尾:世の中に合致するかどうかを第一には考えてないですね。
やひろ:普通、同人の即売会って言ったら、売れるジャンルかどうかを意識して作ってる人っているじゃないですか。そういう人とは違うっていうのはわかると思うんですけど、でも世間のニーズから完全に外れたもの作ってる感じでもないんですよね。
押尾:ある程度はコミットしようとしてますよ。
やひろ:コミットというか、「これがいいと思って作ってるんだな」っていうのが伝わってくるんですよ。
押尾:それ感じるんですか?
やひろ:ずっと何十年も制作してて、でもクオリティーの低い人も世の中にいるじゃないですか。もうそれしかできないっていうか、一緒の惰性でやってる人もいるわけですよね。でも押尾さんは割といろいろ挑戦してやってる感じがします。
押尾:ソール・ライターって言う写真家の展覧会行ったんですけど、クオリティーがすごかったんですよ。1枚だけめっちゃいいとかじゃなくて、さらっと撮ったスナップ写真とかが全部めっちゃかっこいいんですよね。
全部が傑作ってわけじゃないんですけど、何気なく撮ったものがすごくクオリティーが高いと言う。芸術と生活が合体してるというか、生活してたら作品ができるって最強なんじゃないかと思って。すごい闇の底に落ちて作るような作品もいいんですけど、職業にしたら多分もたないと思うんですよね……。
やひろ:村上龍がそれについて昔言ってましたよ。仕事は淡々とやるものだと。小説も基本的には書くべきもの淡々と描いていくのが基本だと。
押尾:でも作業ではない、みたいな。
やひろ:書く量って毎日決めてるんですか?
押尾:決めてないですね。その時の勢いで。
やひろ:僕はストップウォッチで計ってやってますよ。僕の場合、一時間2000字が目安なんで、15分おきに測って。
押尾:完全にマラソンじゃないですか(笑)それで、何も出なかったらどうなるんですか?
やひろ:なにがなんでもひねり出しますね。後から直したりもするんで、そんなに書いた段階では気にしないようにしてます。挙句、「もういいでしょ」みたいな感じになって、とりあえず書き上げよう、みたいなモードになります。あとは、翌日に読み返したときに自分がどう感じるかなんで。ひねり出すのが大事です。ひねり出しただけ前に進むんで。
押尾:うわあ(笑)。僕は、ひねり出さないですね。日常生活の延長で作品づくりをしたいと思ってるから、無理にひねり出せないんですよね。鰹節で出汁取るときに、ぎゅってしぼりたくなるんですけど、絞るとえぐみが出るんですよ。さっとすくって取った出汁のがうまい。なので、絞らない主義です。
やひろ:僕は出なくなってからが楽しみなんですよね。自分が何を思いつくのかっていうのが。意外性自体を楽しむっていうのが僕のやり方。ここらへんはスタンスが対照的なんですよね(笑)。
押尾:ほんとですね(笑)。
*
さんにんめのゲストの押尾信さん、いかがでしたでしょうか。小説家志望同士の、内容の濃い(?)インタビューとなりました。
押尾信さん、本当にありがとうございました!
押尾信さんの活動、および予定の最新情報はnoteまたはツイッターからご参照ください。
サポート費用は、小説 エッセイの資料代に充てます。
