
【高校生物基礎】第16講「ホルモンとは何か?」
~プロローグ~
チョウの幼虫は、その体を劇的に変化させ、チョウになる。このような変化を「引き起こす」のは、ホルモンhormone(「引き起こす」を意味するギリシャ語hormanに由来)とよばれる、小さな分子である。ちなみに、焼き肉のホルモンは「ほうるもん(捨てる物)」に由来していると言われている。
★テストに出やすいワード
①負のフィードバック作用
②内分泌腺
③標的細胞
④脳下垂体前葉
⑤甲状腺
要点:ホルモンは、内分泌腺から血液中に分泌される。
● ホルモンとは、血液中に分泌される、情報伝達に関わる化学物質である。

● ホルモンを血中に分泌することを内分泌(「ないぶんぴつ」または「ないぶんぴ」)といい、ホルモンによる調節のしくみを内分泌系(ないぶんぴつけい、ないぶんぴけい)という。
● ホルモンを分泌する細胞の集まりを内分泌腺(ないぶんぴつせん、ないぶんぴせん)という。

● 体表や消化管、すなわち体の内外表面への分泌を外分泌(「がいぶんぴつ」または「がいぶんぴ」)といい、外分泌を行う腺を外分泌腺(がいぶんぴつせん、がいぶんぴせん)という。外分泌線には導管(どうかん。排出管[はいしゅつかん]ともいう)がある(内分泌腺には導管がない)。
外分泌線の例)汗腺・唾液腺・消化腺
雑談:細かい話をすると、汗腺・唾液腺などは分泌物の種類に基づいて名付けられた名称、消化腺は生理的機能に基づいて名付けられた名称である。高校生は、外分泌は「体の外への分泌」と考えておけばよい。消化管の内表面も体の外であることに注意。我々の体は「ちくわ」状であり、中を貫通する空洞も体の外である。下図はイメージ。

● 下図は外分泌腺の基本的な構造のイメージ。導管という用語のみよく問われる。

雑談:実際は、外分泌線の形にはいくつか種類がある(導管が分岐しているものや、分泌部がらせん状によじれているものなどがある)。
講義動画【ホルモン・内分泌腺・外分泌腺】
要点:ホルモンは標的細胞のもつ受容体と結合する。
● ホルモンは、特定の細胞(標的細胞[ひょうてきさいぼう])に作用する。
● 細胞は、受容体(じゅようたい)とよばれるタンパク質を持っており、その受容体にホルモンが結合することで細胞の中で特定の化学反応がスタートする。受容体は細胞膜上にあったり、細胞内にあったりする。

● 標的細胞をもつ器官を標的器官という。
● ホルモンは血液中を循環するので、微量で長時間効果が続く(対して、自律神経はすばやく働くが、効果は一時的である)。

問題:次の文章は、A内分泌系とB自律神経系のどちらに当てはまるか。どちらか1つを選び、AかBで答えよ。
(1)比較的素早く反応を起こす。
(2)比較的長時間働く。
答え:(1)B(2)A
● 間脳視床下部には、ホルモンを分泌する神経細胞が存在する。そのような特別な神経細胞を神経分泌細胞(しんけいぶんぴつさいぼう)という。
要点:甲状腺はチロキシンを分泌する。チロキシンは代謝を促進させるホルモンである。
● チロキシンというホルモンは、代謝(特に異化反応)を促進する(ほとんどの組織がチロキシンに対する受容体を持つ)。
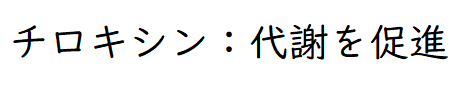
● 両生類では、チロキシンは変態を促進する。鳥類では、チロキシンは換羽を促進する。
雑談:チロキシンは、恒温動物では、ほとんどすべての組織に作用して酸素消費と熱産生を刺激し、基礎代謝量の維持に働く。
雑談:チロキシンによるエネルギー消費増加の詳しい仕組みについては、わかっていないことが多い。チロキシンは、細胞膜上のナトリウムポンプを活性化するとともに、その数を増やすらしい。これによるNa+輸送に伴うエネルギー消費の増大が、代謝の上昇につながる要因の一つであると考えられている。
● チロキシンの分泌
①間脳視床下部(かんのうししょうかぶ)が脳下垂体前葉(のうかすいたいぜんよう)に向けて甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(こうじょうせんしげきほるもんほうしゅつほるもん。「放出ホルモン」と略すこともある)を分泌する。
*間脳視床下部とは、「間脳の視床下部という場所」を指す。間脳には、生物基礎では習わない「視床」という場所もある。
*甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンは、「甲状腺刺激ホルモンを放出しろ」という命令のようなホルモン。
②甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンは脳下垂体前葉に作用し、脳下垂体前葉からの甲状腺刺激ホルモン(こうじょうせんしげきほるもん)の分泌を促進させる。
③甲状腺刺激ホルモンは甲状腺(こうじょうせん)を刺激し、甲状腺からのチロキシンの分泌を促進させる
● チロキシンは、間脳視床下部や脳下垂体前葉にも作用し、それぞれ甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンと甲状腺刺激ホルモンの分泌を抑制する。このような調節の仕組みを負(ふ)のフィードバック作用(負のフィードバック調節)という。負のフィードバック作用により、チロキシンの血中濃度が適切な範囲に保たれている(チロキシン濃度が上がれば分泌量が下がり、チロキシン濃度が下がれば分泌量が上がる)。

講義動画【チロキシン・負のフィードバック作用】
発展:負のフィードバック作用・正のフィードバック作用
負のフィードバック作用において、結果が原因を抑制する向きに働くことを「負」と表現する。増えれば減らす方向に、減れば増やす方向に働くことを「負」と表現している。このしくみによって血液中のチロキシン濃度が一定に保たれている。「結果が原因に戻って行う調節」をフィードバック作用という。結果が原因をさらに促進するような調節も存在し、そちらは正(せい)のフィードバック作用という。たとえば、性ホルモンの調節などにおいて、正のフィードバック作用が知られている。
雑談:「最近のオートメーションの発展によって、人間の活動のあるものに比較しうるような操作を行う機械が工業において用いられるようになった。自動制御機械は生体におけると同じように、その過程のある段階が極端に大きな変動に至ることを防ぐためのフィードバック・ループによって調節されている。このようなフィードバック制御は生きていた動物のあらゆる段階の体制に見られるものである。例えば…温度調節、血糖レベルを比較的一定に保持することなどのホメオスターシスのメカニズムなどである。」アムバーガー
雑談:「フィードバック原理の生理学への重要な応用をのべるのを忘れるわけにはいかない。それはいわゆる'恒常性'(homeostasis)についてであるが、そこでは生理現象にある種のフィードバックが出てくるだけでなく、それが生命の継続に絶対必要である多数の例が見出される。・・・われわれの体内の経済は、巨大な化学工場にも匹敵するほどの、サーモスタットや、水素イオン濃度の自動調節器や、調速機などがなければ成り立たないのである。これらが、相対的に恒常作用として知られているものである。」ウィーナー『サイバネティックス 動物と機械における制御と通信』より
*サイバネティックスは、「動物と機械における通信と制御の理論」と定義された学問分野であり、アメリカの数学者ウィーナーによって提唱された。ウィーナーのサイバネティックスは、情報と制御の科学であり、フィードバック原理を強調している。
雑談:フィードバックは一般的によく使われる用語である。「試合結果を練習内容(原因)にフィードバックする」「お客さんの反応(結果)をサービス(原因)にフィードバックする」などのように使う。
雑談:あなたが恋人から寂しいと言われたとする。あなたは1日に100回恋人に電話する。すると、恋人はあなたを「うざい」と思い、寂しいアピールを減らす。これは、あなたの電話(結果)が彼女の寂しいアピール(原因)を抑制したので、負のフィードバックである。電話回数は下がり、丁度用意程度に維持される(電話回数が減りすぎれば、寂しいアピールが再び増え、電話回数は上昇する)。
一方、次のような例もあるかもしれない。あなたが恋人から寂しいと言われたとする。あなたは1日に100回恋人に電話する。すると、恋人は「最高にうれしい!!でも、100回では足りなくなってきた・・!もっともっと電話してほしい!」と思い、寂しいアピールを『増やす』。あなたは慌てて1日に200回電話をする。恋人は「ああ!!最高!でも足りない・・!もっと!電話して!」あなたは1日に300回電話をする。これが正のフィードバックである。結果が原因を促進し、速やかに限界値に達する。
雑談:フィードバック(制御系において出力を入力側に戻すこと)によって制御量の値を目標値と比較し、それらを一致させるような訂正動作を行う制御をフィードバック制御(feedback control)という(これはもともと、工学用語である)。フィードバック制御は、生物のもつ様々なシステムにおける調節の基本原理となっている(ホルモン分泌量の調節、運動の姿勢の維持など、様々な場面でフィードバックによる制御が行われている)。
発展:エクジソン・幼若ホルモン
昆虫の変態に関わるホルモンとして、エクジソンや幼若(ようじゃく)ホルモンが有名である。エクジソンは脱皮・変態を誘導するホルモンである。幼若ホルモンは主に成虫化を抑制している。
雑談:「でも、あなただって蛹になって、—―そのうちそうなるわよね、—―それから蝶になるわけでしょ。そのときはきっと、ちょっと変な感じがするにきまってるわ、そうじゃない?」ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』より アリスの言葉
発展:間脳視床下部と脳下垂体のイメージ
下図は間脳視床下部と脳下垂体のイメージ。
脳下垂体前葉には、刺激ホルモンを分泌するホルモン分泌細胞が存在する(図1には描いていない)。その細胞が間脳視床下部で神経分泌細胞が分泌した各種の放出ホルモン(たとえば甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン)を受け取り、各種の刺激ホルモン(たとえば甲状腺刺激ホルモン)を分泌している(知らなくてよいが、放出ホルモンは下垂体門脈という血管を通って脳下垂体前葉に送られる)。
脳下垂体後葉には、神経分泌細胞(の軸索という長い突起)が伸びている(腺である脳下垂体前葉に対して、脳下垂体後葉は、脳の一部であると考えてよい)。神経分泌細胞は、脳下垂体後葉において、バソプレシンなどのホルモンを分泌している(図1)。
放出ホルモンやバソプレシンは、どちらも間脳視床下部でつくられる。しかし、放出ホルモンが間脳視床下部で分泌されるのに対して、バソプレシンは(軸索内を通って脳下垂体後葉まで送られ)脳下垂体後葉から分泌される(図2)。
図1

図2(血管は描いていない)

講義動画【脳下垂体】
雑談:脳下垂体の大きさは、およそ1×1×0.5cmである。脳下垂体は発生的に由来の異なる2つの部分からなる。脳下垂体前葉は、視床下部からやってくるホルモンによって分泌調節を受ける。これには下垂体門脈と言う特別な血管が関与する。脳下垂体後葉は、脳の直接の続きであり、視床下部の神経分泌細胞からの軸索がやってきている。
雑談:高校では習わないが、間脳視床下部は、主に、以下の6つのことがらに関わる機能をもつ。覚えなくてよい(バソプレシンは脳下垂体後葉から、糖質コルチコイドは副腎皮質から、成長ホルモンと甲状腺刺激ホルモンは脳下垂体前葉から分泌されるので注意。視床下部からこれらのホルモンが直接分泌されているわけではない。間脳視床下部は、副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン、成長ホルモン放出ホルモン・成長ホルモン抑制ホルモン、甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンを分泌する)。

雑談:脳下垂体の構造や各部の位置関係は動物によって極めて多様である。一般に、脳下垂体には前葉・中葉・後葉という部位がある。
中葉は、クジラ、ゾウ、鳥類では欠損し、ヒトや類人猿では成体になると退化する。中葉からはメラニン細胞刺激ホルモンが分泌される。
*メラニン細胞刺激ホルモン(中葉ホルモンとも呼ばれる):脊椎動物の脳下垂体中葉から分泌され、メラニン細胞に作用し、メラニン細胞内の色素顆粒の拡散、およびメラニンの合成を促進し、体色の黒化を引き起こす。ヒトの場合、中葉の発達は不十分であり、副腎皮質刺激ホルモンにメラニン細胞刺激ホルモンと同様の作用がある。
発展:ベイリスとスターリングによるホルモンの発見
● ベイリスとスターリングがホルモンという語を作った。ベイリスとスターリングは、十二指腸からホルモンが分泌され、すい液の分泌を促すことを発見し、これにセクレチンと命名した(ホルモンという名称・定義は、ベイリスとスターリングがこの物質に初めて与えた)。
● 酸性の胃の内容物が十二指腸に移行すると、その粘膜のS細胞(secretin containing cell)から分泌されたセクレチンが血液に入ってすい臓に作用し、すい液の分泌が促される。すい液により十二指腸内容物がアルカリ性になると、S細胞はセクレチンの分泌をやめる。

雑談:ベイリスとスターリングは、神経を切除しても、酸の存在がすい臓に伝わり、すい臓からすい液が分泌されることを発見した。何かが血液を通って、すい臓に情報を伝えたと考えれば、この現象が説明できた。人類は、神経系とは異なる情報伝達のシステム、すなわち内分泌系を発見したのであった。
雑談:食物が異に到達すると、胃から(正確には胃の幽門部[腸との境界]の粘膜に存在するG細胞[gastrin containing cell]から)ガストリンというホルモンが分泌される。ガストリンは血中に入って、胃に再び戻って働き、胃液分泌を促す。

雑談:水は一度にたくさん飲めないのに、ビールはぐびぐび飲めてしまう、とよく言われる。これは、ビールがガストリンの分泌を促すためと考えられている。ガストリンには胃の出口付近の運動を促進するはたらきがあることが知られている。
Q&A
Q.ホルモンってフェロモンのこと?…違う。フェロモンとは、体外に分泌され、同種の他個体に対して何かしらの情報を伝える物質のことである(集合フェロモンなど。生物基礎範囲外)。ホルモンとは、ある個体の体内の、体液中に(人では血中に)分泌される化学物質。
Q.神経分泌細胞って何?…「神経細胞」なのに、ホルモンを「分泌」する能力のある細胞のこと。
Q.チロキシンっていつ分泌されているの?…24時間、負のフィードバック調節によって一定濃度に保たれながら分泌されている。チロキシンの欠乏や過剰な分泌は疾患につながる。
クレチン症:チロキシンが不足している。
バセドウ病:チロキシンが過剰に分泌されている。
雑談:クレチン症は、胎児期からの甲状腺ホルモンの欠乏に起因する病態である。放置すると知的発育障害をきたすことがある。バセドウ病は、自己抗体により甲状腺が刺激され、過剰にチロキシンを分泌してしまう自己免疫疾患である。バセドウ病では、体重減少、発汗過多、易疲労性、動機などの症状が出現することがある。
雑談:チロキシンの投与がクレチン症の治療に役立つことがわかった時、偉大な内科学者ウィリアム・オスラーは「プロスぺロの魔法の杖も、ヒポクラテスの娘のすばらしく見事なくちづけも、今日われわれがやることができるような変化を今までやることができなかった。」と言って狂喜したという。
Q.ホルモンって何でできているの?…ホルモンによって異なる。ペプチドホルモンやステロイドホルモンなどがある。
雑談:ペプチドはアミノ酸の鎖のこと。ステロイドは脂質の一種(ステロイド骨格という、炭素がつながった特定の構造を持つ)。ステロイドホルモンは、脂質なので、リン脂質でできた細胞膜を通過できる。ちなみに、チロキシンはステロイドではない(チロキシンはチロシンというアミノ酸の誘導体で、ヨウ素を含み、細胞膜を通過できる)が、受容体は細胞内にある。
なお、アドレナリン(第二級アミン。アンモニアの水素原子2個が炭化水素基で置換されている)の受容体は細胞表面にある。
ペプチドホルモンは細胞膜を通過できないので細胞膜上の受容体と結合し、その情報はセカンドメッセンジャーとして働くcAMP(サイクリックエーエムピーと読む。環状AMP)などが伝えていく。
高校で習うほとんどのホルモンはペプチドホルモン(ペプチドホルモンの例:インスリンやグルカゴン)。
ステロイドホルモンは細胞膜を通過できるので細胞内で受容体と結合する(ステロイドホルモンの例:コルチコイドや、精巣・卵巣から分泌されるホルモン)。
講義動画【ペプチドホルモンとステロイドホルモン】
(発展です)
*ペプチドホルモン・ステロイドホルモン・セカンドメッセンジャーについては、以下の発展生物の資料で少し詳しく解説している。生物基礎範囲外。
