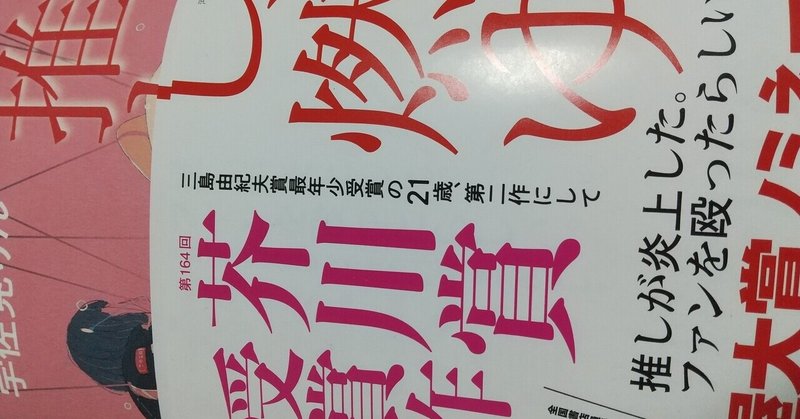
他人の推しを聴くこと――宇佐見りん「推し、燃ゆ」における傷跡の位置
2021年3月27日、私的な読書会で宇佐見りん「推し、燃ゆ」の読書会をおこないました。まさに時宜をえた作品であり、また内容が私たちにとって身近なテーマを扱っているために、意見交換が活発におこなわれとても充実した時間だったとおもいます。そういうわけでまさに読書会向きの小説だと感じました。この記事は私の発表資料をもとに、加筆修正を施したものです。「推し」は私たちの生にとって何を示し、何を導くのか、小説を通してそれをどのように考えられるのでしょうか。
0 推しを聴く
君の書きしるす言葉は想念のうちにある生を推しはかるものでなければならない。
――ジョー・ブスケ『傷と出来事』(1)
「推し、燃ゆ」(初出、『文藝』二〇二〇年秋季号、初刊、河出書房新社、二〇二〇)は、第56回文藝賞、第33回三島由紀夫賞を受賞したデビュー作「かか」(河出書房新社、二〇一九)に続く宇佐見りんの二作目にあたる小説であり、第164回芥川賞を受賞した。
芥川賞選評(2)では、奥泉光が「ひとりの人間の生の形を描ききった」、小川洋子が候補作のなかで「“あたし”の声が、最も生々しく届いてきた」と評し、賛辞を贈っている。また選考委員のなかでも松浦寿輝は、主人公の「心のメカニズム」に対して「知的には理解はしても、何一つ共感するところがない」にもかかわらず、小説終盤では「不意にじわりと目頭が熱くな」り、「共感とも感情移入ともまったく無縁な心の震えに、自分でも途惑わざるをえなかった」と告白し、島田雅彦は「その躍動感に自分まで少女になったような錯覚を覚えた」と述べるなど、率直な言葉が綴られている。
選考委員の多くが賛辞を送り、また率直な読後感を述べるなど、「推し、燃ゆ」の読書体験が、読者に大きな影響を及ぼしていることがわかる。それでは問いたい。「推し、燃ゆ」を読む体験とは、いかなるものなのだろうか。その体験を突き詰めることは、テクストの物語を追い、主人公のあかりの声を、そしてその声と重なる、彼女が推す上野真幸の声を聴き取ることである。ならばすなわち、「推し、燃ゆ」とは他人(ひと)の推しを聴くテクストなのだと、ひとまずはそう言えるだろう。では、それはいったいいかなる行為なのか。本論はこの問いの意味を思考してみたい。
一 垂直と水平
まずはテクストの冒頭部を確認することで、小説がどのようなモチーフの連鎖からなる物語なのかを確認しておこう。テクストはこう始まっていた。
推しが燃えた。ファンを殴ったらしい。まだ詳細は何ひとつわかっていない。何ひとつわかっていないにもかかわらず、それは一晩で急速に炎上した。寝苦しい日だった。虫の知らせというのか、自然に目が覚め、時間を確認しようと携帯をひらくとSNSがやけに騒がしい。寝ぼけた目が〈真幸くんファン殴ったって〉という文字をとらえ、一瞬、現実味を失った。腿の裏に寝汗をかいていた。ネットニュースを確認したあとは、タオルケットのめくれ落ちたベッドの上で居竦まるよりほかなく、拡散され燃え広がるのを眺めながら推しの現状だけが気がかりだった。
無事? メッセージの通知が、待ち受けにした推しの目許を犯罪者のように覆った。
ここからは様々な論点を引き出せる。
まず、小説の語り手についてである。「推し、燃ゆ」の主人公はあかりであり、テクストの多くは彼女に焦点化されることで語られている。しかし、それはあかりの内面をそのまま写し取った言葉ではない。語り手をあかりと同一視すると違和感が残る部分が存在するからである。冒頭部を見るだけでも、まず、携帯電話を名指しするのに〈スマホ〉などではなく「携帯」という言葉を選んで語る点からは、他人に向かって事物を知的かつ冷静に、もっと言うならば公的に語ろうとする印象を受ける。小川公代はこのテクストを「冷淡なほどに温度の低い」文章と評しているが(3)、そうした冷静な視点からの小説の言葉がうかがえるのである。こうした質の文章はテクスト全体から取り出せるが、冒頭部においてもそれは言えるだろう。
そもそも、寝起きのはずのあかりに、推しの炎上を「一晩で急速に炎上した」と把握して語ることは不可能である。もちろん、あかりが事後的に炎上の出来事を把握して語っているのだと理解することもできるが、ここは直截的に語り手の言葉なのだと理解するほうが通りがいい。
つまり、「推し、燃ゆ」の語りとはあかりの視点を通して語り手が語った言葉なのである。それは、「推し、燃ゆ」の言葉はあかりの物語をわざわざ他者に伝えるために開かれた言葉であるということを意味する。すなわち、読者はテクストの言葉を意識的に聴くべきものだとして捉えなくてはならないのだ。読者はテクストの意識下を埋め合わせるようにして読み進める必要がある。「推し、燃ゆ」を読書行為という観点から論じなくてはならないのも、一つはこの点に存立している。これは傷ついたあかりの物語そのものだけではなく、それが語られること、他人が聴くことを内包した物語であるのだ。まずは、これがテクストの読解の前提であり、出発点である。
次に、テクストの冒頭部において論じる必要がある点は、この小説のモチーフについてである。「推し、燃ゆ」の物語とは表題が雄弁に語るように、あかりの推しである真幸がファンへの暴行事件をきっかけにネットで炎上して彼女の前から消える物語なのだが、その推しとはあかりにとっては「背骨」とまで語られているように、彼女にとって肉体の中心に食い込むほどの存在となっている。
その「背骨」たる推しが本作の最後の場面では綿棒に重ねられ、あかり自身によって部屋に散乱する顛末になる。この「背骨」が損なわれていく小説の過程は推しの破壊とともに自死を想起させ(4)、その意味でテクストの炎上の実態は象徴的にあかり自身にまで及んでいること、すなわち綿棒を象徴として炎上によって骨に還元されたあかりを示唆しているだろう点は見やすいところである。
だがその綿棒は「膝をつき、頭を垂れて、お骨をひろうみたいに」片付けられる(5)。その「這いつくば」った姿勢とは「これがあたしの生きる姿勢」であり、「二足歩行は向いてなかったみたいだし、当分はこれで生きようと思った」とあかりは決意を改める。この点において、あかりの自死は変化を伴う再生であることがわかる。
よって、より身体的な観点から眺めてみるなら、この小説は推しの炎上をきっかけに、あかりの身体的姿勢が垂直な二足歩行からより水平に近い――だが腹ばいのように完全に水平なわけではない――姿勢に変化する物語なのだと要約することもできる。
このように要約できるテクストとして、あかりの身体的姿勢に注目してみるなら、冒頭部に現れたあかりの姿勢もまた注意しなくてはならない。実際、テクストの終わりを先取りするかのように、姿勢の変化がそこには象徴的に示されているからである。それは言うまでもなく、あかりが眠りから覚醒する時間が語られていることである。眠りという完全な水平の姿勢から、縦に起こされた目覚めの姿勢へと起きあがること。垂直と水平という姿勢の位相の変移を見逃してはならない。
あかりの姿勢を媒介に、純粋に垂直と水平というモチーフをキーとしてテクストを読み解くなら、冒頭部で注目すべき線がもうひとつある。それは「背骨」として評されるような垂直性たる推しの目許を水平に横切る、あかりの親友である成美のメッセージの線である。
あかりにとって推しの魅力とは、「人を引きつけておきながら、同時に拒絶するところ」であり、その推しの「感じている世界、見ている世界」を共に見たいと願っている。そのような推しとの視線の共有のモチーフがあかりにはあり、推しの特徴もまた「眼球の底から何かを睨むような目つき」である。あかりはそれに「自分自身の奥底から正とも負ともつかない莫大なエネルギーが噴き上がるのを感じ、生きるということを思い出す」。推しの視覚が強調されるこのテクストであるならば、冒頭部でそのような推しの目許を覆うメッセージという描写のもつ象徴的意味は重大である。
垂直と水平。この二つのモチーフがテクストを流れるメインストリームなのだ。あかりが身体に抱える、「背骨」である推しという垂直性のライン。そしてそこに横切るメッセージという形象で流れる水平性のライン。テクスト冒頭では、そのような二つのラインが交差する場面が象徴的に描かれている。「推し、燃ゆ」とは、この複数の線分(ラインズ)の運動が軌跡として交わり、やがてあかりの身体にひとつの結ぼれとして結実していく物語なのである。
ただし、冒頭部におけるあかりの姿勢が「ベッドの上で居竦まる」ものであり、またメッセージで隠される推しの図像が「犯罪者」めいているように、そうしたラインの形象はやがて何かが損なわれる事件性をはらむことを予兆させるものでもある。その身体は、そのラインは、軋み、たわみ、何かを寸断している。
物語はこうした様々な事件を巻き込み、それを語ることとは、「語りの中で過去の出来事を〈関係づけて語る〉ことであり、他者が過去の生のさまざまな糸を何度も手繰りながら自分自身の生の糸を紡ぎ出そうとするときに従う、世界を貫く一本の小道を辿り直すこと」である(6)。それでは、そのラインを辿り直す道は、それぞれの生を導くためにテクストでどのように表現されているのだろうか。その道のなかに、語りを聴くことの意味も手繰り寄せることが可能なはずである。
二 複数の推し
まず、水平性のラインを見てみよう。先に一瞥したように、テクスト冒頭部で象徴的に示されている水平性のラインは、推しが炎上したあかりを気遣う成美からのメッセージだった。この意味において、水平性のラインが示しているのは、主にSNSによってつながることで達成される、ケアの共同体を担保する運動である。
成美はあかりとは異なり、地下アイドルを推しにもつ。留学により芸能界を引退した地上アイドルをもともと推していた成美は、「触れ合えない地上より触れ合える地下」を身上としている。「有象無象のファンでありたい」と願い、推しと「へだたり」を作ろうとするあかりとは、正反対の推しの志向をもつ人物といえる。
推しに対して正反対の志向をもつにもかかわらず、その二人はぶつかり合うことなく友情関係を築いている。二人が推す推しは異なるが、彼女たちは「推し」という出来事を媒介として互いを気遣うことのできる関係をもつ。
「でも、偉いよ、あかりは。来てて偉い」と呟く。
「いま、来てて偉いって言った」
「ん」
「生きてて偉い、って聞こえた一瞬」
成美は胸の奥で咳き込むようにわらい、「それも偉い」と言った。
「推しは命にかかわるからね」
二人は推しを媒介にケアの共同体を作りあげる。それは、あかりが聞き間違いのようにして「生きてて偉い」という自らの生を導く言葉を生み出したように、不完全なコミュニケーションながらも成り立つ関係である。二人のコミュニケーションはゆるい誤読をはらみ、精確で正しい理解可能性を担保としない。
このような推しにかんする二人のケアの共同体は、いわば推しの微細な経験を、誤解をものともせず互いに聴きあうコミュニケーションのあり方を核にもっていると言える。二人は他人の推しをそのように聴くことによって生を導いているのである。
聴くことを主としたコミュニケーションのあり方について、鷲田清一は、「聴くことはかならずしもすべてのことばをきちんと受けとめ、こころに蓄えるということではない。あまりにきちんと聴き、一言一言に対応されると、かえって胸が詰まってしまうときがある」と注意を払い、アースのように「自他の関係におけるある緩みであり、自他の距離感覚である」、「間」が必要であると述べる(7)。鷲田はこのような場を臨床の場と呼び、ケアの経験と接続させて論じているのである。
二人のコミュニケーションもまた鷲田の述べるような聴くことの体験をなぞっていると言えるだろう。ここにあるのは、水平性のラインが、互いの複数の推しの経験を語り合い、聴き合うことによって、主体をケアし合うコミュニケーションの理想像を引く出来事なのである。
成美だけでなく、SNSを介してもあかりはこのようなコミュニケーションをおこなっている。真幸という同じ推しについて、あかりはSNS上でのフィクショナルな人格でありながら、「推しを愛でる会」として友人たちと推しの魅力を語り合い、推しに愛を叫ぶ。それはまた推しの解釈にまつわる「共感」や、推しを介した励ましを含むことによってやはり成立しているのだ。
ならば、ここにあるのは互いの解釈を交えながら一人の推しを複数に愛で、そのようなやり方で主体の生を励ましあう、推しの複数性をめぐるエンパワメントのコミュニケーションである。このように、SNSでのメッセージでつながる関係もまた、あかりにとっては生きづらさを推しによって生の力に変える重要な関係であるのだ。あかりが語るように、「同じものを抱える誰かの人影が、彼の小さな体を介して立ちのぼる。あたしは彼と繋がり、彼の向こうにいる、少なくない数の人間と繋がってい」るのである。
だが、冒頭部ですでに予兆されていたように、水平性のラインが導くのは必ずしもケアやエンパワメントに満ちた理想的なコミュニケーションのあり方だけではない。それは言うまでもなく、推しにかんするアンチコメントがSNSを横切る炎上の出来事である。
推しが炎上した後に、動画サイトやインスタライブといったSNSを横切るのは、アンチによる心ない中傷コメントである。「ファンが何かをきっかけにアンチ化することも多」く、こうしたコメントに対してはあかりも「指をくわえて見ている」ほかなく、また推しの真幸も「普段こういう言葉を無表情でスルーすることの多い推しなのに、「来たくない人は来なくていいですよ、客に困っていないんで」と苛立ちを隠すことができない。中傷的なコミュニケーションは、推しとファンの心理をかき乱し、破壊する。
推しへの無理解に基づく純粋なアンチコメントならばまだよい。だが「まざま座」の解散会見で真幸が左手の薬指の指輪を見せつけ、芸能界からの引退を語ったときは、「炎上したときを上回るほどに活発」なコメントがつぶやかれる。「〈ファンのこと舐めすぎじゃない??????? あなたのために何万貢いだと思ってんの???? は??????? せめて隠し通せ?????????〉」、「食事喉通らないもうずっとぐるぐるぐるぐるしてるなんで明仁くんまで巻き込むの勝手に結婚でもしてやめろよ〉」、「〈え、おめでたいやん ふつうに明るいニュース〉」、「〈元オタ友に解散してもセナくんは芸能界に残るからまだいいよねって言われました~^^こっちはお前の推しのせいで自分の推しのアイドル姿が拝めなくなるんですけど^^〉」等々。
これらのコメントは、単純な推しのアンチから寄せられるコメントではない。同じ推しを、あるいは同じグループの別の推しを推すファンが、自らの解釈で、自らの推しに対する思いを滲ませる、推しにまつわるそれぞれの主体の人生の物語なのである。それらの物語は同じものを推していても、主体のまったく異なった利害関心と解釈をもつ。だから、もはやそこにあるのは同じ推しに対する複数の解釈などではない。それぞれの主体がコメントで痕跡として見せる人生がもたらす、存立を賭けてネットの言論空間に浮かび上がる複数の推しの存在なのである。その物語を背負うぶん、それらは「推し、燃ゆ」のなかでリアルに輝く。
同じ推しやグループを推す共同体であっても、その解釈が、その人生が異なる以上、その共同体はもはや同じ解釈共同体ではない。そこではケアやエンパワメントのコミュニケーションも成立していない。一人一人のミニマムな形からなる、異なる解釈、異なる推しを推すそれぞれの解釈共同体である。それらが、解決も見ないまま、しかし各人の人生を賭けて言論として競合するのである。こうした解釈共同体同士の抗争こそ、SNSがもたらすコミュニケーションのリアリティであり、テクスト冒頭部で示された事件の予兆の結節点なのだ。
すなわち、水平性のラインが導くのは、ケアとエンパワメント、あるいは破壊的な解釈共同体といった両義的なコミュニケーションの形式が並び立つ、単数ではない、複数の推しの物語なのである。そして重要なことはその物語が語られ引用されること、その声を聴くことが「推し、燃ゆ」の言説として存在していることである。それこそが、他人の推しを聴くことの意味の一つの地点を指し示している。これがテクストにおける水平性のラインの物語と言っていい。
三 記憶の堆積
水平性のラインを辿ってきた。それが並び立つ複数の推しの物語を示しているのだとすれば、垂直性のラインはどのような物語の系列を象徴しているのだろうか。それは、あかりのなかの推しの記憶の意味を辿る道になるだろう。
そのラインが垂直たるゆえんは、あかりにとって推しが肉体をまっすぐに貫く「背骨」であるがためであった。「みんなが難なくこなせる何気ない生活もままならなくて、その皺寄せにぐちゃぐちゃ苦しんでいる」あかりにとって、推しを推すことは絶対的な「生活の中心」であり、生きるための動力源である。
あかりのそうした生きづらさは、「ふたつほど診断名」がつく病を抱えていることと、それによる周囲の無理解による。記憶に困難を抱え、バイト先のオーダーや三人称単数のエスが上手く覚えられないことや、それにともなう肉体の「重さ」のことを、あかりの担任は理解することはなく、高校中退にまで追い詰められる。
自らの記憶にそうした困難を抱えるあかりにとって、しかし中心となるのが、推しについての記憶である。
人生で一番最初の記憶は真下から見上げた緑色の姿で、十二歳だった推しはそのときピーターパンを演じていた。あたしは四歳だった。ワイヤーにつるされた推しが頭の上を飛んで行った瞬間から人生が始まったと言ってもいい。
あかりの記憶の起源は推しの記憶なのである。記憶することにかんして困難を抱えているあかりにとって、このことがもつ意味は重い。推しがあかりの頭上を飛び、彼女を真下に捉え見下ろすイメージ。あかりにとっては時間的にも空間的にも、直線的な距離を垂直な位置から捕捉する推しの存在が絶対的なのだ。垂直性のラインがあかりの記憶の意味を導くとは、このようなことを指している。
そうした垂直性をもつ推しの記憶は、堆積するものとしてテクストでは存在している。片付けに支障があるあかりの部屋は散らかっているが、推しのメンバーカラーである青で「徹底的に青く染め上げ」られており、このように記述される。
この部屋は立ち入っただけでどこが中心なのかわかる。たとえば教会の十字架とか、お寺のご本尊のあるところとかみたいに棚のいちばん高いところに推しのサイン入りの大きな写真が飾られていて、そこから広がるように、真っ青、藍、水色、碧、少しずつ色合いの違う額縁に入ったポスターや写真で壁が覆い尽くされている。棚にはDVDやCDや雑誌、パンフレットが年代ごとに隙間なくつめられ、さらに古いものから地層みたいに重なっている。新曲が発表されたら、棚のいちばん上に飾られていたCDは一段下の棚に収められて最新のものに置き換わる。
部屋の全体を占める推しの存在は、サインを中心にしてあかりの部屋のヒエラルキーを形作っている。棚に飾られた推しのグッズは「地層」のようにして積み重ねられており、それは推しの推しとして積み重ねてきた時間の束となっている。ここにあるのはあかりが集めてきた推しのグッズとそれにまつわる記憶のみならず、いわば推しの物語が垂直的な時間の層で積み重なり、推し自身の記憶の層として堆積しているのだ。あかりと推しの記憶は垂直に堆積するものとして空間を占め、それはあかりの存在の寄る辺となっていると言えるだろう。
このように、堆積するものとしての時間と空間や記憶が、テクストを貫く垂直性のラインが導くモチーフなのである。だが、それはあかりと推しの部屋だけではない。
ため息は埃のように居間に降りつもり、すすり泣きは床板の隙間や箪笥の木目に染み入った。家というものは、乱暴に引かれた椅子や扉の音が堆積し、歯軋りや小言が漏れ落ち続けることで、埃が溜まり黴が生えて、少しづつ古びていくものなのかもしれない。その不安定に崩れかかった家はむしろ壊されることを望んでいるようなところがあった。
あかりの家族の空間としての家そのものが、堆積するものとしての本性を露わにして語られているのである。それは時間とともに「少しづつ古びていくもの」であり、新曲が発表されるたびに新しく入れ替わるあかりの祭壇の推しとは、まったく時間のサイクルが正反対に異なる存在なのだ。あかりの家は循環的に記憶が再生され、生まれ変わるものではないのである。
なおこの家の崩壊は、あかりが月経や妊娠といった自身の肉体のリプロダクションを拒んでいることとも無縁ではないだろう。あかりの家と同様にあかりの肉体自身も「少しづつ古びていく」ことに苛立ちを感じつつも、おそらくそれが次第に破壊されるがままになっている。このままいけば、あかりが子供を産むこともないであろうことを感じさせる。こうした記憶の堆積の裏ではたらくリプロダクションの忌避が、テクストに隠されたテーマでもあると言える。
実際、祖母が死んだのちは、あかり自身も引きこもるようにして祖母の家に逃れ出る。垂直な家族の系譜を逆行するようにして、破壊されつつある家族の家から逃走することは、ほとんどあかりの宿命のようでもあった。なぜならば家や家族というハコこそが、テクストのなかでもっとも垂直性のラインとしてあかりに重責として抱え込まれる入れ物だったからである。
実際、あかりの生きづらさの原因である病の無理解は、真っ先に家族から発せられるものであり、それが根本の原因でもある。病のために「普通」に生活を送れないことをあかりは訴えるが、父は「またそのせいにするんだ」となじる。水平性のラインが引くコミュニケーションでは理解可能性が担保されていたが、ここで垂直性のラインが引くコミュニケーションによって現れているのは、そうした成員のあいだの理解不可能性である。家族は「何もわかっていない。推しが苦しんでいるのはこのつらさなのかもしれないと思った」。推しのつらさが、家族のなかでの理解されがたさに重なるようにして、あかりには体験されている。
こうした垂直的に積み重なる家族の間柄でおこるコミュニケーションのすれ違いは、系譜の上で幾度もそれが積み重なったことが原因である。「父の海外への転勤に一家がついていくことに反対した」あかりの祖母について、あかりの母は「恨み言」を吐き出す。「母は散々、祖母にうちの子じゃないと言われて育ってきたらしい」。おそらくあかりはこのような呪詛を日常的に聞かされているのであろう。このような間のないコミュニケーションが垂直的な系譜の上で繰り返されてきたのが、家や家族の軋みの原因なのである。そしてその矛盾はまた「業」のようにあかりにも積み重なる。
このように、ちょうど水平性のラインが導くモチーフを正反対に逆転させたような、様々に積み重なり記憶や時間の層をつくる堆積するものの物語が、垂直性のラインが導くモチーフなのである。家族をはじめとして周囲とのあいだで浮かび上がるコミュニケーションの苦しみや軋みは、「背骨」たる推しに「業」として積み重なり、集約されていく。最終的にその骨はあかり自身によって破壊されることになるのだが、ではその過程はいかにして成立するものなのだろうか。
四 推しと傷跡
水平性と垂直性が導くラインに従って、推しとあかりの存立する記憶を辿ってきた。それらは異なる軌跡を引くラインではあるが、しかし冒頭部で予兆されたように、ときに重なるラインの交叉こそがこのテクストの主題である。では、それらはいかにして交わるのだろうか。その交点に、あかりの身体の再生として帰結する小説の論理の結末もあるはずだ。
それぞれ異なるモチーフの連なるラインを論じてきたが、テクストにおいて、そうしたラインはそのものずばり何で現されているのだろうか。
ベッドの下をあさると、埃にまみれた緑色のDVDが出てきた。子どもの頃に観たピーターパンの舞台のDVD。プレイヤーに吸い込ませると、カラーのタイトル映像が無事に映し出された。傷がついているのか、時折線が入る。
あかりは、部屋に埋もれた記憶の古層を手繰るようにして、推しのDVDを発見する。それは先に述べたようにあかりの記憶の起源であり、推しとともにある生のはじまりだった。推しが映し出されたDVDには、傷の線分が混じり込む。このラインが連なるテクストにおいて一番の象徴こそが、この推しのDVDに痕跡として刻まれているような、傷跡としてのラインである。
なぜか。それは実際、あかりがこのDVDを観たときに感じるのは身体を走るリアルな衝撃だったからである。それはどのようなものだったのか。
真っ先に感じたのは痛みだった。めり込むような一瞬の鋭い痛みと、それから突き飛ばされたときに感じる衝撃にも似た痛み。窓枠に手をかけた少年が部屋に忍び込み、ショートブーツを履いた足先をぷらんと部屋の中で泳がせたとき、彼の小さく尖った靴の先があたしの心臓に食い込んで、無造作に蹴り上げた。この痛みを覚えている、と思う。高校一年生の頃のあたしにとって、痛みはすでに長い時間をかけて自分の肉になじみ、うずまっていて、時折思い出したように痺れるだけの存在になっていたはずだった。それが、転んだだけで涙が自然に染み出していた四歳の頃のように、痛む。
あかりが推しから想起するのは、身体を走る具体的な痛みである。そうした痛みは高校生のあかりにとっては、記憶の古層に堆積した、埋もれた感覚であった。しかし推しと出会った衝撃は記憶の古い傷跡を動かし、現在時のあかりに痛みとともに受肉していくのである。傷跡として疼いていたあかりの身体は、推しとともに痛みを感じる存在へと変化していくのである。あかりの身体はこのような傷跡とともにテクストに立ち現れていくことになる。
テクストにおいて、記憶とはこうした傷跡に響きあっており、それを想起する痛みが身体に現在時として蘇る。こうした記憶はなぜ傷跡と結びついているのだろうか。國分功一郎は人間が退屈に耐えられない理由を解明するために精神医学や当事者研究の知見を援用しながら、こう述べている。人はサリエンシー(人を興奮させる刺激)を避ける方向に生きているが、それに出会った場合は慣れようとする。だがその作業は完全に遂行されるものではなく、いくつかのサリエンシーは痛みの記憶として身体に堆積する。人はそうしたサリエンシーが不快であるためそれを避けて理想的な環境を作ろうとするが、実際にそうした環境が訪れると記憶に堆積したサリエンシーの記憶を自己反省として参照してしまうのだという。慢性的な痛みをもつ人は、とくにこうした痛みの記憶の参照が激しくなっている状態だという。國分は、「常にサリエントな状況に置かれ、落ち着いた時間をほとんど過ごさずに生きてくることを余儀なくされた人は、自らが直面したサリエンシーに慣れることが困難であっただろうから、何もすることがなくなるとすぐに苦しくなってしまう」と述べ、人が退屈に耐えられないのも、何もしていないときに痛む記憶がサリエンシーとして人を悩ませるからではないかとまとめている。よって國分は、記憶とは傷跡なのだと名付けている(8)。
あかりが日常に退屈していたかどうかはわからない。しかし、病によって周囲との間に軋轢として日常的な痛みを感じていたからこそ生きづらさを感じていたのだし、その痛みは語られるように記憶に堆積した古層から発せられているものである。何より「自分の肉体をわざと追い詰め削ぎ取ることに躍起になっている自分、きつさを追い求めている自分を感じ始め」ている彼女は、「業」のように推すことの日常の苦しみを語っていたのだった。あかりがそこで出会うのは、刺激として記憶の傷跡を襲う推しの存在なのである。國分の説明する記憶と傷跡の理論は、こうしたあかりの状態を上手く意味づけることができるだろう。
そしてここからそれ以上のことが言える。その傷跡が個人によって異なる以上、推しはそれぞれの主体によって異なる痛みとして傷跡をなぞりながら身体に現れ、受肉してゆく。ならばこう言えるだろう。推しとは主体の傷跡そのものなのだと。これこそ、「推し、燃ゆ」が推しを傷のラインと結びつけて語る意義なのではないだろうか。
テクストからあかりの傷の意味を確認しておこう。あかりにとって抱えられた傷跡は、どのように推しの真幸の存在と結びついていたのだろうか。
ピーターパンは劇中何度も、大人になんかなりたくない、と言う。冒険に出るときにも、冒険から帰ってウェンディたちをうちへ連れ戻すときにも言う。あたしは何かを叩き割られるみたいに、それを自分の一番深い場所で聞いた。昔から何気なく耳でなぞっていた言葉の羅列が新しく組み替えられる。大人になんかなりたくないよ。ネバーランドに行こうよ。鼻の先に熱が集まった。あたしのための言葉だと思った。
あかりは、病を抱えることによって、家族をはじめとする周囲の無理解に晒されていた。そのことによる生きづらさがあかりには傷跡として刻まれている。その傷跡はあかりにとって「大人になんかなりたくない」という拒絶の意志として顕れている。だからこそ、就職をめぐる父との諍いでも、「理路整然と」「働かない人間は生きていけないんだよ」と説く父に対して、あかりは「なら、死ぬ」と切って捨ててみせるのではなかったか。そのようにして生まれた傷跡が、ピーターパンとしてネバーランドに生きる真幸という推しの形と切り結ぶことになったのである。あかりと真幸の推しの関係とはこのような関係なのだ。
記憶の形も、生きづらさを抱える傷跡も、個人によって特異なものであり、同じものはない。だから、先に水平性のラインを辿ることで論じたように、推しは主体によって必然的に複数の推しとして現れることになる。その推したちがそれぞれの主体の記憶のなかで結びつき、また他人の異なる推しと出会う瞬間が、複数のラインが交叉する時間なのである。
そしてその瞬間はテクストにも訪れていた。推しのラストコンサートが終わった直後、あかりはトイレに駆け込む。
入ると鏡張りの白い部屋に色がひしめいている。緑のリボン、黄色のワンピース、赤いミニスカート、泣いて赤くなった目許にファンデーションを叩きこんでいる青いシャドウを乗せた女性と鏡越しに目が合ったような気がし、その視線の糸を引いたまま、次の方、と案内係の声に示された個室に入った。ばらばらと肩にかかった髪の毛先にまで興奮が残っている。興奮は、耳の後ろをさらさらとあたたかく素早く流れ、心臓をせわしなく動かす。
さまざまな色に染まったコーディネートは、まざま座のそれぞれのメンバーカラーである。あかりは、推しのカラーである青のシャドウの女性と出会い、鏡越しに視線を合わせたような気がする。その女性はトイレから出たときに携帯を触っていた。もしかしたら、この女性もSNSで推しの最期を見届けたその感慨を投稿しているのかもしれない。ひょっとするともともと推しの行為に憤り、炎上に加担していたのかもしれない。しかし、鏡越しというフィクショナルな自己が映る領域で視線を交わしてその目をのぞき込むとき、そこにあるのは「泣いて赤くなった目許」であり、それはその女性の真幸という推しへの、何とも形容のつけることのできない最大の感情が込められた涙をうかがわせる痕跡であるのだ。その痕跡は彼女の推しという傷跡そのものであり、その傷跡に引かれるようにして、あかりとのラインが「糸」として交叉する。あかりが出会うのは、こうした青いアイシャドウに乗せられた他人の異なる推しの姿であり、それを身体に受肉した他人の傷跡の形である。それがラインのようにして他人と交叉するのだ。
そのラインの瞬間的な結ぼれに触れることがあかりにとって他人の推しを聴く時間なのである。それは他人の疼いた傷や苦しみを想起させるだろう。こうした語りが読者に届けられることが、「推し、燃ゆ」が表象する、他人の推しを聴くことの方法であり意味なのである。だから、他人の推しを聴くこととは、他人の傷跡の形に触れることなのである。その傷跡とともに、記憶の古層から傷が生成した瞬間を想起し、想像し、推しはかることが、聴き手の倫理になるのだと言えるだろう。それを、テクストの語りは示している(9)。
しかし、そうして生まれる交叉したラインは、推しの芸能界からの引退と結婚という形でほどかれる。あかりは、そのとき途切れたラインの先端に何を見ていたのだろうか。あかりは、炎上で特定された推しのマンションへと赴き、部屋の一つを眼前に見据えながらたたずむ。そのとき、そこから女性が顔を出す。
あたしを明確に傷つけたのは、彼女が抱えていた洗濯物だった。あたしの部屋にある大量のファイルや、写真や、CDや、必死になって集めてきた大量のものよりも、たった一枚のシャツが、一足の靴下が一人の人間の現在を感じさせる。引退した推しの現在をこれからも近くで見続ける人がいるという現実があった。
もう追えない。アイドルでなくなった彼をいつまでも見て、解釈し続けることはできない。推しは人になった。
あかりを傷つけるものは、「たった一枚のシャツ」や「一足の靴下」であり、それは推しの推しとしての生をこれ以上推しはかることのできない、解釈不可能なものである。それはもはやあかりの傷跡に触れることはない。視点を変えて言い換えれば、それはあかりの推しという傷跡からの回復の過程でもある。しかし、それが逆説的にも推しの生との絶対的な隔離として、あかりの生を傷つけるのである。
こうした傷跡からの回復の過程が、最終的に骨に見立てた綿棒の破壊に行き着くのだ。それは想像上のあかりの自死であり、推しを失ったあかりの喪の過程でもある。それは悲痛でもあるが、あかりの新たな「背骨」は変形を遂げ、異なった身体として再生する。こうした再生を果たしたあかりの身体はいわば「新たなる傷つきし者」であるが(10)、彼女はもはや推しの傷跡を業のように参照し、傷つくことはないだろう。なぜならば、推しから最後に与えられたのは、推しの解釈不可能なものと「ずっと深いところで」繋がっている力だからである。それは、アイドルとしての推しが人間個人として生まれる瞬間である。その個人そのものである解釈不可能なものと結びつくラインは、あかりの新たな寄る辺になるだろう。推しの解釈不可能なものに触れること。それが、推しの声を、そしてテクストにおいてそれを語る語り手の声を聴くことの、最後の意味だろう。そのラインに到達するまでが、このテクストの時間だったのである。
【注】
(1)ジョー・ブスケ『傷と出来事』(谷口清彦・右崎有希訳、河出書房新社、二〇一三)、六一頁。
(2)「芥川賞選評」(『文藝春秋』第99巻3号、二〇二一)、三三四-三四三頁。
(3)小川公代「不文律を貫く巡礼者――宇佐見りん論」(『文学界』第75巻3号、二〇二一)、一八七頁。
(4)「創作合評」(『群像』第75巻9号、二〇二一、五五三頁)において、亀山郁夫は小説のラストについて「自死を思わせるモチーフ」だと発言している。
(5)この場面の直前で祖母の火葬と残った骨のことが回想されており、また綿棒の白く細い棒の形状からして綿棒=骨であることは象徴的に自明であり、わざわざ「お骨をひろうみたいに」と語られるのは、やや読者に対して親切にすぎる印象も受ける。しかしそれを逆転させるなら、この場面でも語り手の位相が逆接的にまたしても強調されているのだと捉えることもできるだろう。
(6)ティム・インゴルド『ラインズ』(工藤晋訳、左右社、二〇一四)。
(7)鷲田清一『「聴く」ことの力 臨床哲学試論』(阪急コミュニケーションズ、一九九九)、七六ー七七頁。
(8)國分功一郎「傷と運命」(『暇と退屈の倫理学 増補新版』太田出版、二〇一五)、四一三ー四三七頁。
(9)こうしたあかりの病やそれにかかわる困難を提示する語りを、「傷ついた物語の語り」と呼ぶこともできるだろう(アーサー・W・フランク『傷ついた物語の語り手』鈴木智之訳、ゆみる出版、二〇〇二)。フランクは傷ついた状態を語ることは病の混沌や回復の過程をはらみ、それが聴き手に届けられることが癒やしにつながるのだと論じている。「推し、燃ゆ」でも、たとえばあかりがバイトで働くシーンに明確なように、その語りはときに混沌をはらむ。この小説の文体は象徴的に病んでいるのである。しかし、その語りを聴く聴き手を要請することを語るのがこの小説の語り手であった。ならば、この聴き手を求める語りの過程こそ、フランクに倣えば癒やしの瞬間なのである。この小説の語りと文体はそのようにして構造化されているといえる。
(10)カトリーヌ・マラブ-『新たなる傷つきし者 フロイトから神経学へ、現代の心的外傷を考える』(平野徹訳、河出書房新社、二〇一六)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
