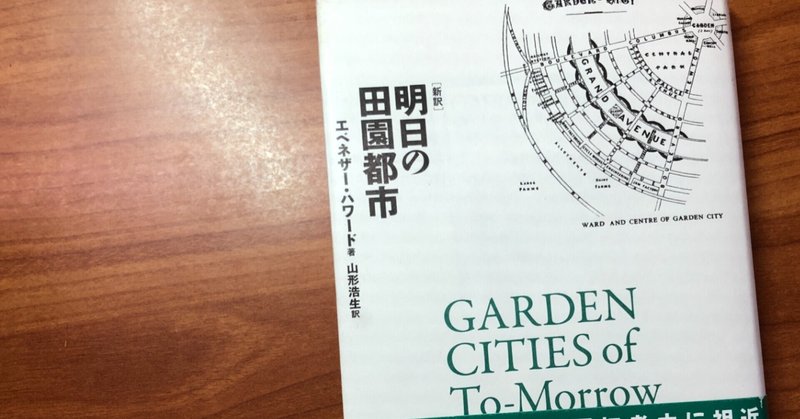
ハワードの「田園都市」から考えるライフスタイルのこれから
1. はじめに
サタデーブックスで毎月最終土曜日に開催しているオンライン読書会「サタデーブッククラブ」。いつか読もうと積読になっている小難しい本を、1冊ずつ課題図書にして、読む機会を作っている。2021年3月27日(土)の課題図書に選んだのは、19世紀末にイギリスのエベネザー・ハワードが執筆した都市計画の古典『明日の田園都市』。
「郊外の農村地域に新しい都市をゼロから作り、大都市から人口を移動させる」という趣旨の田園都市構想は、その後の世界の都市計画に大きな影響を与え、渋沢栄一が開発に携わった田園調布(東京都)や、東急グループが高度経済成長期に開発した多摩田園都市(同)も「田園都市」を名乗っている。1970年代に大都市近郊に作られた「ニュータウン」もハワードの影響を受けた発想だと言えよう。同書は都市論に関心のある人や、ディベロップメントや建築に携わる人は必ず知っている頻出図書だ。
だが、「田園都市」は知っていても実際にハワードの著作を読んだことがあるという人とは会ったことがなかった。
本稿は、私自身が知ったかぶり状態を脱するために、まずは読んでみて要約をまとめるものである。そして、『明日の田園都市』をスタート地点に、昨今のコロナ禍や2拠点居住のムーブメントを踏まえた「じゃ、どうずればいいのか?」「次はどうなる?」を考えてまとめてみるものとする。
2. 『明日の田園都市』の要約
今回読んだのは2016年に鹿島出版会から出版された新訳版(訳:山形浩生)だ。1968年にSD選書として出版された旧版があるが、建築に携わる年上の知人に聞いた話では、そちらは原著で読んだ方がわかるというくらいの悪訳らしい。だから読んだことのある人が少ないのだろう。新訳版を読んだ感想としては、本にしてみれば分厚いが1章ごとの文章量は少ないし、読むのが難しい内容ではなかった。
それもそのはず。1898年に原著が『To-Mrrow: A Peaceful Path to Real Reform』として刊行された目的は、ハワードが発明したアイデア”Garden-City”を実現に移すために、資本家たちに出資を呼びかけるためだったからだ。いわば、本書は長いプレゼン資料である。
要約にあたっては、私が通読して記憶に残った箇所をまとめている。また、用語も含めて曖昧なところも勢いで書いているので正確性は保証しないことはあらかじめお断りしておく。
(1)エベネザー・ハワードという人間
ロンドンで自営業を営む家の子供として生まれる。その後、アメリカに入植し農業を始めるもうまくいかず、シカゴで速記者の仕事に就く。イギリスに帰国してロンドンで速記者の仕事を続けながら、ものづくりが好きなことがこうじて新型タイプライターの開発をするなど発明家としても活動を行う。
都市計画についても、発明のひとつとして位置付けられる。本人は学者でもないし、建築家でもない。役人でもなければ政治家でもない。アマチュアの人だった。田園都市によって有名になってからも、威張ることはせず、温厚で庶民的な人だったそうだ。
(2)発明の端緒は「ロンドンの大都市問題をどう解消するか」
19世紀末という時代は、1765年の蒸気機関の発明、1804年の蒸気機関車の発明などに代表される「産業革命」がひと段落ついた時代だ。産業化が進み、農村で農業を営んでいた人たちが都市に流入し工業労働者として定着をした。その結果、ロンドンの住環境は悪化し、スラムが広がり、労働者たちは過重労働に苦しめられていた。資本主義の負の側面にスポットが当てられ、社会主義運動がヨーロッパで広まった時代でもある。
そんなロンドンの都市問題を解決する、というのがハワードの構想の出発点だ。ロンドンの姿は、工場煤煙に悩まされ、高い家賃の支払いに追われ、狭くて上下水道もろくに整っていないような場所で不健康な暮らしを送る人々の姿だ。
(3)解決策としての「田園都市」
田園都市構想を一言で言うと「畑以外なにもない原野に新都市を作ってロンドンから人口を移動させる」というもの。ハワードは「町(TOWN)」「いなか(COUNTRY)」に対する第3極として「町・いなか(TOWN-COUNTRY)」を構想した。
委員会(自治体)を作って出資を集め、地価の安い広大な土地を購入して都市を作り、移住してきた新住民たちから集めた地代を元に、30年で土地購入に当てた借入を償却するというプランだ。人口は3万人。広さは24キロ平方メートル。24キロ平方メートルは、東京都立川市と同じくらい。東京ディズニーランド48個分。
何もないところにゼロから計画された都市なので、機能的で衛生的だ。中心部には広場と公共施設があり、買い物ができる商店エリアがあり、その外側にゆったりとした住居があり、公園があり、工場や作業場がある。上下水道や電話電信・電力は共同溝で配置。衛生的なインフラが整う。文化施設や教育機関もきっちりと配置されて運営される。
都市の境界はスプロールしないように厳密に定められ、境界の外には農業地域が広がり都市部に新鮮な食料を供給するとともに、都市住民にとってのレクリエーションの場にもなる。24平方キロメートルは農業地域も含めた自治体全体の面積で、円形につくられる都市部の面積は4平方キロメートルほどだ。円の中心から外周までは1130メートル。
新宿駅を中心にしたら東は新宿御苑の東の入り口「大木戸門」くらいまで。西は新宿中央公園のまんなかくらいまで、というスケール感。
銀座数寄屋橋交差点を中心にしたら北は大手町、南は汐留くらいのスケール感。
ここに、住居も、公共施設も、公園も、学校も、商業も、職場も含まれるのだから、徒歩や自転車で行ける範囲に収まっている印象だ。
(4)「田園都市」の特徴
①社会主義と個人主義の両立
今で言うところのイノベーションを重視。全体主義的にお上が計画した都市で計画されたライフスタイルをおくるのではなく、個人の創造性が発揮できる環境としての田園都市を構想している。(共産主義やヒッピーのコミューンと誤解されないように説明を重ねている)
②地域内に循環する経済
1度にドーンとつくるのではなく、少しずつ都市開発を進める。そうすることで、家を作るお金が大工さんにまわり、大工さんが地域で生活のためにお金を使い、巡り巡って新しく家を立てる施主の元にお金が戻る。都市を作るのに必要な金額は大きいが、実際に流通しているお金は小さい。そして田園都市ない部で循環する。地域通貨にも通じるような発想。
③委員会が地代を集めて公共のために使う
住民から信託を受けた委員会が地代・税を住民から集め、初期費用にかかった借金の利息と減価償却費を支払い、残ったお金を住民サービスに充てる。計算上はロンドンで暮らすよりも安い地代・税で、より恵まれた住民サービスを受けられるようになるとのこと。
3. 『明日の田園都市』以降の展開
本書は、プレゼン資料。企画書である。薔薇色の未来を書き連ね、妄想を膨らませる。この時点では、絵に描いた餅、空想小説に近い。
ハワードのすごいところは、実現したことだ。モデル都市として、1903年、ロンドン郊外にレッチワースが着工。1920年には同じくロンドン郊外にウェリンが着工する。
ただ、本書の時点では、当然のことながらその結果は描かれていない。大風呂敷広げたけど、実際どうなったのか知りたいところだ。
訳者のあとがきによると、いろんな主体の思惑が重なって、ハワードの描いたような田園都市をそのまま実現するには至らなかったようだ。ハワードの理想と大人の事情の現実との妥協の産物としてレッチワースとウェリンは存在するようである。
ハワードの発明の影響力は大きく、西欧にアメリカにそして日本に田園都市協会がつくられ思想は伝播していく。そして、その後の各地のニュータウン建設へと形を変えて引き継がれていった。
だが、特に20世紀後半に至っては、田園都市とその系譜にあたるニュータウンは失敗を重ね、批判に晒される。新都市をつくったものの人口密度が低くスカスカ。ご近所同士のコミュニケーションが生まれづらい。生活水準が似た住民が集まるから均質で多様性のないコミュニティになる。働く場所は大都市にあるので「通勤苦」が発生する。
アメリカでは1960年代からニュータウンがスラム化して問題になったし、日本のニュータウンは子ども世代が離れ老人だけが取り残された姥捨山状態だ。本書のあとがきにも触れられているが、N.Yの都市開発に抵抗したジャーナリストであるジェイン・ジェイコブズは『アメリカ大都市の生と死』(1961年)でハワードの田園都市を痛烈に批判している。(ジェイコブズは近年映画にもなるなど改めて注目を集めている)
ただ、失敗したのは田園都市からそのアイデアの一部を引き継いだニュータウンであり、ハワードの田園都市そのものではなかったことは注釈として加えておく。(ハワードの理想は結局のところ完全な実現をみていない)
21世記の最初の20年は、大都市が再評価された時代だったと思う。ニューヨークやポートランドの、かつては倉庫街だったような場所が新しい機能を持った街へとリデザインされ、アーティストやクリエイティブな才能を持った若いプレーヤーが集まり、活気のある街をつくる。
日本でも、東東京なんて言われる、蔵前あたりが注目を集めた。
都心部には新しいオフィスビルがニョキニョキと立ち並び、ファッションとカルチャーの最先端の発信地としても、その力は衰えない。リーマンショックでぶっ飛んだのは、むしろ車社会の郊外ではなかったか。
所有しないライフスタイル、IT技術の進歩と社会の変化。組織から個人へ。そんな時代の流れは、郊外から都心回帰へと人の心と住居を向かわせたように思う。
2020年に迎えたコロナ禍にあって、再認識したのは都市の価値の方だった。多様な人との偶然の出会いがあること。人が集まりそこから新しい何かが生まれること。よい気は人の集まるところに生じる。コミュニティではなくアソシエーション。それらはニュータウンではデザインしにくいものだ。
良い都市は人を引きつけ、ますます都市力を向上させていく。人口3万人の小さな町では、それはなし得ないことだろう。大都市問題の解消も進み、住環境はかつてのロンドンのような非人道的な状況には置かれていない(狭い高いは変わらないが、だいぶマシにはなっている)。
まとめると、
(1)産業革命で大都市問題が発生
↓
(2)田園都市&ニュータウンの建設
↓
(3)大都市への回帰
と時代は変遷してきた。
4. これからの都市はどうあるべきか
それでは、都市はどうあるべきなのか。ここからは私の持論を展開する。
それを考えるにあたっては人間の暮らしがどうあるべきかを先に考えるべきだろう。どんな都市を作るのかは手段として想像すべきだ。
ーーー
(1)自らの人生にオーナーシップを持つ人が増える
キーワード:個性の尊重/贈与的関係性/シェアリングエコノミー/LIFE SHIFT/イノベーション
いい大学いい会社で定年まで、という人生モデルは崩れた。というか、そんな呪縛から人間が解放された。もっと一人ひとりが自由に生きるのが当たり前の世の中になる。なってほしい。
そのためにお金に依存しない経済と生活のあり方を作るべきだと思う。生活のために何かを犠牲にして働くようなことから、自らを解放するために。
(2)人間中心主義
システムに対する人間中心主義。
キーワード:×工業部品としての人材/使用価値を評価される存在ではなく存在が受容される/社会的包摂/セーフティーネット
(3)環境負荷を減らす
キーワード:SDGs/自給自足(食とエネルギー)/フェアトレード/ゴミを生まない/水資源を守る
ーーー
これまでの都心回帰からは、また一歩変化が必要だと思う。大都市には現在も問題がある。「消費はあるが生産の場がない」というのは歪だ。暮らしが外部に依存している。お金を出して買う比重が高い。消費者であるにもかかわらずクリエイティブな生活をしているとカンチガイしている。その暮らしは、目には見えにくい誰かの暮らしを犠牲にして成り立っている。犠牲にされるのは都市内外のエッセンシャルワーカーや、外国の低賃金労働者。そして地球の環境だ。大都市の生活を成り立たせるために、原発も必要というロジックがまかり通ってしまう。
結局、ハワードの田園都市はうまくいかなかった。それらしいモデル都市はできたけれど、それも完全ではないし、世界に広がらなかった(広がった亜種は失敗した)。
だが、発明家としてのハワードの活動から、私は学ぶことがあると思う。
都市の問題・人間の暮らしの問題を解決するために構想を打ち立てて実現に移す姿勢。ハワードに倣って、次の時代の都市と人間のあるべき暮らしを、自由に想像してみる。その想像力が私たちは試されている。そして、ハワードと同じ轍を踏まないよう現実的な実行力をも。
5. 新たな「町・いなか」をつくろう〜大都市の「町」と大都市近郊の「いなか」2拠点居住〜
コロナウィルスの流行は、数年で終息する。いまは「おうち時間」が重要でも、いずれ大都市(ハワードのいうところの町)の力は戻ってくる。一方でテレワークができることが実証されて、働き方はコロナ以前とは変わる。無駄な時間や手間が排除され大事なことに集中できるようになる。この時代には、「町」と「いなか」のいいとこどりが実現できるのではないだろうか。
前提として、東京23区で町といっても、人間が集積するから価値が出る「町性」があるのはその一部だ。私は以下の3類型に相当するエリアを「町」と呼びたい。
①消費とカルチャーの町:新宿・渋谷・代官山中目黒・上野浅草など→これは残る。ワクワクするし、遊びに行きたい町だ。
②仕事の町:大丸有・新宿副都心など→これは弱めていい。仕事の場所の価値は相対的に下がるので。ビジネスセンターは残しつつ、床面積は減らしていい。
③暮らしの町:世田谷とか目黒とか杉並とか。暮らしとカルチャーの近接した町。
※下町は、どちらかというと埼玉や千葉のベットタウンに近い。機能として住む場所に偏っているので。
「町」の魅力は、上にも書いたように、人が集まり交流が生まれるところにある。多様な人が集まるからこそ、バイブスが合う仲間とも出会うし、人生のロールモデルにも出会う。メンターにも出会う。男女の出会いだってある。新しいビジネスや社会変革のためのプロジェクトも起こる。チャンスが舞い込んできやすい。そして、合わない人とは付き合わなくていい自由がある。一方にこの「町」がある。
そしてもう一方には電車で1時間圏内の「いなか」がある。飯能や奥多摩、三浦半島あたりだろう。「いなか」には「いなか」の魅力がある。
地価が低いから住のコストが低い。静かで空気が美味しい。お金に頼る割合を減らせるし、食もエネルギーも比較的手の届くところに置いておける。すると暮らしが自由になる。時間が生まれる。ものを考えるゆとりができる。
ハワードは田園都市という「町・いなか」を発明したが、私は「片道1時間の2拠点生活」として「町・いなか」を作ってみたい。
✴︎タイプA:「町」に週の3/4、「いなか」に週の1/4。
想定するのは、主には独身者。基本的には「町」で働き遊び、(文化やアイデアとして)新鮮な空気を取り入れる。OFFの日には「いなか」で遊んだり休んだり。
「町」では賃貸の単身マンションに住んで、「いなか」ではゲストハウスを定宿にする。
「いなか」に拠点を持つことで、「いなか」の農業生産者と繋がり、食べるものは週に1回ペースで「町」に持って帰れる。災害その他、いざという時の逃げ場にもなる。
将来的にライフステージが変わったら、タイプBへと移行できる。
✴︎タイプB:「町」に週の1/4、「いなか」に週の3/4。
想定するのは、主にファミリー。あるいはものづくりのクラフトマンや、自然からインスピレーション受けたいクリエイター。
基本的には「いなか」の環境に住んで暮らし、週に1回は泊まりで「町」に行って仕事をしたり交流をしたりする。「いなか」では持ち家の一軒家に住んで、「町」では仕事場やゲストハウスに滞在する。(ワークスペース付きのゲストハウスなんてあったらいい)。
「いなか」で安く、のびのびと子育てしながら、一方で、「町」も犠牲にしない。テレワークが進んだから、できる人も増えるのではないか。
タイプAもBも、生活の比重が重い方に本宅がある。そして、「町」と「いなか」、比重の軽い方にも決まった滞在場所を持つ。部屋を一つ借りるのはコスト的に重いと思うので、ゲストハウスのような宿泊施設があると良いと思う。そこが交流拠点にもなり、「町」にしても「いなか」にしても人的繋がりのハブになる。「いなか」の中にも「町性」のある場所がある。
田園都市のように、大風呂敷を広げて都市開発をするのではなく、ソフト面でライフスタイルをつくっていければ良いと思う。
西埼玉に拠点を置いている私の視点では、西武池袋線の端っこの飯能市と、直通電車で繋がる副都心線・東横線のどこかの町と、一つずつ滞在拠点を作って往復関係を産んでみたい。
滞在拠点には、寝る場所があり、交流する場所があり、働く場所がある。ゲストハウス&バーラウンジ&コワーキングスペースを合わせたような施設。東京の方にはありそうだし、1箇所になくても使う人が組み合わせることはできると思うので、まずは「いなか」側だと思っている。
6. まとめ
田園都市は、その時代の社会問題を解決する都市計画として、発明家・ハワードが提唱して広めた。日本では鉄道会社が換骨奪胎して似て非なるニュータウンを作った。残念なことに、そういう地域は面白そうには思えない。全てお膳立てされた地域には自由がないから。
コロナ禍で郊外が見直されている今だからこそ、「いまこそハワードに立ち返ろう!」的なことを『明日の田園都市』を読む前までは思っていた。だが、読んでみて、田園都市は田園都市で突っ込みどころ多かったと思う。だから、その時代その場所で姿を変えて実行されていくのは、むしろ肯定されるべきことだなと思うようになった。
ハワード自身も計画がそのまま実現するとは思ってはいなかったんじゃないだろうか?発明家はプロトタイプを作って検証してまた作るを繰り返して、課題解決に近づいていくものだから。
上に書いた未来の話は、まだまだ妄想段階だ。だが、願って口に出していれば何かの形にはなる。それはハワードの姿が教えてくれることだと思う。
「人はいかにして自分を知りうるのか? 絶対に内省では不可能だー行動によるしかない。汝が、己の責務を果たすべく努めるやり方によって、汝は己のうちにあるものを知るであろう。しかしながら己の債務とは何か? その時の目先の用事である」
『明日の田園都市』に引用された、ゲーテの言葉だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
