
故きを温ねて(JR最長片道切符の旅2022夏第2日)
昨日からいよいよ始まった最長片道切符の旅。前回の記事を見ていない人はそちらを先にご覧ください。
昨日は網走で終わりました。今日はまず釧網本線の始発で釧路へ向かいます。その後は根室本線、富良野線、函館本線、室蘭本線を乗り継いで、ルート外にある苫小牧を目指します。今日は釧路湿原や富良野といった北海道を代表する観光地を通っていく予定です。

早く着きますがそうはいきません
雨の朝
2022年8月2日。午前6時の網走は気温14℃、降水量3mmの冷たい雨が降っていました。8月に10℃台とは今まで真夏日の東京で過ごしていただけに、とてもとても同じ日本の夏とは思えません。
網走の駅にはコンビニや駅売店の類はありませんが、待合室に飲料水の自販機がありました。こうも寒いとつめたい水は欲しくありませんが釧路まで補給ができないので買っておきます。脱水症状は列車旅の天敵です。このときから気を付けていれば最後の最後でつらい目に遭わなくて済んだのですがね…

釧網本線4725D 釧路行き 網走(641発)→釧路(1000着)
昨日網走に来た時は駅舎と直結している1番線に着きましたが、今日はこ線橋を渡った先の2番線から出発です。特急列車が一番便利なホームに着くのは昔からの伝統でしょうか。

四国にはよく似た車両がおり、こちらも現役です。
2番線にはすでに列車が待っていました。網走から釧路方面への初電なのですがたった1両。いまは普通列車が僅かな本数走るばかりの釧網本線ですが、かつては釧路から網走を経由して札幌へ向かう急行列車も存在しました。その列車は「大雪」といいます。そう、昨日乗車しましたね。今では「オホーツク」の補完的役割が大きな列車ですが、大雪は1960年代にはすでに存在した由緒ある優等列車なのです。
かつての北海道はまさに優等列車王国といった形相で、優等列車に使用される車両も多く在籍していました。しかし、航空路線や高速道路網が発達した現在ではもはや過去の栄光でしかありません。
さて、釧網本線で使用されているキハ54は国鉄の最末期、ちょうど急行列車の命運が尽きようとするときに製造された車両です。そのためかこの仲間には急行列車として使用された豪華な仕様の車両もいますが、本日乗車の車両は残念ながら根っからの普通列車用車両です。座席にリクライニングはついていますが肝心の座席の向きが車両の中央を向いて固定されています。ヨーロッパではこの形態が普通みたいですね。
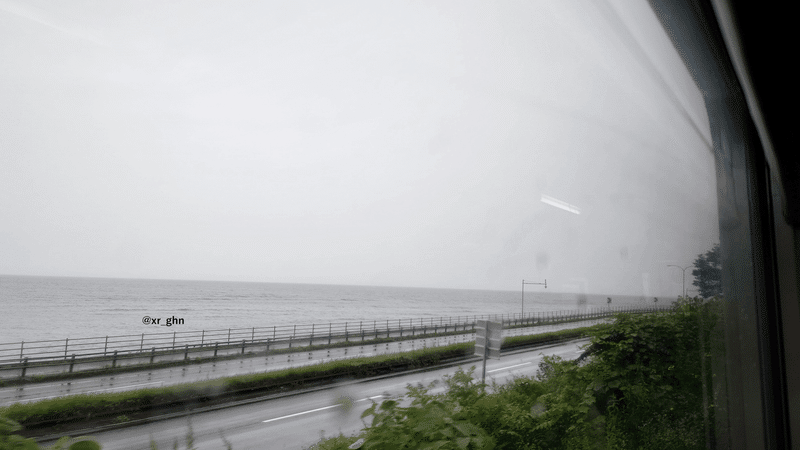
列車は知床斜里までオホーツク海に沿って進みます。雨の今日はなんだかどんよりとした空と時化た海で気分も浮きません。
道東観光の拠点である知床斜里まで進むと、ここでは列車交換待ちで4分の停車となります。しかし倒木の影響で対向列車が10分ほど遅れてくるようです。改札外にあるお手洗いを借りることにしました。

対向列車の遅れは増大し結局12分遅れで知床斜里を出発しました。海沿いを進んできましたが大きく方向を変えて山中を進みます。山を抜けた先で急に開けてくるとそこには釧路湿原がひろがっていました。現在でこそ環境保護が重点的に行われている釧路湿原ですが、高度経済成長期までは農地への転換が試みられていました。現代になってから釧網本線を建設したらただの環境破壊ですが、建設されたころは北海道開拓のために必要な存在であったのでしょう。いまは物流としての役割はほとんどなく、私のような観光客を迎え入れるため多くの観光列車が運行される路線となっています。

この列車を途中で降りてノロッコに乗るのも楽しいでしょう。冬にはSLが走ることでもおなじみの区間ですね。
湿原を抜けて街に出ると突然場外馬券場のWINSが現れました。釧路には地方競馬の場外馬券場J-Placeもあり、そちらでも中央競馬の馬券が買えるはずなのですが、どうしてここにWINSがあるのでしょう。
それを過ぎるとぎるとすぐに東釧路に到着。ここで釧網本線は終わり根室本線に入ります。
列車は必死の回復運転のおかげで遅れを挽回し定刻通り釧路に到着。ここでは1時間と少しの待ち時間時間があります。
かつてのにぎわい
釧路に来たら前からやってみたかったことが勝手丼です。駅近くにある和商市場でどんぶりに入ったご飯を買って、市場にあるどんぶりの具を自由に選ぶシステムとなっています。
公式サイトのクーポンを印刷していくと割引になります。
観光地では滅多に海鮮は食べないのですが今日は食べます。カニ汁の用意もあるそうです。私は地物を中心に選び、最後は店の人のおすすめの山わさびをかけました。

さすが北海道。海の幸が美味しい。山わさびが絶妙なアクセントとなっています。機会があればまた来たいところです。
和商市場の中にもセイコーマートが入居していました。この市場に来ればなんでも揃いそうですね。

戻った釧路駅の駅舎は、官民共同で建設され民間店舗が入居する民衆駅という国鉄では異例のシステムが採用されています。現存最古の駅ナカ・駅ビルといったところでしょうか。そんな駅の中にはセブンイレブンやおにぎり屋さんがあります。おにぎり屋さんは鉄道関係者をはじめ多くの人が並んでおり盛況を見せていました。
根室本線4006D おおぞら6号 札幌行き 釧路(1123発)→新得(1332着)
さて、まもなく特急おおぞらが入線するはずなのですが列車がまだやって来ていません。この列車は札幌から特急おおぞら1号として釧路に来て折り返しおおぞら6号となるのですが、そのおおぞら1号が遅れているようです。札幌から朝一番にやってくる特急ということで、釧網本線のくしろ湿原ノロッコ号も根室本線(花咲線)の快速ノサップの根室行きもおおぞらからの乗り換え客を待つために足止めとなりました。

特急より先にパトロールの警察官がやってきました。地方都市の玄関駅ではこちらもありがちな光景です。
定時から10分ほど遅れてようやくキハ261系がやってきて、時間の止まっていた釧路駅は一気に騒がしくなりました。促されるように乗り込むと、息つく間もなく出発しました。
釧路を出てしばらくの間、列車は太平洋沿いを進みます。本州でみられる太平洋とはずいぶん様子が異なり、こちらでは波が荒々しく岩を砕いています。

北海道名物のカツゲン
釧路からの乗客はあまりいませんでしたが、十勝平野に入り日本の食糧倉庫である池田と帯広に停まると、指定席はサラリーマンでほぼ満席となりました。札幌までの高速道路の整備が進んでおらず飛行機という距離でもないことで鉄道に利のある区間のようです。
さて、列車は新得に着きました。現在、この新得から札幌へ向かう主要ルートは南千歳を経由する石勝線・千歳線ルートですが、このルートが繋がるまでは富良野と滝川を経由する根室本線・函館本線ルートでした。これからその根室本線の狩勝峠越えに挑みます。
狩勝峠は日本三大車窓の一つとして知られた根室本線屈指の景勝地で、そして難所でした。現在は峠ごと新狩勝トンネルで突破しています。このため鉄道でのアクセスは永久に不可能かと思われた狩勝峠でしたが転機が訪れます。2016年の台風災害により根室本線は甚大な被害を受け、新得~東鹿越間が寸断されました。この区間の代行バスが狩勝峠の鉄道の上方にある国道を経由するのです。まさかの形での復活ということになりました。
というわけで、最長片道切符ではこのかつての主要ルートへ進みます。それでは駅の外に出ましょう。
日本三大車窓は当地根室本線の狩勝峠、篠ノ井線の姨捨、肥薩線の矢岳越えであるといわれています。路線が付け替えになった狩勝峠、利用者が少なかったため被災後も代行輸送が形骸化している矢岳越えと現状は厳しいものがあります。
根室本線列車代行バス 新得(1357発)→東鹿越(1504着)
駅の外では地元のバス会社のバスが待っていました。唯一利用しやすい時間帯、上下の特急からの接続もよい、夏休み真っ只中と好条件であるにも関わらずバスが1台のみというのがすべてを物語っています。
この区間は長らくバスによる代行が続いていますが、ついに2024年での廃止が決まりました。恐らく二度と鉄道でこの区間を移動することはないでしょう。この区間が廃線後は最長片道切符のルートは現在とは全く異なるものとなります。
さて、バスは国道38号線の難所である狩勝峠に挑みます。路肩と中央線を示す矢印が頭上に並びます。それだけではなくすべり止めの砂や非常用電話の設置位置を示す看板が目立ちます。これは相当雪深い場所のようです。
峠の途中にはリゾートホテルがあり、このバスはホテルの送迎も兼ねているようで少しだけ峠道を外れホテルに寄りました。
ついに峠の天辺付近にきました。私は進行方向右側という狩勝峠の景色とは反対側に座ってしまうというミスを犯しましたが。峠は深い靄に包まれほとんど何も見えませんでした。
道路は大型車が頻繁に通っているのか車線が多く路面もよく整備されています。時間だけはかかりますが頂上についてしまえばあとは下るだけ。まもなく映画「鉄道員」の舞台となった幾寅駅に立ち寄りました。あまりに有名だからか占冠や富良野、旭川からバスのバスがあります。ですからここはもはや鉄道で来る場所ではないのかもしれません。
国道を外れダムの横の大型バスがようやく通り抜けることができるような道を進むと東鹿越に到着です。

根室本線2482D 滝川行き 東鹿越(1512発)→富良野(1551着)
この近くで交換設備のある駅は落合駅ですが、その落合駅周辺が被災したため折り返しのできる設備のあるこの東鹿越まで列車が来ているのでしょう。周辺は駅以外に何もなさそうです。一応鉱山があるようなのですがその気配を感じることはありませんでした。
この駅に来る列車は1日に4往復半のみ。設備の関係上これでも精一杯の本数だと現在の運行が始まったときのプレスリリースにはあります。

ところでこの旅で初めてキハ40系に乗車しました。日本中で運用されていたキハ40グループですが、徐々に数を減らしつつあります。この旅ではあと何回かお目にかかることがありますのでお楽しみに。森の中から街へかけて車窓は移り変わり、そうこうしているうちに富良野に着きました。
聖地巡礼の需要
乗ってきた列車は寸断された根室本線のもう一つの終点である滝川に向けて走り去っていきました。ここからは富良野線に乗り換えですが普通列車は7分前に行ってしまいました。したがって普通列車は1時間待ちですが、今は夏の観光シーズンですからアレがあります。

富良野線9436レ 富良野・美瑛ノロッコ6号 旭川行き 富良野(1611発)→旭川(1745着)
北海道最大の観光地である富良野には様々な観光列車がこれまでも運行されてきました。中でもこのノロッコ号は、除雪に使用する機関車が牽引する名物列車です。

ノロッコ号の3両のうち自由席が2両あり、一番後ろの1両が指定席です。車両は窓を大きく開けてトロッコにすることができ外気がびゅんびゅんと入り込んできます。夏真っ盛りならよいのでしょうがこの日はあいにく涼しい気候であったためかえって寒く感じました。
車内を見渡すと天井にラベンダーが飾られています。乗車は8月上旬と沿線のラベンダー畑はどこもシーズンが終わった様子でその姿はありませんでしたが、ここでラベンダーを見ることができました。

かつて富良野のラベンダーは国鉄のカレンダーに使われたことで窮地を脱しました。近年の北海道は不況から抜け出せないながら中国で北海道を舞台とした映画「狙った恋の落とし方」が流行したことなどにより中国人観光客が押し寄せていました。今でこそ映像作品の舞台を誘致して町おこしを試みるところは多いですが、この辺りはずっと聖地巡礼特需が発生していたのかもしれません。しかし、入国制限のあったこの2022年夏は観光客の姿はほとんど見えずノロッコ号も人はまばらでした。

臨時駅のラベンダー畑駅を過ぎると車窓はラベンダー畑から玉ねぎ畑へと変わります。ここまでくると観光地というより都市近郊です。すこしネギ畑独特の臭いがするような気がします。
さらに進むと旭川近郊の住宅地という感じでもう車窓に見どころはなさそうです。真新しい高架に入ると間もなく旭川です。

昨日ぶりに旭川に来ました。昨日とは違い途中下車ができますから、駅弁を買うことにしました。いったん駅の外にでて駅弁を購入するともう発車時刻です急いでホームに上がり特急に乗り込みました。
函館本線3040M ライラック40号 札幌行き 旭川(1800発)→岩見沢(1859着)
函館本線の旭川~札幌間は北海道で一番特急の走っている区間です。旭川~札幌間の特急列車はカムイ、ライラックと稚内行きの宗谷、網走行きのオホーツクと多種多様であります。私が乗る列車はライラック号、かつてスーパー白鳥として活躍した789系で運転されます。

ライラックは6両編成で1号車の前半分がグリーン車、そして1号車の後半分は指定席となっています。ライラックは指定席を含めてこの1号車だけ他の車両にはないコンセントが付いています。指定席に乗るならこの車両だと思うのですが、とうとう岩見沢までほかに人は来ませんでした。ここで携帯の充電をしつつ駅弁を食べることにしました。

ホタテがでかくておいしい。ただ一つ一つの料理はおいしいのですが如何せん量が少ないのでそれが欠点かもしれません。
さて岩見沢にやってまいりました。もう次の停車駅が札幌というところだったのですが札幌の到着は明日の朝になります。

岩見沢は現在のところicカードkitacaの利用エリアの端に位置し、札幌都市圏の一部のようです。この駅は利用客が多く、待合スペースに座ることができませんでした。
室蘭本線1474D 苫小牧行き 岩見沢(1939発)→苫小牧(2105着)
今日の移動は根室本線の代行バスとこの室蘭本線を効率的に抜けられるように計算して行われていました。もっと言うと稚内の出発からここまでの接続が最適化されています。それぐらい室蘭本線は本数の少ない路線なのです。
例えば富良野でノロッコに乗らずに普通列車に乗車した場合、旭川でライラック40号に乗り継ぐことができません。30分後の特急は臨時化されてこの日は運転されないので1時間後のカムイ44号に乗り継ぐことになります。この列車での岩見沢着は19:59で次の室蘭本線は21:32分発の終電になります。
さらには根室本線の代行バスは始発が新得7:59発で次が13:57発。始発は帯広に泊まらないと乗り継げません。ちなみにこれに乗っても旭川で1時間、岩見沢で2時間待ちになります。なんてこった

待っていたのはキハ150系の2両編成でした。学生の通学時間なので発車までにボックスは大体埋まりました。今日もなんだかんだで500km以上移動する日ですが、これが最後の一本です。
キハ150系は窓が開けられるようになって大体の窓が開いていました。この窓はトンネルに入ったときに風圧ですべて閉まり、トンネルを出ると重力に従ってまた開きと大きな音を出して開閉を繰り返していました。窓が開いていると涼しい風が入ってくるのですが、残念ながら入ってくるのは風だけではなく大きな虫たちも乗車してきます。招かれざる客とともに沼ノ端に到着します。
最長片道切符の経路は沼ノ端から千歳線に進みますが今日は乗り越して苫小牧へ向かいます。続きは明日。

最長片道切符を使った移動距離:640.9km
累計1130.6km/10792.4km
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
