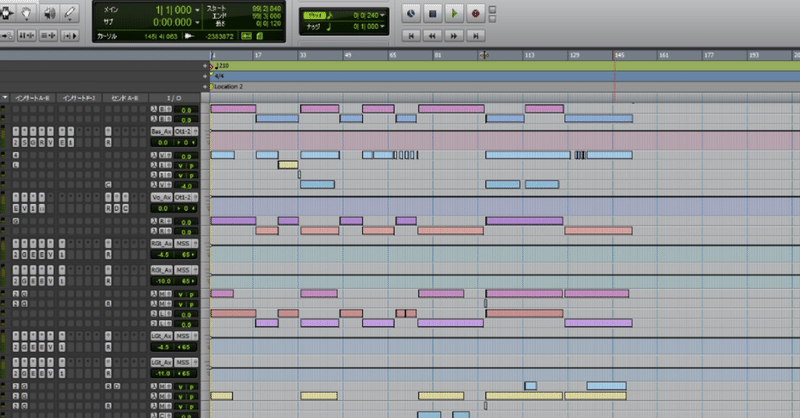
「イマイチ盛り上がらない……」作曲初心者にありがちな"つまらなさ"を解説①
Wrenです。
僕はPan-Potという音楽サークルをやってます。
2019年3月にサークルを立ち上げ、同年11月に同人音楽イベント「M3」にてイベントデビューしました。
ボカロジャンルで活動を始めたにも関わらず、投稿した動画はゼロ。視聴も楽曲のほんの一部しか公開していません。そもそもM3ではボカロはマイナージャンル側。
しかし、初参加で計12枚のCDを手に取ってもらいました。翌年は新型コロナウイルスで規模が半分近くになっていましたが、7枚ほど。他のイベント等も合わせると、CDをリリースして半年で20枚以上を出すことができました。
リアルでのライブ活動やSNSでのライブ配信といった生の音を届けられないボカロ系では動画投稿は必須。しかし、僕らは動画を投稿していません。それでも並のボカロジャンルのサークルさんと同じくらいのレスポンスをイベントで出しています。それだけ訴求力のある音楽を作れている自負があります。
誇らしい実績もなければ有名サークルの仲間入りをしたワケでもありませんが、「音楽」だけで言えば、初心者さんに作曲のアドバイスをできる程度の実力はあると思い、僭越ながらこうして解説する記事を書いた次第です。
「初心者っぽさ」は一体どこから?
この記事を読み始めたということは、恐らく貴方は自分でも心当たりがあるのでしょう。
どうして自分の曲から「初心者っぽさ」を感じるのか、理解している人は今回の記事を読む必要はありません。同じ記事タイトルで幾つかのシリーズにする予定なので、「理解はしているけどどうすればいいのか分からない」といった方は次の記事からお読み下さい。どうすればいいのか分かってる人はより高見に向けて一層の研究と制作を僕と一緒に精進していきましょう。
さて「初心者っぽさ」は大きく2種類に分けられます。
1つは「音そのもののチープさ」です。
打ち込みで制作される方だと、まずは「音源」です。DAW備え付けの音源にも使える音源はありますが、基本的に付属音源はDAWを扱って制作する練習に使うものと考えて下さい。フリーの音源はピンキリですが、有料版も存在するような音源であればフリー版はフリーで配れる程度のレベルだと制作サイドが公言しているようなもの。完全フリーの音源は制作者の趣味で作ったか別の有料音源の宣伝材料に作ったと考えられます。シェアウェアのような投げ銭形式のフリー音源は、お金を払ってもいいと思わせるだけの自信を持っているワケなので、結構よくできているイメージがありますね。
プロの音源は膨大なライブラリと高品質な録り音、細かく調整できる高度なプログラムでできている、高価なものを使っている場合が多いです。それでも最近はその気になれば学生でも買えちゃうくらい安くなっていると聞きます。打ち込みの音源に関しては、「お金で音が良くなる」。間違いないッス。
宅録で制作される方だと、「演奏スキル」「機材」と一気にハードルが上がります。前者は努力で。後者はやっぱりお金がかかっちゃいますね。
しかし、貴方に財力が、もしくは人脈があるのであれば、「他の人に演奏を任せる」という解決手段があります。これは別の話になってしまうので詳しい話はまた別の記事で書きますが、他の人に任せることはメリットが多く、大きい。
そして打ち込み勢と宅録勢に共通するもので「ミックスダウン」があります。打ち込みの音は元から余計な音が入ってなかったりするので幾分かマシなのですが、同様に元から音がチープなのでミックスではどうもならなかったり。宅録だとミックスは必須です。
ミックスの問題は最近はAIを利用した自動ミックス・マスタリングといった解決法があります。iZotope社のプラグインが代表的ですね。ただ、AI任せのエンジニアリングには罠もたくさんありますので、補助的にならドンドン使って良いと思いますが、任せるのはオススメしません。そして学生さんなんかだとアイゾのプラグインが買えないよという人もいるでしょう。解決方法が被りますが、ミックスも「他の人に任せる」という解決が最も早くて効果も見込めるでしょう。スキル提供サービスの「ココナラ」では、「歌ってみた」のようなミックスであれば3,000~5,000yenくらいが相場です。人と曲にもよりますが、フルコーラスでも2ケタ万円はかからないでしょう。
と、まぁここまでは今回の記事の趣旨ではありません(その割には長く書いてしまった)。
僕が今回の記事から幾つか記事を書いていきたいと思っているのは2つ目の方です。
それが「曲にメリハリが無い」です。
これを解説していくのがこの『「イマイチ盛り上がらない……」作曲初心者にありがちな"つまらなさ"を解説』シリーズの趣旨であります。
その曲の盛り上がりドコは何処?
楽曲は幾つかのセクションが組み合わさっています。
例えば「イントロ→Aメロ→Bメロ→サビ」といった具合。邦楽では過半数がこういう構成ですね。洋楽だと「イントロ→Aメロ→サビ」のような構成がよく見られます。
このように必ずBメロがないと~とか、イントロがないと~、という決まりはありません。BメロがAメロと繋がっていて、「A'メロ」のような曲もありますし、フーガ形式のようにフレーズを繰り返す曲も稀にあります(このパターンは例外なので今回扱いません)。
しかし、曲にメリハリを付けるには絶対に分けなければならないセクションがあります。それは、「サビ」です。
底辺ボカロP(言うて僕もその一員ですが)の楽曲にありがちなのが、「サビがサビの役割を果たしていない」。要するに他のセクションとのメリハリが無かったり、あってもその差が小さかったり、或いはサビが「A'メロ」「B'メロ」のような性質だったり。先ずはそれに気づいて欲しい。
「じゃあサビにメリハリをつけるってどういうコト?」ってなりますよね。
「メロに跳躍をつける」「リズムを変える」……と言いたいかもしれませんが、それはメリハリではありません。メロやリズムにおける、ただの「変化」です。サビにつけるメリハリというのは、「セクションとしての役割の変化」です。ここを感覚からしてはき違えて理解したつもりでいるうちは、売れるとか売れないとか以前の問題、そもそも音楽として誰にも聴いてもらえません。付き合いのあるフォロワーが社交辞令的に再生して一言コメントをくれるぐらいが精々でしょう。
それでいいなら構いません……とは僕は言いませんよ。自己満足で完結するならば、投稿する必要はないんです。自分で作って自分のウォークマンなりiPodなりスマホなりに突っ込んで一人で聴いて下さい。プロを目指しているとか広告でお金を稼ぎたいとか、そういった大きな夢と野望と熱を持って作る必要はありませんが、誰かに聴いてもらいたいならば、誰かが聴きたいと思うものを作る必要があります。聴いてくれたらいいなーというささやかな気持ちでも、それは「承認欲求」です。それを肯定することから、貴方の音楽のレベルアップが始まります。
次回予告
さて、本稿の主文は「サビに役割の変化を与えることが曲のメリハリの第一歩」です。
サビに与えるべき「役割の変化」には2つの手法があります。
記事執筆当初はその手法までを初回として書き記すつもりでしたが、長くなったのでまた次回。
初めての音楽指南記事で問うは「サビの意義」。
次回、『「イマイチ盛り上がらない……」作曲初心者にありがちな"つまらなさ"を解説②』
おっしお前ら創造の時間だッ!!
Wren
―――
Wren個人Twitter@WrenRD
Pan-Pot公式Webサイト(β版)
http://pan-pot.deci.jp/
☆Pan-Pot公式LINEスタンプ配信中☆
https://store.line.me/stickershop/product/8975089/ja
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
