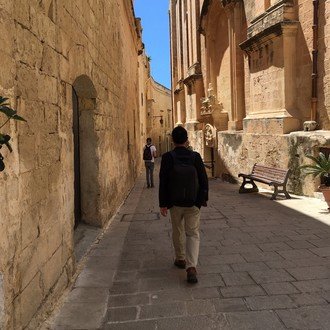(全文公開)探究学習は新たな工場生産型人間の育成の場
先日、サステイナブルブランド国際会議(以下SB国際会議)東ブロック大会に生徒を引率して参加してきた。これは東日本の高校生が集まり、①教育(ベネッセホールディングス)、②森と水の保全(サントリーホールディングス)、③気候変動(積水化学工業)、④ツーリズム(日本旅行)の中から興味のあるテーマを選び、各テーマ担当企業の持続可能な取り組みに関して講演を聞いた後、ビジネス提案を行うという内容のものだ。昨年は縁あって全国大会に参加させて頂いたのだが、今年も高校生らしい提案が数々聞かれ、個人的に楽しませてもらった。
さて、我々の学校は②の森と水の保全活動をテーマに選びサントリーホールディングスさんの話しを聞いた。良い水を作るというのは大変な作業で、その活動を始めた時には科学的な知見もほとんど無く、手探りしながら事業を進めていったとのことである。何をしたら良い水を作れるのかというはっきりした方法が無い中、多大な投資や労力を費やし、今のようなおいしい水を提供できるようになったというのは本当に頭の下がる思いだ。考えてみれば、世の中、何か新しく始める時に確定されたものなど何も無い。説明書を自ら書いていくような作業だ。サントリーの担当者さんは「雨水を抱擁するフカフカな土壌を作ることが大切ではないか。」と提案したところ、科学者から「そんなの意味はない。」と一蹴されたとのことである。それでも、自分の信念を信じ、データーを集めていったところ、自身の考えが立証されるに至ったという。つまり、確証無い中で何かを進める一番の言動力は誰の何の反対にも負けない強い信念である。もちろん人の意見を聞かないというのは問題であろう。そのバランスを保つことが大切なのである。
さて、最近学校教育では「探求」という考え方が導入されるに至った。生徒の学問に対する意識を高め、自学自習できるような人材を育成することが目的であるが、そもそも何かに対する興味関心を高める努力を学校が国からの強制で果たさなければならないという現状に将来を憂う。世の中で起きることに対して興味関心を引き出すために必要なことは、なるべく箱の中から外に子供を追い出し、駆け回り、手足を動かすことではなかろうか?自分の手で触り、感じ、時には痛い経験をすることで、脳は活性化され新たなアイデアと結びつく。
俗に言う工場生産型人材育成からの脱却を目指しながら、プログラミングの義務教育化を始め、結局はクリエイティブという名の新たな工場生産を日本の教育は目指しているように感じる。
最近の教育は足されすぎのように感じる。教育の原点である知識の伝達と発展という観点をつきつめればそろそろ加わっているものを引いていき、生徒達から体をめいいっぱい使って表現する場を作るべきではないだろうか?
参照:
世界を旅するTraveler。でも、一番好きなのは日本、でも住みたいのはアメリカ・ユタ州。世界は広い、というよりも丸いを伝えたいと思っている。スナップシューターで物書き、そうありたい。趣味は早起き、仕事、読書。現在、学校教員・(NGO)DREAM STEPs顧問の2足の草鞋。