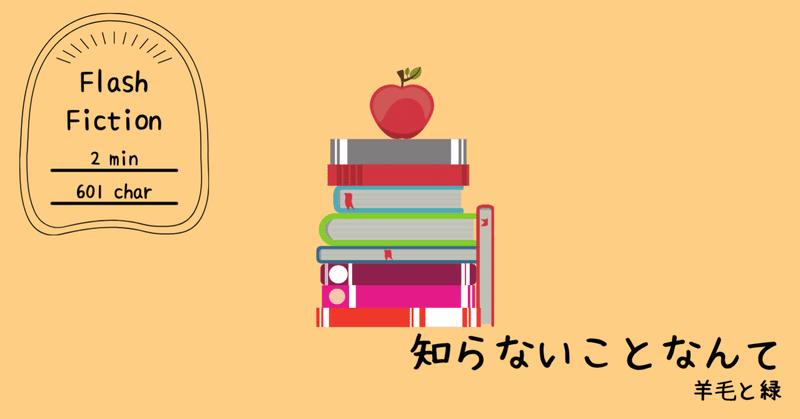
知らないことなんて
「あのころのぼくは」だなんて振り返るとき、ぼくは少しだけ違和感を覚える。
遠く幼いころのぼくが覚えている日々は、まだ世界についても何も知らないときだったのだから。
無限に広がっている空にどこまで伸びているって思えた近所の道。
それが丸い地球でずっとまっすぐに進み続けていると、いつのまにか見覚えのあるものに囲まれていることに気付いたら。そうしたらきっとそのころのぼくだって、今のぼくみたいにつまらないってなんでも決めつけてしまう子供になってしまっているはずだ。
「でも、世界がこうだって知っている顔して何にも知らないのだから、きみは子供のままじゃないのかい?」
ぼくの知らない世界から声が聞こえた気がした。この声が未来のぼくからのものならば受け入れられる。けれど、もしこの声の主がぼくのことを知らないのであれば、ぼくらお互いのことを知らないのだから余計なお世話だって思う。
「ぼくのことをきみは知らないから、つまらないって思うんだ。だから、知らなければ知ろうとしてみてほしい。それからぼくのことを余計なお世話だとか、そんな風になじってほしい」
もっともだって思ってしまった。いい大人がものしり顔でななめに構えていたことを見抜かれてしまった。ぼくは、自分がとても恥ずかしくなった。
よくも知らない世界の声に諭されてしまうほど、ぼくはものを知らなかったのだ。ぼくはいつの間にか、知らないことなんてないと思っていたのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
