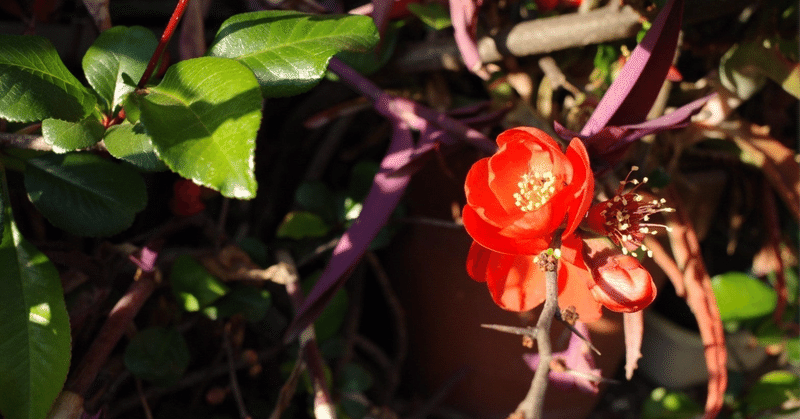
日曜、a ma terrasseの前で-おばあちゃんの家-
習慣というものをあまり持たない私が、近頃、日曜の午後に自宅の近くのカフェに行き、そこで読み物をしたり書き物をするというペースを築きつつある。
午前中に掃除をして、ゆっくりとお風呂に入り、昼食を食べてから家を出て、気分の向くまま幾つか候補のあるカフェのいずれかに行く。
そこで、たいてい2時間あまり、ひとりの世界に没頭するのだ。
気がつけば夕方が近づく時刻、カフェの席を立ち、まだ歩いたことのない路地を探して街を歩き始める。
私は、まだこの街の初心者だ。
雑誌やインターネットから仕入れた情報で、行ってみたい店、興味のある場所は幾つもある。
迷路みたく入り組んだ小路を、「こっちかな、あっちかな」とうろつくのは、この界隈で週末に目にする観光客と大差ない。
こないだの日曜も、一つ一つの角、一本一本の道を丁寧になぞりながら、また新しい道を徘徊してみた。
幾つかの有名フレンチレストランやビストロがあって、情報誌から仕入れた知識と実際の街並みを照らし合わせながら、気になる店をチェックしたり。
「成金横丁」という、由来を訊いてみたい名前の小路に、a ma terraseという小さなビストロがあり、美味しくてリーズナブルだと評判を聞いていたので、ちょっと立ち止まってエントランス前に掲げられたメニューを覗き込んだ。
なるほど、手ごろな値段でプリフィクスがいただける。
ふうんと思っていたら背後から、おばあさんの声が私を呼んだ。
「ここのお店で食べたことあるの?」
もちろん知らないおばあさんだ。
80は過ぎているだろう、背中が大きく曲がって杖をついている、小柄なおばあさん。
そのわりに声には張りがあって、快活に呼びかける。
「いえ。食べたことないです」
「あらそう。私もないの。美味しいのかしらね」
「どうでしょう。美味しそうですよね」
それから少しだけ、おばあさんと立ち話をした。
「私ね、もうここらへんに50年も住んでるのよ」
「へえ」
「娘と一緒にね。あそこの、あの高い建物の裏っ側に住んでんの。
ずっと。ずっとよ」
「そうですか。私は最近住み始めたばかりなんです」
「あらそう。いいところだからね。
他に行こうなんて思えないわよ」
「ええ、いいところですよね」
「このへんは人がいいのよ。
昔は芸者さんなんかがいて、花街だったでしょ。
だから、このへんは、そういうとこに行くような立派な人が多いのよ。
変な人はいないの」
「そうですか」
「それに美味しいところがいっぱいあるしね。
私もしょっちゅう外で食べるの」
「いいお店が多いですもんね」
「でも、今日はうちで娘がおでん作ってるって言うからね、さっきまでお友達んとこに行ってたんだけど、今から帰るの。
おばあちゃん、今日は早く帰ってきてって言うから」
「そうですか。よろしいですねえ」
私のひいおばあちゃんは、何kmも歩いて友だちの家を何軒もまわる日課を持っていた。
色んな人の家に出向いて、お茶をよばれながら世間話をしていたようだ。
世間といっても、ひいおばあちゃんの世間はごく狭い範囲なので、大した話題もなさそうに思うのだが、それでも年がら年中、友だちを訪問し続けていた。
友だちとどんな話をしていたのかは知らないけれど、ひいおばあちゃんが私たちにしてくれる話は、何十年も前の思い出話と、誰かの悪口と、好物の蟹や栗の話題だった。
思い出話と言えば、ひいおじいちゃんとの馴れ初めの話や、もう既に亡くなった人で名前を聞いても全然分からない親戚の話が定番だった。
あと、自分が子どものときの話。
「アホやったから、小学校も落第したんや」とケタケタ笑いながらする話。
私が高校生のとき、アメリカ人の女の子がうちでホームステイをしたことがあったが、そのときも、ひいおばあちゃんは、何ら臆することも遠慮することもなく、堂々と日本語で話しかけていた。
洗面所の前で一緒になったときは「ちょっとごめんよ」と断ってから蛇口の下に手を入れて、手を洗い終わった後、彼女を見上げて「あんた、背え高いなあ」としみじみ声をかけていた。
きょとんとした青い目の女の子の前で、ひいおばあちゃんはやっぱりケタケタ笑った。
ひいおばあちゃんは、フレンドリーで話好きな人だった。
近所の野良犬に声をかけたり、テレビに向って話しかけることも多かった。
先週、久々に夢にひいおばあちゃんが出てきて、もうどんな内容だったかは忘れてしまったけれど、何か言葉を交わして、懐かしいような切ないような、愛しいような幸福なような、ひいおばあちゃんのことを大々大好きだという気持ちが、夢の中の胸に湧き起こってきた。
目が覚めたとき、下校するときつないだ、ひいおばあちゃんの手のひらの冷たい感触が蘇ってくるようだった。
保育園のお迎えのときは見上げていたはずの私の視線が、やがて、中学生にもなれば見下ろすような、見守るようなものに変わっていた。
私は、ひいおばあちゃんが大好きだった。本当に、本当に大好きだった。
日曜、a ma terraseの前で、人懐っこく話しかけてきたおばあさんは、この街にずっと暮らしてきて、この先もこの街に暮らしていくのだということを、誇らしげに語った。
「呼び止めちゃって悪かったわね」
「いえいえ、そんなこと」
「じゃあ、私、もう帰るわ」
「どうぞお気をつけて」
腰を曲げ、杖をつくおばあさんの歩みは遅い。
私が5秒で横切る道を、30秒くらいかけて進む。
ひいおばあちゃんもそうだった。
手をとって、その歩みにあわせて、ゆっくりゆっくり帰る夕暮れには、大切な思い出がしみこんでいる。
「おばあちゃんの家」という韓国映画は、腰がまがり耳も遠い祖母を馬鹿にしてわがままばかり言う孫と、それでもいつも温かい愛で包む祖母の、短い思い出を描いている。
ひたむきで、限りなく優しい。
おばあちゃんは、長い時を生きた大人なのだ。
幾仕事も終えた、幾山も越えた、たくましい大人なのだ。
いつか年をとって、身体が自由に動かなくなって、昔のようなスピードで歩けなくなったら、きっと悲しくなるだろう。
自分を平気で追い越していく若い人々を見て、かつての自分を思い出し、悔しい気持ちになるだろう。
きっとそんな日が来るだろう。
けれど、ゆっくりとしたスピードでしか、見えないものがあるようにも思う。
その年になって、何者からも自由になって、そのときにようやく見えてくるもの、感じられるものもあるのだろう。
曇った水晶のようなひいおばあちゃんの瞳が、見ていたものはなんだろう。
それを知る日が来るのだろうか。
おばあちゃんの家(2002年・韓)
監督:イ・ジョンヒャン
出演 キム・ウルブン、ユ・スンホ、ミン・ギョンフン他
■2007/11/3投稿の記事
昔のブログの記事を少しずつお引越ししていきます
サポートをいただけるご厚意に感謝します!
