
いのちの文化人類学[序論]
現代医療はサブカルチャーだ

「誕生 病気 死」
この巨大とも言えるテーマをなんと驚きのA6サイズ200ページ強でざっくりまとめた本。
それでいて民俗学的な事例はカラフルで一つ一つが示唆的であり、それ一つで一つ本が書けそうなくらいである。
入門書の宿命と考えれば、個別の内容にはあまり踏みこんでいないと言う批判は当たらないだろうが、通底するテーマというか、議論の展開は埋もれて見えづらい印象だった。
元新聞連載であったせいかもしれない。
なので、各テーマごとに自分なりにある話の流れ(問いかけと答え)のようなものを読み取って、それをベースに以下要約していこうと思う。
(独り言)
介護人類学を唱えた六車氏が主張するように、
民俗学がその存在意義でもある、”公平な(自己を引き離すような)視座”を確保しながら書くためには"分厚い著述"(ボトムアップ的)というものがそもそも必要なのかもしれない。
その意味で、文化人類学の(しかも網羅的な)入門書とはそもそも困難な作業と言える。
一方、もし問題解決(トップダウン)的に整理していくとしたら
個人的にこのテーマは倫理学の話になるのではないかと思う。
臓器移植にしても生殖技術にしても、
従来の文化的身振りと、医療文化の軋轢は、特に倫理的な問題として大きく議論されるように思う。
だから現代倫理学の論理をベースに考えるとまた一歩踏み込んだ整理ができるのではと感じた。
近々この本の書評もしてみたい。現代倫理学入門
要約⑴序論
本書の前提にある議論の骨子はこうだ。
人は死ぬ。
人の生命には限りがあり、どのように工夫し努力しようとも人は必ず死ぬ。
そうした存在であることは無論、古代より人類は認めてきた。(生の有限性)
一方で、
各時代や文化圏における何らかの動機によってー基本的には自我によって生じる死への恐怖であろうがーその限界のある生命を「無限なもの」だとする思考は常に働いてきた。(命の有限性へのリアクション)
そのことはキリスト教文化における「肉体は滅びても魂は神のもとで永遠の生命を与えられる」とか仏教文化における輪廻転成の思想、日本の「イエ」制度に見られる、祖先崇拝など枚挙にいとまがない。(その態度の違い。)
たとえば伝統的なイエ制度では、死んでしまった個人の存在を33年ないし49年、その個人名は儀礼の中で強調される。 あらゆる宗教の原則と言えるかもしれないが、個人の存在の意義を最小限としながら、有限の生命を無限のものとみなす機能が見て取れる。
(家制度の背後にある生命観)
筆者はこうした考えかたを「開かれた」生命観として、 近年の医療をはじめとする急速な変化がもたらした「閉じられた」生命観と区別している。
(全く新しい生命観)
近年の変化とは即ち
(1)人間の寿命が急速に伸びた
(2)現代医学の発達とその普及
とそれらによる
(3)「生命論パラダイム」
と呼びうるような、認識論ないし世界観の発達
の3つだ。
つまり
①死が身近でなくなった。
平均寿命以下で死ぬことがあたかもなんらかの過ちであるかのように扱われるようになり、人を看取る機会も減った。
②現代医療が強調し続ける生命の唯一無二性というイデオロギー
例えば、「延命治療」問題。
医療費の増大が社会全体に歪みを与えていても、「唯一無二の生命体」に対して個々の医療が行われる。
③閉じられた生命体に対する反省やアンチテーゼとして科学的にカウンターカルチャー的に生じた思想群の存在
例えばDNAの運び手に過ぎないのだ”とするリチャード・ドーキンスの「利己的な遺伝子(1976)」に代表される生命観や地球は一個の生命体ですよというガイア思想など。
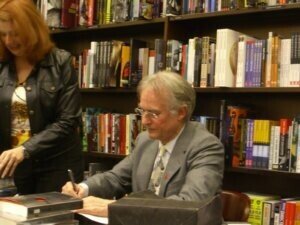
”「ある一人の人物が妄想にとりつかれているとき、それは精神異常と呼ばれる。 多くの人間が妄想にとりつかれているとき、それは宗教と呼ばれる」”
要約⑵本論
本書はそんな話から
「人の生育と誕生」
「病いと癒し」
「死と再生」
の三部に分けてそれぞれ地理的・時間的(歴史的)違いによって「いのち」がどのように違った扱われ方をするかを手際よく整理している。
統合すると非常に長い文章になるので、誕生の章・病の章・死の章各部に分けて投稿していきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
