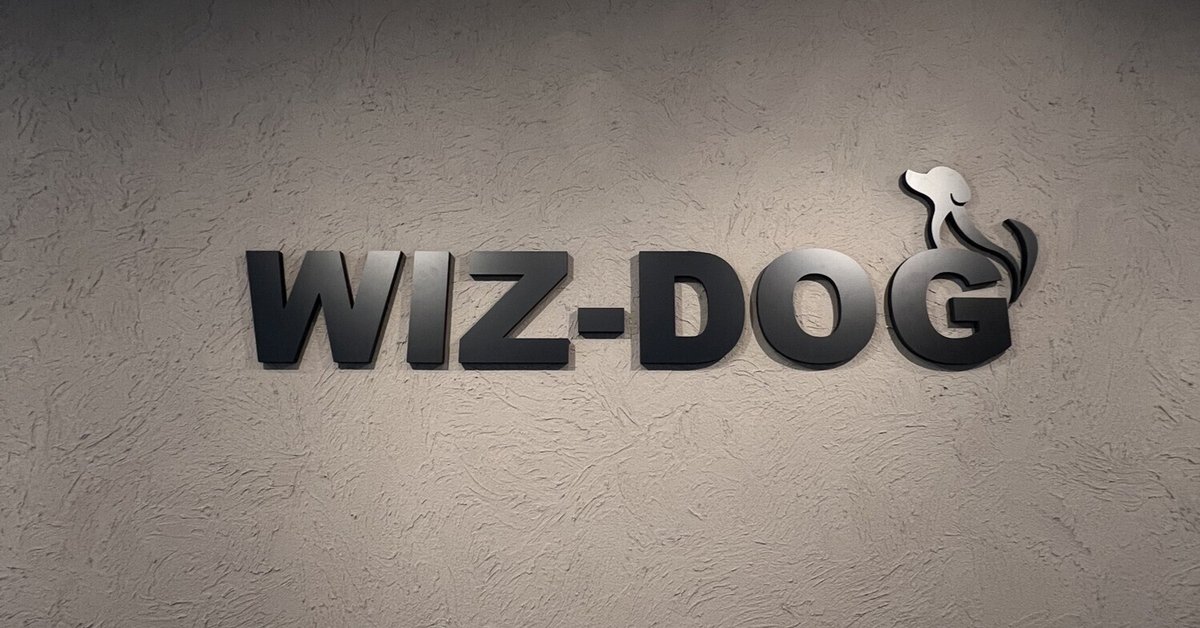
4.NOを教える、NOで教えない
いつも仏頂面の私に「イヌに笑顔で接する」ことの大切さを教えてくれたのは、日本盲導犬協会の訓練士多和田悟氏です。今回の記事は、その多和田氏が教えてくれたもうひとつの大切なコト「NOを教える、NOで教えない」について書きます。
この2つの「NO」は意味が違います。「NOを教える」の「NO」は「やってはいけないこと」、「NOで教えない」の「NO」は「否定すること(叱ること)」です。
「NOを教えるためにはNOを使わないとできないでしょ?」
多くの人はそう考えます。つまり、「叱らない(NOを使わない)でどうやって、イヌにやってはいけないこと(NO)をやってはいけない(NO)、と教えられるの?」と言う認識です。
その認識がこびりついている限り、おそらく多和田氏の考え方を理解することは無理でしょう。街中で激しくわが子(らしき子)を叱咤している親を見ることがありますが、ああいったヒトたちですね。口には出しませんが、「あの子、気の毒だなぁ~」と思いながら、ただただ見ています。
「ただ単に犬を叱る方法は、1プラス1は2であることを教えず、永遠に3ではない4ではない5ではないと言い続け、そのたびに罰を与えるのに似ています。私は、このやり方を「NOで教える」と呼んでいます。NOで教える方法の最大の欠点は、何がYESであるのかを犬に伝えないところです(犬と話をつけるには 多和田悟著 文藝春秋 2006年)」
実は、このYESを教える、という教育法は、昨今、ヒトの幼児教育でも重要なポイントであると認識されつつあります。
「発見的学習法(子ども自身に考えさせて結論を導かせる、正解を得させるという学習法)というのはそそられる考え方だが、残念ながら効果がないことは何度も明らかにされている。...…要するに、生徒が(課題に対して)やる気をもって能動的に関与するのは大事だが、だからといって、本人の独力に委ねればよいということではない。構成主義(≒発見的学習法)の失敗は、明示的な教育的指導(=教師あり学習)が必須であることを明らかにする。教師は生徒に、順序良く、できるだけ早く頂上に導けるように意図された、明瞭な構造を持つ学習環境を提供しなければならない。……失敗よりも成功の方から学習することがずっと多い(脳はこうして学ぶ スタニスラス・ドゥアンヌ著 森北出版 2021年)」
もちろん、知的好奇心を維持させることが大前提ですが、子どもに自らの力で正解を探し当てるまで考えさせる教育法よりも、先に正解を教える教育法の方がより効果的な教育法である、と訴えているわけです。
先の多和田氏の著書でも、正解を教える重要性を述べています。
「盲導犬を訓練するとき、私は徹底して人が何を望んでいるかを犬に示します。犬がそれを理解し、納得し、結果に満足するまで繰り返します。この方法を私は「NOで教える」に対して「NOを教える」と呼んでいますが、一般には「YESを教える」と言った方がわかりやすいかもしれません。...…一連の訓練で「NO」を使うのは、間違ったことをしたときに犬の注意を喚起するためで、その後即座に何をすべきかを示さなければなりません。これが大事なポイントです。なぜ「NO」なのか、何が「YES」なのか、を犬に理解させようとしてはいけません。犬にとっても「YES」「NO」「は快・不快でしかなく、それは人間が求める善悪の基準とはまったく異なるのですから(同上「犬と話をつけるには」より引用)」
「犬と話をつけるには」と「脳はこうして学ぶ」、両書籍とも、叱ることの副作用あるいは弊害について、多くのスペースを割いています。イヌと暮らす時は「叱らない」ことを心に刷り込んでおいて欲しいと願っています。

