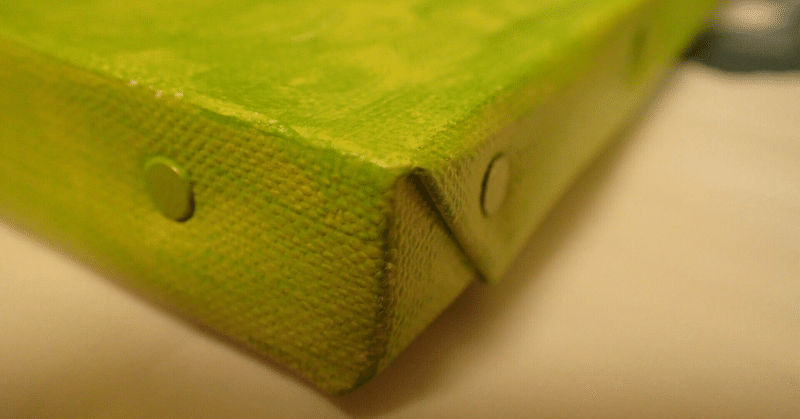
「キャンバスの裏側」もしくは「相互偏執の原風景」【一輪劇場裏話】
俺の親父は画家だ。一日の大半を絵の具とキャンバスに向き合って終わる。俺はそんな親父があまり好きではない。というか、むしろ嫌いの域に達している。絵に魂を込めるあまり、父親としてのあの男はもぬけの殻なのではないか。そう考えては、無性に腹が立った。
そのことを母に話すと、「あの人はあれでいいの」と穏やかな顔で言われた。どうして、あの男に振り回されている母があんなことを言えるのだろうか。母に苛立ちはないのか。ぐるぐる考えて、また腹が立った。
俺はあいつとは違う。将来は親父以上の画家になって、あいつとは逆の生活を送ってやる。誰も絶対に一人にはしない。そんな思いが、積乱雲のように膨れ上がっていた。
そんな日々が続いての今日。記録的な猛暑なのでアイスキャンディ―を食べながら部屋で自分のスケッチを見返していた。教育委員会のお偉いさんから褒められた記憶を辿っていると、玄関のベルが鳴った。正直言って、面倒だった。しかし、放置するわけにもいかないので、階段を下りる。
ドアを開けると、まとわりつく熱気。その中に、隣人である少女が白いワンピース姿で立っていた。
彼女はつばの広い帽子の不安げな目元を隠し、スケッチブックで喜んでいるような口元を覆っていた。
「あの、私の絵、見てくれませんか?」
挨拶もなく、上ずった声で聴かれた。
「あ、ああ。その前に、家に入らないか」
「はい」
彼女を通し、スケッチブックを受け取る。
俺と彼女が親父から手ほどきを受けていた時は互いに見せ合っていたものだが、俺が親父のことを受け入れられなくなってからは一度も見ていない。多分、二年ぶりになるのだろう。
懐かしさを感じながらスケッチブックを開く。そこには緻密に描かれた寂しい砂漠。次のページには迫力あるタッチで作られた激流に逆らう鯉。どのページにも、書き手の技量と想像力の豊かさをありありと表現するもので満ちていた。
圧倒的だ。自分との差を感じ取った。震える手で彼女にスケッチブックを返す。すると、「どうでしたか?」と不安げな声で聞かれた。
「良かったよ……」
それしか返せなかった。その言葉にひまわりにも似た満面の笑みを彼女は浮かべる。
「やった」
そして、こちらをじっと見つめてきた。
「武宏くんのも見せてほしいです。昔みたいに、描いたものも描いているところも」
無邪気な、明るい声で言われてしまった。
「——今度でいいか? スケッチブック、学校に置いてきたままなんだ」
つまらない嘘だ。でも、彼女はあっさり引っ掛かってくれた。それから少し世間話をした後、彼女は「また、見せ合いっこしましょうね」と告げて親父のところへ向かう。胸に感じたことがない痛みが走った。
リビングからアナウンサーの冷静な声聞こえてくる。今晩は激しい雷雨になるらしい。
夕食後、親父のアトリエに呼ばれた。憂鬱な気分でドアを閉めるなり、目も合わせずに「あの子の絵、どうだった?」と聞かれた。
「……完敗だ」
答える苦々しく俺を尻目に、親父は手元の本を眺める。
「ゴッホ、カラヴァッジオ、レンブラント、葛飾北斎……芸術に生きる者は皆、波乱万丈な人生を送った」
「それがどうかしたのかよ」
「あの子もいずれ……いや、もうそんな人生を送っているのかもな」
無性に頭にきた。実の子に掛ける言葉なのか、それが。
部屋を出ようとすると、声を投げかけられた。
「お前は、どっちだ?」
その言葉が最後の一滴だった。家を飛び出して、俺は走った。堰を切ったように、叫び声を上げながら。
振り始めた雨に気がつく頃には、坂の頂上にある公園に立っていた。屋根付きのベンチで休もうと思っていると、「あれ、武宏くん?」と、彼女のやわらかい声が聞こえた。
「こっちに来ます?」
「ああ……」
少しずつ強くなっていく雨のカーテンに囲まれた俺たち。正直、今一番会いたくない相手だった。だが、こんなところで会ってしかも二人きり。何か話さなくていけない。でも、何も話したくない。
彼女がゆっくり口を開く。
「どうして、ここにいるんですか?」
「あー、親父と言い合いになってな」
半分嘘だ。あんなもんは言い合いじゃない。
「そっちこそ、どうして」
「んー、家に居づらいんですよね。親は喧嘩してるし、お姉ちゃんは彼氏さんの所に居るし」
寂しげな言葉に、頭が揺さぶられた。
「……なら、こんなところじゃなくて友達のところにでもいた方が……」
「友達……ですか……」
彼女が俯く。ここで俺はようやく気付いた。彼女はここにいるしかないことに。
瞬間、遠くで鳴った雷に彼女は小さく悲鳴を上げた。
「これは、しばらく帰れませんね」
雨音にかき消されそうな声のどこかに、安堵が混ざっているように聞こえた。
「心配するな。俺がいる」
我ながら歯が浮きそうなセリフだ。これが無意識で出てしまったのだから、どうしようもない。
「そうですね」
でも、そんな言葉に、小さく笑ってくれた気がする。
そうだ。今、目の前に居る女の子は俺と同じなんだ。同じ弱い生き物なんだ。絵を描き、笑い、悩み、苦しむ。そんな彼女の助けになりたい。例えそれが、忌避している両親の似姿であろうとも。
雷鳴は激しく、雨風は強い。地上に星が多いから、夜明けはまだ先なのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
