
千葉室の手記
まいった。もう映画の上映日が来ちまったじゃあないか。まだ終わってない。まだこの映画はぼくの中では終わってない。そう思い続けて、この映画がクランクアップした2021年12月12日からここまで来ちまいやがった。上映日は9/9(土)の14:30〜だ。ぜひ観てほしいと思いつつ、ぼくの演技には目を瞑り、しかしきちんと批判もしてほしいし、みんなとつくったこの映画をいろんな人に観てほしい、どんなことでもいいから感じてほしい、そう思って止まぬ。ああ、来ちまった。ここまで来た。ここまで来て思うのは、まだ自分がふわふわしてること。何もできていないこと。何もつくりあげられていないこと。そんなことばかり頭に出てきて、ダメだなぁと思う。


別に、ダメなんかじゃない。そう人は言うし、もちろんぼくも思う。でも、それじゃあダメだと思って、この映画づくりに参加したんだ。そう思ったから、中野さん(映画『リテイク』の監督)にお金の交渉もしたし、キャストのみんなとたくさん話し合いもした。それ全てがぼくの中の挑戦だった。でも、今はどうか。手元にあるものは何か。全く貯まらない貯金と、いくつかの小説の断片、いつか映画にしたいと思ってちまちま撮っている(でもあまり撮れていない)恋人との映像である。何もない。本当に何もない。これをふわふわと言わずしてなんなのか、これでも「ダメなんかじゃない」と言うのか。人にはそう言ってもらって構わないけれども、自分で「これで良い!」って言ったらそりゃバカだろ。ここで悶々とするのが世の中一般で言われる「良い人」だろう?だから悶々とするんだよ。悪いか。
別に悪かないよな?それはそうですよなんたって人の人生なんだから人がどう生きようが人の勝手ですよ。でもやっぱり、それでもバカになれたらどれだけ楽だろうと思う。一途に夢を追えたらどれだけ楽だろうと思う。そういう人を羨望のまなざしで観ていたのが『リテイク』制作・キャストに入る前のぼく。いまは違う。ぼくは変わりました。世の中に「気持ちの良いバカ」はいない。それがいまのぼくの世界観だ。
たらたらとふわふわと生きているぼくが、何を感じたか、どう生きたか、を書くことになる。こんなにつまらないことはない。なぜかって、結局そんな生き方を肯定しようとするんだもの。じゃないとこうやって書き始めないでしょ。でも、ぼくは人に向けて書いてる。全力で書く。どうなってもいいからぼくの中でこの映画『リテイク』を終わらせる。結局、人に見せることにこだわることでしか人に気持ちは伝わらない。人々がこの映画『リテイク』を観ても、ぼくの感じたことは伝わらない気がする。この『リテイク』っていう映画のすごいところを、端的に伝えたい。ただ、端的にっていったって、端的に伝えられないから映画も小説も長くなるんであって、それを「端的に」伝えるって食リポじゃないんだから、意味がない。ぼくはこの映画『リテイク』には「意味がある」と思ってる。ぼくがね。だから長くなる。でも端的に伝える努力はする。それ自体が映画『リテイク』が実践していることでもあるんだけど、それは本当に観てほしい。
これに加えてゲンロンという会社のことを自分の物語に引き付けて書く。社長が上田洋子で有名なのは東浩紀がやっている会社ってことだ。東浩紀は哲学者で上田洋子はロシア研究者。ぼくはこの会社にも恩を感じている。その情報は『ゲンロン戦記』という本と東浩紀の突発生放送というプラットフォーム『シラス』で配信される動画からが主だ。とにかく、20歳でゲンロンを知って、その会社がつくる「ゲンロンカフェ」という対談番組含め、その全部に感動していた。それが、この『リテイク』という映画をつくるうえで、原動力になっていた。そのことも、こうかもしれない、ああかもしれない、なんて自分の行動を振り返りながら、書いていくから、どうやったって自分語りになる。
ぼくは本当に、「ぼくが、ぼくが、ぼくが!」だ。本当にぼくだ。だから嫌になる。ぼくにだってぼくが「ぼくが、ぼくが、ぼくが!」だってことはわかってるんだけど、どうにも治らない。ぼくが本当にどうしたらよいかはぼくにはわからないことはよくわかったんだけど、それにしたってぼくがぼくであることをいちばん悩むのはなぜなのか。それがいちばんわからない。わからないと、不思議にぼくの話になる。
うっとうしいから、そう思う人は、どうかご勘弁を。
ただいま2023年9月7日20:37。
1 大学を辞めた!ぼくのヒーローは坂口恭平だ!
映画監督を志してぼくは2019年、東京造形大学の映画映像専攻領域に入った。まぁ、もちろん映画監督を志したのも、今思えばぼんやりしたものだった。他の人がどう思うかわからないけど、造形大学ってのは、映画監督を目指す人には向いてない。いわゆる商業映画の「映画監督」だけども、本当にそれを目指すのには向いていないと思った。ならなぜ入ったかといえば、そこに好きな先生がいたからだ。川部良太である。

川部良太はぼくの高校のときの先生であった。ぼくの通っていた埼玉県立芸術総合高等学校は、映像学科という科があって、その授業に大学の先生をお招きし、講師として授業をしてもらうのである。高校2年生のときの先生が、川部先生であった。
「はじめまして。川部良太っていいます。えーっと、普段は大学で授業したり、たまーにドキュメンタリーをつくったり。高校のときはラグビー部にいました。ぼく、ヘッドスライディングが好きで」
おもむろに立ち上がると、ホワイトボードの前を陣取ってそのまま動かない。
「そんで、最近は、豊島ってわかりますか?四国の、島なんですけど、そこでこの前はね、そこら一面の草を刈ったんです。そこはむかし人が住んでたところで。その刈ったあたり一面をみて、なんかもう、これが映画だ!と。その時間が、なんか心にグッとくるんです」
みたいなことを。
詳細は覚えていないが、当時は、「うーん、ぼくもこうなっちゃうのかぁ」なんて思っていたが、それからしばらくして「ぼくもこうなりたい」と思った。もう、そうはなれないといまは知っているけれど。
感性が豊かと言ってしまえばそれまでだが、その映画に対する情熱を感じたのは川部先生がはじめてだった。映画に対する情熱そのもの。それを知れたのが高校時代、という言い方ができるかもしれない。
そもそも、なぜ映画に興味を持って、芸術総合高等学校なんてところに入ったのか。この高校は、普通科がない、いわゆる芸術系の高校である。そこに入って、ぼくは映画をつくろうとしていた。そのそもそもの映画をつくりたいと思ったきっかけは、園子温の『ヒミズ』だった。中学2年生の頃にはじめて観て、すごく面白く感じた。いまはどう感じるかわからないけれど、涙がとまらなかった。それで、だから映画がつくりたいと思ったわけじゃなく、つくりたいと思ったのは最後のエンドロールの短さによってだった。2時間の映画をつくるのに、こんなに少ない人数でつくれるのか!と、そこに、なにか風穴を開けられたような気がして、明らかにものづくりにたいする見方が変わった。映画というものは大人数でやる、失敗できないもの。そういった考え方が、一気に崩れていったのだ。ぼくにとって魅力的だったのは、低予算ということではなくて、少人数ということだった。それでも、今思えばやっぱり多くの人がその映画には関わっているし、その責任も大きい。それでも、そのときは、「これならぼくにでもできるかもしれない」なんて思ってしまったんだ。

余談だけど、ぼくはある美術館の作品自体の警備員をしていて、長時間作品のそばに立っていることが多い。すると、やっぱりいろんな人が来る。有名人も来る。そこに、あるとき園子温が来た。でっかい絵を眺めて、そばには多分奥さんと幼稚園生くらいの小さな子どももいた。あらゆる人が来るから、それにぼくも仕事だから知らないふりをするのは上達してたんだけど、このときばかりは体が固まった。しかも、園子温がセクハラ(記事を読むとそれどころではない)の記事をスクープされた少し後だったから、それもぼくの中を去来して、本当に体が動かなくなって、凝視したままになっていた。するとやっぱり園子温は気づいたみたいだった。別にマスクもしていなくて変装も何もなかった。その、園子温に気づいた、ということに気づかれた。やってしまった!と思ってサッと視線を外して違うポイントに歩いていった。彼のそばでは子どもが
「道は〜?道はどこ〜?」
なんて言っていた(どういう意味だろう?)。
少し歩いてチラッと振り返ると、もうそこにはいなくなっていた。すごく後悔した。あのときのぼくの目は明らかに「好奇の目」だった。もう2度としたくない。
ぼくの映画との出会いは2つ。それは園子温と川部良太だった。だから映画を学ぶことに迷いはなかったし、商業映画じゃなくてもいいから「映画に対する情熱」だけを育んでいきたいと思っていた。東京造形大学は、その自分には合っていると思った。
でもやっぱり、ダメだった。情熱だけじゃ生きていけない。当たり前だけど、そんなことを痛感した大学生活だった。これでもかというくらいふわふわしていた。情熱と生活が合わさらなかった。それをどうにか合わさるようにするのが技術なんだけど、それをする覚悟もなかった。何もなかった。それを知った。
大学の図書館で、足りない知識を補うために、映画コーナーを行ったり来たり、なぜかダーウィンの進化論を読んだりしながら、右に左に、じっとしていられない時期が大学に入ってすぐはじまった。園子温関連の本はたぶん全部読んだ。その中で、園子温が坂口恭平という人物について言及していた。園子温は彼のことを「こういう若者がいるなら大丈夫」と太鼓判を押していたのだ。坂口恭平は、「自殺者をゼロにする」という目標を掲げ希死念慮に苦しむ人々との対話「いのっちの電話」(090-8106-4666)を続けている、気合の入った人である。坂口恭平自身、躁鬱病であることを公言している。だからかわからないが、彼は1年中死にたい人の電話に出るのである。自殺者をゼロにするために。
ぼくは園子温が太鼓判をおす坂口恭平のことを何も知らなかった。嫉妬した。だから、どんなもんだろうと坂口恭平の本を手に取った。その本がほんとうに面白かった。最初に読んだのは『独立国家のつくりかた』。それから、どんどんハマっていった。坂口恭平・宮台真司・高木新平の対談映像をYouTubeで観て、心が軽くなった。こんな人がいるのか、と思った。

正直、この人がいるなら、ぼく頑張らなくていいんじゃないかな、そんなふうに思った。そのとき、なぜか「自分が何かしなくちゃいけない」と思っていたことに気づいた。何もしなくてもいいのに。
「いまは俺の時間!お前ら何もすんな!」
坂口恭平は、真剣だった。マジだった。マジだから自分の電話番号090-8106-4666を公開して、1年中死にたい人のために電話に出るし、マジだから人の心に届く言葉を持っている。マジの人を見ると、自分のふわふわさに気づく。ある意味、地に足がつく。ふわふわしている自分を生きることに、自覚的になったような気がする。
そうなってくると、なぜ大学に通っているのかちょっとずつわからなくなっていった。自分の中に少しばかり、表現することこそが世の中に求められていることだという気持ちがあったことを、坂口恭平に嗅ぎ当てられたような気がしたからだった。恥ずかしい。誰もぼくの表現なんか求めていない。ぼくがぼくの表現を求めているのに、なぜか「何かしなくちゃいけない」と思ってしまう。この矛盾はなんだ?どんどん大学を辞めたくなっていった。
つまり、表現することの意味がわからなくなったのだ。いまもわからないが、意味がないとはもう思わない。世の中はもっと複雑だ。でも、そのときは坂口恭平の言葉を都合よく解釈して、大学を辞めちゃった。ちょうどコロナもあったから、お金の問題も絡んできて、完全に退学に心の針が振り切れた。
でも心配だから占い師に高い金払って占ってもらったりなんかして。2回も。まだまだだなぁ、なんていまは思うけど、そのときは必死だった。
2 はじめた畑 はじまるリテイク
2020年の春、大学を辞めようと決心した頃、坂口恭平が畑をはじめた。それは、すごく楽しそうに思えた。坂口恭平自身はものごとにすぐ飽きるから、一旦お試しでやろうと思っていたらしい。でも、それが続いた。鬱も良くなったと言っていた。もともと、いのっちの電話というのを彼はしている。年間2000人くらい、死にたい人の電話に出ているのだ。彼の電話番号は公開されているし、それを今も続けているから、継続が苦手ということはないはずだった。
なんでもいいからぼくも新しいことをはじめたいと思っていた。そんなときに坂口恭平が畑をはじめたら、ぼくもはじめたくなるに決まってる。大学を辞めて、映画の道を諦めて、まずは、何かやりたいことをやろうと思ったのだ。






結局、長続きしなかったけれど。それしか言うことがない。
やっぱり、ふわふわしていたんだと思う。2020年9月いっぱいで大学も正式に(?)辞めて、いよいよ本当に何もなくなった。そのときのぼくには、ちまちまピーマンやトマトが取れる畑と、少しばかりの貯金と、持続化給付金で得た10万円をはたいて買ったMacBook Pro1つ。もうこれしかない。本当にこれしかなかった。
そんなことはなかった。ぼくには高校の頃から付き合っている彼女がいた。名前をシホという。

同い年で、もうその頃から(つまり20歳から)結婚を考えていたけれど、それは成り行きとしてしか考えていなかった。いま、ぼくはまだ彼女と結婚していない。そんなことができる金銭的余裕はない。結婚に金銭は関係ないけれど、きちんと働けるようになってから結婚したいと思っている。そうじゃないと将来子どもができたときに示しがつかない気がしている。
子どもの話ができるようになったのも、彼女のおかげである。いま生きていられるのも彼女のおかげである。
彼女は占い師に
「あなたは絶対子どもを産む。見えるのは、4〜5人はかたいわ」
なんて言われて
「やった〜産んじゃおっ」
と言っているから、まぁよかった。占い師は
「あなた運命の人3人いるから、いまの人がダメでも大丈夫。心配ないよ」
いやいやそりゃないよ。捨てないで。
捨てるような人ではないことは十分わかっているが、そのときのぼくは、ぼくが彼女の幸せを捨てている可能性はないか、なんて考えていた。過去、民主党と国民新党による菅連立内閣が「最小不幸社会」と唱えていたけれど、まさにそんな感じの考え方だといま思う。それがむしろ前向きだと思っていた。いまもそういうところはあるけれど、うーん、前向きか?なんて思うようにはなっている。
彼女の不幸を最小にしたかった。
話が飛ぶが、ぼくは大学を辞めた2020年9月から、色々考えてやっぱり大学に入り直した。今度は通信制の大学で、3年次編入もできなかったから、また1年生からやり直すことになった。法学部政治経済学科。なんで文学部にしなかったかというと、ふわふわしている自分を固めたかったから、というまたもふわふわした理由である。
2020年9月に大学を辞めたと同時に畑をはじめて、2021年の4月に映画『リテイク』がクランクインしたと同時にその通信制の大学に入り直した、ということである。
2021年4月クランクインから、2021年12月12日クランクアップした映画『リテイク』にかまけていたからか、その年、つまり1年生の年は、単位は憲法の4単位だけしか取れていなかった。いま思い返しても愕然とする。舐めている。
ぼくは何も気づいていなかった。やばいということもわからなかった。だって、映画を完成させることのほうが大事だと思っていたから。ぼくはせっせと2週間に1回髪を金髪に染め直してもらい、髪型を整え、セリフを覚えて、車で2時間神奈川の藤沢まで毎週末走っていった。大変だったけれど、映画を完成させたかった。自分のために。周りが見えていなかった。シホが悲しそうにしていた。
通信制の大学に入り直すことを、シホは良いと思うと言ってくれた。そのときは、シホのためにも大学は出ておかないといけない気がすると話していた。でも、シホのためにできていることは少なかった。映画のためならいくらでも動ける気がしていた。こと、『リテイク』においては。
話が飛んでいるが、ぼくが話したいのは『リテイク』クランクアップ後のぼくとシホとの余談のことである。
ざっくりいうと別れ話。
ぼくは
「こういう話をするのは、最終回だと思ってた」
シホは
「シホも」
何の成り行きで別れ話になったのかは覚えていないけれど、『リテイク』の映画撮影がクランクアップして少しあと、ぼくらは別れ話をした。結局は別れなかったわけだが、色々と話せてよかったと思う。別れ話直後にその気持ちを綴ったものがある。
『破天荒な暮らしを求めて、しほとの生活を見直す、のではなく、しほとの暮らしがそもそも破天荒なんだ、とかんがえる』
書き出しだ。うむ、考えている。
『占い師に、しほとの相性はあまり良くないと言われてから、自分の能力が上手く発揮できないのは、しほと一緒にいることで星の巡りが滞っているからなんじゃないかという思考が頭の中にこびりついていた』
これは、そのままシホに言ってしまったことだ。バカである。
『占いに行ったのも、ロールモデルを提示してほしかったからだ。僕は尊敬できる人しか好きになれない。映画づくりも俳優も畑も、園子温と山田孝之と坂口恭平にあこがれたからだ。三人とも、破天荒なというか、性格も性質も、人生も人とは風変わりなものを持って送っている。僕にとっての憧れだった。でも、今は、その破天荒に乗れば、僕は順風満帆になると思っている。一つ一つ、段階を上って苦労を重ねることで、破天荒な人生が送れると思っている。...果たしてそれは破天荒なんだろうか?もう想像できることなんじゃないか。僕にとっての本当の破天荒な人生は、しほとの生活、というか、しほが破天荒でふりまわされているのが今なんじゃないか』
シホにぼくが振り回されている気がする、ということを、別れ話のときも伝えたのだ。
『破天荒な人生とは、アッと驚くような出来事の連続である。僕にとって、新鮮な驚きは、いつも突然、しほからやってくる。今まで得た知識も哲学も、しほとの関わりの中で実感させられ、血肉になる気がする。破天荒なのはしほである。僕は普通かもしれない。でも、破天荒な人生は送れる、のかもしれない。しほとの関係を通して。僕にとって子どもができるかもしれないことや、本で読んだことだが、そのとき女性の体にかかる負担、しほが僕に頼ってくることなど、思考も体も振り回されることばかりである。僕はそれを望んでいたのかもしれない。しほと暮らせば、平穏な暮らしが想像できる。僕はそれを望んでいたのかもしれない。それこそが、予定調和な破天荒な人生ではなく、一番つかみ辛い、難しい破天荒人生なのかもしれない。まだうまく言葉にできないが、そうやって捉えることで、道が開けるんじゃないか。今、そう思う』
ノートの、次のページ。
『しほと別れ話をした。しほは、終始泣きそうになっている声で、それでも、泣くまいと、僕と話してくれた。泣いたら話せなくなるから。引け目を感じて僕が話せなくなるから、しほは泣かない。僕も泣かなかった。むしろ、話せてすっきりした。僕の思っていることを、多分全部話せた気がする。ストッパーを付けている部分があることも含めて、多分。 ・・・ 別れ話は、電話でした。話は進んだ気がする。しほは、自分の話もしてくれたし、僕は、僕の話をできた、ような気がする。気がする、というのは、僕自身、今まで自分の言葉が、二転三転、ころころ変わることを知っているから、きっと、これからも、新しい言葉がやってくるから、ただ今は、このときは、こう思っていた、というところまでで留めておきたい。一つ、進展があった、というか、僕の中で一つ知れたことでよかったことは、しほも僕と一緒の部分があった、ということだ。しほも、先が見えないし、悩んでいるけれど、僕のことを考えてくれている。僕は、それで心が軽くなった。お金のことも、今後のことも、それはそれとして、今はどうか、ということを教えてくれた。僕は、すぐに周りが見えなくなる。だから、しほがくれる言葉は、僕の視界をひらかせてくれた。いつもそうだけど、最近、ずっと深くそのことを感じる。僕一人では、この現状を受け止めきれないこともわかった。今の僕には周りのサポートが必要だ。絡まっているひもを解くように、物事を一つ一つに戻していく必要がある。それには、周りのサポートが必要だ。今の僕には周りのサポートが必要だ。 ・・・ 「二人はそれぞれの道を歩んで、横を見たら姿が見える、でいいんじゃないかな?」としほは、僕に語りかけた。また、視界が広がったような気がした。それは心強いことに、僕には思える。背中合わせに思える男と女も、一人に思えたなら、きっと、きっと、なんだろう...きっと、前を向いて歩くときも、どんなときも、横に姿が見えたなら、安心するんじゃないか。比ゆでしかない。けど、歩んでいる道と、見えるものは違うから。歩んでいる道と、実際見える景色は、 どうでもいいか。そんなこと。心が軽くなった。嬉しい気持ちにしてくれた。話し合うことって大事だ。知識を得るためではなくて、 どうでもいいか。そんなこと。どうでもよくないこと、話し合うこと。今しかないよこんなこと。話し合えるのは今しかない。話し合おう。話し合おう。話し合える人と出会えたと思ってもいいんじゃないか。話し合う。話し合う。話し合う。話し合う。大人になった、と思って、しほと二人、笑い合ってもいいんじゃないか。大人になった 大人になった 大人になった 大人になったなぁ俺ら なぁ』
ちょっと地に足がついた気がした。
しかし、2020年9月の大学退学時点では畑をやっているぼくはまだ全然地に足がついていないし、そもそも2021ねん4月クランクインの映画『リテイク』の制作にも参加していないから、ただ大学を辞めた坂口恭平のファンだった。バイトも全然していなかったし、何もかも理由が欲しいときで、働く意味がわからないと嘆いていた。
やることといったら坂口恭平の本を読むくらいで、毎日せっせと読んでいた。聴く音楽も坂口恭平で、Twitterを開いても坂口恭平。たまに園子温の映画を観た。ある意味幸せである。
そんなとき、『発光』という坂口恭平のTwitterの言葉をまとめた分厚い本を読んでいたら、鬱から抜け出した3種の神器を坂口恭平が語っているのを見つけた。その中の1つに、はじめてネット番組を買ったと言って、中沢新一と東浩紀と(名前を忘れて)もう1人の3人での対談番組のことが書いてあった。その対談が面白すぎて鬱が抜けたんだとその本に書いてあった。これは観るしかない。そう思って調べたら、ゲンロンのことを知った。
ゲンロンは、社長は上田洋子、有名なのは東浩紀がやっている会社ということで、東浩紀は哲学者、上田洋子はロシア研究者である。その会社の事業の1つが、「ゲンロンカフェ」という対談ネット番組で、それを観て坂口恭平は鬱が抜けた。だからぼくも買ってみた。



はじめて観たゲンロンカフェは、たしか浅田彰の還暦祝いイベントで、東浩紀が赤い上掛けを浅田彰にかけて、それでイベントが始まった。登壇者は浅田彰、東浩紀、千葉雅也だった。なぜはじめてなのにそれを買ったのかはもはや覚えていないが、とにかく、3人が言っていることが何もわからなかった。テーブルに左から東浩紀、浅田彰、千葉雅也と並んで座っていたが、真ん中のおじいちゃんが長々と話しているだけで、左の中年男性と右の兄ちゃん風の男性は何も話さず頷いているだけ。おじいちゃんが話し終えると、もう番組開始から30分くらい経ってたんじゃないかな。なんだこれは、と思った。横の2人何も聞いてないだろうと思ったら、めちゃめちゃ話聞いててびっくりした。何一つ話していることがわからないのに面白かった。
それからゲンロンカフェにハマったのだ。それ以降今に至るまで、ハマり続けている。それくらい影響を受けている。しかもふわふわしていた時期だったから、また感受性を刺激されてしまって、坂口恭平にハマってはじめた畑が何だかしっくりこないと思っていたから、今度はゲンロンカフェばかり観るようになってしまった。シホは
「ほんと、スポンジね」
わかってるんだけど、どうにもならなかった。
結局、畑はやめることになった。やって良かったとは思うけれども、別にやることが畑じゃなくてもよかったなと思った。ゲンロンカフェには依然としてハマり続けていたし、2020年の冬の時点では、この先のことは何も決まっていなかった。そんなときに、TwitterのDMがきた。そんなこと滅多にないから、誰だろうと思って見たら、造形大学の講師だった日下部先生からだった。
日下部先生はすごく優しそうな先生で、実際優しかった。ただ、ちゃんと話す機会がある前にぼくが大学を辞めちゃったから、気になる人だなぁと思うだけで何も進展はなかった。それなのに、急にDMがきた。内容は、自分の知り合いが今度映画をつくるから、もし暇なら参加してみないかというものだった。脚本、読んで考えます。そう答えて、しばらくしたら脚本が送られてきた。
嬉しかった。大学を辞めたあとも気にかけてくれてたんだと思うと泣きそうになった。ああ、いま思うと、嬉しい気持ちから映画をつくりはじめたのはこれが初めてかもしれないな。だから没頭しちゃった部分もあるかもしれない。とにかく嬉しかった。
読んだ脚本がすごく面白くて、それじゃあ監督と会おうかということになった。その監督が映画『リテイク』の中野監督である。
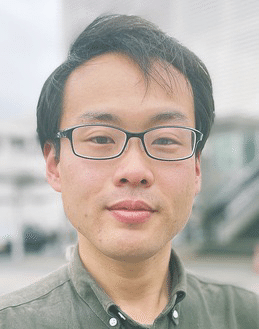
会ったときのことはぼんやりと覚えている。気の弱そうな人だなぁと思った。全然そんなことなかったけど。
ぼくの役は「ジロー」だと聞かされていた。中野さんは、
「個人的には、千葉くんのつくった映画が『金次郎の夏』っていう題名だったから、ジローじゃん!って勝手に縁を感じてた」
ああ、そうですか。
ちゃんと自分で物語をつくる人なんだなと思った。
はれて映画『リテイク』のジロー役に抜擢されたぼくは、映画の道を諦めたはずなのに、映画づくりをすることになった。ウキウキする気持ちしかなかった。脚本は面白いし、映像にしたらどういう風になるんだろうと妄想した。実際は、撮りはじめると中野さんのやりたいことの過激さが見えてきて、驚くのであるが。
映画『リテイク』のキャスト・スタッフの顔合わせは、神奈川県のどこかで行われた(もう地名は覚えていない)。まず、お酒やらジュースやらを飲んで親交を深めようというので、レジャーシートと飲み物食べ物を抱えてまだ桜が満開になる前の川沿いに行った。そこは街中だったから、河川敷みたいな場所はなく、コンクリートの高架下みたいな場所で橋の下を陣取ってみんなで話し始めた。ビュービュー風が吹いてきて、雨も降ってきたから、飲みなおそうということで、みんなで走ってカラオケに向かった。改めて周りを見渡すと、中野さん以外みんな20歳前後。1人2人20代後半もいたかな。でも、明らかに中野さんだけがおじさんで不思議な空間だった。ぼくはそのとき場を盛り上げようと思ってあることないこと言ってしまったが、それを除けば良いみんなとの初対面だった。そのときは、もうすぐ春になる頃だった。4月になれば、撮影がはじまる、そう思いながら生活していた。
3 中野さんのやりたいこと
そもそも、中野さんはどんな映画をつくりたかったのか?そして実際、どんな映画をつくったのか。撮影の裏話を交えながら考えてみたい。
ぼくの考える中野さんの映画づくりは、過激なものだ。
まず、映画『リテイク』の趣旨を説明しよう。

ある夏、高校生が夏休みを利用して映画を撮ろうとする。映画づくりは比較的スムーズに進むが、至るところで人間関係に亀裂が走る。そこには各々の物語がある。恋愛模様や、友情、夢がないことの焦りなどが描かれる。わかりやすい青春映画だ。
あらすじとしては、主人公の青年ケイが、ヒロインであるユウと、ひょんなことで出会い、ユウの映画づくりに半ば強引に参加させられることからこの映画『リテイク』ははじまる。


ユウは監督、ケイはカメラマンとして映画をつくろうとするが、キャストがいない。録音がいない。そこで、キャストにユウの後輩のウミと、ケイの中学時代の同級生ジローを招き、録音にユウとは友情に亀裂の入ったままの親友であるアリサが加わり、本格的に映画制作がはじまる。



ユウとアリサの友情に亀裂が入った理由、これは映画内でも丁寧に説明されるが、ユウとアリサはバンドを組んでいた。ユウがギター&ボーカル、アリサがベース、もう1人ドラムがいて、このドラムの青年がユウのことを好きになってしまう。ユウは別に好きでもないのにその青年と付き合ってしまい、結局別れることになるのだが、その結果バンドの空気は悪くなり、ユウのやる気が落ちてしまう。そして、ユウはバンドを辞めてしまう。そんなユウに、アリサは怒るのだ。「あんたの中で音楽はそんなもんだったの?」と。
それなのになぜアリサが映画づくりに参加するのかは、ひょんなことで、という他ないが、アリサ自身は「どんなもんか見てやろうと思って」なんて言っている。本音ではユウのことが羨ましいのだ。そしてその気持ちは、「もっとユウと音楽がしたかった」という不完全燃焼の気持ちからきている。アツい人物だ。
いずれにせよ、彼女はもっとユウと音楽がしたかった。だからユウと映画づくりをする。このねじれに気づかないまま、アリサもユウも表面上はスムーズに映画づくりを進めていく。思春期の人物は、「なにに」情熱を燃やすかを常に気にする。それが絆の拠り所だからだ。その思春期の部分を残しつつ、けれども、「誰と」時間を共にしたかを重視する共同体的な感覚も持っているから、アリサは、「ユウと」「音楽」がしたいけれども、「ユウと」「映画」をつくるという矛盾を抱える、とぼくは考える。もうすでにアリサはユウとの、その「と」に関する友情を感じているにも関わらず、まだ音楽に固執している。アリサは音楽が好きなのではなく、音楽が好きなユウしか知らないのだ。このねじれを映画『リテイク』は、まず描く。
一方で、恋愛模様も描かれる。恋仲になるのは、ジローとウミである。ジローとウミは映画『リテイク』内でつくられるユウの映画の中で主役として演じており、だんだんと仲良くなっていくから、わかりやすくくっつく。他方、ケイのユウに対する恋心も描かれる。ケイは、ユウに対して恋をする。だが、それは、ユウにとっては「よそ見」でしかない。なぜなら、映画づくりに心血を注ぐのが、ユウにとっての恋みたいなものだったからだ。
まあ、ここら辺は映画を観ればわかる。とりあえずは、人間関係に亀裂が走る要素がいくつかあるということがわかってくれればいい。重要なのは、次のことである。
『リテイク』では、途中、映画にカットがかかる。この『リテイク』という映画自体にカットがかかる。そして、物語は夏休み序盤から、また「リテイク」される。先ほど、ケイはユウに恋心を抱いたが、ユウからすればそれは「よそ見」以外のなにものでなかった、ということを述べた。まさにそれが理由で、ユウは映画づくりを辞めてしまうのである。電話でユウからそのことを聞いたケイは、うなだれて、動かなくなってしまう。と思いきや、スッと顔を上にあげ、「カット」とつぶやき、こちら(観客)の方に近寄ってくるのである。
そして、映画はまた冒頭のシーンへと戻ってしまう。
少しばかりちがう物語のルートを通りながら、彼らの映画づくりはまた少しずつ進んでいく。その後も、何回かの「リテイク」を重ねる。何度も何度も映画づくりは危機に瀕する。けれども、なんとか彼らは映画づくりを進められる。この映画『リテイク』は高校生たちの映画づくりを最後まで見届けることができる「かもしれない」という、そういう映画なのである。なにを言っているかわからないかもしれない。しかし、本当にこういう映画なのだ。
あらすじと、大体の趣旨はこれでわかってくれたと思う。いま一度整理すると、この映画『リテイク』は、ある夏の高校生たちの映画づくりを描きつつも、ループ映画でもあり、しかしまったく同じループは繰り返さないし、いつかは映画が完成する「かもしれない」という映画である。実際は『リテイク』の中で、彼らの映画は一応は完成するのだが、中野さん自身、「そうじゃないかもしれない」装置を埋め込んでいる。
映画の冒頭、ヒロインのユウの鼻歌が聴こえてくるが、その鼻歌は、「リテイク」されたあともまた聴こえてくる。つまり、この映画は冒頭から、すでに何度目かの「リテイク」「かもしれない」ということを示唆しているのである。
具体的に話そう。映画の冒頭は、湖のカットからはじまる。そのあと、ユウの(この時点ではユウということはわからない)鼻歌が聴こえ、主人公ケイの寝顔が映される。この映像と鼻歌は、「リテイク」されたあとも同じように流れるのだ。重要なのは、主人公ケイがまだユウの存在を知らないにも関わらず、映画の冒頭にその鼻歌はすでに使われており、しかも「リテイク」されるたびにまたその鼻歌が流れていることである。
これは、観客の物語に対する信用可能性の地盤を切り崩すことになっている。ぼくがそのことを指摘したら、中野さんは
「それもありかな、と思ってる」
と言って、ぼくは驚いた。つまり、中野さんは、ケイが映画を完成させられようがさせられまいが、どっちでもいいのだ。それは観客自身が思うことであって、中野さんのやりたいことではない。中野さんはケイに映画づくりを終えてほしいと思っていないし、終えないでほしいとも思っていない。それはケイの問題であって、中野さんのやりたいことは別にあるのである。
たぶん、なにを言っているかわからないかもしれないが、おそらく、これから話すことでわかってもらえると思う。たぶん、とか、おそらく、とか、もう信用可能性が崩れかけているが、それはともかく、中野さんにはやりたいことがあった。それはなにか。
映画『リテイク』を観たらわかるのだが、この映画はループするし、登場人物が何回も同じことを繰り返したり、同じ風景が映ったりするから、これらは観客からしたら全て「同じもの」なのである。「同じもの」なのに、ちょっと違う。「同じ時間」なのに、出来事が違う。そうやって映画『リテイク』は進んでいく。
たとえば、1回目の「リテイク」では、1テイク目のアリサは、映画づくりの最中、なにかの音が気になってそれを録りたいとユウに申し出る。でも、ユウは必要ないと軽くあしらってしまう。1テイク目はそれで終わりなのだが、「リテイク」したあとの2テイク目では、アリサがユウに音が録りたいと申し出ると、ユウがそれをあしらった後に、ケイが「いいんじゃない?録っても」と割って入ることで、少し違う分岐に入るのである。
これが「同じ時間」なのに違う出来事になる、ということであるが、ぼくが感じてほしいのは、当たり前のことだがあまり意識しないところのことである。たとえに出したシーンを例に挙げるならば、このシーンは、最低でも2回撮っている、そのことを感じてほしい。
「なにを当たり前なことを」というかもしれないが、その当たり前のことを感じてほしいのである。中野さんは、繰り返しのシーンを、かならずもう1回撮っている。つまり、同じテイクの使い回しがないのである。
ふつう、繰り返しを演出する場合、よく使われるのは、同じテイクを何回も使う、である。そのことで繰り返しの演出を行うのだが、中野さんがやっているのは、繰り返しを演出はするが、しかし「違っていることを描くこと」。これである。まだわかりにくいかもしれない。
最後に、このことを徹底したシーンの撮影の裏話を1つしたい。この映画の最初から最後まで挿入される、湖のカットについてである。
この映画の構造は途中でカットがかかり、映画がまた最初の場面にあるいは少し前の場面に戻るというものだが、その「リテイク」の最初のシーンは、必ず湖のカットを背景に、「take1」だったり「take2」だったりを書いたカチンコを用意して、「テイク2!よーい、ハイ!」とカチンコを鳴らす。これはテイクが変われば、「リテイク」のたびに表れる。この湖のカットは中野さんが1日で撮ったものだ。10近くのテイクを映画『リテイク』は「リテイク」して繰り返すから、1日で撮りきらなければ面倒である。それに、この湖は山奥にあるので、わざわざ「リテイク」のたびに撮りにくる、ということもできない。だから1日で撮り切るのだが、その「撮り切り方」が、中野さんの特徴的なところだった。
ふつうなら、湖を背景に、カチンコを用意して、「テイク1!よーい、ハイ!」とカチンコを鳴らしたら、しばらく湖を撮って、カットをかける。そのあと、カチンコに書かれた「take1」の文字を「take2」に変えて、もう1度同じことを繰り返せばよいのである。しかし、中野さんはそうはしなかった。「take1」〜「take3」くらいまではその場で撮り切ったのだが、そのあとの「take4」〜最後のtakeまでは、映画『リテイク』の繰り返しのシーンを撮ったあとに撮っているのである。

下手な図だが、A地点から撮っているのが湖とカチンコのカットであり、B地点から撮っているのが、ループの中で何度も出てくるイメージのカットであり、C地点はB地点と同様の意図のカットである。「take1」〜(おそらく)「take3」までは先ほどもいったようにA地点でそのまま撮り切っている。しかし、この湖のシーンで繰り返されるクライマックスのシーンは、まずA地点から撮ったあと、わざわざB地点に移動して、そのあとC地点、そのまたあとにやっと次のテイクの撮影がA地点ではじまるのである。これを、たしか4回は繰り返した。
映画を撮影したことのある人なら誰しも思うだろうが、こんなことをしたら陽の位置が変わってしまうし、シーンの雰囲気も、時間帯も、別物になってしまう。実際、PFFの審査員からもそういった趣旨のコメントがあった。映画『リテイク』のクライマックス部分は、湖のループのカットが何度も挿入されるにも関わらず、先ほどの撮影順序に従って撮影を行なっているので、だんだんクライマックスに近づくにつれて日が暗くなっていっているのである。あれ?時間経ってない?と思う。ぼくも同感である。カチンコを打てば、時間は巻き戻る。そういう設定のはずだ。しかし、思い出してほしい。中野さんは、主人公ケイが映画を撮り終えてほしいとも、撮り終えないでほしいとも思っていない。中野さんのやりたいことは別にある。だから、主人公ケイの時間がちゃんと巻き戻っても、巻き戻らなくても、どっちでもいいのである。中野さんはドラマがやりたいわけではない。じゃあ本当になにがしたいのか。ぼくは、「時間が過ぎること」と「行為」を映画の中で結びつけたかったんだと思う。
ここでいう「時間が過ぎること」というのは、ざっくりいうと変化のことである。どんなものにも変化はつきものだ。その変化はなぜ起きるかというと、ただ時間が経つからというわけでもない。なにかしらの「行為」がなければ変化は促されない。逆もまた然りだが。
「時間が過ぎること」と「行為」が裏表の関係になって、やっと中野さんのやりたいことが見える気がする。結論を言ってしまうと、「時間が過ぎること」+「行為」=「映画撮影」である。中野さんは映画が撮りたかった。それだけである。
ここまで長々と書いて、結局それなのか、と思うと思うが、安心してほしい、このあとちゃんと、次の展開につながる。ただ、ここまで書かないと、中野さんのやっていることへのリスペクトは感じられないと思ったのだ。だからってダラダラと書いたつもりもないし、ある程度的を得ているとも思っているが、いずれにせよ、中野さんは「映画撮影」それ自体がしたかったというのは本当である。本人も否定はしないだろう。
とはいえ、それだけだとこの映画のユニークさは説明できない。そこでぼくが思うのは、中野さんは「映画撮影」それ自体を映画にしようとしたんじゃないか、ということだ。これが、「時間が過ぎること」と「行為」を映画の中で結びつけたかったのだ、と言ったことの本当の意味である。ここがいちばん重要であると考える。
さっきも言ったが、中野さんの撮影方法はかなり異様だった。ループものなのに同じテイクを使わないし、あえて「同じ時間」のシーンを順番に撮ったりするから、現実世界の時間が過ぎていって映画の中のループ映像のループ感と齟齬が起きている。なぜなら明らかに日が暮れているから。なぜこんなことをわざわざするのかというののぼくの1つの仮説が、「映画撮影」それ自体を映画にしたかったのではないか、ということだ。
こうなるとまた「映画撮影」それ自体を映画にするとはどういうことかっていうのを説明しなきゃいけなくなるんだけど、本当に長々と申し訳ない。まとめて話せない。とりあえず、ぼくが言いたいのは、ぼくの考える中野さんが考える「映画撮影」というのは、映画に映らないものなんだ、ということ。たとえば、さっき「時間が過ぎること」+「行為」=「映画撮影」と書いたけど、「時間が過ぎること」っていうのは単純に光源だけ撮ってれば、つまり太陽だけ撮ってれば勝手に沈んでいくんだからできてしまうと思う。これで時間が過ぎていることになるのかって思うかもしれないけれども、むしろぼくらの視覚情報としての時間感覚は光源=太陽に依存しているから、カメラでそれを表現するならそれが端的である、というのがぼくの考えだ。一方、「行為」を表現するにはどうしたらいいかっていうと、これはまぁアクションのことだから、つまり動きだ。動いてるものを撮ればいいと思う。シネマトグラフの語源は「動きを書きとる」だから、語源的にもぴったりくるだろう。それで、なんでこの2つを足すと「映画撮影」になるかっていうことだけど、端的にいってさっきいったような定義の「時間が過ぎること」と「行為」を一回で表現できるメディアは映像しかないからだ。別にアニメーションでもできるけれども、CGとかでも、でも、まぁ、今回は中野さんはカメラを持って撮ることを選んだ。だからこそできることもある。それが先ほどの撮影手法で、それによるある効果である。
ぼくはいま、その効果をある映画で思い起こした。『シン・エヴァンゲリオン』である。大きくでた。ちょっとこわい。でも、あながちこの感覚は間違ってないんじゃないかと思う。ここで『シン・エヴァ』の映画の趣旨を説明する気力はもはやないが、とりあえず触れたいところだけを説明すると、『シン・エヴァ』は、後半で、セル画をそのまま映像に使っている。セル画とは、色を上からつける前の、簡単にいえばラフ画(?)みたいなもの、のはずである。あそこだけ見ると、ただ手描きの絵がアニメーションっぽく映っているようにみえる。庵野秀明がなぜそのシーンを挿入したのかは本当のところわからないが、推測するに、ある種現実世界の手ざわりみたいなものを感じさせたかったんじゃないかと思う。『シン・エヴァ』はいうまでもなく大ヒット映画で、そもそもアニメにそんなに興味のない人も観るくらいには想定視聴者が広い映画だ。アニメを観る人でも、そもそもどうやってアニメがつくられているのか知らない人も少なくない(ぼくも含め)。そこに、現実世界の手ざわりを埋め込むことが、「さようなら、全てのエヴァンゲリオン」に込められているメッセージの1つではないか?とシンプルに思うので、まぁ、ざっくりいうと、アニメばかりじゃなくて現実世界にも目を向けようぜ!てな感じが少しある。でも、確実にある。
その感覚と、中野さんの撮影手法は感覚として少し似ている。先ほども述べたが、映画『リテイク』を観ただけでは中野さんの撮影手法にまで思いが至るかはわからない。それよりも、だんだん日が暮れているなぁ、ループなのに。という感想を抱かれてもおかしくはない。ただ、中野さんの撮影手法は、さっきいった現実世界の手ざわりをわざわざ残したやり方なんじゃないかということだ。
アニメーションは絵だ。手づくりだ。しかし、なかなか現実世界と結びつけて考えられることは一般的には少ない、気がする。そこを意識してぼくは『シン・エヴァ』はつくられていると思っている。そして、映画『リテイク』も、そうなんじゃないか。『シン・エヴァ』は手描きのセル画を残した。アニメーションの外部として人の手仕事を残した。映画『リテイク』も、人の手仕事を残したのではないか。なんのために?ループだけれどもその映画に映らない部分で人が移動していることを意識させるため。なんの得がある?わからない。けれども、もしこの「リテイク」が10やそれどころじゃなく1000とかあった場合、冗談じゃなくそうかもしれない構造で映画『リテイク』はつくられているから、そうなっている場合、ループなのに「映画撮影」の時間はかかるから、たとえば夜中の2時なのにまた同じループをしてたりするんじゃないか。1000テイクとかになったら、7日後になるかもしれない。人はそんなに、テイクを重ねられない。でも、やろうと思えばやれる。これはほんとうに。でもそうはしない。繰り返したり、繰り返さなかったり。でも、繰り返される「かもしれない」想像力だけは残したい。そのせめぎ合いが、中野さんの撮影手法によって、映画『リテイク』で表現されているのではないか。「映画撮影」における想像力と実際の仕事のせめぎ合い。これを「映画」で表現するならば、「映画内映画」や「ループ」や「ループにも関わらず日が暮れる撮影手法」を経由しなければならなかったのではないか。そんなふうに、思うのだ。
中野さんがやりたいことというのは、こういうこと、だったんじゃないか?と思う。でも、ただの推測だし、妄想だ。それに、その撮影手法も、ただ日が暮れていると思われればそれまでだ。でも、ぼくはそれを間近で見たから、興奮が冷めやらないのである。おもしろかった。なにをしてるんだろうこの人と思った。時間がない時間がない、日が暮れる日が暮れる、と言いながら、A地点からB地点、B地点からC地点、C地点からA地点へと、ひたすらぐるぐるぐるぐる撮影し続けていた。着実に日が暮れるけれども、中野さんは無言でそれを肯定していた。そんなおもしろい映画撮影があるだろうか。この「時間」に対する感覚はなんだ?「ループもの」というのは、ある出来事に対する固執と捉えられるけれども、出来事に固執しつつ時間は過ぎていくその感覚を、映画でそのままやり、なおかつ青春映画としてわかりやすくつくるということをやっている。何者だ?不思議だ、不思議だ、ずっとそう思っている。
4 リテイクの完成とあたらしい生活
とはいえ、中野さんのそういった撮影手法が見れたのは、撮影がはじまってから終わるまでの半年間でいうと中盤あたりだけだった。それまでとそのあとも撮影は続くし、もろもろに手間暇がかかる。
とりあえず撮影は完了して、まぁ、いよいよPFFにも選ばれて、国立アーカイブで上映である。いま、ぼくはその会場に向かいながら文章を書いている。
楽しめるだろうか。自分の演技はともかくとして、以前みせてもらったときから再編集もされているし、また違う感じ方になるのかもしれない。いずれにせよ映画の構造は変わることはないし、もしいまから観て先ほど書いた感覚と違うものを感じたとしたら、またそれは書きたい。
とりあえず、ここまで書いたけど、ぼくの中で映画『リテイク』は終わっていない。そもそもそれが終わるってどういうことだと思うが、ぼくの実感はそうなのである。中野さんの言葉を借りれば「次に進めない気がした」というところだろうか。
ただいま13:29。映画『リテイク』の上映は14:30からだ。いま南砂町駅に着く。14:00には国立アーカイブに着くはずだ。そのあとみんなと映画を観る。それだけだ。それだけ。
ただいま13:30。南砂町駅に着く。階段を降りる。改札を抜ける。
ただいま13:31。電車に駆け込む。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
