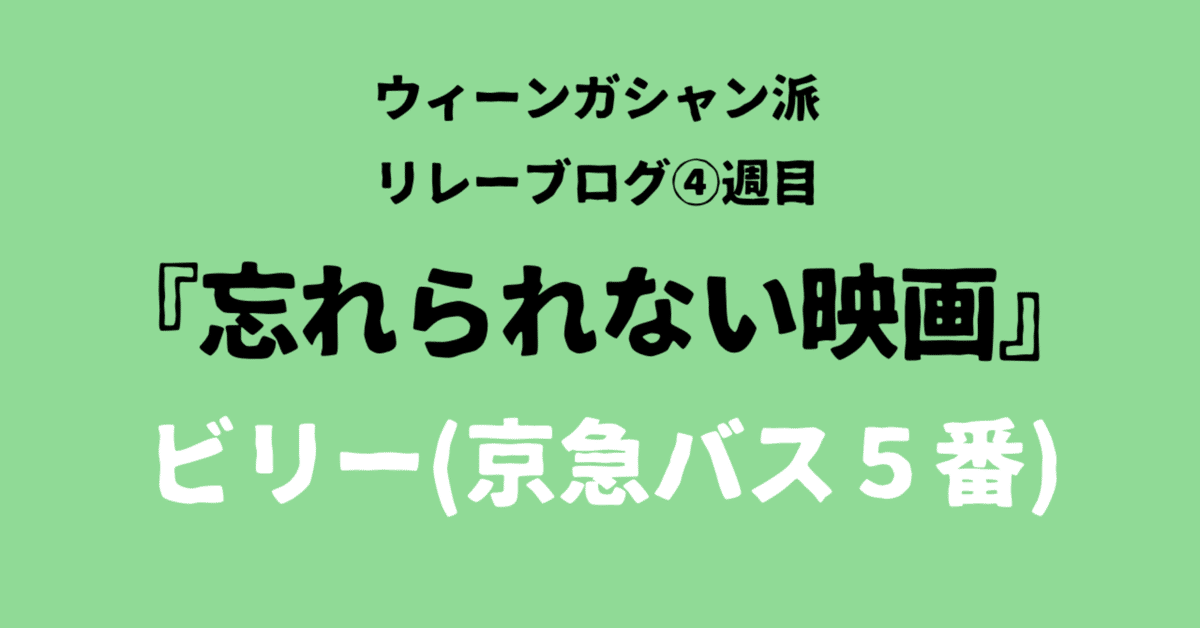
『太陽がいっぱい』/ビリー(京急バス5番)
めっきり映画を見ない生活になってしまった。見ることがあっても、月に二、三本を消費する感覚で流す程度で、それはおおよそ、忘れられない映画と出会える態度ではない。正確に言うと、忘れられない映画になりそうだと思う映画はそのような契機で選ばない。いずれ来る、忘れられない映画と出会いたくて仕方がなくなるその時にまとめて見ようと思う作品が三十本ほど。これはまた別の機会にしよう。
そんな自分がこのたび忘れられない映画として挙げるのは『太陽がいっぱい(Plein Soleil)』である。監督はルネ・クレマン、音楽はニーノ・ロータで主演はアラン・ドロン。あらすじ等は割愛する。各自見るように。この映画を見たことがある場合、この映画が果たして忘れられない映画と呼ばれるタイプなのか疑念を持つかもしれないが、それはご指摘の通りかもしれなくて、これを挙げるのは個人的な嗜好がゆえだと認める。なので、ここでは映画そのものよりも個人的な嗜好についてベラベラと語らせてもらうようにする。
犯罪が好きだ。犯罪史も好きだし、犯罪者も好きだ。もちろん、犯罪に対して憎む気持ちもあるし、犯罪者に対する処罰感情、嫌悪も社会通念レベルには備えている。ただ、いかんせん惹かれる。何故か。それは第一に理解できないからだ。いわば異界である。凡庸な日々の対極、究極の非日常がそれである。犯罪に関わる人間の精神状態は想像することも出来ない。しかし、犯罪の魅力の真骨頂は、そのような非日常が、ふとした日常に唐突にぽっかりと風穴をあけて、あんぐりと口を開いて我々を飲み込む可能性を常に孕んでいる事なのではないかと、こう思っている。まあ、勉強机の引き出しが実はタイムトラベルの入口だということにワクワクすることと、本質的に変わりない。
『太陽がいっぱい』は犯罪映画であるが、この映画を見たとき、犯罪に対する日常と非日常の混濁と、遠いようで近い異界の淵に半ば強引に連れ出された感覚があったのだ。人の物を盗もうと思ったことはあるだろうか。どれくらいの解像度でその顛末を想像したことがあるだろうか。あるいは、もう時効だなどとたかをくくっているような、はるか昔に犯してしまった罪はないだろうか。なかったことには出来ない。自供して人から蔑まれ、償うまで罪悪感を感じるべきだ。それが嫌であれば隠し続けなければならない。なんて野蛮だ。卑劣だ。最低だ。
この瞬間、自称純潔の不届者を異界が一口に飲み込む。
常識と法律と倫理から解き放たれた自然状態の発想。それは残酷ながらも懐かしい。まさしく異界への懐古だ。この映画は我々に異界を見せてくれる。忘れ去られることはない。
書き手:ビリー(京急バス5番)
テーマ:忘れられない映画
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
同一テーマについて、
曜日毎の担当者が記事を繋ぐ
ウィーンガシャン派のリレーブログ。
今週のテーマは『忘れられない映画』
明日、水曜日は「べこべ」が更新します。
ウィーンガシャン派は11/20(日)文学フリマ東京35に出店予定です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
