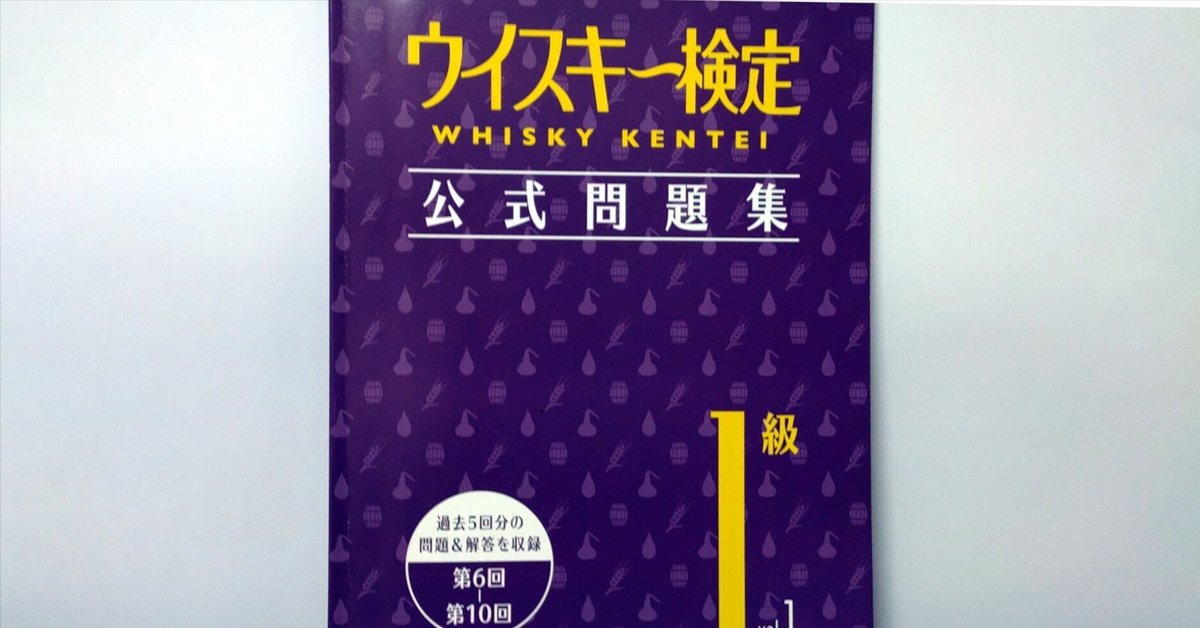
ウイスキー検定1級への道 その1
ウイスキー好きのみなさま、こんにちは。
本日から、2024年2月23日(金)に開催される
「ウイスキー検定1級」試験の合格を目指して勉強し、
その道中を記事にしていきますのでよろしくお願いいたします。
1.受験しようと思ったきっかけ
まずなぜウイスキー検定1級を受験しようかというところからです。
ウイスキーを飲み始めて十数年、
国内外の蒸溜所を見学したり大型イベントに参加する中で、
大手の最新の取り組みや新興蒸溜所の創意工夫を目の当たりにして
もっとウイスキーについて
ちゃんと知りたいなという気持ちが日々募っておりました。
でも、ここ一、二年は某感染症蔓延にかまけて
あんまり意欲的に情報収集をしておらず、
折角得た知見が時と共にうやむやになっていくのを体感しています。
ということで、2024年は心機一転、一通り学び直そうと決めました。
取り掛かりとして、直近で手ごろに受けられそうなのが
ウイスキー検定だったので、ウイスキー検定1級を受験してみるか!
と思ったわけです。
勉強を始めるにあたりその手引きとなるブログやSNSまとめを
ざっと探してみたのですが、見当たらなかったので、
じゃあ自分で勉強しがてらまとめてみようかな?という
軽い気持ちでこのノートを始めてみました。
同じようなことを考えている方の参考になれば幸いです。
2.そもそもウイスキー検定とは?
まず、そもそも、ウイスキー検定とは
ウイスキーをもっと知り、もっと楽しむための知識を問う試験です。
世界のウイスキーを対象に、歴史、原料、製法から様々な飲み方、ウイスキーにまつわるうんちくまで、奥深いウイスキーの世界をより楽しむための知識を問います。(公式ホームページより)
1級の累計受験者数は 1,112人で、累計合格者数は298人だそうです。
合格率は27%となかなか狭き門のようですね。
3.ウイスキー検定1級の難しさ
ウイスキー検定1級に挑戦するには、
・ウイスキー検定2級に合格している
・ウイスキーコニサー試験に合格している
(ウイスキーエキスパート/ウイスキープロフェッショナル
/マスターオブウイスキー)
のいずれかを満たしている必要があります。
私はどちらも満たしてはいるのですが、
最後に机に向かったのは3年前なので
過去の遺産はあるような、ないような微妙な状態です。
そして、合格するには100点満点中80点以上獲得しなければなりません。
専門知識を問う資格試験としてはなかなかに高いボーダーに思えます。
さらには、1級のみ選択問題だけではなく記述問題があります。
専門用語/地名/人名を正確なアルファベット、漢字で書く必要があります。
この記述問題がとても厄介に思えて仕方がありません。
例えば、「竹鶴政孝をスコットランド留学に送り出した摂津酒造の当時の上司は誰か」という問題があったとします。
①鳥井信治郎②佐治敬三③岩井喜一郎④本坊東吉⑤小西儀助
のように選択肢が与えられれば、
正しく知っていれば、「③だ!」と即答できますし、
記憶が曖昧であっても
・鳥居信治郎は竹鶴政孝をヘッドハンティングしたから違う
・佐治敬三は鳥居信治郎の次に社長になった人だから違う
・本坊東吉は岩井喜一郎をヘッドハンティングしたから違う
・小西儀助は鳥居信治郎の奉公先だから違う
というように消去法で③という正解を導くことができます。
でも、記述せよと言われると
「岩井ってウイスキーがあるから苗字は憶えているけど…」
「喜一郎?輝一郎?わからないや…」
ということが起こりえます。
ウイスキー関係の漢字は常用外であることも多いので正確に暗記しなければ得点源にすることができないのがたいへんなところですね。
また、受験者平均点が67.0点であることから、
選択問題のレベルもなかなかに高いことが伺えます。
4.合格へのロードマップ
このように、なかなかに難しい挑戦となりそうなので、
漫然と勉強するわけではなく条件を縛って取り組んでいきます。
まず、
勉強期間は本日1月10日(水)から本番2月23日(金)までの45日間とします。
そして、別途国家資格の勉強をしている息抜きとしての受験なため、
平日1日1時間/土日2時間程度の勉強時間でチャレンジしてみます。
この条件で1ヶ月半…間に合うのか?という不安はありますが、
勉強期間を長くとれば合格率が上がるという性質のものでもないので、
短期・短時間集中で頑張ってみることにします。
この限られた時間の中で成果を出すには優れた戦略が必要です。
受験経験者によると、5~6割程度は過去問から出題されるらしいです。
となると、過去問は繰り返し解いて同じ問題は必ず正解できるように
する必要がありますね。
ということで過去問演習を優先順位1位にもってきます。
次に、問題を何となく分類してみます。
A 地理
B 歴史
C 商流(所有会社や特筆すべき商品など)
D 製法
E カクテルなど
といったところでしょうか。
このうちCの商流に関しては、度重なる業界再編や時事ネタが絡み、
確実な得点源とすることは難しいように思えます。
過去問を完璧にしつつ、気分転換にウイスキーガロアを流し読みする
くらいに留めるのが得策かと考えます。
これに対し、Aの地理/Bの歴史/Dの製法は、
もちろん新しい動きもあるものの、
基礎となる事実は変わりようがないので、
厳密に理解し得点源とすべきだと考えます。
Eのカクテルは出題されても1~2問なので過去問をやるくらいに留めます。
そして、
α スコットランド
β 日本
γ アイルランド、アメリカ、カナダ
δ 新世界
のように分けることもできるかもしれません。
ここについてもやはり優先順位があるでしょう。
ウイスキー検定を実施するウイスキー文化研究所という団体は、
元々スコッチ文化研究所という名前でしたので、
αのスコットランドはかなり出題数が多いことでしょう。
また、
βの日本については、最近「ジャパニーズウイスキーイヤーブック」という書籍が発売されたことから、重点的に出題されるのではないかと考えます。
最新の蒸溜所の情報もおさえておかなければならないでしょう。
γのアイルランド、アメリカ、カナダに関しては、5大ウイスキーという
団体が提唱する括りからそれなりに出題されるでしょうが、
・アイルランドは新興の勢いが凄いがまだ数えられる範囲
・アメリカはマイクロディスティラリーの数が2,000を超えたと言われる
・カナダもアメリカ同様爆発的に増えている
という状況から察するに、アイルランド>アメリカ>カナダの順に
重きを置いて勉強するのが良いように思われます。
δの新世界については、
・オーストラリア(タスマニア)
・台湾
・インド
あたりが定番でしょうか。
・イングランド/ウェールズ
・フランス
・イタリア
・フィンランド
・イスラエル
あたりも出るかもしれませんが、
・ドイツ
・オランダ
・南アフリカ …
手を広げだすとキリがないので、過去問を中心に勉強することにします。
ということで、方針としては、
1 過去問を解く
2 躓いた問題のうち、地理/歴史/製法は周辺知識も含めじっくり学ぶ
3 商流はスコットランドと日本についてを中心に学ぶ
4 アイルランド>アメリカ>カナダ>新世界はほどほどに、カクテルも
という感じです。
忘れかけていることを思い出し、日々のウイスキーライフに潤いをもたらすことが目的なので、合格不合格で何が変わるわけでもないのですが、
折角であれば合格したいところですね、頑張ります!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
