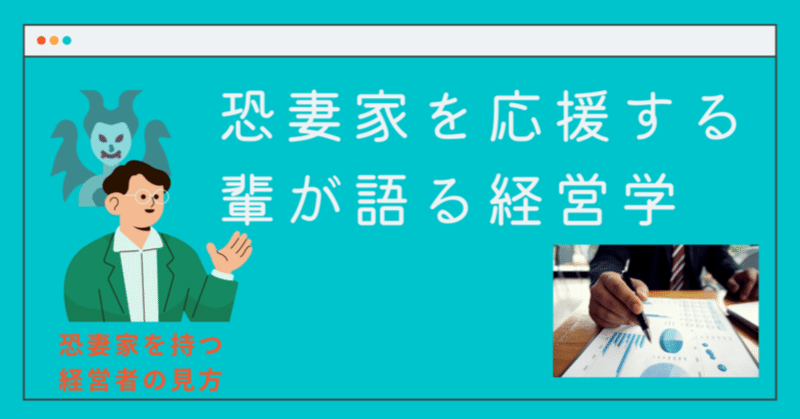
恐妻家から学ぶ_わかりやすい労災保険④
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
今回、業務時間中に生じたパワハラやセクハラといった社内問題により患った疾患に関しても労災として認められるようになりましたので、そのあたりをわかりやすくお伝えします。
(1)精神疾患
勤務時間中の業務による直接的なケガや病気だけでなく、長時間労働やパワハラなどを原因とした精神疾患についても、2020年の労働施策総合推進法の改正に伴い、労災保険の補償が受けられるようになりました。
ただし、精神疾患については他の労災とは別に認定基準が設けられており、労災の認定を受けるには認定の要件を満たしていることが必要です。
(2)精神障害の労災認定要件
精神疾患の場合は、原因が業務によるものなのかという業務起因性の判断が難しいとされています。
このため、うつ病や適応障害などの精神疾患については、精神障害の労災認定基準が設けられています。
①認定基準の対象となる精神障害を発病していること
業務に関連して発病する可能性が高い精神障害として、うつ病や急性ストレス反応、適応障害などがあげられます。
②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
強い心理的負荷がかかる業務をおこなっていたかどうかは、「業務による心理的負荷評価表」を用いて判断されます。
評価表を利用し、心理的負荷が「強」と評価されたのであれば要件を満たしたことになるのです。
例えば、直近1か月間の時間外労働が160時間超えるなどがあります。
心理的負荷評価表については『厚生労働省のホームページ』で確認可能です。
③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと 精神障害の既往症やアルコール依存などの、個人の問題による精神障害で死亡した場合は、労災と認定されません。
「業務以外の心理的負荷評価表」を用いて心理的負荷の強度を評価し、業務以外の原因で発病していないことを確認します。
(3)最後に
全国労働衛生団体連合会が公表する「精神障害等の労災補償状況」によると、平成30年度(2018年)の精神障害による労災認定率は31.8%と全体の3割程度とのことです。
今後精神疾患による労災が多くなる傾向ですので、知っておくことをお勧めします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
