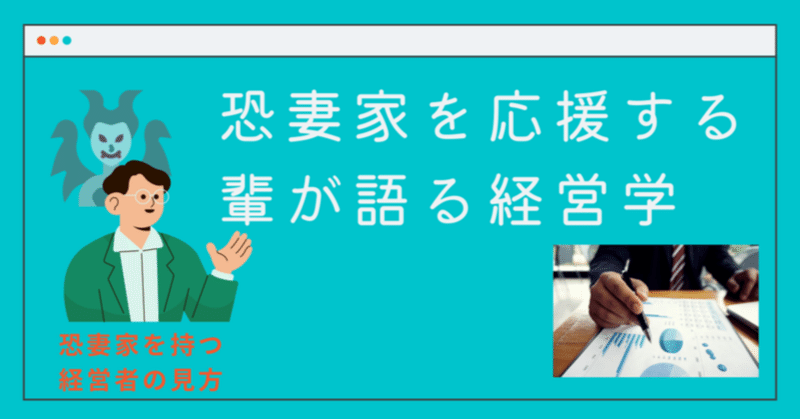
恐妻から学ぶ_わかりやすい原価②
製品に対するコストを把握できれば、コスト削減による収益性向上・適切な予算計画の編成や経営判断など、多くのメリットが得ることが可能になります。
今回、企業の経営のポイントである原価計算についてわかりやすくお伝えいたします。
(1)原価計算
原価計算とは、商品の原価を計算する方法を指します。
売上げのために販売する製品の製造にかかった費用を計算して、製造コストを算出することができます。
原価計算で製造コストが算出されれば、同時に、商品・製品が1個売れるたびにどれぐらいの粗利が得られるのかがわかることになります。
(2)原価計算の目的
原価計算の目的に関しては、次の2つに集約されます。
①財務会計目的
株主や会社の利害関係人などの会社外の人たちのために行う会計業務を指します。
製品の原価を明らかにすることによって生産活動によって会社にどれだけの利益をもたらしたかを外部に報告することが目的になります。
企業は、自社株主や銀行等の融資機関、投資家に経営状況を公表しなければいけませんが、その際に使用される財務諸表の1つである損益計算書(P/L)を作成するために、原価計算は重要な役割を担います。
②管理会計目的
会社内の業務効率化等のために行う会計業務を指します。
企業が思い描いていた理想の原価と実際の原価とを比較できることにより、コストダウンや工程の効率化などの管理が可能となり、より高い生産性を追求することができます。
細分化するとさらに4つに分かることができます。
・価格計算目的
→商品価格の決定に役立てるため
・原価管理目的
→商品の製造が効率的かをチェックするため
・予算編成目的
→製造ラインの予算を決めるため
・経営計画目的
→経営者が中長期的な経営計画を立てるため
(3)原価の種類
原価計算はその目的に応じて次の3種類に分類できます。
①標準原価計算
製品の標準原価(理想的な状況で当該製品が生産されたときにかかる理論上の原価)を求めるための原価計算を言います。
②実際原価計算
製品の製造にあたり、実際にかかった費用を集計する原価計算を指します。
原価計算を実施するにあたり、売上原価、販管費等すべての原価要素を網羅的に計算する原価計算を「全部原価計算」と呼びます。
③直接原価計算
製品の製造コストを固定費と変動費に振り分け、変動費に重点をおいて原価計算を行う原価計算を指します。
上記の全部原価計算に対し、売上原価と販管費に含まれる変動費部分だけを計算する原価計算を「部分原価計算」と呼びます。
(4)最後に
製造業関係の企業では、原価計算が正しく行われなければ、現状のコスト状況の把握・コスト改善のチェック機能・製品に関する経営判断が難しくなります。
原価計算を正しく運用することで、最終的には企業の収益性自体がアップするほど、原価計算は重要な役割を担っていますので、まずは理解されることをおすすめします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
